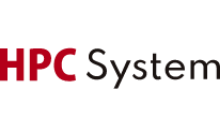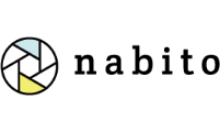MESSAGE

今こそ、新しい日本、
新しい社会モデルを創るー
今こそ、新しい日本、新しい社会モデルを創るー

私たちフラクタルグループは今こそ市民が主体となり
新しい社会モデルを創ることができる最大の機会であると考えます。
様々な社会課題が行き詰まりを迎えている今、日本全体が進むべき道を求め、彷徨っています。
しかし同時に多くの人々が「助け合い」や「絆」の尊さに気付き、価値観の転換が起こっていることもまた事実ではないでしょうか。
今こそ、私たち市民一人ひとりの良心による実践を結集することで自立型・循環型の新しい社会モデルを構築し、拡げて行くことが大切であると考えます。
そのための私たちが推進する事業が「人づくり事業」と「社会づくり事業」です。
フラクタルグループはこれからも社会の公器としての役割を高め「人類」「社会」そして「地球」に貢献することを最大のミッションとし、取り組んでまいります
株式会社ガイアシステム会長
渕上智信
プロフィール
Profile
渕上智信 -Fuchigami Tomonobu-
- 株式会社ガイアシステム 代表取締役会長
- NPO法人ユナイテッド・アース 理事長
- 公益社団法人日本青伸会 理事
- 一般社団法人 野遊びリーグ 理事
- 同志社大学大学院 総合政策科学 修士。地域公共政策士。
1987 年に創業。人材派遣事業、IT 事業などを経て、チームビルディングにより信頼ある組織づくりを実現する
独自の人材教育プログラム「HPC システム」を数多くの企業に導入。
2006 年には NPO 法人ユナイテッド・アースを設立。
地球規模の社会課題が山積する中で「強い意志をもって立ち上がった市民がつながりあい、良心のネットワークを構築し、
持続可能な地球の将来社会に向けて、共に実践することが重要である」と考え、事業と社会貢献活動においていくつものプロジェクトを推進。
現在は、持続可能な循環型の社会、心育まれる幸福な社会を地方から実現するために、各地の自治体と連携し、
地方から日本の社会を変える雛型をつくるための「社会づくり事業」に取り組む。
本来あるべき日本の精神性を取り戻し、次世代を担う若者がこの国に誇りと自信を持って活躍できる社会を残すべく日々奔走している。
講演実績
Lecture record
- 国連本部「Human Rights Day 2011」
- 国連本部「コモンヒューマニティ会議」
- 東京大学「Africa Empowerment」
- 同志社大学ライフリスク研究センター主催・シンポジウム「ソーシャル・ビジネスと信頼を基盤とした社会の構築」
- 国際教育学会・京都大学経済研究所ほか共催・公開シンポジウム「学びを科学する」
- 鹿児島大学稲盛アカデミー「企業家鹿児島研修」
- 中国無錫市「経営経験座談会」
- 学校法人追手門学院 おうてもん教育セミナー
- エスピーシー関西理美容事業協同組合 他多数



創業ストーリー
Founding story
幼少期から、「人と人との繋がり」や「心を育むこと」が蔑ろにされている社会に対して強い違和感を抱いていた渕上は、「皆が幸福を実感できる社会を実現したい」─その志一つで、1987年、わずか50万円の資金を手に起業に踏み切った。ワンルームマンションからスタートし、イベント業・広告代理店の株式会社シャンバラを創業。その後、株式会社ガイアシステムを設立し、IT事業や人材派遣業を通して会社は急成長を遂げ、全国展開を果たす。そのステージは上海、ニューヨークへも及んだ。
さらに、自社における教育の取り組みをもとに独自に構築した人材育成の仕組み「HPCシステム(人間力創発の仕組み」は、一過性の研修とは異なり、社員同士が日常の実践を通してともに学び、成長し、繋がりを深めていくことのできる「継続的に人が育つ仕組み」として、口コミで全国の企業へと拡がり続けている。また、一人ひとりの自立性・自発性を育むこの仕組みは、社内風土の向上やチームビルディングにも目覚ましい効果をもたらし、時代の変化にも負けない「全員経営」を可能にする仕組みとして、経営学の観点からも注目されている。
2011年東日本大震災直後より、宮城県南三陸町・登米市にも拠点を構え、復興支援と新しい街づくりに尽力。被災者に寄り添った様々な支援を展開する傍ら、太陽光発電を中心とした自然エネルギーの推進は、被災地から全国各地へと拡がり、災害の教訓を活かした「循環型の新しい社会モデル」の創造に向けて、神戸・東京・大阪・福岡・宮城の社員が一丸となって取り組んでいる。
「社会変革には、多くの人が人生の大半を過ごす職場=企業の経営者が、利他の精神に変わっていくことが重要である」との想いから、31歳の頃(1994年)、志高い経営者が集まり「人生哲学・経営哲学」を学ぶ勉強会に入塾。2001年には、塾内で月例勉強会を提案。発起人、座長として数人からスタートする。次第に多くの方々から共感・応援を頂くようになり、やがて約700名が入る会場が毎月満席になるような勉強会へと成長した。
そこでは、毎回経営者同士のすさまじく真剣な対話が繰り広げられ、各界のリーディングカンパニーの経営者が、いかにして艱難辛苦を乗り越えてきたのか。企業のコア・コンピタンスをどのように創り出し、会社を成長させてきたのか。その方法は、継続的・発展的なものなのか。そこに理念や志はあるのか─。生身の経営者の実体験を通した本物の学びがあった。こうした多くの経営者の経営体験から培われた経営力と、志高い経営者とのネットワークは、その後の活動にも大きな原動力となっている。
この勉強会の座長を10年間務めた後、2010年末に座長を後継の方々に引き継ぎ、かねてより取り組んでいた社会貢献活動により軸足を移して活動していく道をスタートした。
協会の設立
創業当初から、事業収益を原資として海外への自立支援活動や若者の心を育むイベントの開催など様々なCSRに取り組む中、さらに発展的な「市民主体の社会変革」を目指すべく、2006年にNPO法人神戸国際ハーモニーアイズ協会※を設立。渕上本来の夢、ライフワークを本格的に始動した。映像とITを活用した「社会貢献専門動画配信サイト」の立ち上げや、多くの著名アーティストのご協力を受けて、アフリカ支援のためのチャリティCDをリリースした「社会貢献専門音楽レーベル・ハーモニーアイズレコード」の活動、大規模な市民イベントの開催など、市民一人ひとりの良心を開き、社会貢献活動に主体的に参加できる「仕組みづくり」に奔走する。
(※2016年3月、特定非営利活動法人ユナイテッド・アースに名称変更)
参考ホームページ 社会貢献専門動画配信サイト 「UNITED EARTH CHANNEL」
アースの取り組み
やがて、多くのNPO団体から経営上の相談を受けてきた経験を通して、社会貢献活動における「経営力」の重要性、また分野を越えた連携の必要性を改めて痛感した渕上は、社会貢献の共同組合のような組織として、市民共同団体「ユナイテッド・アース(現在の特定非営利活動法人ユナイテッド・アース)」を設立。
NPOや企業、アーティスト、有識者、学生など…市民の共働によって、「技術」や「資金」、「ネットワーク」を結集し、一団体や一個人だけでは解決できない様々な社会問題に対して、より効果的・継続的な取り組みを開始した。すでに、カンボジアやケニア、中国四川省涼山など海外の貧困地域の自立支援や、東日本大震災の復興支援、次世代の社会起業家育成に向けた教育活動、環境エネルギーへの取り組み、平和推進活動など様々な実践を展開。また東京・関西を中心に開催している交流の場「UE-Café」では、多くの企業からの会場協力のもと、毎回10代から60代、70代の方まで立場や年齢を越えて盛り上がり、素晴らしい繋がりが生まれている。
このように、ユナイテッドアースでは、参加しやすく気軽にはじめの一歩を踏み出せるイベントや、ソーシャルメディアを通じた一万人を越える規模のムーブメントを数多く手掛けながら、それらが決して一過性の取り組みに終わることなく、根本的な社会問題の解決に繋がる仕組みを発信すべく、戦略的に組織的実践を展開。初めの一歩は低いハードルで参加しやすく、学びの奥行きは深く─様々な団体と共働しながら、ユナイテッドアースそのものも進化成長を続けている。
参考ホームページ 「特定非営利活動法人ユナイテッド・アース」
東日本大震災を大きな契機として、従来の大量生産・大量消費型のライフスタイルや既存の社会システムでは、もはや立ち行かなくなっていることを多くの人々が自覚した。そのような今だからこそ、自立型・循環型の「新しい社会モデル」の創造が必要であり、そのためには時代を担う若者の育成が必要不可欠である─
そのような想いから、これまで培ってきた「人づくり」のノウハウや経営者、社会活動家としての経験を活かし、正しい「考え方」と「実現力(経営力)」の両面を育む、「社会起業家育成」のための授業を天理大学や同志社大学など様々な大学機関と連携し、2013年よりスタート。「社会を良くする実践者」を一人でも多く育成し、「良心のネットワーク」を構築すべく、今、本当に必要な学びとは何か─魂を込めて伝えている。
今、我々を取り巻く環境は、少子高齢化に伴う地方の疲弊、産業の低迷、貧困の連鎖、さらに世界でも、多発する大規模な自然災害、世界経済の低迷、二極化する格差社会…地球規模の社会課題が山積みとなっている。
例えば今、首都直下型地震や南海トラフ地震が起きれば、被害を受けた地域のみならず、日本全体の経済が大きな打撃を受け、社会機能そのものが機能不全に陥る可能性がある。そのような有事対策としても、各地域で自立循環型の「新しい社会モデル」の構築が求められている。
現在、ガイアシステム、ガイアサイン、ユナイテッド・アースでは、全国の自治体との連携を進めるとともに、安全・安心な食料・水・電気が自給できる自立した循環型システムを構築し、有事にも耐えうる強い街の連帯をつくることを目指している。10年後、50年後の未来を見据え、市民主体の新しい社会のカタチを描く渕上の挑戦は続く─