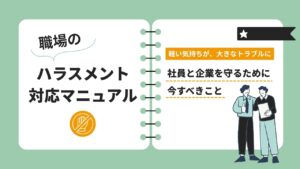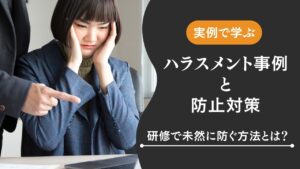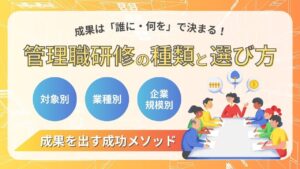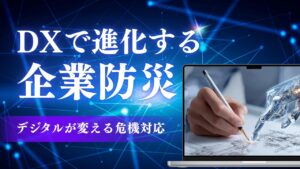職場のハラスメント対応マニュアル|社員と企業を守るために今すべきこと
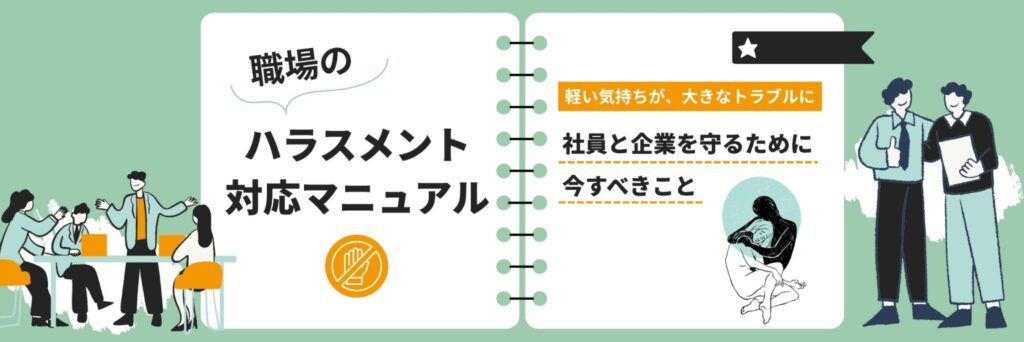
「ちょっと言い過ぎただけ」
「本人は冗談のつもりだったらしい」そんな軽い気持ちが、職場の大きなトラブルにつながることがあります。
実際、企業がハラスメントへの対応を誤ったことで、被害者の退職や、企業イメージを著しく損ねる訴訟に発展するケースも後を絶ちません。法改正により、ハラスメント対策が企業の義務となった今、企業に求められているのは、「見て見ぬふりをしない」そして「適切に対応する」という毅然とした姿勢です。

この記事では、人事担当者の皆さまが、自信を持ってハラスメント問題に対応できるよう、ハラスメントの種類ごとの対応のポイントや、実際に相談を受けた際の初動対応の具体的なステップを、わかりやすく解説します。
やってはいけない!職場ハラスメントのNG対応とは
職場でハラスメントの相談があったとき、ついこんな対応をしていませんか?
- 「気のせいじゃない?」
- 「本人に悪気はないと思うよ」
- 「もう少し様子を見ようか」
- 「それくらい、誰でも言われてるよ」
- 「あなたにも落ち度があったんじゃない?」
- 「加害者もストレスが溜まってるんだよ」
- 「それ、証拠あるの?」
- 「この話、他の人には言わないでね」
- 「あの人はそういうキャラだから」
- 「気にしすぎだよ。大げさだなあ」
- 「間に入って話を丸くおさめようか」
NG対応の多くは、「早く終わらせたい」「波風を立てたくない」という心理から来ています。
しかし、対応を急ぐほど問題は深刻化します。まずは被害者の声に安心して話せる空間をつくることが第一歩です。
ハラスメントのNG対応は、被害者に「相談しても無駄だった」「結局、会社は何もしてくれない」と感じさせてしまい、会社の信頼を失うことにつながります。
職場のハラスメントは、誰にでも起こり得る問題
また、社内での放置や甘い対応が原因で、問題が表面化し、SNSでの拡散、メディア報道、さらには損害賠償請求といった法的なトラブルに発展するリスクも高まります。これにより、企業のブランドイメージは大きく傷つき、優秀な人材の離職や採用活動への悪影響など、計り知れない損失を招く可能性もあります。
だからこそ、「職場のハラスメントは、誰にでも起こり得る問題」として、ハラスメント発生時の対応スキルを磨いておくことが重要です。
一目でわかる!職場ハラスメント対応の良い例・悪い例
ハラスメントの相談対応、つい「よかれと思って」やってしまう言動が、実は逆効果になっていることも。
対応ひとつで、被害者の安心感も、職場の信頼も大きく変わります。良い例・悪い例を比較しながら、適切な対応のポイントを押さえておきましょう。
| 状況・言動のテーマ | NG対応(やりがちだけどNG) | OK対応(信頼される対応) |
|---|---|---|
| 被害者の感情への対応 | 「気にしすぎじゃない?」 「大げさだなあ」 | 「辛かったですね」 「話してくださってありがとうございます」 |
| 初動の姿勢 | 「証拠あるの?」 「本人に悪気はないと思う」 | 「詳しく状況を教えてください」「あなたの感じたことが大切です」 |
| 相談の扱い | 「この話、内緒にしてね」 「関わりたくないな」 | 「守秘義務を守って対応します」「安心して話してください」 |
| 加害者の擁護 | 「あの人、そんな人じゃないよ」「キャラだから仕方ない」 | 「全ての関係者から事実を確認します」 |
| 被害者へのアドバイス | 「もうちょっと我慢したら?」 「仲良くやってよ」 | 「まずは安全を優先します」 「職場環境を見直しましょう」 |
| 解決の方向性 | 「早く和解してくれない?」 「一緒に謝って終わりにしよう」 | 「必要に応じて処分や再発防止策を講じます」 |
| 話の遮り | 「でも君にも非があったんじゃ?」「前にもそんなこと言ってたよね」 | 最後まで話を聴く意見や判断は後回しにする |
| 継続支援 | その場限りで終了 「様子を見ましょう」で終える | 定期的なフォロー心理的・物理的な支援策を提示する |
ケースによって変わる?ハラスメント別対応のコツ
ひとことで「ハラスメント」と言っても、内容や状況によって適切な対応はさまざま。
ここでは、相談の多い6つのケースをもとに、対応のコツをわかりやすくご紹介します。
パワーハラスメント対応のポイント

業務指導とパワハラの境界線は曖昧になりがちです。どのようなケースでパワハラと判断され、どのように対応すべきかを見ていきましょう。
30代の社員が、上司から日常的に強い口調で叱責されており、「いつも怒鳴られて萎縮してしまう。体調も崩しがちで仕事に集中できない」と人事に相談がありました。しかし、上司は「指導の一環だ。成長してほしいから厳しくしているだけだ」と主張しました。
この場合、まず確認すべきは、その言動の「継続性」と「業務上の必要性を超えた言動があったか」という点です。
たとえ指導目的であったとしても、「人格を否定するような言葉」や「他の社員の前で大声で叱責し、恥をかかせるような発言」があれば、それはパワハラに該当します。
パワーハラスメント対応のポイント
- 第三者による冷静なヒアリング
被害者だけでなく、加害者、そして周囲の社員からも丁寧に話を聞き、事実関係を多角的に把握します。
感情的にならず、あくまで客観的な視点を持つことが重要です。 - 客観的な証拠の確認
録音データ、メールやチャットのやり取り、業務日報、周囲の証言など、客観的な証拠を収集し、事実認定の材料とします。 - 「指導」と「パワハラ」の線引き
業務指導の範囲を超えているか、個人の尊厳を傷つける言動がないかを慎重に見極めます。
必要であれば、専門家の意見も参考にしましょう。
セクハラ対応のポイント

セクハラは、被害者の感じ方が重要視されるのが特徴です。その特性を踏まえた対応のポイントをご紹介します。
男性上司が女性部下に対して「今日の服、すごく色っぽいね」「彼氏はいるの?」「今度二人で食事に行こうよ」といった個人的な発言を繰り返し行っていたことが問題に。
上司は「褒めただけ」「親睦を深めようとしただけ」と主張しています。
セクハラは、被害者の「不快かどうか」という受け止め方が非常に重視されます。つまり、本人が不快に感じた以上、それはセクハラと判断されます。
「性的な要素を含んでいたか」「相手が不快と感じたか」が判断基準となります。加害者に悪意がなくても、被害者が不快に感じればセクハラとなり得ます。
セクシャルハラスメント対応のポイント
- プライバシーに最大限配慮したヒアリング環境の整備
周囲に聞こえない個室など、被害者が安心して話せる環境を確保します。 - 被害者に「あなたは悪くない」と伝えること
被害者は自分を責めたり、相談することに躊躇したりする傾向があります。
まずは共感し、被害者が悪いわけではないことを明確に伝えて安心させることが大切です。 - セクシャリティに関する無意識の偏見にも注意
性別役割分担意識や、異性に対する無意識の偏見がセクハラにつながることもあります。
つまり、自分では意識していなくても、性別や性的指向に関する決めつけや思い込みが、意図せずハラスメントにつながる可能性があります。
人事担当者自身も、自身の価値観に偏りがないか振り返る視点を持つことが重要です。
マタニティハラスメント(マタハラ)対応のポイント

妊娠・出産・育児は喜ばしいことであるはずが、職場での不当な扱いに繋がることがあります。マタハラから社員を守るためのポイントです。
ある女性社員が妊娠を報告したところ、上司から「人手が足りなくなるから、産休は取らないでほしい」「時短勤務は他の社員に迷惑がかかる」と言われたと人事に相談がありました。
また、同僚からは「(妊娠を理由に)仕事のペースが落ちて困る」という陰口も聞こえてくる状況でした。
マタハラは、妊娠・出産、育児に関する制度の利用を理由とした不利益な取り扱いや、就業環境を害する言動が該当します。妊娠等を理由にキャリア形成を阻害したり、精神的な苦痛を与えたりする行為です。
マタニティーハラスメント対応のポイント
- 制度の周知徹底と理解促進
産前産後休業、育児休業、時短勤務などの制度を全社員に周知し、利用しやすい雰囲気作りと、制度利用者のサポートの重要性を啓発します。 - 個別面談と状況確認
妊娠・出産を報告した社員とは、個別に面談を行い、体調や希望する働き方、不安な点などを丁寧にヒアリングします。 - 周囲の理解と協力体制の構築
制度利用者だけでなく、その周囲の社員にも、業務分担やサポート体制について理解を求め、協力体制を築くための働きかけを行います。
ケアハラスメント(ケアハラ)対応のポイント

介護と仕事の両立は、多くの社員にとって現実的な課題です。
介護を理由としたハラスメントから社員を守るための対応ポイントです。
ある男性社員が親の介護のため、介護休暇の取得を上司に相談したところ、「介護は家族でやるものだ」「仕事が滞るから、休暇は最小限にしてほしい」と言われたと人事に相談がありました。
また、介護のための早退や遅刻を理由に、評価が下がったと感じている状況でした。
ケアハラは、家族の介護に関する制度の利用を理由とした不利益な取り扱いや、就業環境を害する言動が該当します。介護離職を防ぎ、社員が安心して介護と仕事を両立できる環境を整備することが重要です。
ケアハラスメント対応のポイント
- 介護関連制度の明確化と周知
介護休業、介護休暇、短時間勤務制度など、介護に関する社内制度を明確にし、全社員に周知します。 - 個別相談と情報提供
介護が必要な社員に対しては、個別に相談に応じ、利用可能な制度や社内外のサポート体制に関する情報を提供します。 - 上司・同僚への理解促進
介護と仕事の両立の難しさや、介護休業・休暇取得の必要性について、上司や同僚への理解を深めるための啓発活動を行います。
モラルハラスメント(モラハラ)対応のポイント

精神的な攻撃により、じわじわと相手を追い詰めるモラハラは、表面化しにくい特性があります。その見極めと対応のポイントです。
ある社員が同僚から、仕事のミスを執拗に指摘されたり、無視されたり、人格を否定するような陰口を言われたりしていると人事に相談がありました。
直接的な暴言はないものの、精神的に追い詰められ、出社するのが辛いと感じている状況でした。
モラハラは、言葉や態度によって精神的な攻撃を繰り返し行い、相手の尊厳を傷つけ、精神的な苦痛を与える行為です。
パワハラと異なり、地位の優位性を伴わない場合もあり、また、目に見える証拠が残りにくいのが特徴です。
モラルハラスメント対応のポイント
- 精神的苦痛の有無を重視
被害者が精神的な苦痛を感じているかどうかに焦点を当ててヒアリングを行います。 - 複数の視点からの事実確認
目に見える証拠が少ないため、周囲の社員からの証言や、被害者の日々の記録(言動、日時、心境など)を丁寧に収集し、総合的に判断します。 - 被害者のメンタルヘルスケア
精神的なダメージが大きい場合が多いため、産業医やカウンセラーとの連携を積極的に行い、被害者の心のケアを最優先します。
カスタマーハラスメント(カスハラ)対応のポイント

顧客は「神様」という考え方が、社員を苦しめることがあります。社員をカスハラから守り、安心して業務に取り組める環境を作るためのポイントです。
あるコールセンターの社員が、顧客から長時間にわたる執拗なクレームや、個人的な罵倒を受け、精神的に疲弊していると上司に相談がありました。他の社員も同様の経験をしており、業務へのモチベーションが低下している状況でした。
カスハラは、顧客や取引先からの、理不尽な要求やクレーム、暴言、暴力などにより、社員が精神的・身体的苦痛を受ける行為です。企業には、顧客対応を行う社員の安全と健康を守る義務があります。
カスタマーハラスメント対応のポイント
- 対応ルールの明確化と周知
カスハラに該当する行為の具体例や、カスハラを受けた際の対応手順(上司への報告、対応の中止、警察への連絡など)を明確にし、全社員に周知します。 - 対応の記録と共有
カスハラが発生した際は、日時、相手、内容、対応状況などを詳細に記録し、社内で共有することで、組織的な対応を可能にします。 - 社員のメンタルヘルスサポート
カスハラを受けた社員に対しては、ストレスチェックやカウンセリングの機会を提供するなど、精神的なケアを積極的に行います。 - 毅然とした対応
悪質なカスハラに対しては、顧客との関係性よりも社員の安全を優先し、サービス提供の停止や法的措置も辞さない毅然とした態度で臨むことを明確にします。
ハラスメント対応の手順|人事が知っておきたい5つの行動
ハラスメントの相談を受けたとき、対応を間違えると被害の深刻化や組織の信頼低下を招くおそれがあります。
ここでは、人事担当者が知っておくべき基本の5ステップを、わかりやすく解説します。
安心して話せる「相談窓口」をつくる
まず大切なのは、「ここなら話しても大丈夫」と感じてもらえる窓口を整えること。
信頼できる人事担当者を配置し、性別や年齢の多様性も意識しましょう。
可能であれば、外部の専門家(弁護士、社労士、カウンセラー)と連携する体制もあると安心です。
匿名で相談できる仕組み(メール・フォーム・ボックスなど)も有効です。
事実確認は“丁寧に、記録を残して”。
被害者・加害者・周囲の関係者からの聞き取りは、冷静に、丁寧に行います。
日時、場所、言動、状況、当事者の心理的変化など、できるだけ詳細に確認しましょう。
ヒアリング内容はすべて記録に残し、面談日・場所・出席者・内容・記録者名を明記することが重要です。
感情的にならず、あくまで事実ベースでの情報収集を徹底します
社内規定に沿って、公平に判断する
集めた事実をもとに、社内のハラスメント防止規程や就業規則と照らし合わせて判断を行います。
ハラスメントが確認された場合は、以下のような対応を検討します:
- 口頭注意
- 異動・配置転換
- 懲戒処分(減給、出勤停止、解雇 など)
判断は迅速かつ公平に行い、組織としての姿勢を明確にしましょう。
職場全体への周知と再発防止策を講じる
個別の対応で終わらせず、再発を防ぐための取り組みを継続することが大切です。
- 「何がハラスメントにあたるのか」を明文化し、社内で共有
- 全社員向けのハラスメント研修
- 管理職向けのコミュニケーション・リーダーシップ研修
- 相談窓口の周知と利用促進
などを、定期的に実施していきましょう。
被害者・加害者への継続フォローを忘れずに
被害者へのフォローは最優先事項です。必要に応じて、産業医やカウンセラーとの面談をすすめ、心身のケアに配慮しましょう。
希望があれば、加害者との接触を避ける配置転換なども検討します。
一方で、加害者側に対しても、再発防止に向けた指導やカウンセリングを行うことが重要です。
どちらに対しても、職場復帰や人間関係再構築への支援を忘れないことが信頼回復につながります。
よくあるお悩みQ&A
企業と社員、どちらも守るための“対応力”を
職場のハラスメントは、「ある日突然、起こる」こともあります。だからこそ、普段からの備えと、いざというときの冷静な対応が大切です。適切なハラスメント対応は、被害者を救うだけでなく、健全な企業風土を醸成し、最終的には企業自身を守ることにもつながります。
ハラスメントを未然に防ぎ、万一発生した際にも迅速かつ適切に対応できる「対応力」を、組織全体で高めていきましょう。まずは、ハラスメントに関する正しい理解と、対応フローを社内で共有することから始めてみませんか?
ハラスメント研修・対応サポートについて
弊社の研修は、企業ごとの課題に合わせたオーダーメイド研修に加え、制度設計や対応フローの整備などを支援するコンサルティングサポートも行っています。
・どこから手をつけていいかわからない
・現場に合わせた実践的な研修がしたい
そんなお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。
お客様の課題やカリキュラムに応じてお見積りパターンをご提案しています。
まずは気軽にご相談ください!
お電話でのお問い合わせ 0120-117-450
専任のコンサルタントが丁寧にご相談を受け付けます。
お気軽にご相談ください。