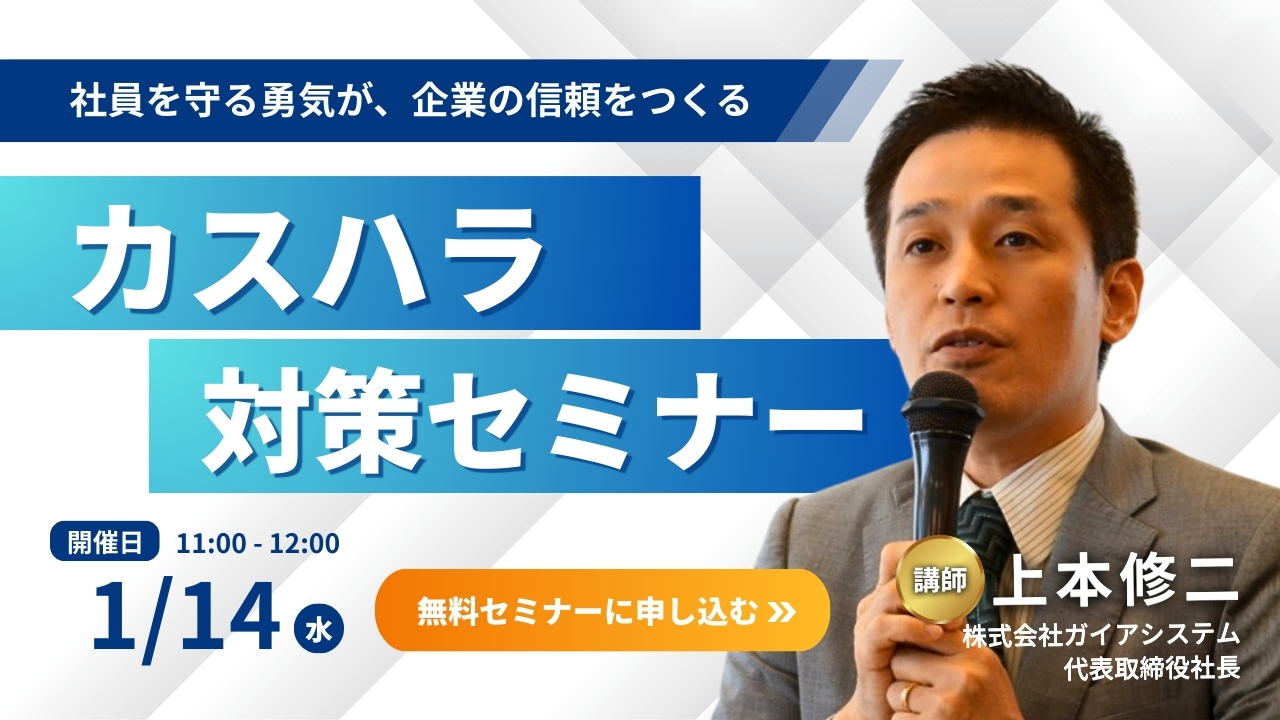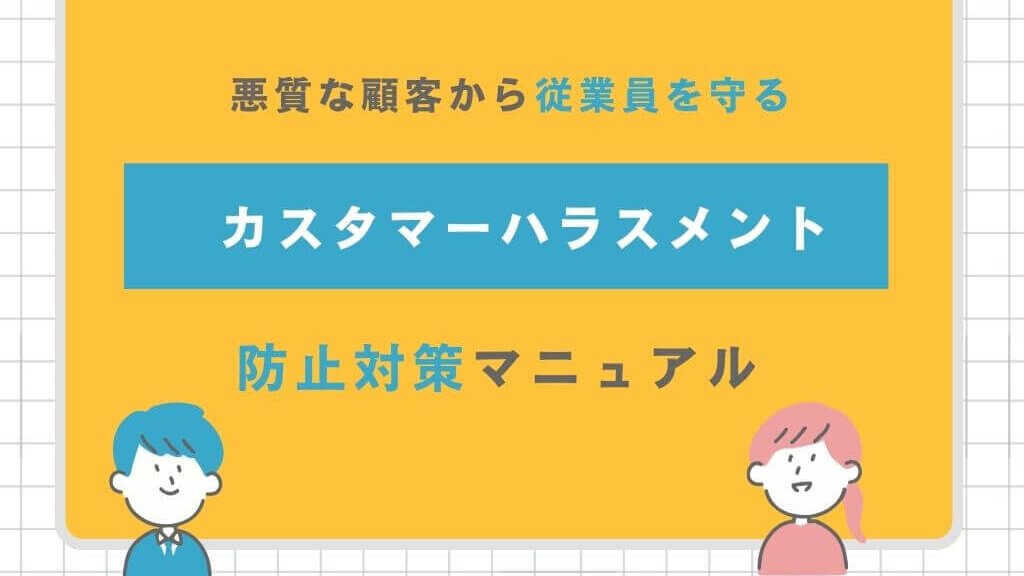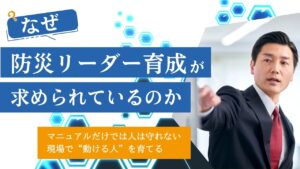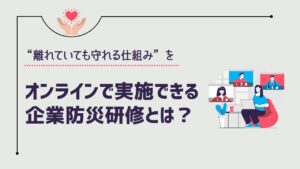災害時のメンタルケアが企業に求められる理由

地震や豪雨、台風など、自然災害の多い日本において、企業は“人と組織の安全”を守るための防災対策を進めています。
しかし、災害対応というと、避難訓練や備蓄管理といった「物理的な備え」が中心になりがちです。実際に現場で求められるのは、もう一つの備え―社員の「心の防災」です。
災害時、人は強いストレスや不安を感じます。恐怖、喪失感、罪悪感、そして「何も感じない」ほどのショック反応。そのような心理的ダメージをどう支えるかが、組織の回復力を左右します。

「防災=心の支援」。それは、社員の命を守るだけでなく、職場の信頼関係や企業文化を守ることでもあります。
災害時に社員が抱える心理的ストレスとは
災害に遭った社員の心は、時間の経過とともに変化していきます。これは特別な人に限らず、誰にでも起こりうる自然な反応です。
| 時期 | 主な心理反応 | よく見られるサイン |
|---|---|---|
| 発災直後(急性期) | 強い恐怖・混乱・無気力 | 判断力の低下・涙が止まらない・放心状態 |
| 発災数日後(亜急性期) | 罪悪感・焦り・不眠 | 「自分だけ助かった」などのサバイバーズ・ギルト |
| 数週間〜数か月後(慢性期) | 無力感・うつ傾向・孤立 | 仕事への意欲低下・感情の起伏・体調不良 |
このような心の変化は、発災から時間が経ってから表面化することもあります。職場では一見普段どおりに見えても、心の中では緊張が続いている社員も少なくありません。

企業として、どの段階でどんな支援が必要かを理解しておくことが大切です。
企業が行うべきメンタルサポートの3段階
災害時のメンタルケアは、段階に応じた支援が求められます。
災害時に社員の心を守るには、事前準備 → 災害直後の対応 → 継続的なケアという3段階で支援体制を構築しておくことが重要です。
以下は、厚生労働省「職場における災害時の心のケアマニュアル」や、産業保健の実務にも基づいた実践ポイントです。
事前準備:平時から「心の防災体制」を整える
研修の実施
- 全社員を対象に「ストレス反応と対処法」を共有し、セルフケア研修を行う
- 管理職には「ラインケア研修」を行い、部下の変化に気づくスキルを養う
- 防災訓練に心理的ケアの要素を組み込み、「体と心の両面の備え」を意識づける
相談窓口の設置
- 災害時・平時を問わず利用できる社内ホットラインを設け、匿名で相談できる仕組みを整える
- 社内のメンタルヘルス担当者や人事部を窓口として周知し、「どこに相談すればいいか」を全社員が把握できる状態に
専門家との連携
- 産業医、心理士、EAP(従業員支援プログラム)といった外部専門家と平時から連携協定を結んでおく
- いざというときに紹介・相談がスムーズにできるよう、連絡フローをマニュアル化しておく
情報共有の仕組みづくり
- 災害発生時に「誰が」「どの経路で」「どんな情報を発信するか」を明確にしておく
- 誤情報や憶測が不安を増幅させるため、一次情報のみを発信するルールを設ける
災害直後の対応:安心を届ける初動行動
共感的な傾聴
- 相手の話を急かさず、穏やかに、忍耐強く聴く
- 「無理に話させない」「沈黙も受け止める」ことが基本
- アドバイスよりも、「怖かったね」「大変だったね」と共感の言葉を
業務への配慮
- 被災した社員には、業務負担を軽減する柔軟な勤務調整を
- 職場復帰を急がせず、体調・家庭状況を考慮したペース配分を行う
- 「心の疲労は見た目よりも長く続く」ことを管理職が理解する
正確な情報提供
- 企業の対応方針や今後の見通しを、正確かつ分かりやすく伝える
- 特に経営層からのメッセージは、社員の心理的安心に大きく影響する
- デマや憶測が流れないよう、公式発信ルートを明示しておく
継続的なケア:心の回復を支えるフォローアップ
休職・復職支援
- 心身の不調が見られる場合は速やかに休職対応を
- 復職の際は、本人・上司・産業医の三者で話し合い、段階的に業務を再開
- 復職直後はフォロー面談を定期的に行う
専門家への紹介
- 症状が長引く、夜眠れない、涙が止まらないなどのサインが見られたら、専門医やカウンセラーへの相談を早めに勧める
- 「我慢せずに相談していい」という風土づくりも重要
変化への注意
- 気分・行動・言動の変化に早期に気づくこと
- 「いつもと違う」と感じたら、人事・産業医・上司が連携してサポートする
セルフケアの促進
- ストレスマネジメントやリラクゼーション法など、社員自身が実践できるケアを継続的に発信
- 呼吸法・マインドフルネス・睡眠管理など、具体的なスキルを日常の社内研修で学べるようにする
- 「助けを求めることは弱さではなく、勇気である」という価値観を組織に根づかせる
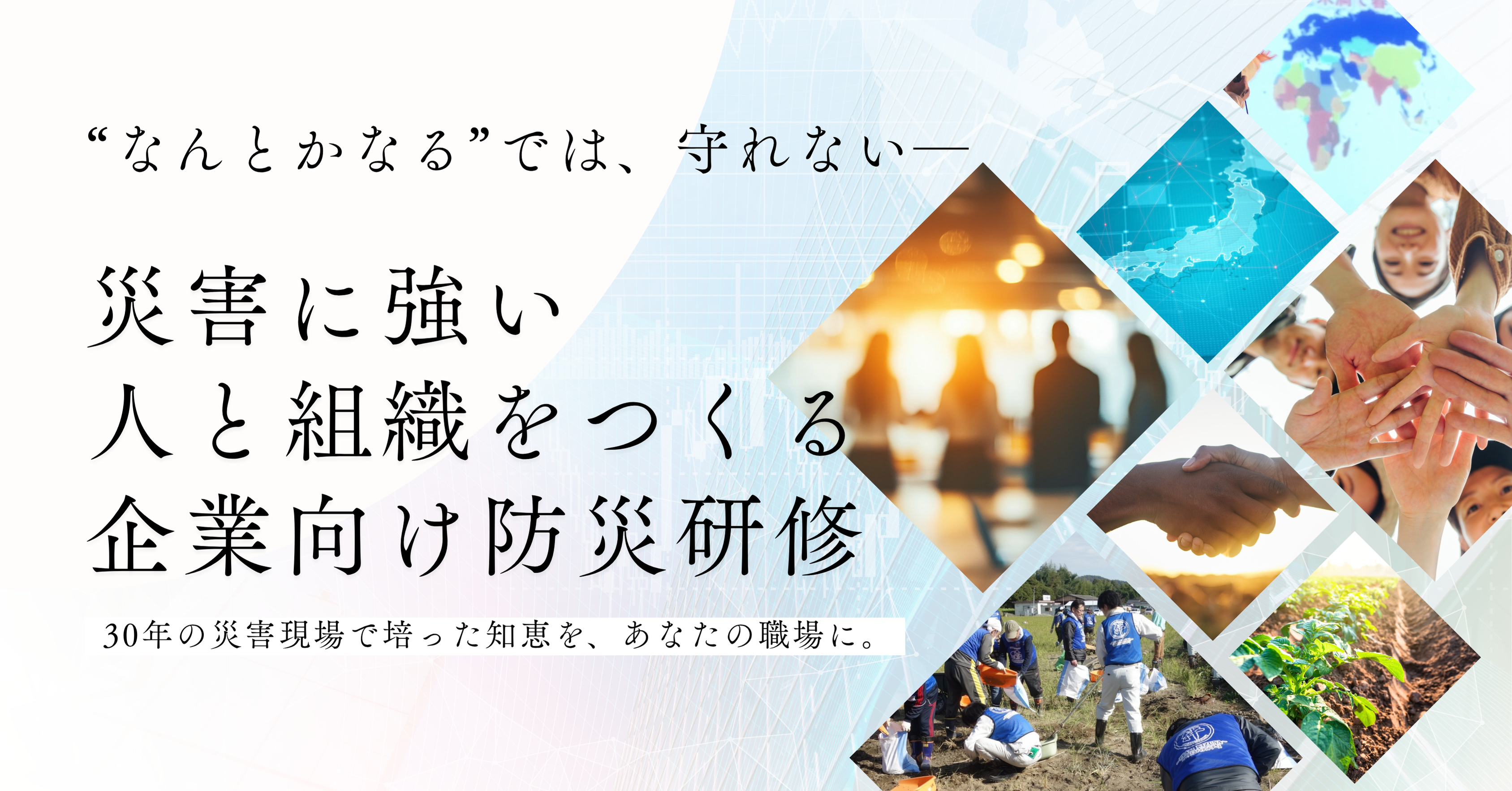
管理職・人事ができる心のケアの仕組み
心のケアは特別な専門家だけが行うものではありません。

日常のコミュニケーションの中で「気づく・受け止める・つなぐ」を実践できる環境を整えることが大切です。
気づく
- 表情・口数・勤務態度の変化に敏感になる
- 業務ミスや遅刻が増えたら要注意サイン
- 「最近どう?」と気軽に声をかけることが第一歩
受け止める
- 「頑張れ」より「つらかったね」と共感を
- 話をさえぎらず、評価せず、ただ聴く
- 涙や沈黙も自然な反応と受け止める
つなぐ
- 社内の産業医やEAP、地域の相談窓口へ案内
- 「ここに相談していいよ」と明確に示す
- 人事部が一次窓口を担う体制を整備する
管理職自身も、被災者であり支援者です。支える人が燃え尽きないよう、上層部が「支援者のケア」も意識する必要があります。
社員と家族を支える企業の姿勢
災害時、社員本人だけでなく、その家族もまた深い不安を抱えます。
家が無事か、家族が避難できているか、連絡が取れない—。そんな状況の中で社員が冷静に業務にあたるのは、決して容易ではありません。
だからこそ、企業として「家族への配慮」も“心の防災”の一部として位置づけることが大切です。
家族を支援する3つの基本行動
- 弔慰・特別休暇・保険手続きなどの支援をスムーズに行い、家庭の混乱を最小限にする
- 社員本人だけでなく、家族からの相談窓口を設けて、安否や支援情報を提供する
- 復職支援では家庭の状況を考慮し、家族の理解を得ながら段階的に職場復帰を進める
【事例】家族向けの防災研修を導入した事例
ある船舶関連企業では、航海業務で社員が長期間不在になることから、「もし家族だけが被災したらどう守れるか」という不安の声が上がりました。
そこで、同社は家族向けの防災研修を導入。家庭での備蓄方法、避難経路の確認、災害時の連絡手段などを実践的に学ぶプログラムを実施しました。
「家族の命を守ることが、結果的に社員本人の安心と職務遂行につながる」
——そんな思いから生まれたこの研修実施は、社員にもご家族にも大変喜んでいただきました。
家族を支えることは、社員を守ること
社員が心から安心して働けるのは、「家族も会社に守られている」という信頼があるからです。
家族の安全を守る仕組みを整えることは、社員の命を守ることにも直結します。

「この会社でよかった」「家族も安心している」そう感じてもらえる企業であることこそ、真の意味での“企業防災”だと言えるでしょう。
【無料】資料ダウンロード

防災研修 | カリキュラム事例
【資料の内容】
・防災研修が必要な理由
・企業の災害対策の実態
・企業の災害対策に関する実態調査
・防災研修のカリキュラム紹介
・価格表/実績紹介
メンタルケアを組織文化に定着させる方法
メンタルケアを一時的な対応で終わらせず、組織の文化として根づかせることが、真の防災力につながります。災害が起こっても「助け合う」「支え合う」が自然に行動として出てくる組織は、日頃の積み重ねによって育まれています。
心理的安全性のある環境をつくることは、「非常時に人を守れる組織」をつくることと同義です。
防災×メンタルケア研修を継続的に実施する
防災研修に“心の防災”の要素を取り入れることで、社員が「人の心の変化」や「支え合い方」を学ぶことができます。
たとえば、被災地支援や体験ワーク、ケーススタディなどを通して、感情に寄り添う力を養う。
ある製造業の企業では、年に1度の防災訓練と同時に「メンタルケアワークショップ」を実施。
社員同士で“心のSOSの見つけ方”を共有するプログラムを続けた結果、「職場の雰囲気が柔らかくなった」「相談しやすくなった」という声が多数上がりました。
このように、訓練の一部に“心を育てる時間”を設けることが、文化定着の第一歩です。
日常に「心の対話」を取り入れる
心理的安全性は、特別な場面で育つものではなく、日常の小さな会話の積み重ねによって築かれます。
- 朝礼や終礼で「感謝」「気づき」を共有する時間をつくる
- 社内SNSで“ありがとう投稿”を促す
- 業務報告に「今日の気づき」や「学び」を加える
こうした取り組みを通じて、社員が互いの心の状態に自然と目を向けるようになります。

「お互いを気にかけること」が組織の習慣になると、災害時にも自然と助け合いが生まれます。
定期的なメンタル点検とフィードバック
防災訓練と同じように、年1回の“心の安全点検”を行いましょう。
ストレスチェックだけでなく、職場の雰囲気や人間関係の変化もヒアリングし、「今の職場にどんな不安があるのか」をチームで共有します。
結果を可視化するだけでなく、改善アクションまで一緒に考えることが重要です。
社員の声を聞く場を設け、トップや人事が直接対話することで、「会社が自分たちの心を気にかけてくれている」と感じられるようになります。
リーダーシップ教育に“心のマネジメント”を組み込む
管理職研修や昇格研修の中に「メンタルヘルス・マネジメント」を含めることで、リーダーが“数字”だけでなく“人の感情”を扱えるようになります。
特に災害時や緊急対応では、リーダーの一言がチームの安心感を大きく左右します。
「まず人を守る」「心の声を聴く」という姿勢が、部下の信頼を深め、結果として組織全体の回復力を高めます。
経営層が「心の安全」を発信する
経営者や役員が、自らの言葉で「人を大切にする文化」を語ることが、何よりも強いメッセージになります。
防災方針や安全衛生方針の中に「メンタルケア」や「心理的安全性」の項目を明文化することで、社員は“心を大切にする会社”という安心感を持てます。
ある企業では、社長自らが災害時の被災経験を社内で共有し、「どんなに備えをしても、人の心が折れては意味がない」と語ったことがきっかけで、社内に“心の防災委員会”が設置されました。トップの発信が文化形成を後押しする好例です。
「心の防災」を理念に取り込む
最後に、メンタルケアを単なる福利厚生ではなく、理念の一部として位置づけること。
企業理念やクレドの中に「人を思いやる」「安心して働ける環境を守る」といった言葉を盛り込み、日常の判断基準として根づかせます。
文化とは、「繰り返し行うこと」で形になります。年に一度の研修よりも、日々の小さな“声かけ”の積み重ねこそが、“心の防災文化”を育てていくのです。
心のケアを文化として育てるということは、単に「不調を防ぐ」ことではなく、互いに支え合える関係性を育むことです。災害時に社員の命を守れる企業は、平時に人の心を大切にしている企業です。

メンタルケアを“防災の一部”として捉え、組織全体で心の安全を守る文化を築いていきましょう。
公的・専門機関との連携(参考窓口)
平時から地域の医療機関・相談機関とつながっておくことで、発災時の迅速な対応が可能になります。
- 厚生労働省「こころの健康相談統一ダイヤル」:0570-064-556
- 労働者健康安全機構「職場における災害時の心のケアマニュアル」
- 都道府県精神保健福祉センター(地域窓口)
よくある質問(Q&A)
まとめ|“心の防災”を実践する企業へ
災害への備えは、「モノ」と「ココロ」の両輪です。
物理的な備蓄やマニュアル整備だけでなく、社員の心を支える仕組みを持つことが、これからの企業防災のスタンダードになります。
- 心理的安全性のある職場
- 支え合う人間関係
- リーダーの共感力
それらを育てることが、「強い組織」ではなく「しなやかな組織」をつくります。
社員の心の安全を守る“防災×メンタルケア”研修も、ガイアシステムにご相談ください。
防災研修カリキュラム
有事に備え、社員の命を守るー実践的な防災対策を!
企業向け防災研修
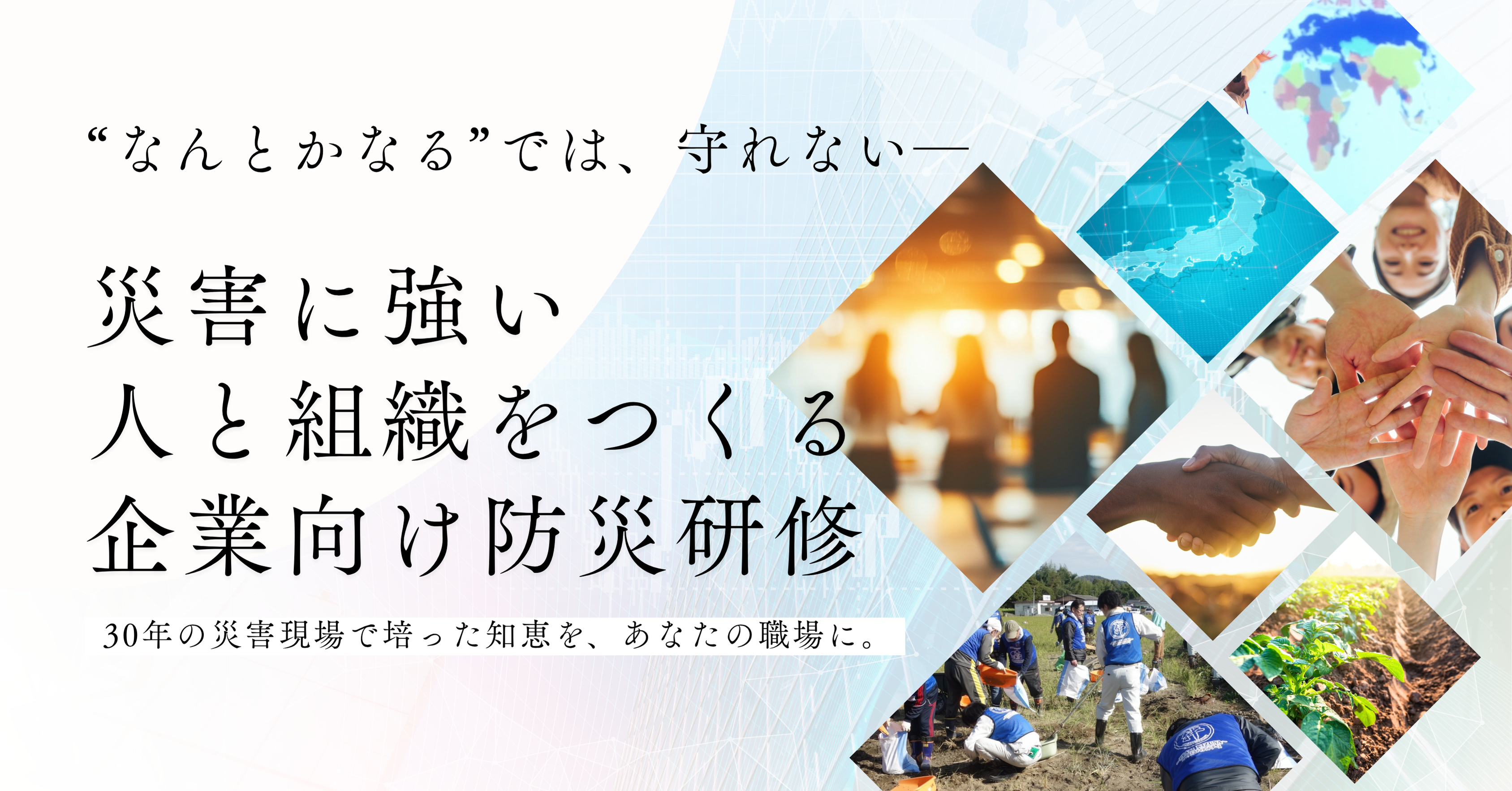
30年以内に80%の確率で発生すると言われる南海トラフ地震。企業には社員の命を守る具体的な「防災力」の強化が求められています。
本研修は、いざという時に“行動できる力”を育てる実践的プログラム。有事に備え、社員の安全を確保するための第一歩を、踏み出しませんか。
企業活動を止めずに従業員や顧客の安全を守る!
BCP(業務継続計画)研修

自然災害が頻発する日本において、企業活動を止めずに従業員や顧客の安全を守るためには、防災への備えが欠かせません。
本研修は、従業員一人ひとりが危機時に適切に対応し、企業全体で迅速かつ効果的に復旧を図る力を養うことを目的に、基礎知識の習得から実践的なシミュレーションを通じて企業全体の防災力を強化します。
リスク意識を高め 危機を未然に防ぐ!
リスクマネジメント研修
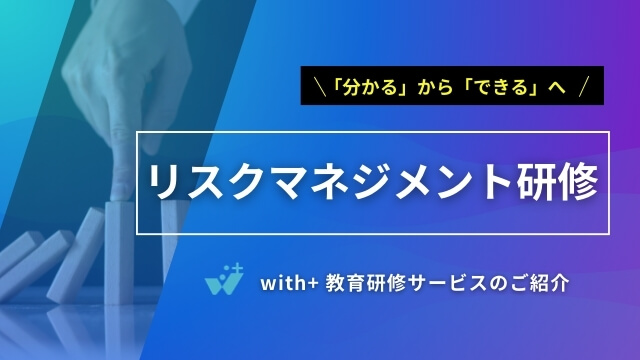
リスクマネジメント研修は、企業が直面する様々なリスクを特定、評価し、適切な対策を立てる能力を養成する教育プログラムです。
リスクの洗い出し、優先順位付け、対応策の策定などを学び、組織全体のリスク管理能力を向上を目指します。
企業防災コラム一覧
-
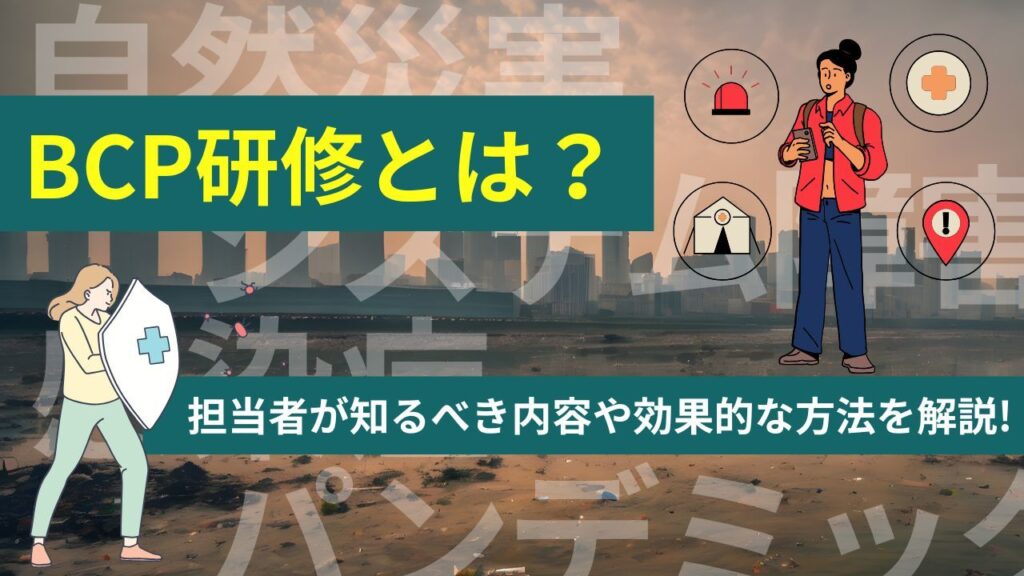
BCP研修とは?担当者が知るべき内容や効果的な方法を解説
-
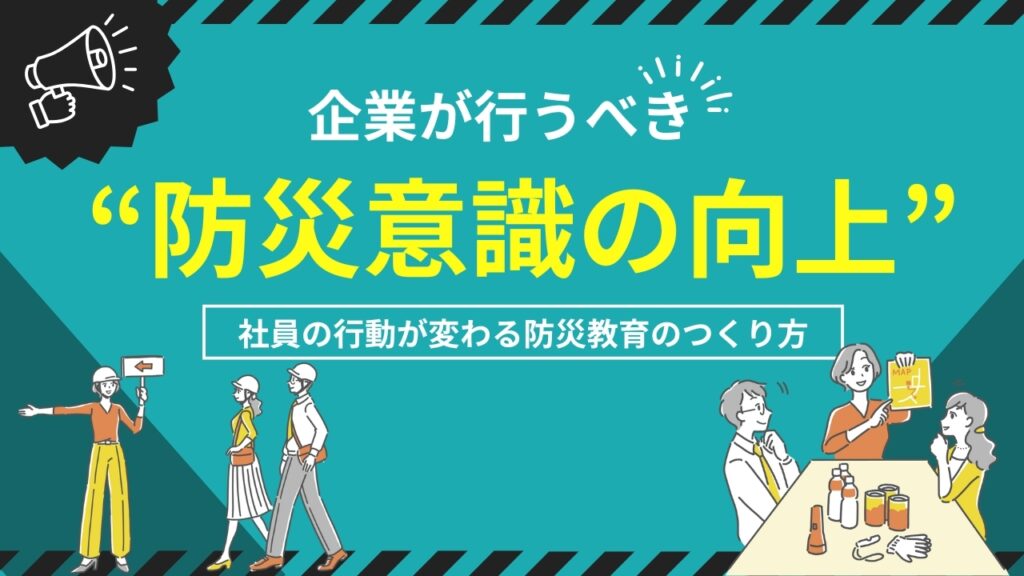
災害時に“行動できる社員を育てる”企業防災とは?防災意識を高める具体策
-
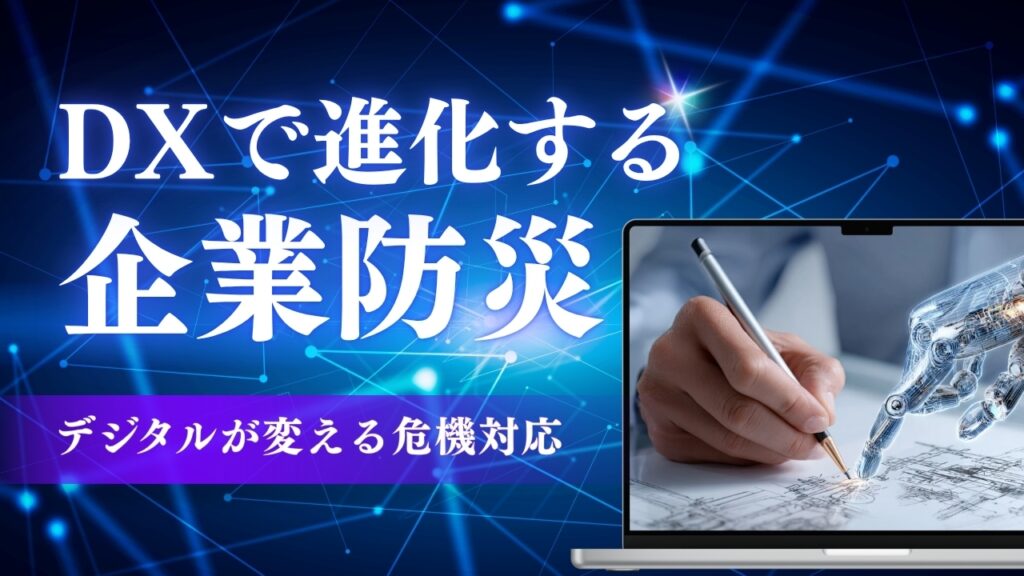
DXで進化する企業防災|デジタルが変える危機対応
-
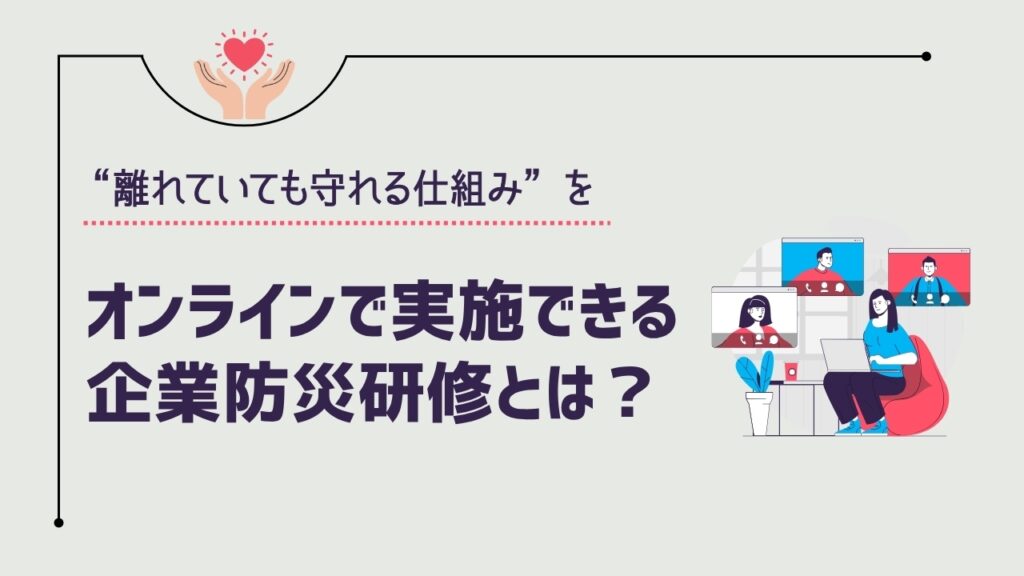
オンラインで実施できる企業防災研修とは?
-
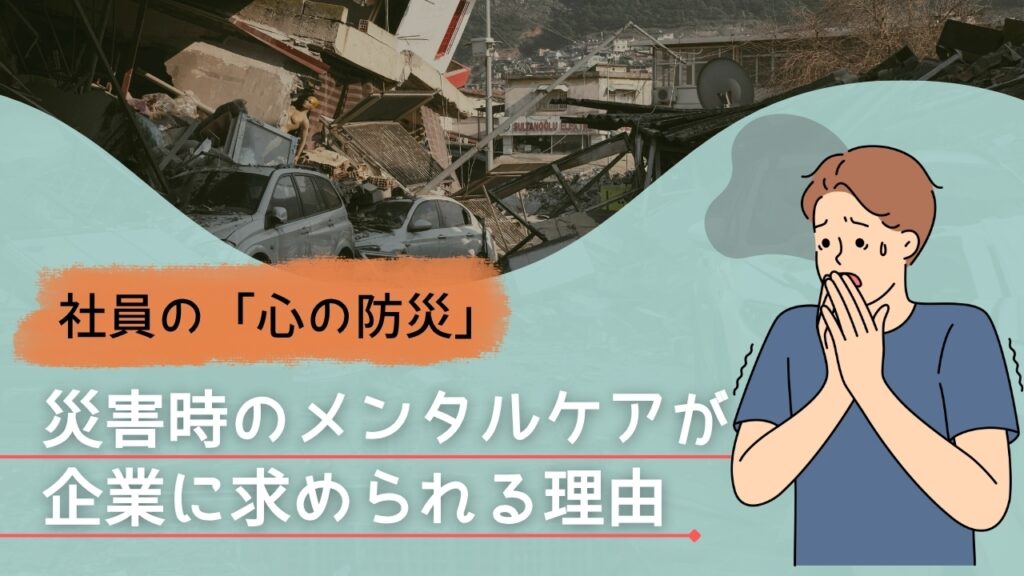
災害時のメンタルケアが企業に求められる理由
-
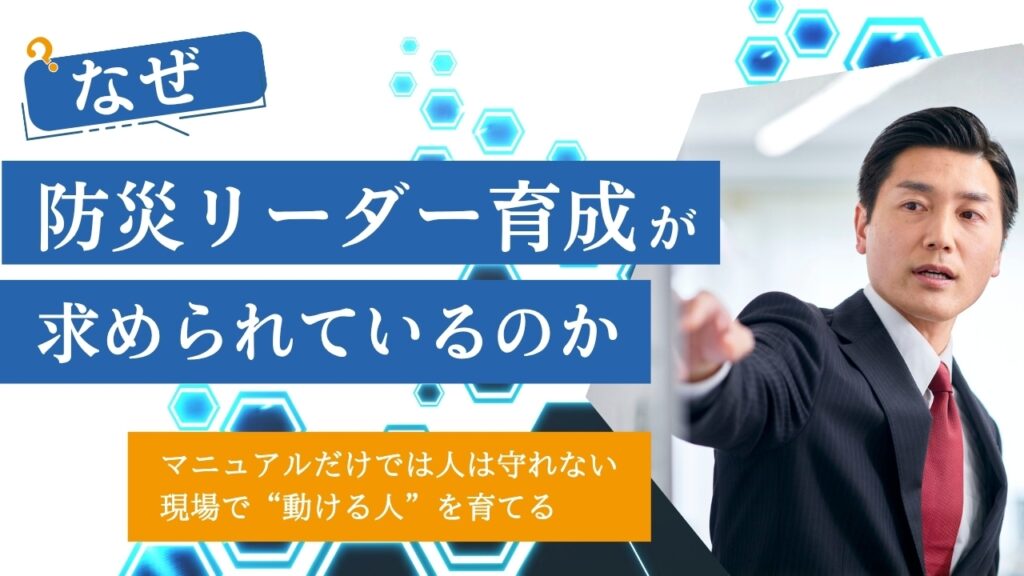
なぜ今、防災リーダー育成が求められているのか
-
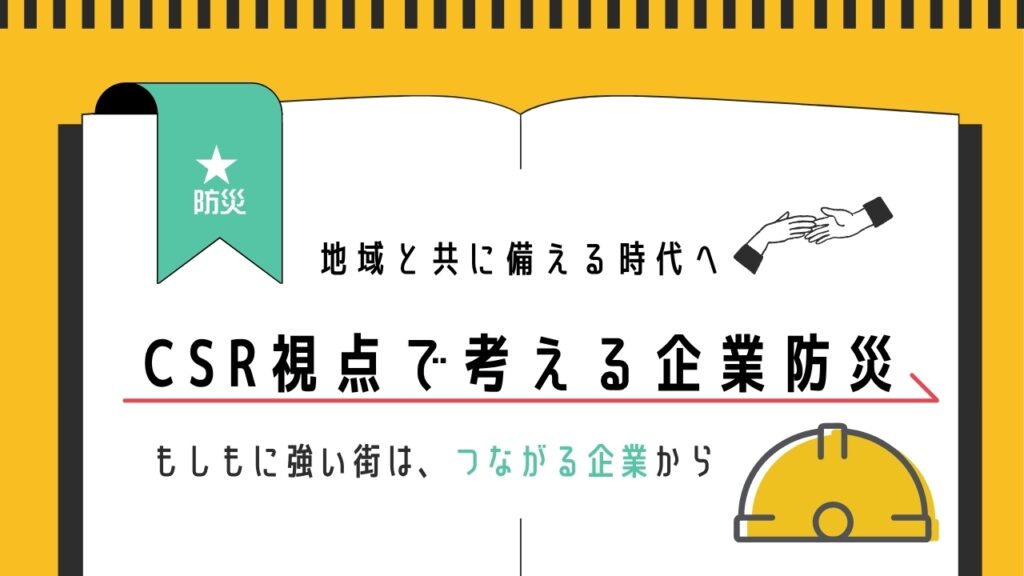
CSR視点で考える企業防災|地域と共に備える時代へ
-
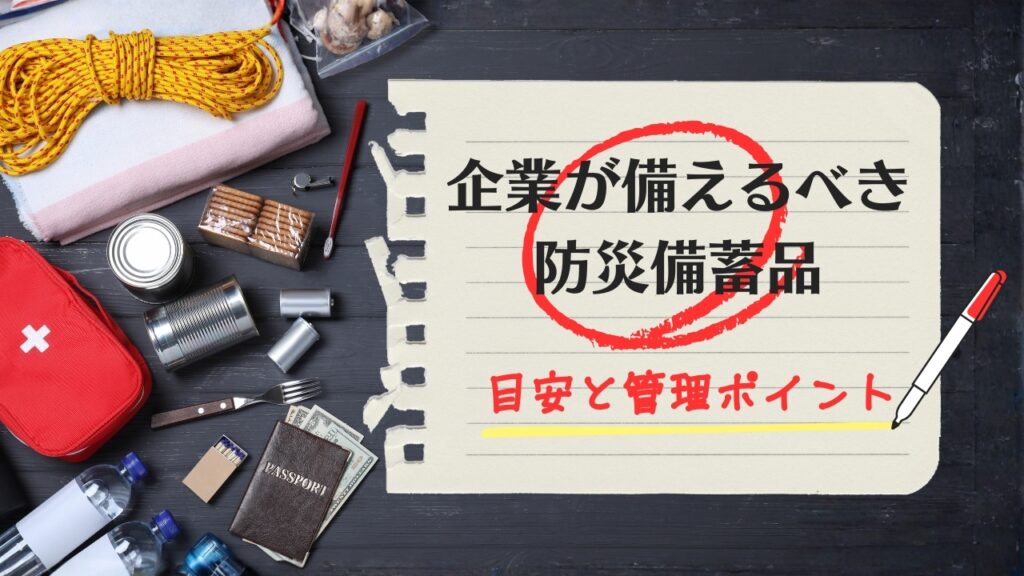
企業が備えるべき防災備蓄品の目安と管理ポイント
-
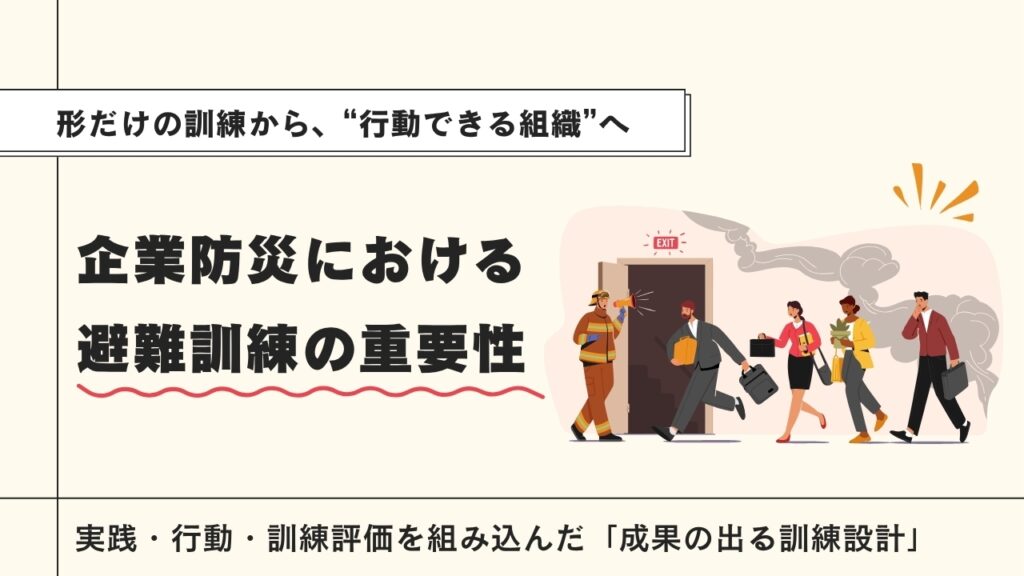
企業防災における避難訓練の重要性|形だけの訓練から、“行動できる組織”へ
-
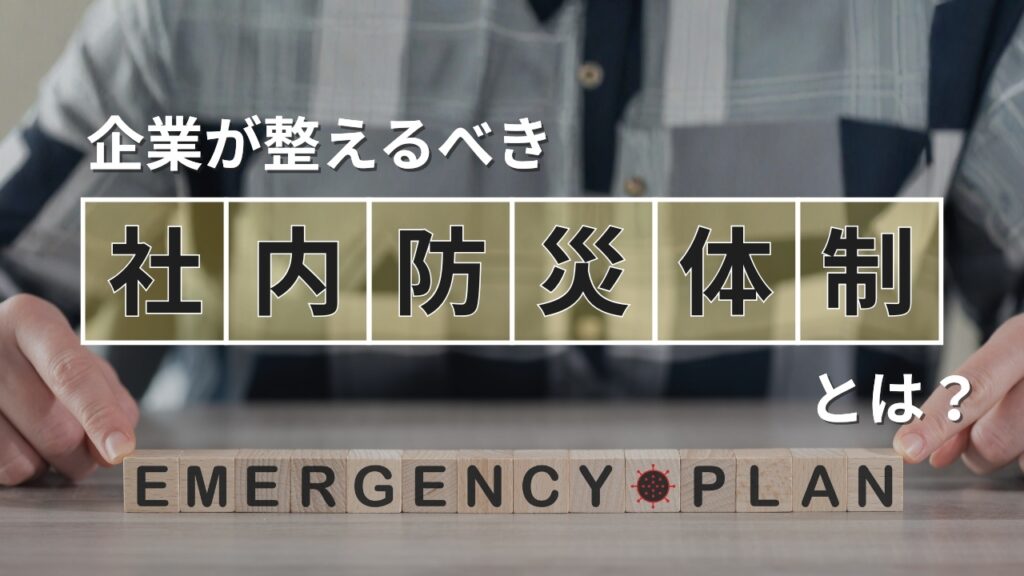
企業が整えるべき「社内防災体制」とは?
-
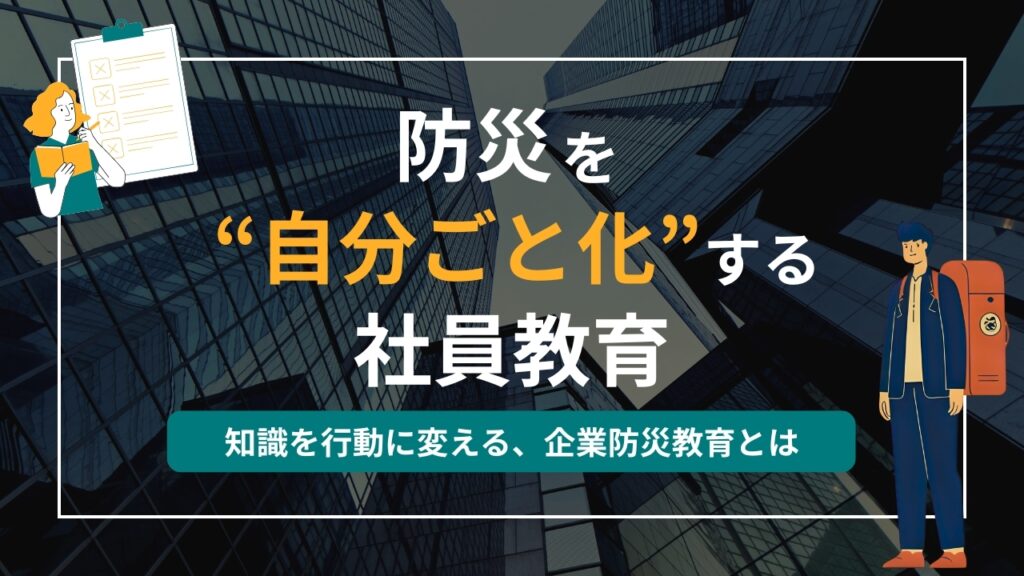
防災を“自分ごと化”する社員教育 |知識を行動に変える、企業防災教育とは
-
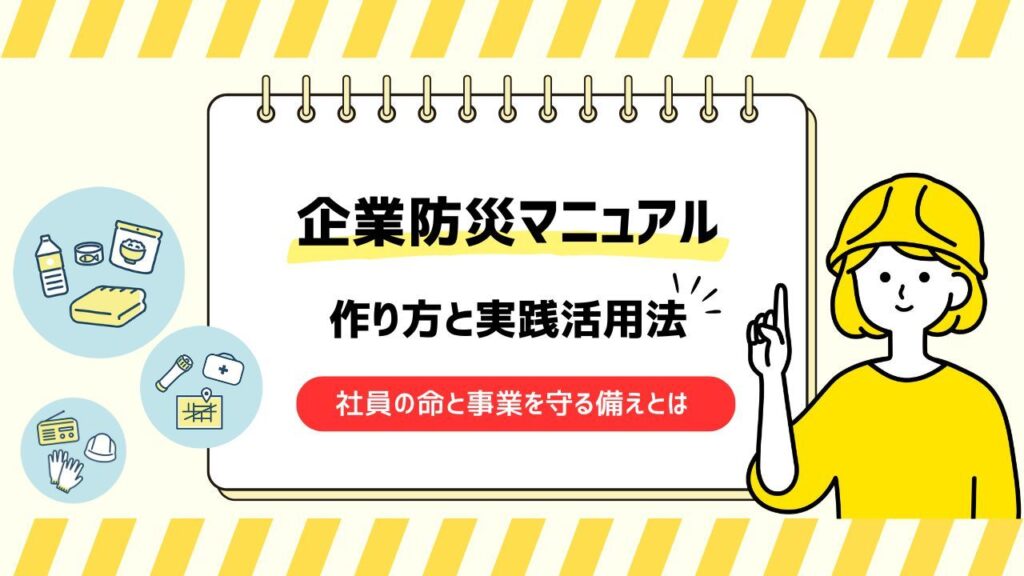
企業防災マニュアルの作り方と実践活用法|社員の命と事業を守る備えとは
-

企業防災とは?企業を守る実践的な防災・BCP対策ガイド
-

【企業防災研修】で社員と会社を守る!防災意識を高めるオーダーメイド研修とは
-
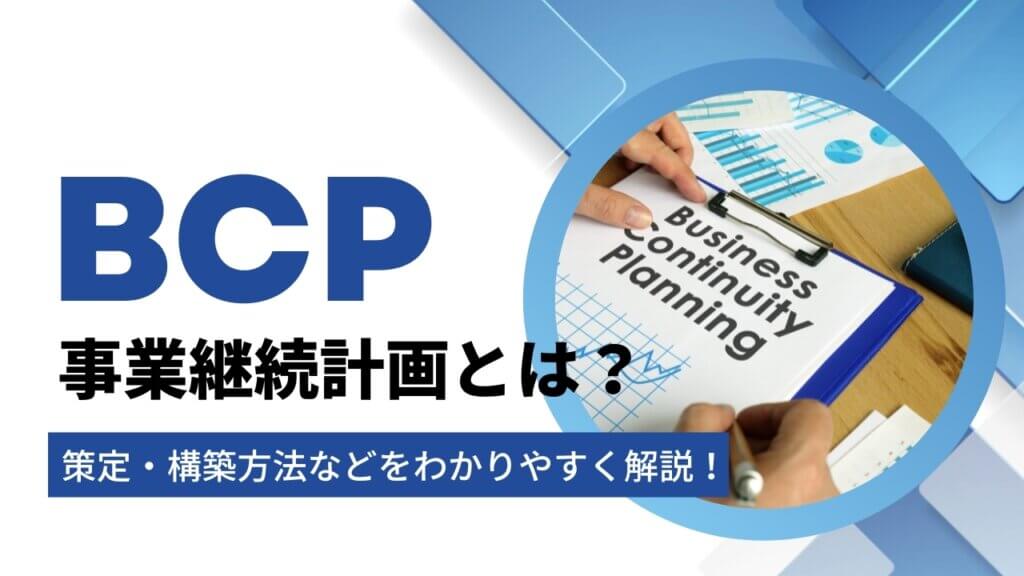
BCPとは?事業継続計画の策定・構築方法などをわかりやすく解説!