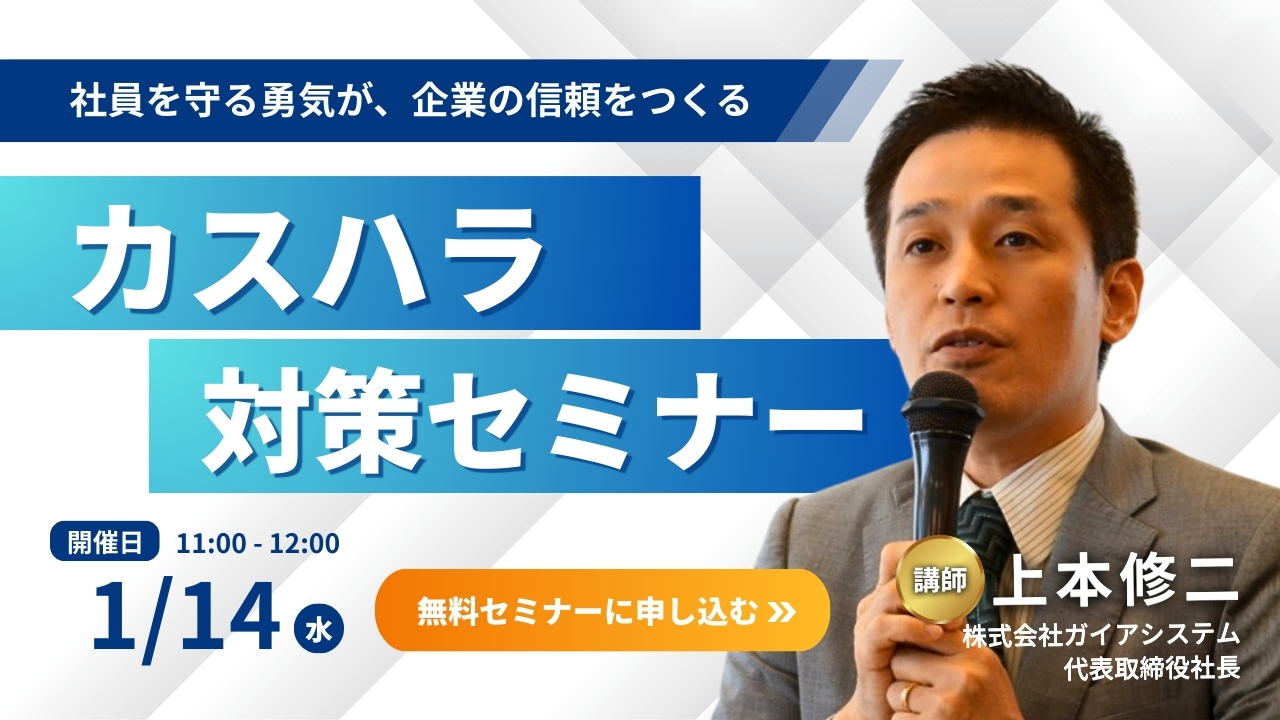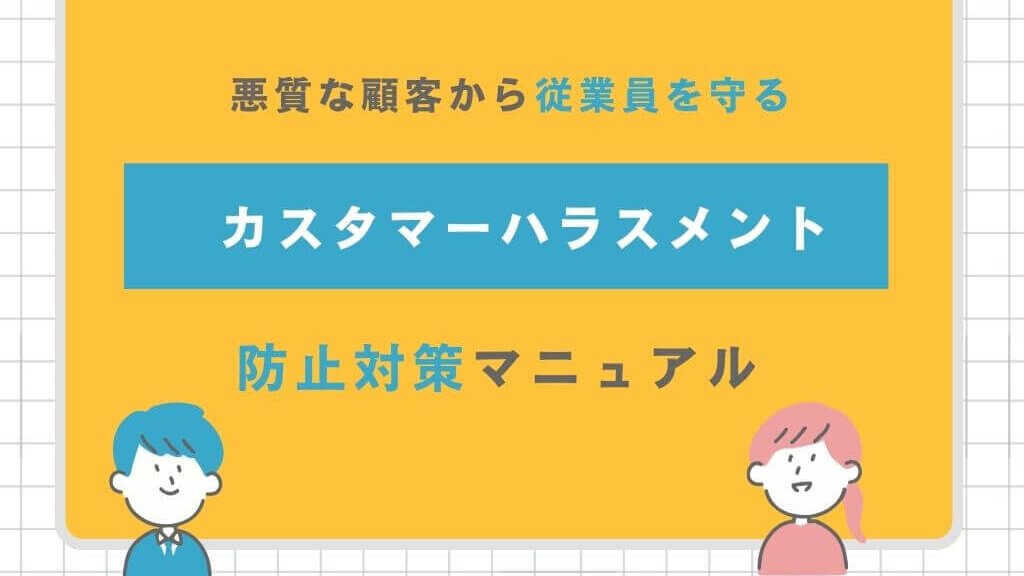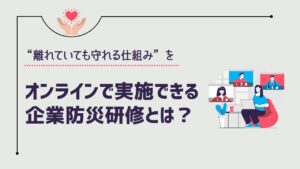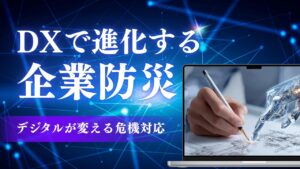オンラインで実施できる企業防災研修とは?
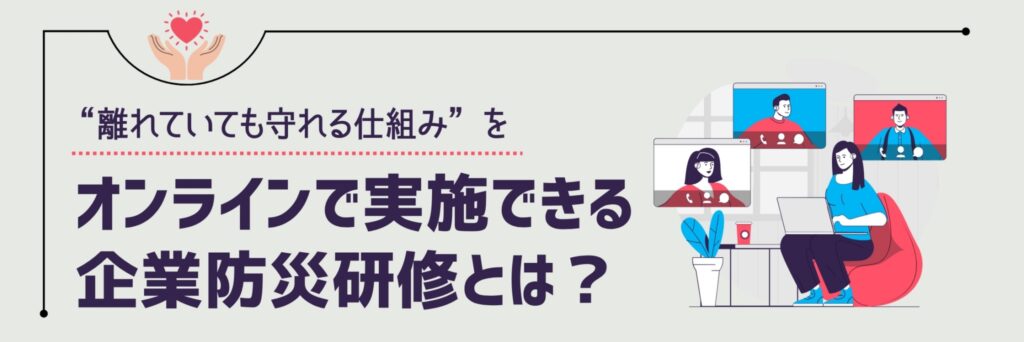
企業の「防災力」は、経営の持続性そのものを左右します。地震・水害・感染症などのリスクが高まる今、全社員が同じ防災意識を持ち、行動できる体制をつくることが急務です。
その新しい形として注目されているのが、オンラインで実施する企業防災研修。時間や場所にとらわれず、全国・海外の拠点をつなぎ、同じ防災文化を共有する仕組みが広がっています。
オンライン化が進む理由
働き方が変われば、防災研修のかたちも変わります。
テレワークや拠点分散が進む中、企業は“離れていても守れる仕組み”を求めています。
テレワーク・分散拠点の増加が背景に
これまで、企業の防災教育といえば「集合研修」が主流でした。しかし、コロナ禍を経て働き方が多様化し、その前提は大きく変わりました。
リモートワークやハイブリッド勤務の普及、地方拠点・在宅勤務者の増加により、“全員が一か所に集まる研修”は現実的ではなくなっています。それでも、災害は地域や職種を問わず、ある日突然やってきます。
だからこそ、今求められているのは「どこにいても社員が学べる仕組み」です。オンライン防災研修は、そうした新しい働き方に合わせて急速に広がっています。ZoomやTeamsなどのツールを使えば、全国の社員をリアルタイムでつなぎ、同じ災害想定のもとで“行動を考える”学びが可能です。

一極集中型の教育では、全社員の安全を守れません。
だからこそ「どこにいても学べる」オンライン研修が選ばれています。
防災研修 講師メッセージ:
「災害は“遠くの出来事”ではなく、ある日突然“自分の会社に起こる”ものです。
私自身、阪神淡路大震災で被災し、その後も東日本大震災や能登半島地震の現場を支援してきました。
その経験から感じるのは、“知識よりも、想像力と行動力が命を守る”ということ。
オンラインでも、現場の実感と心の緊張感を伝えることを大切にしています。」
オンライン防災研修のメリットと注意点
オンライン化は“便利”なだけではありません。防災教育を全社員に浸透させる、持続的な仕組みづくりの鍵になります。
「全員に届く防災教育」がオンラインで可能に
防災研修をオンライン化することで、防災教育はより「公平で、継続しやすい仕組み」へと進化しました。地理的な距離や時間の制約を超えて、すべての社員が同じ内容を学べる。それが、オンライン化による最大の強みです。
防災研修は、何より“早く、広く、正しく届けること”が大切です。だからこそ、役職や部署の垣根を越えて、全員が同じ危機意識を共有することが欠かせません。
これまで集合研修では参加が難しかった拠点や職種の社員にも、防災意識をしっかり届けることができます。地域や立場を超えて同じ意識を持つことが、結果的に“組織全体の危機対応力”を高めていくのです。
主なメリット
- 全国どこからでも受講可能
拠点間の温度差をなくし、全社一体で防災文化を形成できます。 - コストと時間の最適化
講師の移動や会場手配が不要なため、費用を30〜50%削減できます。
また、昼休みや短時間枠でも開催でき、通常業務との両立が容易です。 - 継続的な学びができる
リアルなオンライン研修ですが、ご要望により、録画し再視聴で反復学習も可能です。
新入社員研修やご家族向けの研修としても活用できます。 - BCP(事業継続計画)との連携が容易
オンラインだからこそ、災害後の連絡体制・在宅勤務中の安否確認など、BCP対応教育にも直結します。
注意点
一方で、「オンラインでは臨場感が薄れる」「受け身になりやすい」といった課題もあります。
実際に体を動かす避難訓練や、消火・応急手当などの体験型要素はオンラインでは再現しにくいため、別の機会に実地で行うことが望ましいでしょう。
また、通信環境による格差や、参加者同士の温度差が生まれやすい点にも注意が必要です。こうした課題を補うために、双方向型の構成(投票・チャット・事例ワーク)や、被災映像を用いた臨場感ある演出を組み合わせることが効果的です。
オンラインの特性を理解したうえで、「知識+体験」を組み合わせることで、最も効果的な防災教育が実現します。
ガイアシステムの防災研修では、この「オンラインの限界」を補うために、講師陣が実際に被災地で活動しているという強みを活かしています。

阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震、能登半島地震など、
数多くの災害現場で支援を続けてきたスタッフが登壇し、
現地で得た“生の教訓”と“人の声”を研修に取り入れています。
さらに、希望する企業には被災地を訪れて学ぶ「スタディツアー型研修」も実施。現地で語り部の話を聞き、復興の現場に触れることで、社員一人ひとりが「自分に何ができるか」を考える実践的なプログラムです。
こうした取り組みを通じて、ガイアシステムは「オンラインで学び」「現地で感じ」「日常で活かす」という三位一体の防災教育を提供しています。それが、“企業の防災文化を根づかせる”ための本質的なアプローチです。
防災研修 講師メッセージ:
「ガイアシステムの防災研修は、“教育研修のノウハウ × 災害現場の経験”から生まれました。
20年以上の人材育成経験をもとに、行動変容を引き出す“心に届く教育”を設計しています。
被災地で聞いた『もっと備えていれば助かったかもしれない』という声を、学びに変えていく――それがこの研修の使命です。」
【無料】資料ダウンロード

防災研修 | カリキュラム事例
【資料の内容】
・防災研修が必要な理由
・企業の災害対策の実態
・企業の災害対策に関する実態調査
・防災研修のカリキュラム紹介
・価格表/実績紹介
実際に効果を上げるオンライン研修の設計方法
効果的な防災研修に必要なのは、“伝えること”より“行動を変えること”。オンラインでもそれを実現する設計が可能です。

防災研修の成果は「学んだこと」ではなく「動けるかどうか」。
その行動を育てる3つの要素を押さえることが大切です。
「知識ではなく、行動を育てる」ための3ステップ
オンライン防災研修を成果につなげるには、単に映像を流すだけでは不十分です。
重要なのは、社員が“自分の行動を変える”ための設計にあります。
目的を明確にする
まず、「何のために行うのか」を明確に設定します。
たとえば、
- 災害時の安否確認フローの理解
- 初動行動の迅速化
- 在宅勤務時の安全確保
- BCPの社内定着
といった具体的なゴールを設定することが成果の鍵です。
リアルなシナリオを設計する
実際の災害映像や事例をもとに、「あなたならどう動くか」を考える構成にします。
リアルなケースを通じて、自分事として危機を捉えることで、理解が行動に変わります。
たとえば、「地震でエレベーターが停止したら?」「豪雨で帰宅できなくなったら?」といった具体的な状況をシミュレーションします。その判断の積み重ねが、“命を守る思考力”と“即時対応力”を養うのです。
双方向性を高める
チャット・投票・ブレイクアウト機能などを活用し、受講者が意見を共有できる仕組みを取り入れます。
「講師の話を聞く」だけでなく、「自分が考え、判断し、発言する」プロセスを設計することが重要です。
防災研修 講師メッセージ:
「災害対応力は、“反射的に動ける力”です。日常の中で小さなシミュレーションを重ねることで、いざというときに迷わず行動できます。知識よりも、“訓練の積み重ね”が命を守る最大の備えです。」
受講者を巻き込む仕掛け
オンラインでも“体験”を共有することで、学びは深まります。五感と想像力を使った参加型設計が、防災教育の効果を左右します。
想像力を鍛えるワークが、命を守る行動を生む
オンライン防災研修の肝は「体験の共有」です。画面越しでも“体で覚える”感覚を生み出すことが、行動変容に直結します。
ガイアシステムの防災研修では、被災地で活動してきた講師が登壇し、現場で見て、感じた「リアルな災害の姿」を伝えます。
東日本大震災、熊本地震、能登半島地震などの写真や映像を交え、災害が起きた瞬間、何が起こるのか――その「現実」を体感してもらいます。
講義では、次のような流れで、想像力と行動判断を高めていきます。
- 防災の基本と意識づくり
なぜ研修会社が防災研修を行うのか?
その目的を明確にし、「自分と仲間の命を守る」行動を考えるきっかけをつくります。 - 災害現場のリアルを知る
被災地で実際に起きた出来事や、避難所での生活環境を知り、想像を“現実”に近づけます。 - 大規模災害の危険性を学ぶ
南海トラフ地震など政府発表の想定被害をもとに、「助けが来ない前提」で考える重要性を理解します。 - 映像で感じる災害の現実
「日常が一瞬で失われる」ことを、映像シミュレーションで体感。
南海トラフ地震や東日本大震災の記録映像を通じて、現実との距離を縮めます。 - 命を守る具体的な行動訓練
オフィス・外出先・車内・水害時など、状況ごとの行動を整理。
実際に「どう動くか」をシナリオ形式で考えます。 - 地域リスクの把握と備え
ハザードマップを活用し、職場・自宅・通勤経路での避難行動を可視化。
自分の地域特性を踏まえた行動判断を考えます。 - 備蓄・避難・応急対応の基本
「3日分の備蓄」では足りない、という現実を踏まえた長期化への備えを学びます。
出血や骨折などの応急処置、避難時の判断、車中避難などを具体的に解説。
また、研修後のアンケート分析により、部署ごとの防災意識を可視化し、社内の改善に活かすこともできます。オンラインだからこそ、データを活用した教育の継続が可能です。
防災研修 講師メッセージ:
「防災で一番大切なのは“想像力”です。
『ここで地震が起きたら?』『家族がいたら?』――
その“もしも”を日常の中で想像する力が、いざというときに命を守ります。
そして、全員が同じ危機感を共有していることが、組織の強さになります。」
また、研修後には各社員が「日常でできる備え」を見直すためのワークシートを実施。家庭の備蓄リストや地域の避難経路をチェックし、“職場と家庭の両方で備える力”を身につけます。
オンラインであっても、受講者が頭と心の両方で「行動を想像する」こと。それこそが、このプログラムの最大の特徴です。

リアルな想定を通して「自分ごと」に変わる瞬間があります。
その気づきこそが、防災教育のゴールです。
よくある質問(Q&A)
まとめ|どこからでも学べる「実践型防災教育」へ
防災研修の目的は「知識を増やすこと」ではなく、「命を守る行動を身につけること」です。
オンラインであっても、心を動かす学びと実践の機会を提供することで、その本質は十分に伝わります。
講師メッセージ:
「私たちが防災研修を行う理由は、被災地で聞いた“後悔の声”を次につなげるためです。
“備えていれば助かったかもしれない”という声を、もう二度と聞かないために。
オンラインを通じても、全国の社員が“命を守る判断力”を身につけてほしい――それが、私たちの願いです。」
全国どこからでも受講できるオンライン防災研修については、ガイアシステムへご相談ください。
防災研修カリキュラム
有事に備え、社員の命を守るー実践的な防災対策を!
企業向け防災研修
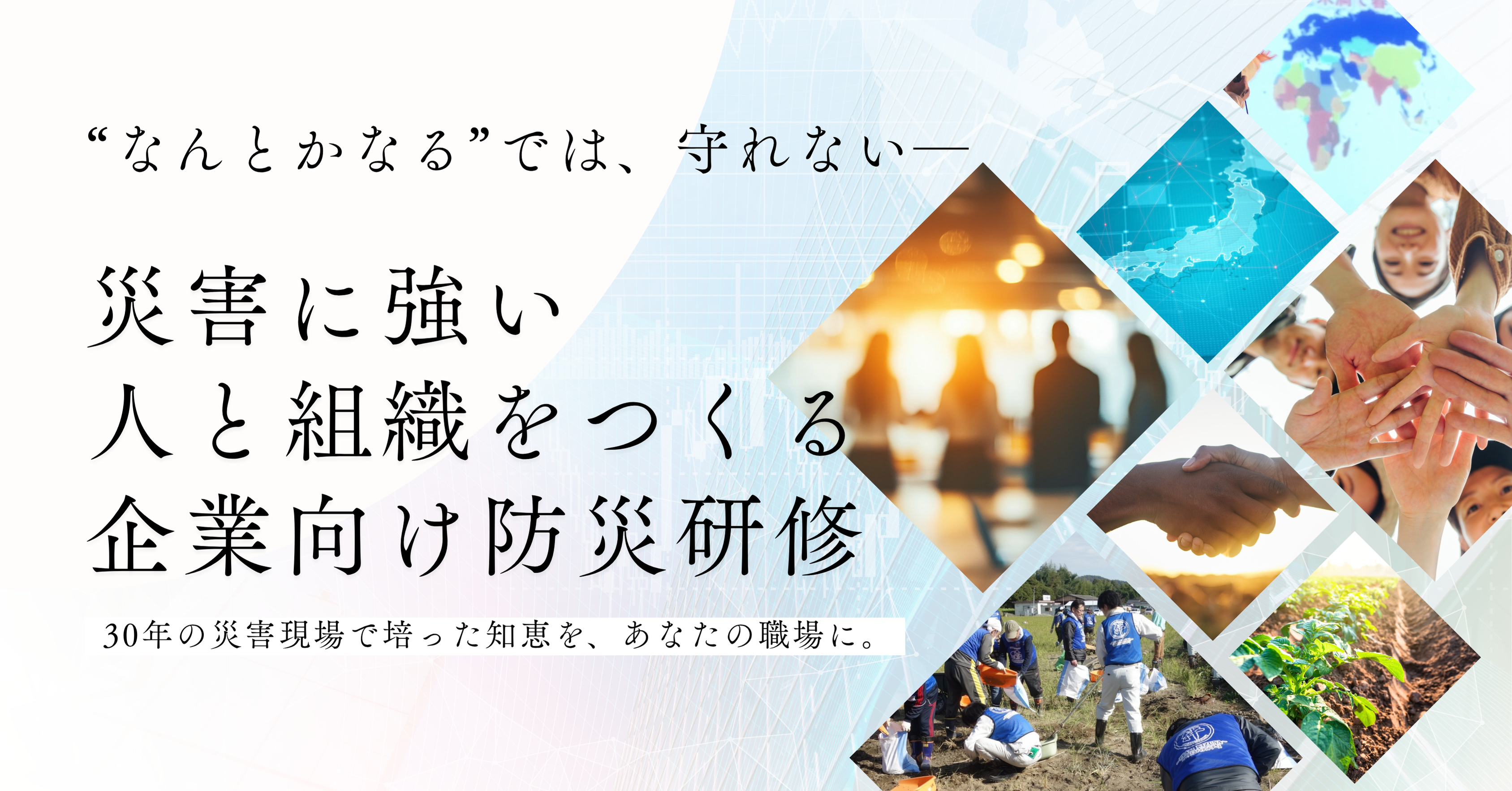
30年以内に80%の確率で発生すると言われる南海トラフ地震。企業には社員の命を守る具体的な「防災力」の強化が求められています。
本研修は、いざという時に“行動できる力”を育てる実践的プログラム。有事に備え、社員の安全を確保するための第一歩を、踏み出しませんか。
企業活動を止めずに従業員や顧客の安全を守る!
BCP(業務継続計画)研修

自然災害が頻発する日本において、企業活動を止めずに従業員や顧客の安全を守るためには、防災への備えが欠かせません。
本研修は、従業員一人ひとりが危機時に適切に対応し、企業全体で迅速かつ効果的に復旧を図る力を養うことを目的に、基礎知識の習得から実践的なシミュレーションを通じて企業全体の防災力を強化します。
リスク意識を高め 危機を未然に防ぐ!
リスクマネジメント研修
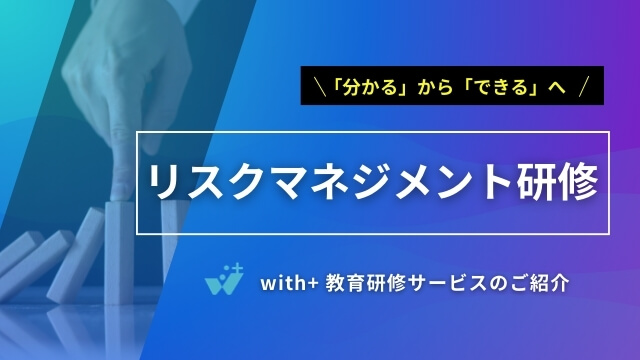
リスクマネジメント研修は、企業が直面する様々なリスクを特定、評価し、適切な対策を立てる能力を養成する教育プログラムです。
リスクの洗い出し、優先順位付け、対応策の策定などを学び、組織全体のリスク管理能力を向上を目指します。
企業防災コラム一覧
-
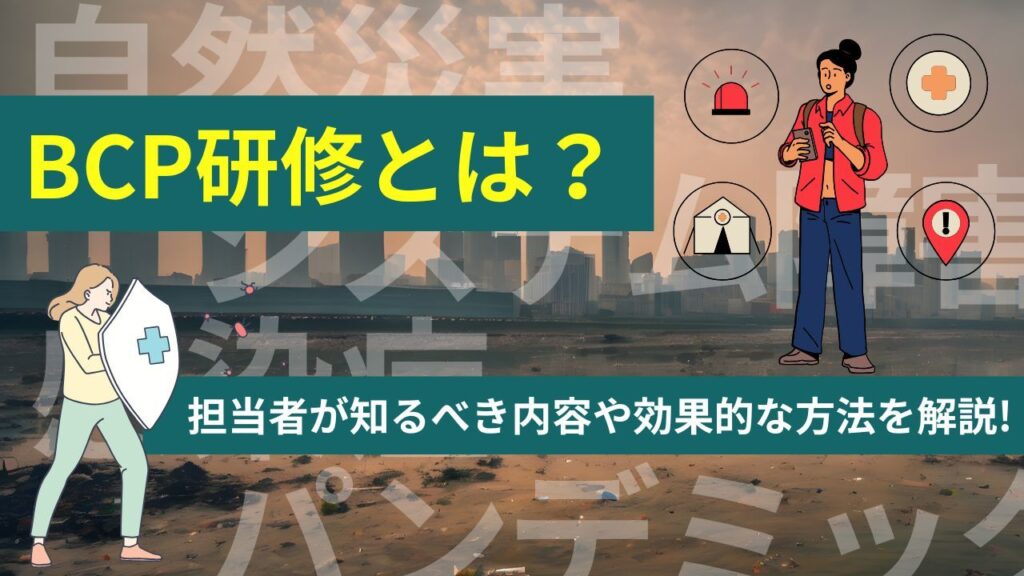
BCP研修とは?担当者が知るべき内容や効果的な方法を解説
-
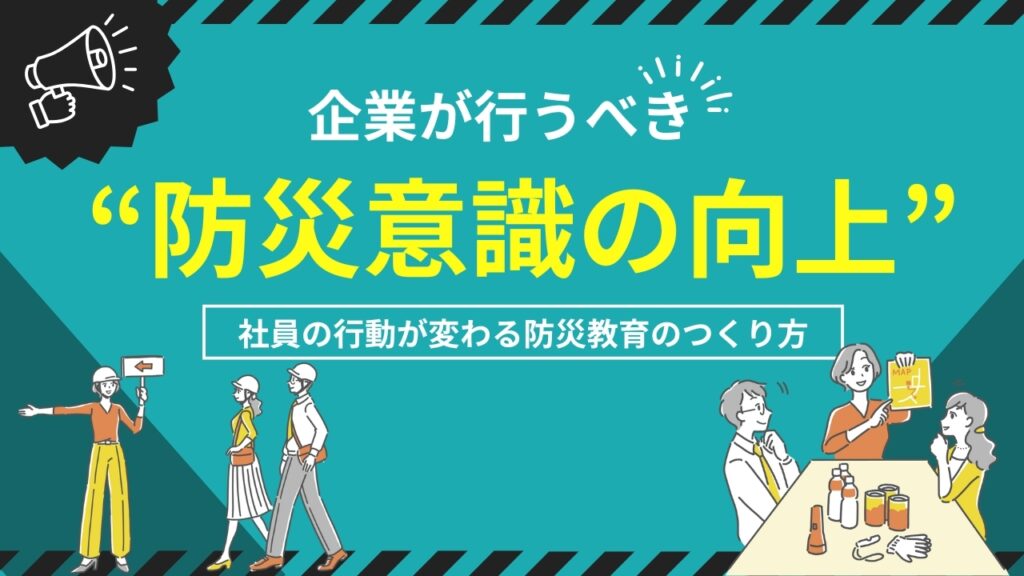
災害時に“行動できる社員を育てる”企業防災とは?防災意識を高める具体策
-
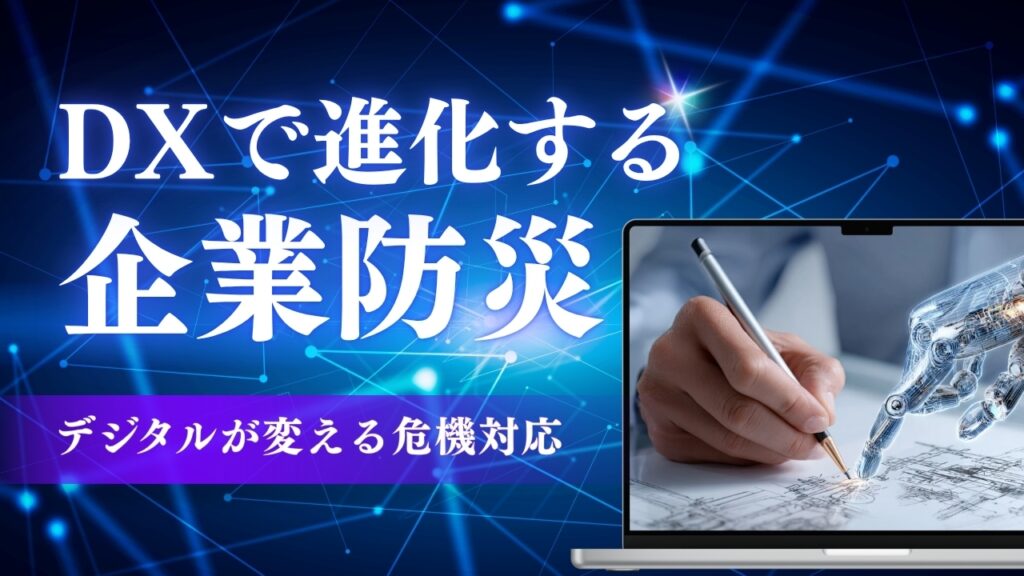
DXで進化する企業防災|デジタルが変える危機対応
-
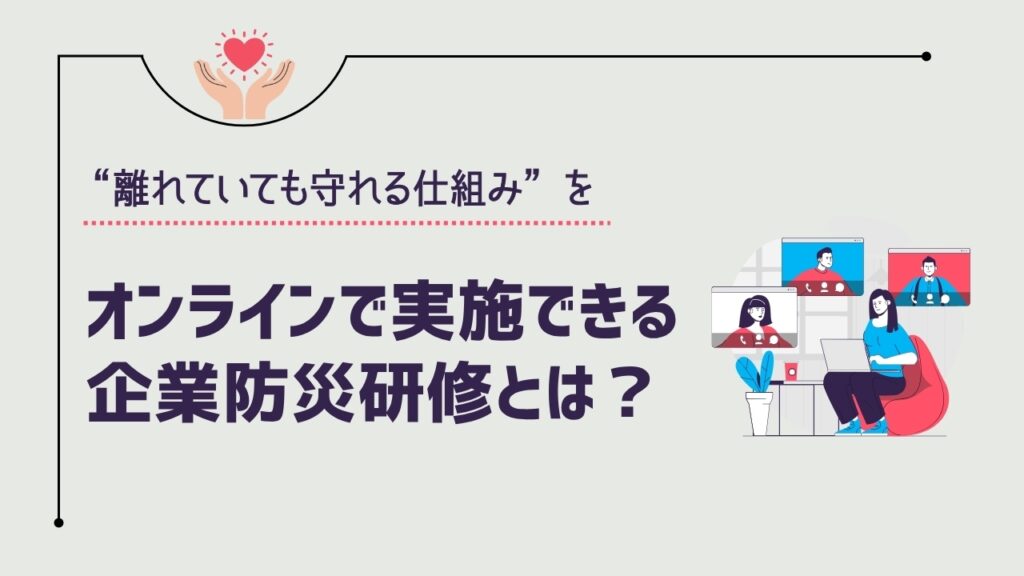
オンラインで実施できる企業防災研修とは?
-
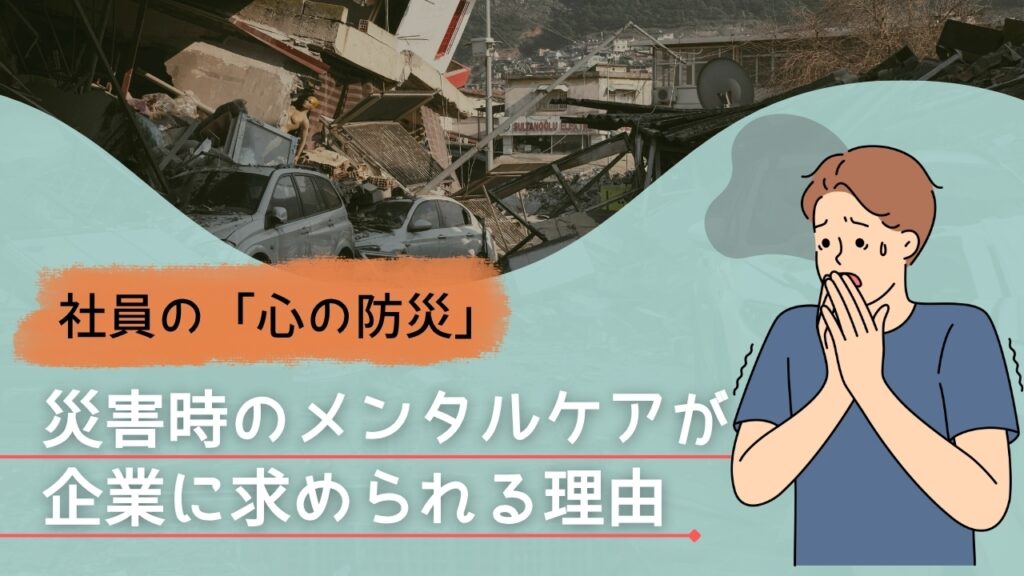
災害時のメンタルケアが企業に求められる理由
-
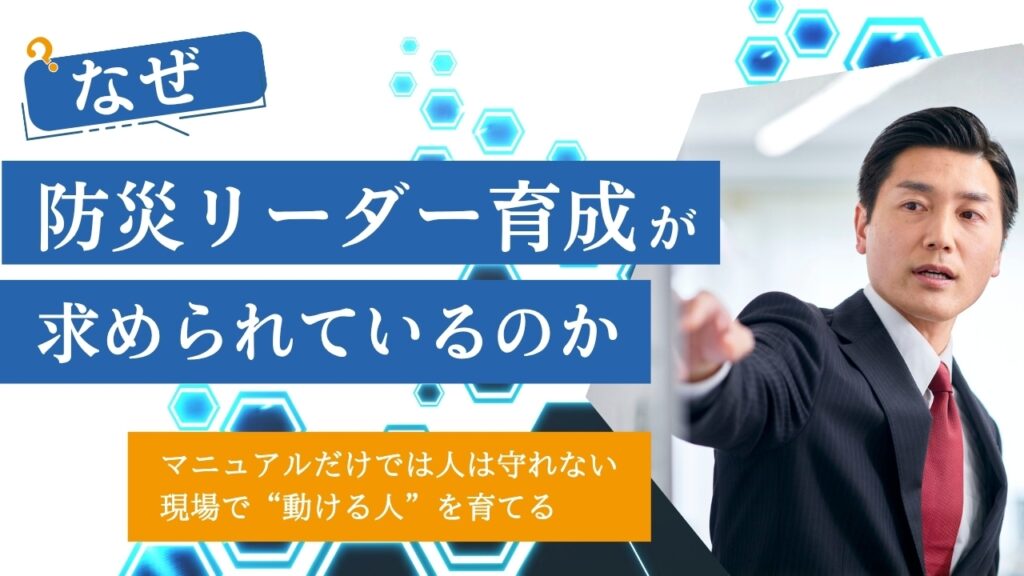
なぜ今、防災リーダー育成が求められているのか
-
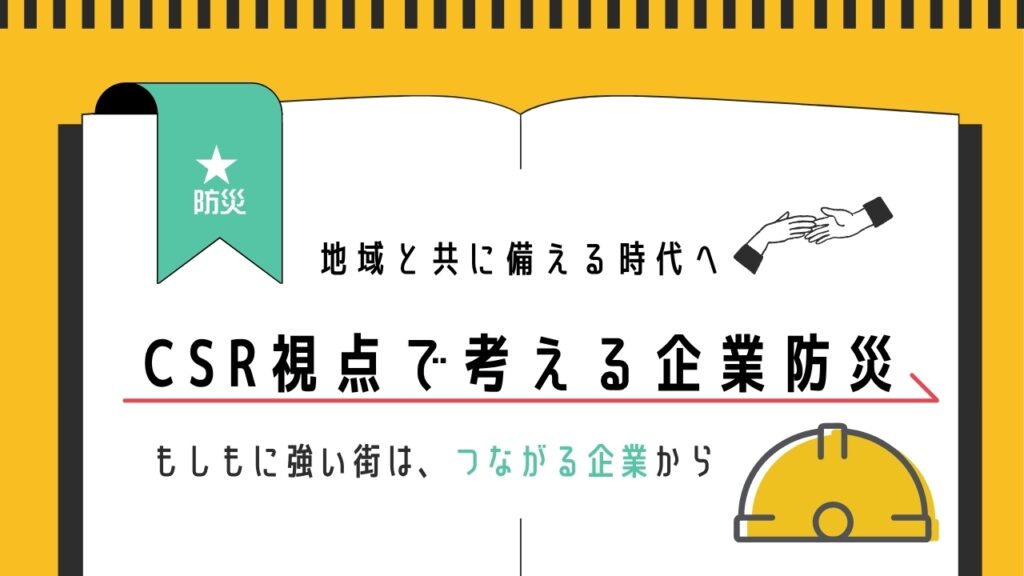
CSR視点で考える企業防災|地域と共に備える時代へ
-
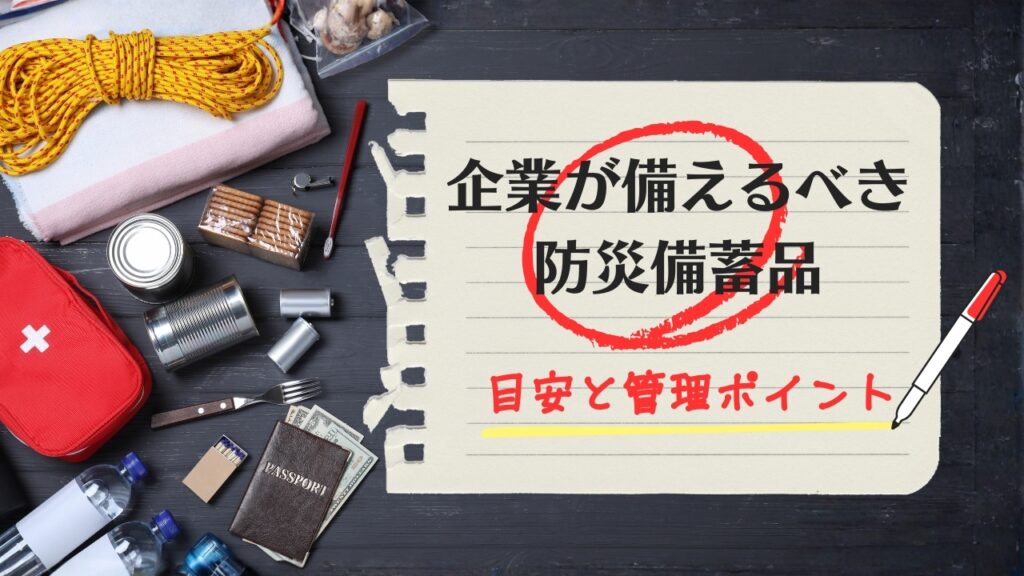
企業が備えるべき防災備蓄品の目安と管理ポイント
-
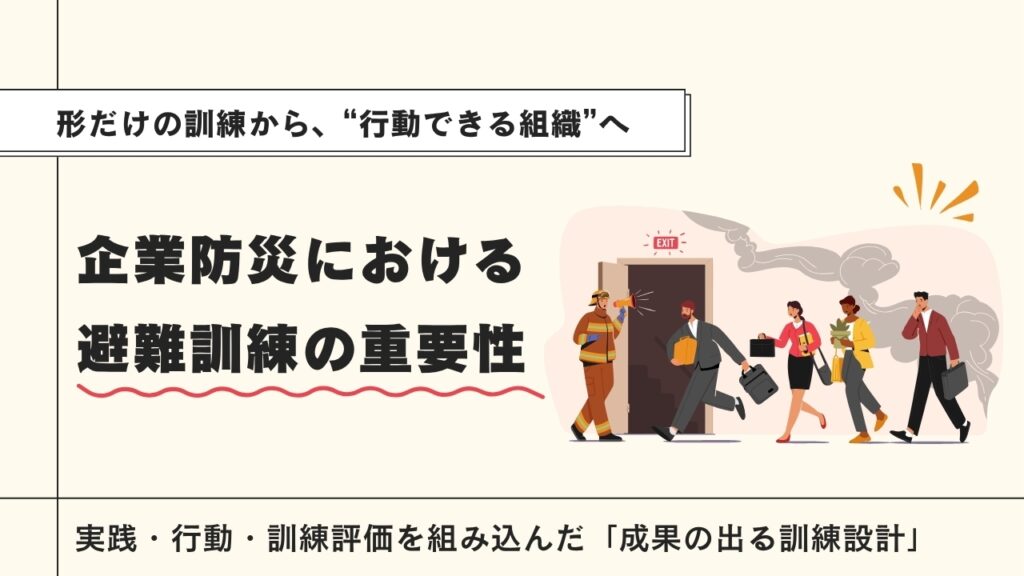
企業防災における避難訓練の重要性|形だけの訓練から、“行動できる組織”へ
-
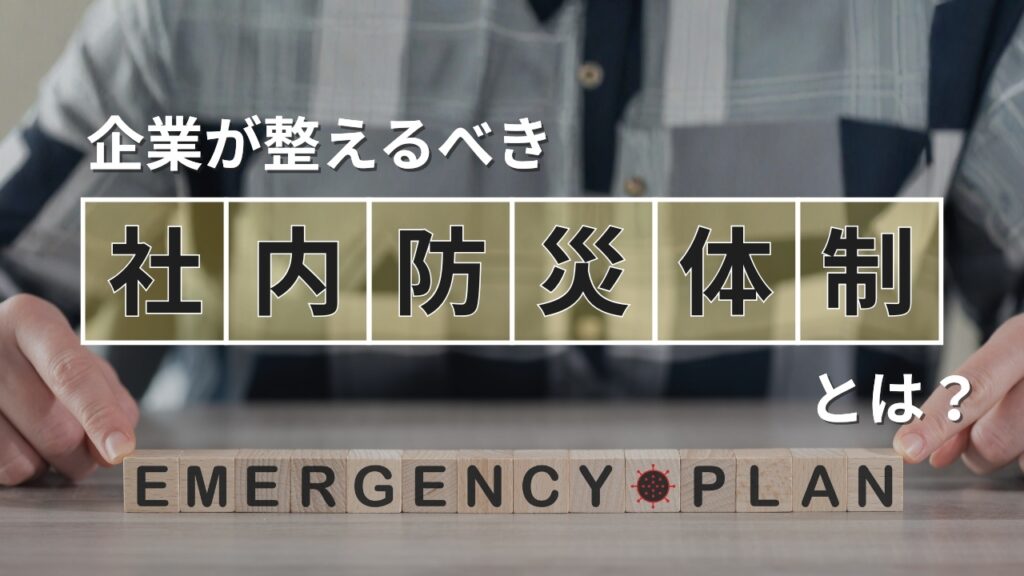
企業が整えるべき「社内防災体制」とは?
-
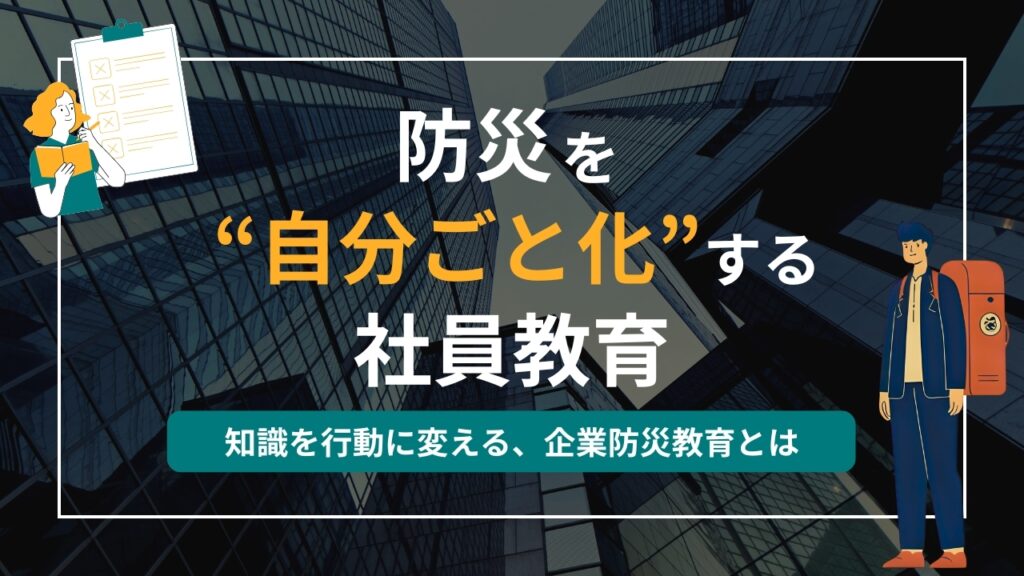
防災を“自分ごと化”する社員教育 |知識を行動に変える、企業防災教育とは
-
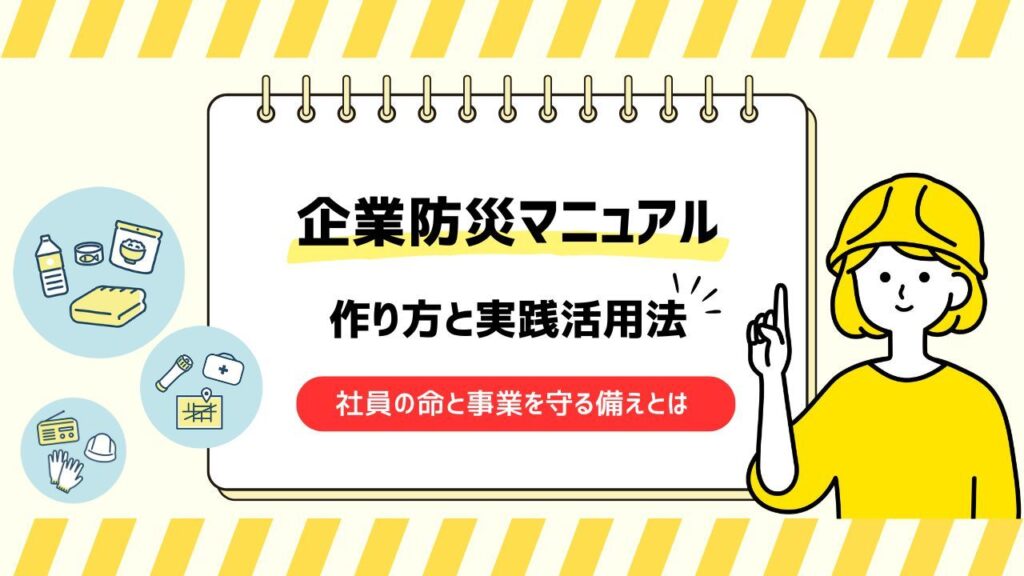
企業防災マニュアルの作り方と実践活用法|社員の命と事業を守る備えとは
-

企業防災とは?企業を守る実践的な防災・BCP対策ガイド
-

【企業防災研修】で社員と会社を守る!防災意識を高めるオーダーメイド研修とは
-
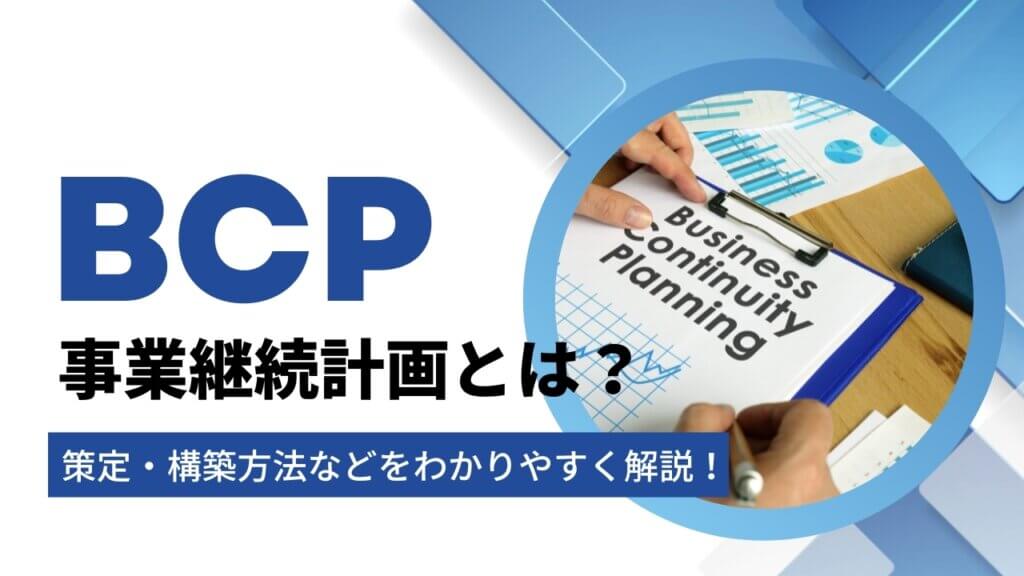
BCPとは?事業継続計画の策定・構築方法などをわかりやすく解説!
防災研修カリキュラム
有事に備え、社員の命を守るー実践的な防災対策を!
企業向け防災研修
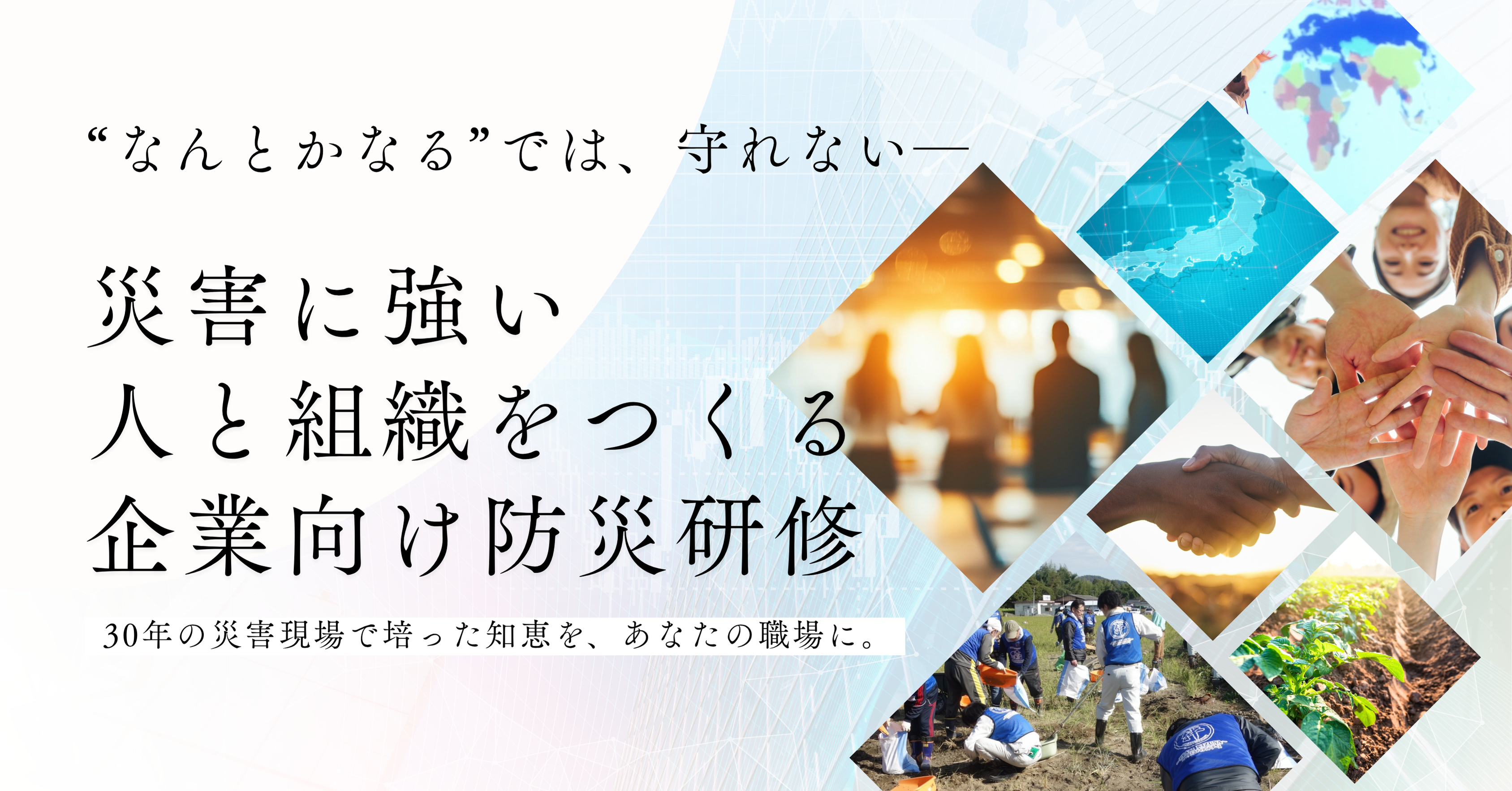
30年以内に80%の確率で発生すると言われる南海トラフ地震。企業には社員の命を守る具体的な「防災力」の強化が求められています。
本研修は、いざという時に“行動できる力”を育てる実践的プログラム。有事に備え、社員の安全を確保するための第一歩を、踏み出しませんか。
企業活動を止めずに従業員や顧客の安全を守る!
BCP(業務継続計画)研修

自然災害が頻発する日本において、企業活動を止めずに従業員や顧客の安全を守るためには、防災への備えが欠かせません。
本研修は、従業員一人ひとりが危機時に適切に対応し、企業全体で迅速かつ効果的に復旧を図る力を養うことを目的に、基礎知識の習得から実践的なシミュレーションを通じて企業全体の防災力を強化します。
リスク意識を高め 危機を未然に防ぐ!
リスクマネジメント研修
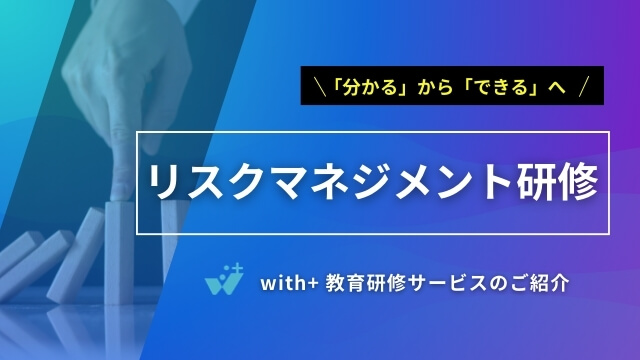
リスクマネジメント研修は、企業が直面する様々なリスクを特定、評価し、適切な対策を立てる能力を養成する教育プログラムです。
リスクの洗い出し、優先順位付け、対応策の策定などを学び、組織全体のリスク管理能力を向上を目指します。
企業防災コラム一覧
-
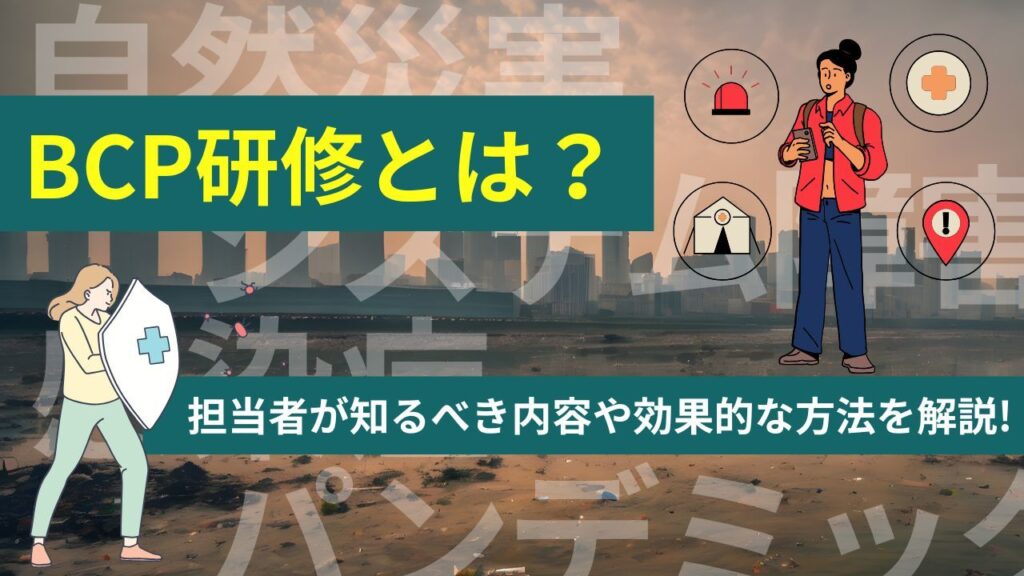
BCP研修とは?担当者が知るべき内容や効果的な方法を解説
-
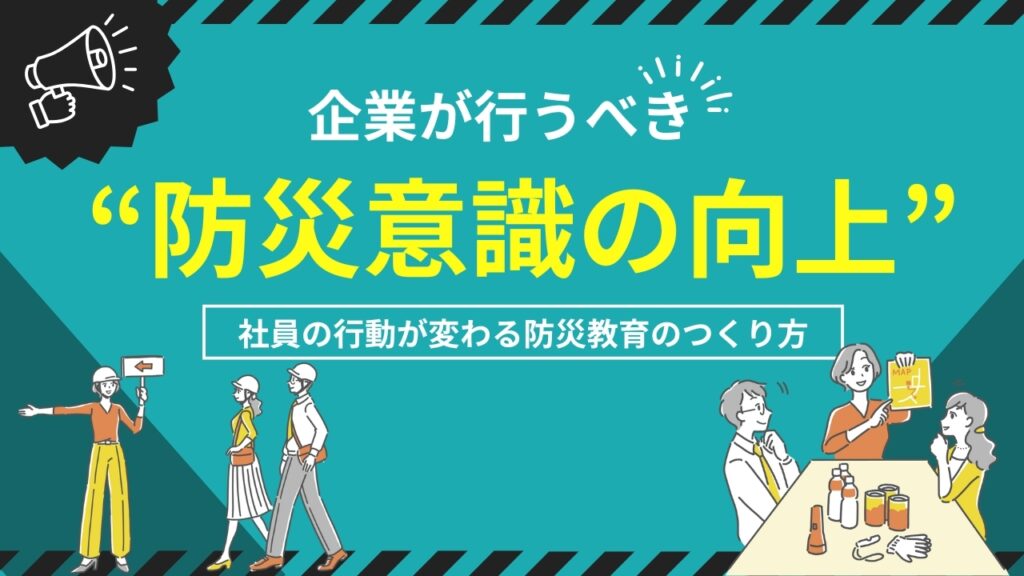
災害時に“行動できる社員を育てる”企業防災とは?防災意識を高める具体策
-
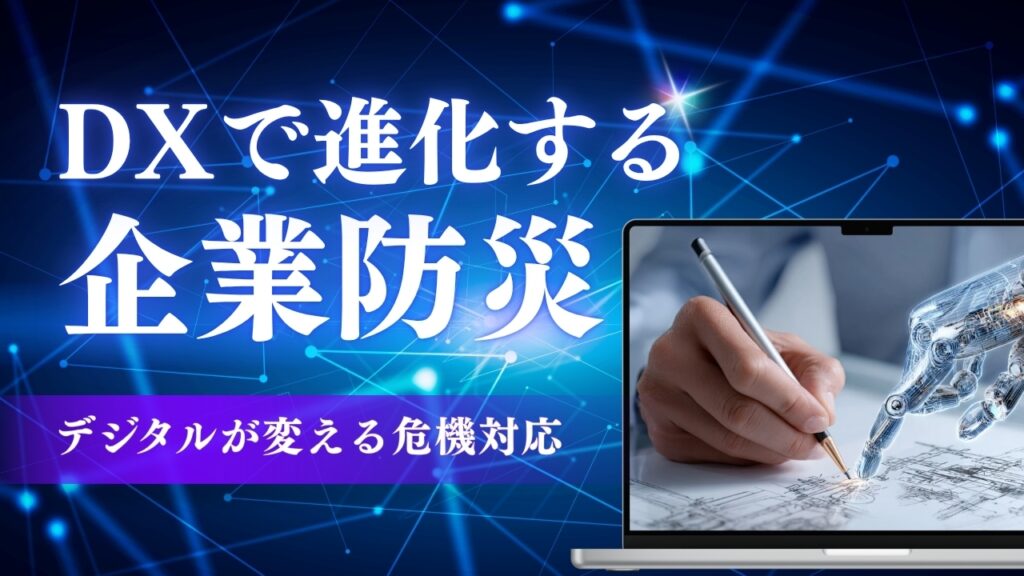
DXで進化する企業防災|デジタルが変える危機対応
-
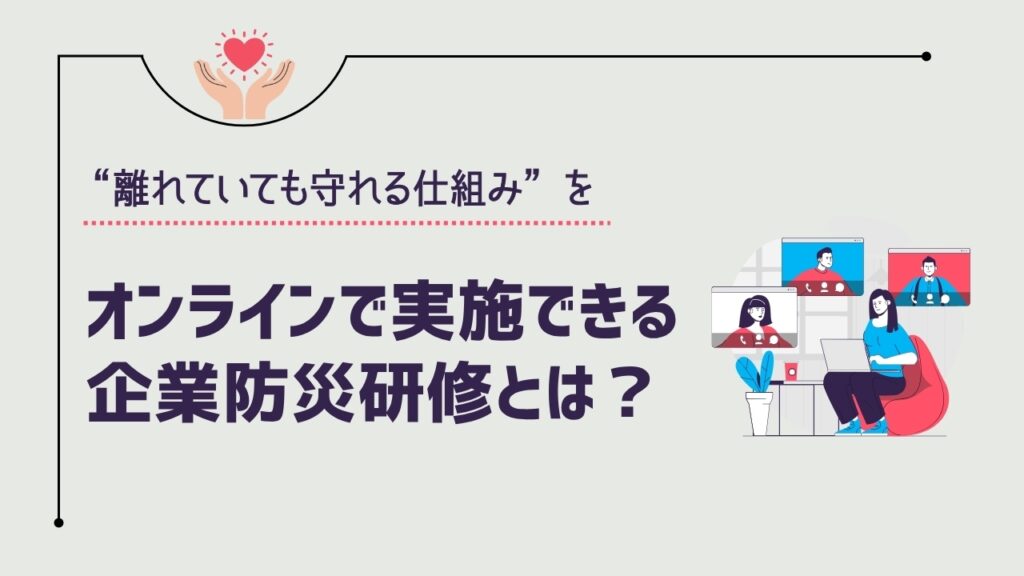
オンラインで実施できる企業防災研修とは?
-
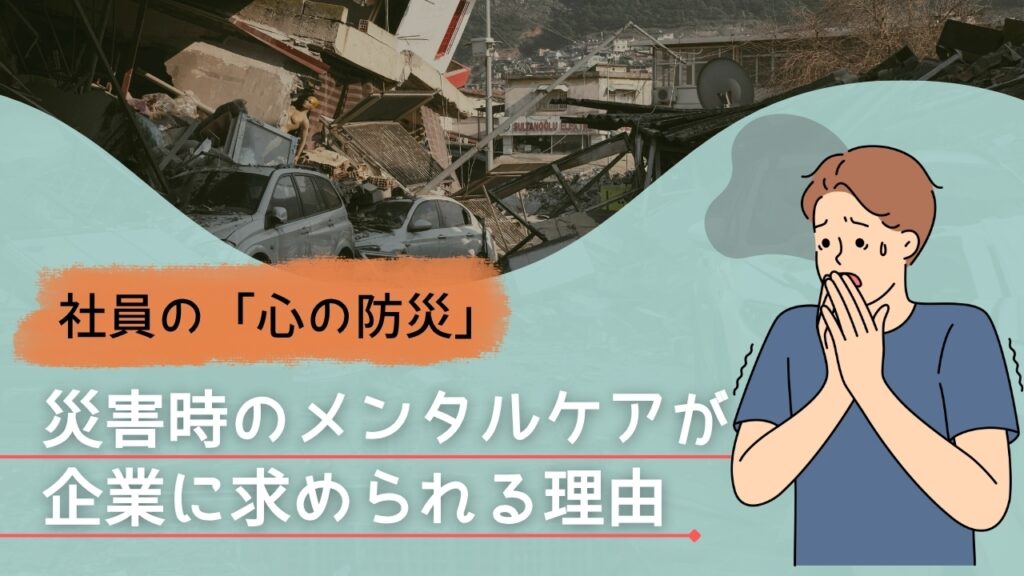
災害時のメンタルケアが企業に求められる理由
-
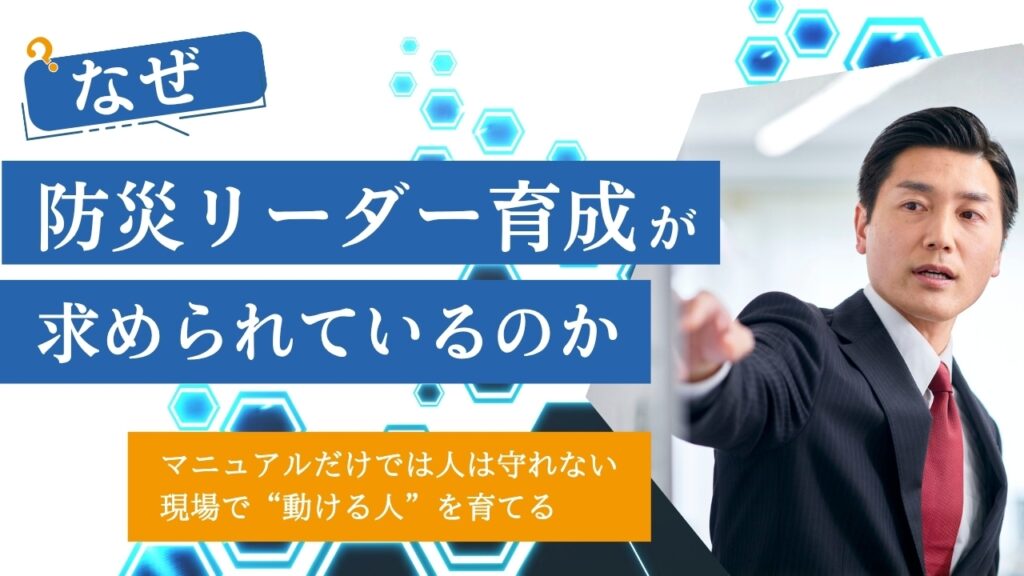
なぜ今、防災リーダー育成が求められているのか
-
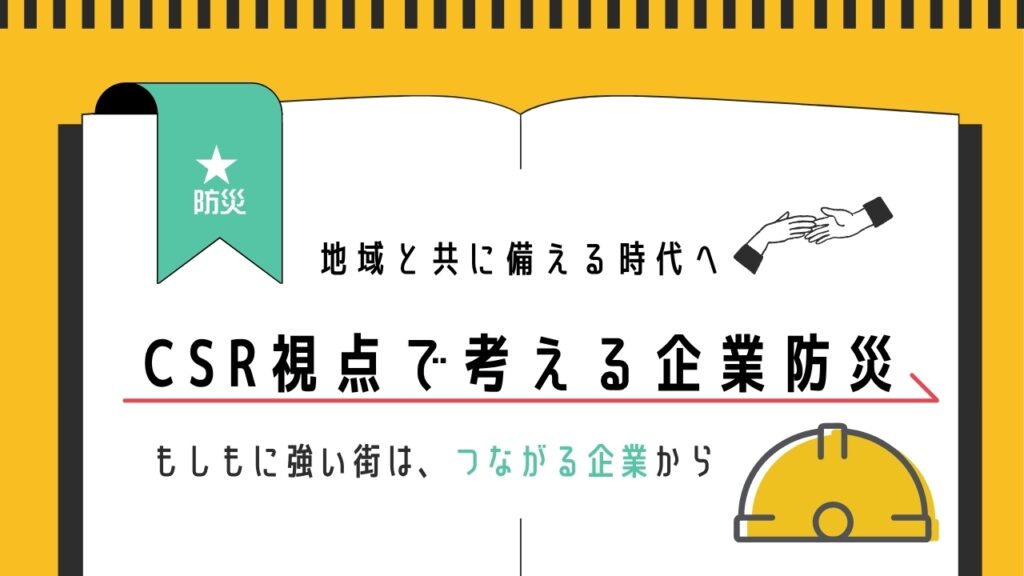
CSR視点で考える企業防災|地域と共に備える時代へ
-
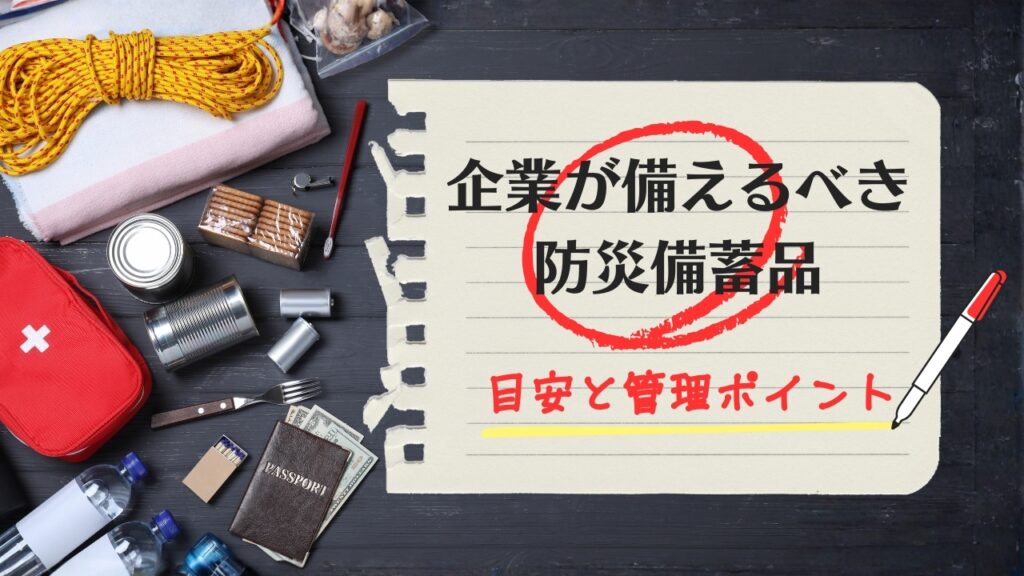
企業が備えるべき防災備蓄品の目安と管理ポイント
-
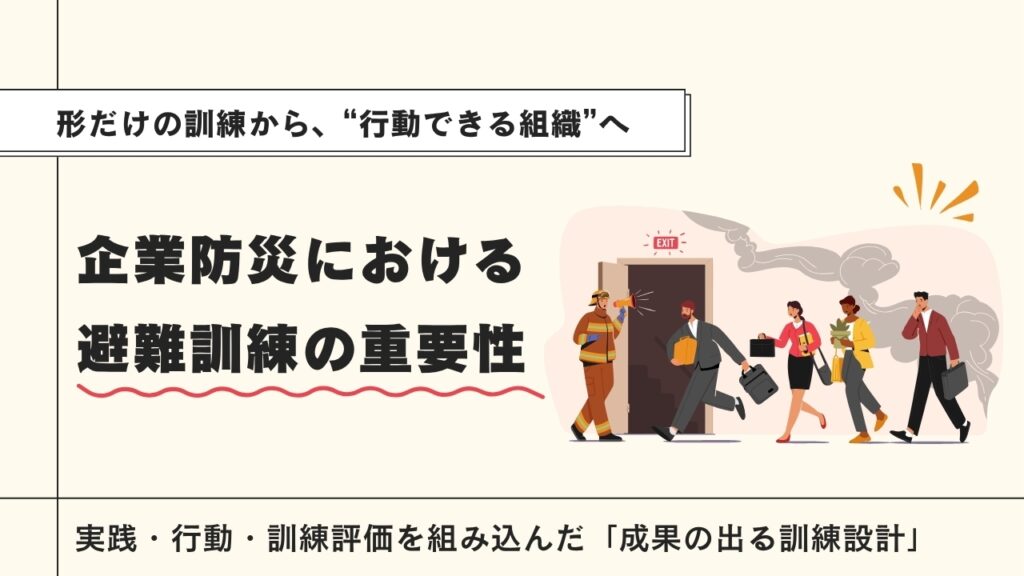
企業防災における避難訓練の重要性|形だけの訓練から、“行動できる組織”へ
-
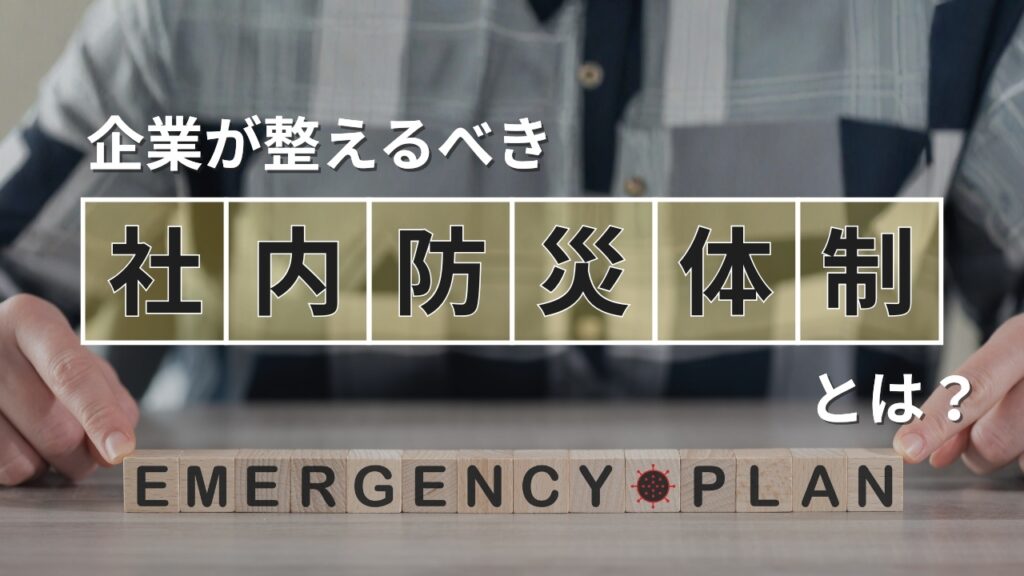
企業が整えるべき「社内防災体制」とは?
-
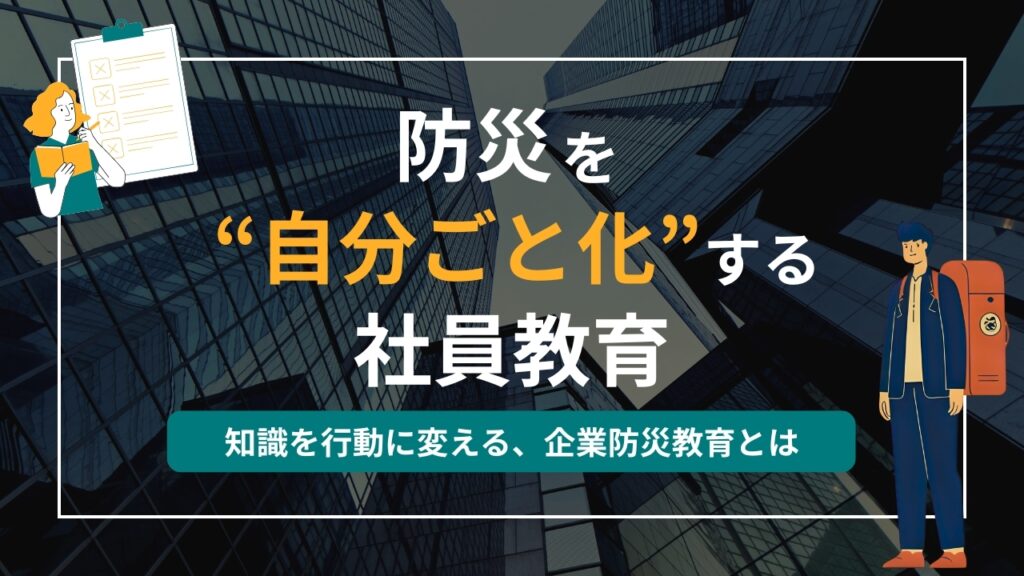
防災を“自分ごと化”する社員教育 |知識を行動に変える、企業防災教育とは
-
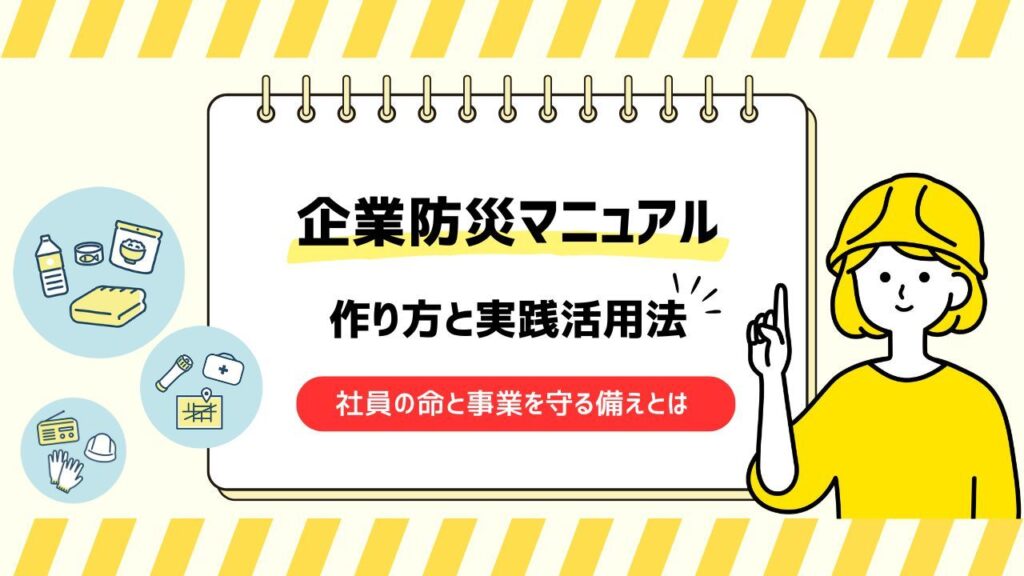
企業防災マニュアルの作り方と実践活用法|社員の命と事業を守る備えとは
-

企業防災とは?企業を守る実践的な防災・BCP対策ガイド
-

【企業防災研修】で社員と会社を守る!防災意識を高めるオーダーメイド研修とは
-
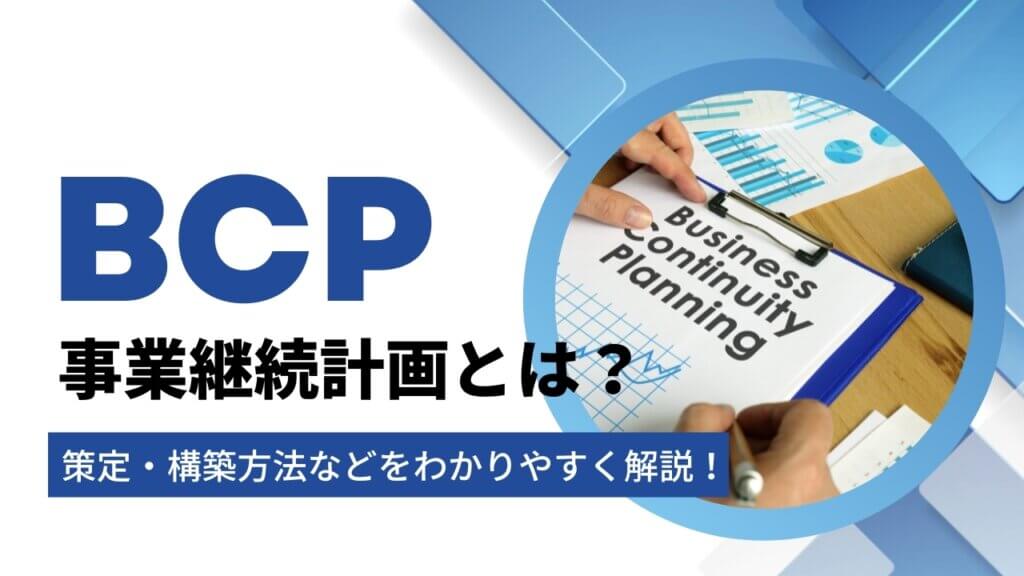
BCPとは?事業継続計画の策定・構築方法などをわかりやすく解説!