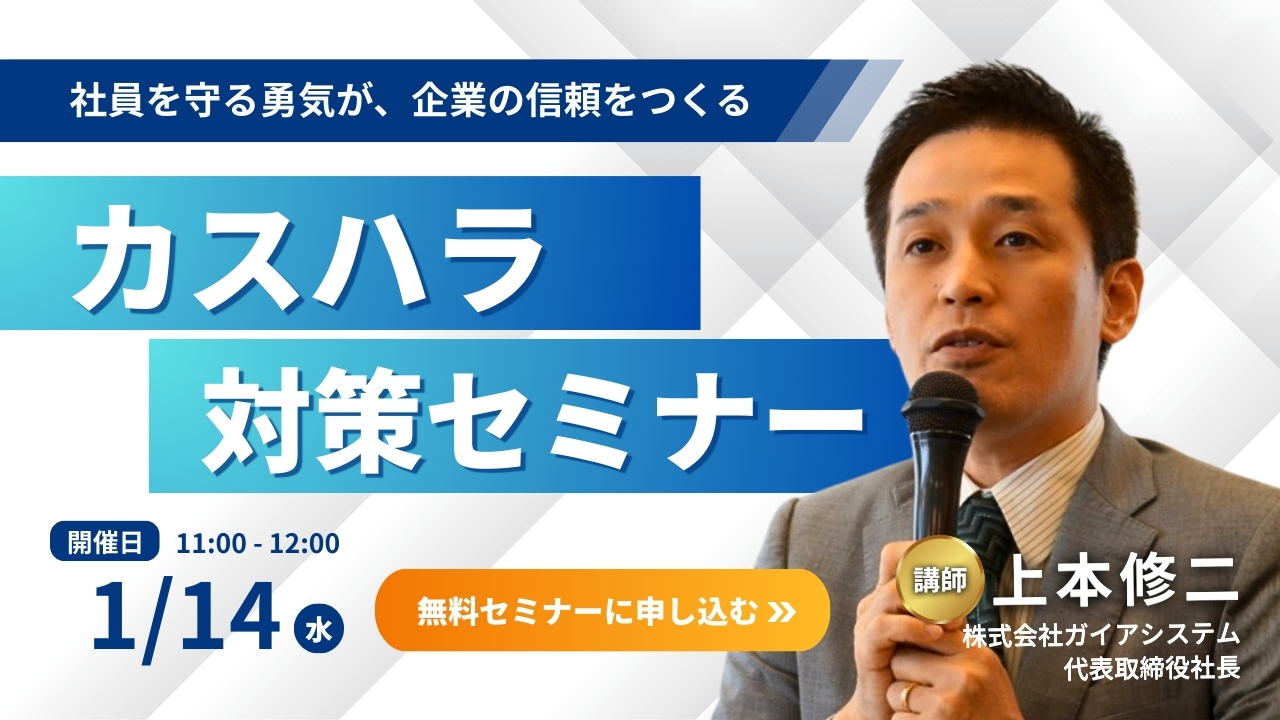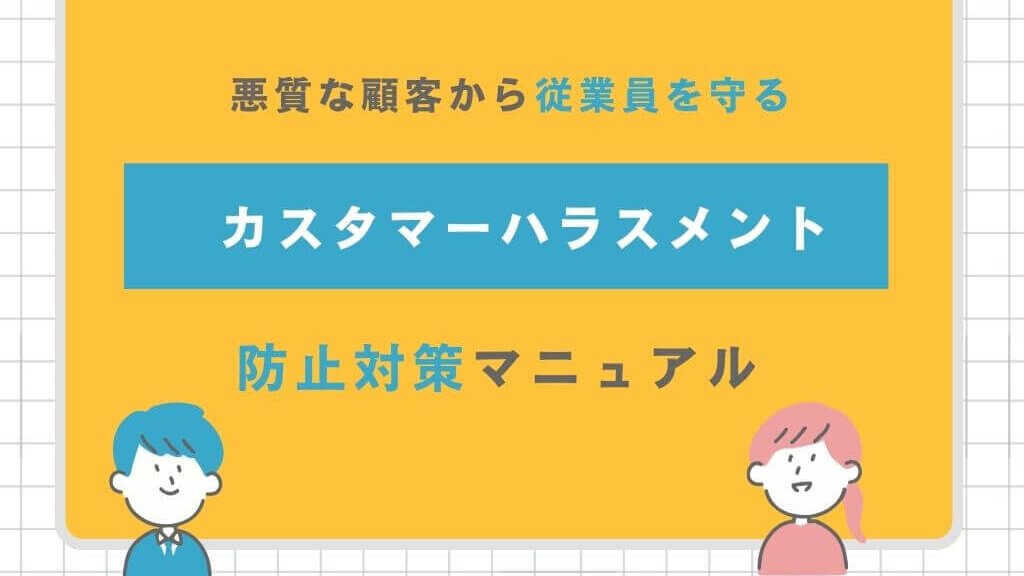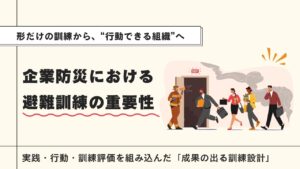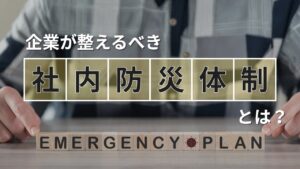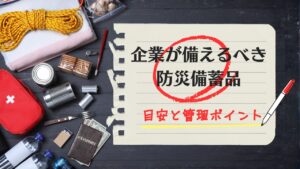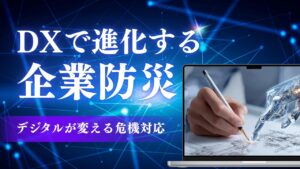企業防災における避難訓練の重要性|形だけの訓練から、“行動できる組織”へ
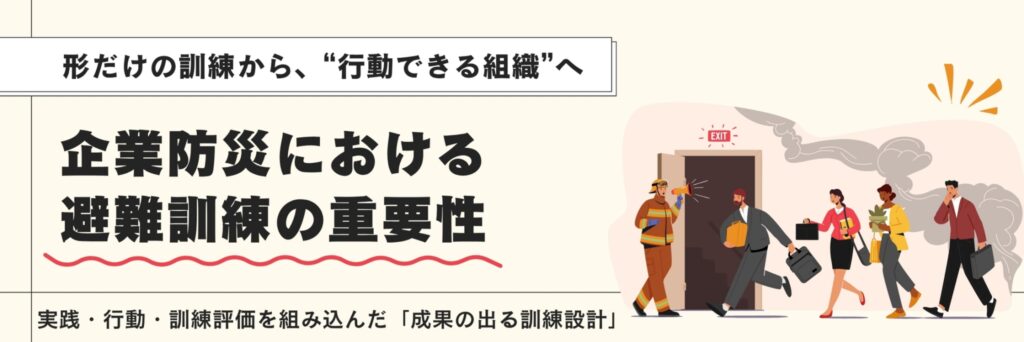
企業の防災対策で最も成果を分けるのは、「避難訓練の質」です。どれだけ防災マニュアルを整えても、社員が“動けなければ”安全は守れません。 実際の現場で“体を動かす”ことを中心にした避難訓練こそ、社員一人ひとりの命と企業の信頼を守る鍵になります。
本記事では、「企業 防災 避難訓練」をテーマに、単なる形式的な訓練ではなく、実践・行動・訓練評価を組み込んだ“成果の出る訓練設計”の方法を解説します。

避難訓練が形骸化してしまう原因を整理しながら、総務・人事担当者が押さえておくべき「設計・実施・振り返り・改善」の流れを、すぐに活かせる形でお伝えします。
なぜ避難訓練が形骸化するのか?(よくある失敗例)
避難訓練を毎年実施していても、内容が繰り返し・形式的になりがちで、いざ有事の際に期待した通り行動できないといったケースも少なくありません。
以下、よくある失敗例をご紹介します。
避難訓練が「形骸化しやすい」失敗例
- 目的が曖昧になっている
「毎年やっているから」「法令で義務だから」という理由だけで実施すると、社員も「いつもの訓練」と捉えてしまい、真剣な行動変化に結び付かないことがあります。 - シナリオがマンネリ化/想定災害が限定的
「地震発生→みんな机の下→避難所へ」という流ればかりでは、実際の災害対応力は育ちません。
風水害、火災、パンデミック影響下での避難など、状況が変化する中で“本当に使える動き”が求められます。 - 役割分担が明確でない・責任者が不在
避難誘導や的確な指示が出せる担当者が不明確だと、訓練中も“誰が何をする?”という混乱を生み、実際には行動に結びつきません。 - 実施後の振り返り・改善がない
「訓練やりました」「皆、避難できました」で終了してしまうと、どこが課題だったか、どう改善するかが曖昧なまま。次回も同じ内容・同じ課題を反復してしまいます。 - 参加者のモチベーション・理解が薄い
座学中心、受け身型では「研修だから出席」という雰囲気になり、肝心の“行動に移す意識”が育ちません。
これらを踏まると、避難訓練を“行うだけ”ではなく、“成果を出すための設計と運用”が必要なのです。
成果を出す避難訓練の設計(目的・シナリオ・役割分担)
では、社内の避難訓練を「形骸化」から脱却し、実際の行動変化につなげるための設計ポイントを整理します。
目的を明確にする
避難訓練の成果を出すためには、まず「この訓練で何を達成したいか」を規定しておくことが重要です。
例えば:
- 地震発生直後の初動対応と安全確保(30秒~1分以内に机の下に入るなど)
- 火災発生時の避難経路と集合場所への移動時間を計測し、理想時間を設定
- 台風・洪水発生時の“判断と行動”(例えば、浸水想定エリアから高層フロアへの移動)
- 在宅勤務や分散オフィスも想定した“オンライン/ハイブリッド”時の避難指示フロー
目的を設定したら、それに合わせた「成功基準(KPI)」も決めておきましょう。例えば「避難所まで3分以内に集合」「避難指示から行動開始までの時間を1分以内」など。
シナリオ設計
目的を元に具体的なシナリオを用意します。よりリアルに、社員が“体験”できるように設計するのが鍵です。ポイント:
- 現実に即した災害想定
貴社の所在地、建物の構造、業務形態をベースに「この状況ならどう動くか?」を想定。例えば、深夜勤務中に地震・火災併発、エレベーター停止、停電、通信障害など、複合災害パターンも検討。 - 役割・場面・移動ルートの明示
避難誘導責任者、各フロア点検者、集合場所確認者などの役割を事前に設け、各自がどう動くかを把握しておく。ルートも「通常ルート」「代替ルート」「障害発生時の対応ルート」をシナリオ化。 - 時間・環境を設定
実施時間(勤務中/終業後/休日勤務)、天候(大雨/風/夜間)、建物構造(地下・高層・倉庫型)など“いつ・どこで”の条件を変化させる。 - 障害/発見事項入りモデル
例えば「避難経路途中に煙発生」「集合場所への通路に瓦礫あり」「停電で誘導灯が消える」など、普段起きない事象を織り交ぜて“思考・判断”を促す。 - オンライン・ハイブリッド対応
従業員が在宅勤務・サテライトオフィス勤務中という前提で、「災害発生/本社・分社双方」の動きを訓練。また、指示連絡フローはスマホ・チャット・電話混在という想定で。
役割分担と責任体制
避難訓練の設計で一番曖昧になりがちなのが「誰が何をするか」です。以下を押さえましょう。
- 避難誘導責任者(フロア・部門ごと)
…訓練時に動線確認・点呼・安全確認を実施。 - 安全点検(事前)担当
…建物・設備・避難経路・誘導灯・非常用電源など、訓練前点検を実施して“障害想定”の設定も。 - 集合地点確認責任者
…全員が到着しているかどうか、点呼・報告まで。 - 役割外一般社員
…実際に“行動”を起こす対象。点検者・誘導者とは別。彼らの“動き”が評価対象。 - 事後振り返り責任者
…訓練後に評価・改善案の取りまとめを行う。
明確な役割分担を訓練開始前に共有し、「あなたはこの訓練でこの役割を担います」という形で、意識を持たせてから実施すると効果が高まります。
準備物・環境の確認
訓練を動かすための“物理的・環境的”な準備も忘れずに。
- 避難誘導サイン・照明・非常用電源・通信手段(無線・携帯・チャット)など、実際に機能するか確認しておく。
- 訓練中に使用するデバイスや記録ツール(ストップウォッチ・スマホカメラ・点呼シート)なども準備。
- 動線に障害を入れるための物品(例:ビニールテープで通路塞ぎ・暗転設定)など、“演出”を入れて臨場感を持たせる。
- 訓練を記録するための動画・静止画撮影も事前に手配しておき、後で振り返り資料として活用。
【無料】資料ダウンロード

防災研修 | カリキュラム事例
【資料の内容】
・防災研修が必要な理由
・企業の災害対策の実態
・企業の災害対策に関する実態調査
・防災研修のカリキュラム紹介
・価格表/実績紹介
実施と評価のポイント(振り返り・改善・動画記録など)

避難訓練設計が整ったら、次は「実施」と「評価・改善」です。ここを抜かすとせっかくの訓練が“やっただけ”になってしまいます。
実施時のポイント
- 訓練開始前に目的と成功基準を改めて共有する
(社員に「今回の訓練で◯◯分以内に集合」「◯◯の行動を起こす」という目標を伝える) - 開始合図をリアルに設定する
(例えば地震発生アラーム+火災報知器模擬音)をリアルに設定し、日常とは違う非日常感を演出 - 社員が動き始めたら、誘導者・点検者は予定ルートに沿って実際に動き、障害想定を設定
例えば「誘導灯が消えた」「通路に荷物あり」など。 - 集合地点到着時に点呼・報告を実施
「誰が来ていないか」「どこで止まっていたか」の記録を取る。 - 動画・静止画で全体の動きを記録
スマホ・タブレットでも構いませんが、訓練中の動線・声掛け・判断の瞬間を映しておくことで、後の振り返りで説得力のある資料になります。
振り返り(リフレクション)
訓練直後に、振り返りの場を設けましょう。ポイントは「振り返りを形式だけで終わらせない」こと。
- 全体で「何が予定通りだったか?」「どこで想定外が起きたか?」を共有
- 各役割(誘導者・点検者・集合責任者)から「計画ではこうだったが、実際にはこうだった/こう感じた」という報告を得る
- 動画/写真を用いて、実際の動きを可視化しながら議論。例えば「この場面で、移動に60秒かかっていた」「この誘導で混線が起きていた」など。
- 成果(成功基準)に対する数値的な振り返りを行う。例:集合まで2分30秒、目標3分以内を達成。誘導灯反応遅れ30秒あり。点呼漏れ2名。
- 改善案を具体的に決める。「次回までに避難ルート標示を追加」「誘導責任者用の肩章/識別バンドを導入」「集合点呼シートをデジタル化」など。
- この改善案を次回訓練に反映させる「次回アクションプラン」まで引き出す。
継続的な改善と記録保持
避難訓練は一度実施して終わりではなく、「定期的な実施+改善+再実施+記録」が鍵です。
- 年に1回だけでなく、半年ごと・異なる条件(夜間・休日・在宅勤務時)で実施を検討
- 各回の記録(動画・写真・点呼記録・振り返り報告書)を整理し、社内の防災ノウハウ資産として蓄積
- 記録を社内イントラ/掲示板で共有し、社員全体の防災意識を継続的に高める
- 成果が出ているかを定量的に把握(避難時間短縮、点呼漏れ率低下、社員アンケートで「自分の動きが分かった」など)し、経営層・担当部門に報告できる形に整えておく
リアル×オンラインでできる訓練事例
近年ではオフィスに加え、在宅勤務・サテライトオフィス勤務・ハイブリッド勤務体制も増えています。
訓練も “リアル” と “オンライン” を組み合わせた形式が効果的です。
リアル(集合形式)訓練の事例
- 本社オフィス・工場など社員が集合する拠点で、実際に避難誘導ルートを歩いてみる。
天井・床・照明・通路の障害有無も含め確認。 - 役割者が実際に誘導を試み、遅延要因(荷物・通路混雑・段差)などを可視化。
- 動画撮影して、社員全員でその日のうちに「どこがスムーズだったか/どこが課題か」を共有。
オンライン・ハイブリッド訓練の事例
- 在宅勤務者を想定し、災害発生アラート→社員個別チャットで「安否確認」「自宅からの退避ルート確認」を実施。
- 本社とリモート拠点を結び、「本社では火災、サテライトでは停電」、両方の条件を同時進行で訓練。
社員はチャット・動画通話で所属長の指示を受け、避難判断を行う。 - オンライン参加者に対してもモバイル端末・チャットツール・位置情報・簡易避難シートなどを活用し、通信障害を想定した“電話・SMS代替手段”も試す。
- その後、オンラインで振り返りセッション(15–30分)を開催し、リアル参加者・オンライン参加者の動きを比較。オンライン参加者には「自宅から安全な退避場所に移動できたか」「通信手段は確保できたか」などを確認。
このように、「いつ・どこで・どんな災害が起きても、社員が適切に行動できる体制」をリアル×オンラインで確認・改善することで、全社的な防災力が向上します。
よくある質問(FAQ)|企業防災・避難訓練の実践ガイド
まとめ|「行動につながる防災研修」で社内文化を育てる
企業の防災対策においては、知識をインプットするだけでは不十分です。特に「避難訓練」を通じて社員が実際に動くこと、判断すること、振り返ることが、初動対応・被害軽減・事業継続力強化につながります。

総務・人事ご担当者としては、次のポイントを押さえておくと安心です。
- 目的・KPIを明確に設定する
- 実践的なシナリオ・役割分担・環境設定を行う
- 実施時にはリアルな動線・障害・記録を取り入れる
- 振り返りを数値・動画・改善案まで含めて実施する
- オンライン・ハイブリッド勤務も想定し、リアル×遠隔両対応の訓練体制を整える
- 訓練結果を社内共有し、防災行動が“文化”として定着していくようにする
そして、避難訓練の設計・運用において、「どう設計すれば良いか/どう振り返れば良いか」で迷われる場合には、信頼できる研修パートナーを活用するのが効率的です。
例えば、研修教育企業の 株式会社ガイアシステム は、企業向け防災研修を「単なる知識提供」ではなく「有事を乗り越えるための実践力」に重きを置いたプログラムを提供しており、オーダーメイドでの避難訓練設計・運用支援も可能です。
貴社の防災研修・避難訓練を、ぜひ「行動につながる」ものにアップグレードしてみてはいかがでしょうか。ご希望があれば、ガイアシステムの研修プログラムについてもご紹介可能です。
防災研修カリキュラム
有事に備え、社員の命を守るー実践的な防災対策を!
企業向け防災研修
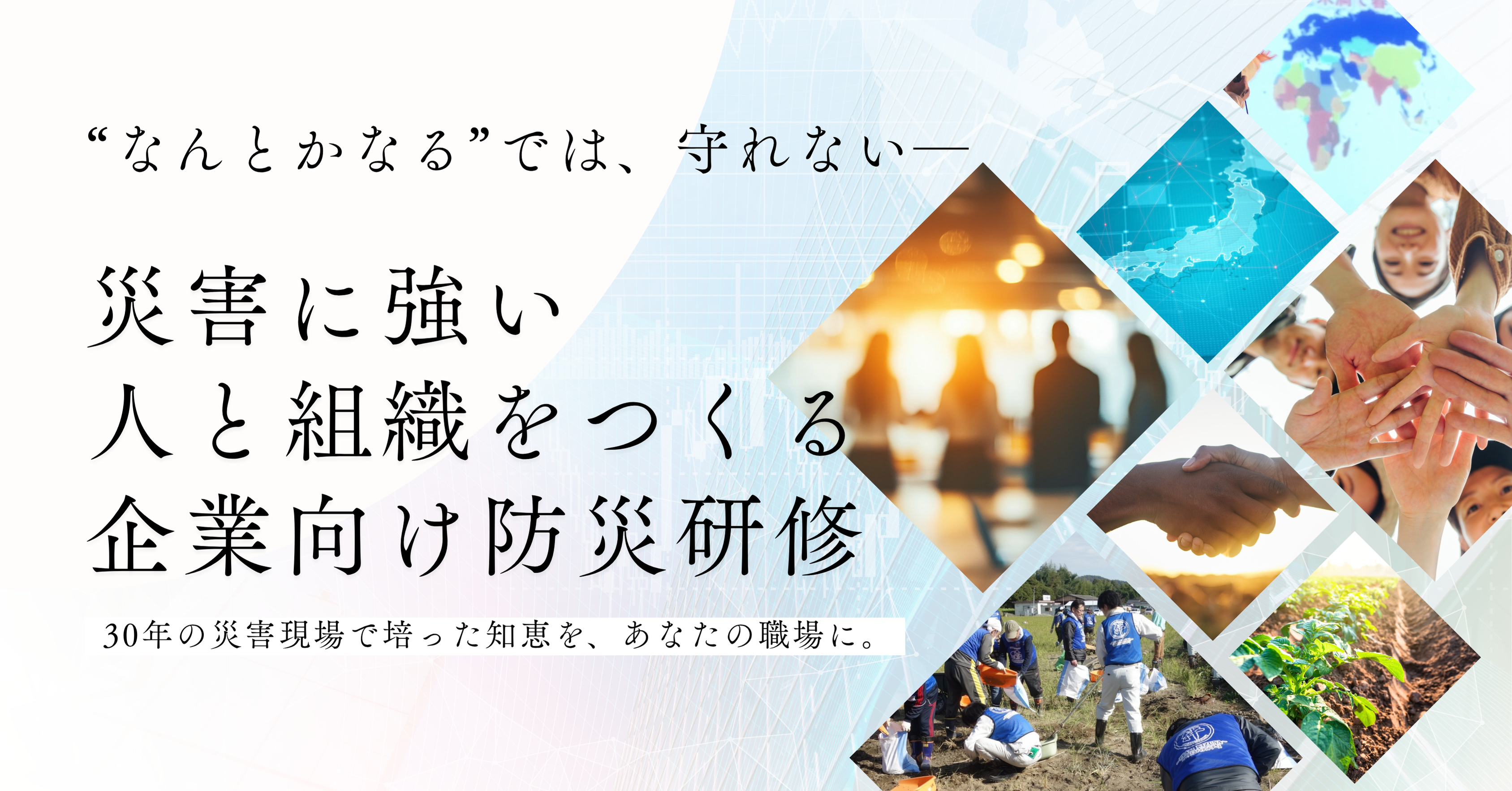
30年以内に80%の確率で発生すると言われる南海トラフ地震。企業には社員の命を守る具体的な「防災力」の強化が求められています。
本研修は、いざという時に“行動できる力”を育てる実践的プログラム。有事に備え、社員の安全を確保するための第一歩を、踏み出しませんか。
企業活動を止めずに従業員や顧客の安全を守る!
BCP(業務継続計画)研修

自然災害が頻発する日本において、企業活動を止めずに従業員や顧客の安全を守るためには、防災への備えが欠かせません。
本研修は、従業員一人ひとりが危機時に適切に対応し、企業全体で迅速かつ効果的に復旧を図る力を養うことを目的に、基礎知識の習得から実践的なシミュレーションを通じて企業全体の防災力を強化します。
リスク意識を高め 危機を未然に防ぐ!
リスクマネジメント研修
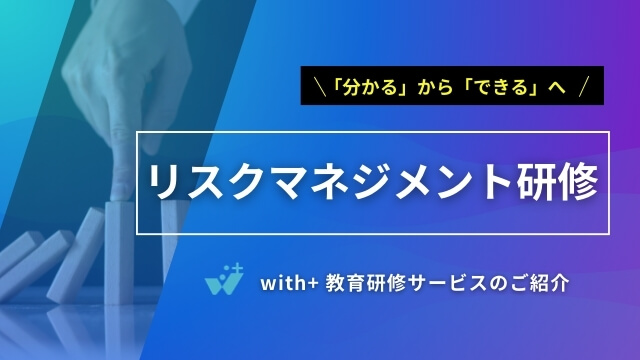
リスクマネジメント研修は、企業が直面する様々なリスクを特定、評価し、適切な対策を立てる能力を養成する教育プログラムです。
リスクの洗い出し、優先順位付け、対応策の策定などを学び、組織全体のリスク管理能力を向上を目指します。
企業防災コラム一覧
-
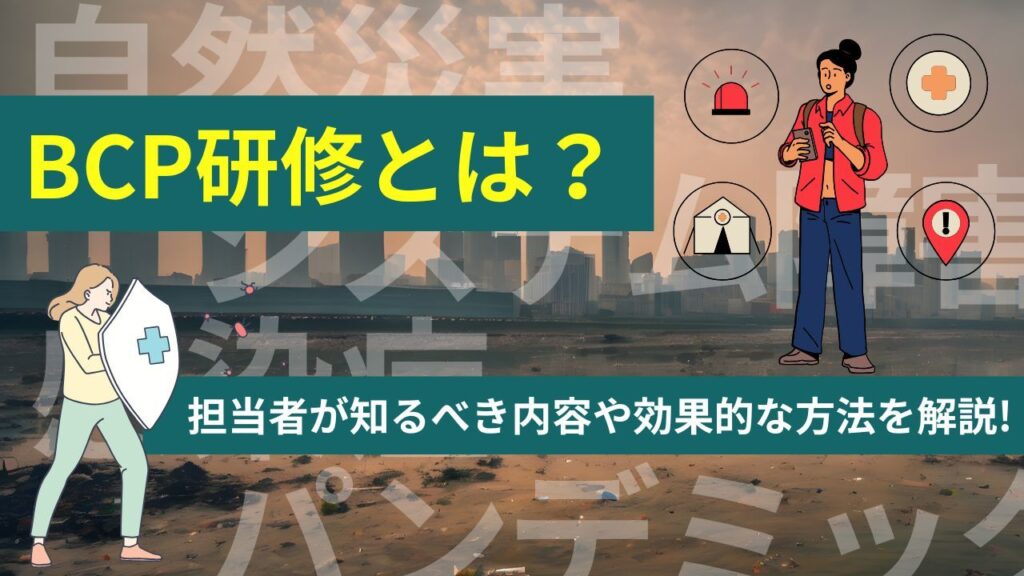
BCP研修とは?担当者が知るべき内容や効果的な方法を解説
-
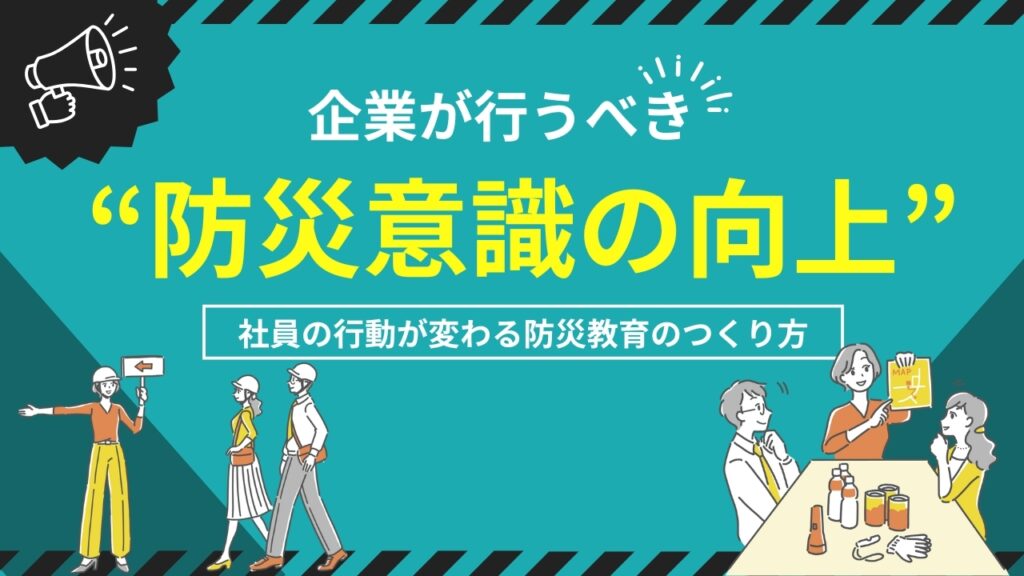
災害時に“行動できる社員を育てる”企業防災とは?防災意識を高める具体策
-
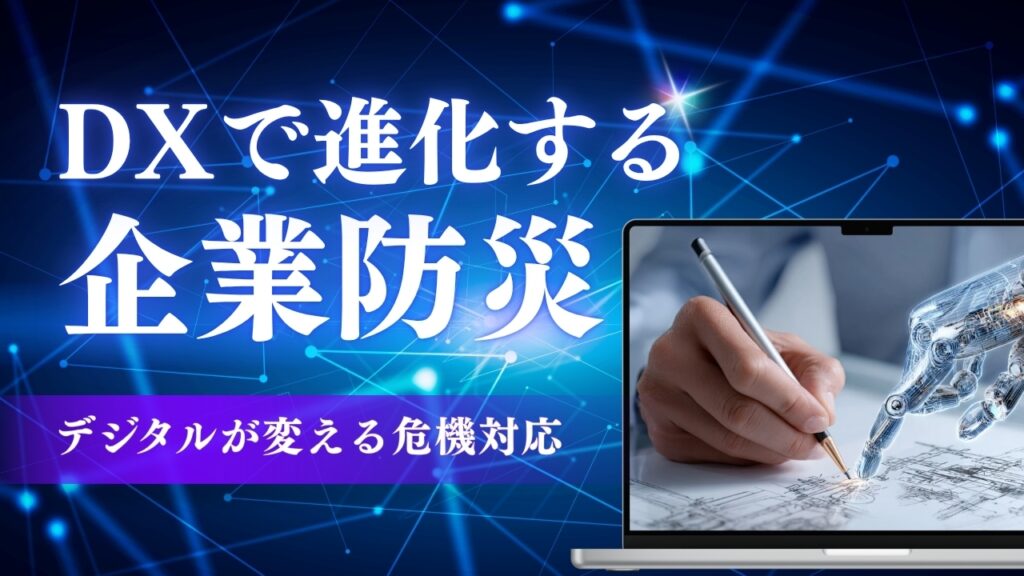
DXで進化する企業防災|デジタルが変える危機対応
-
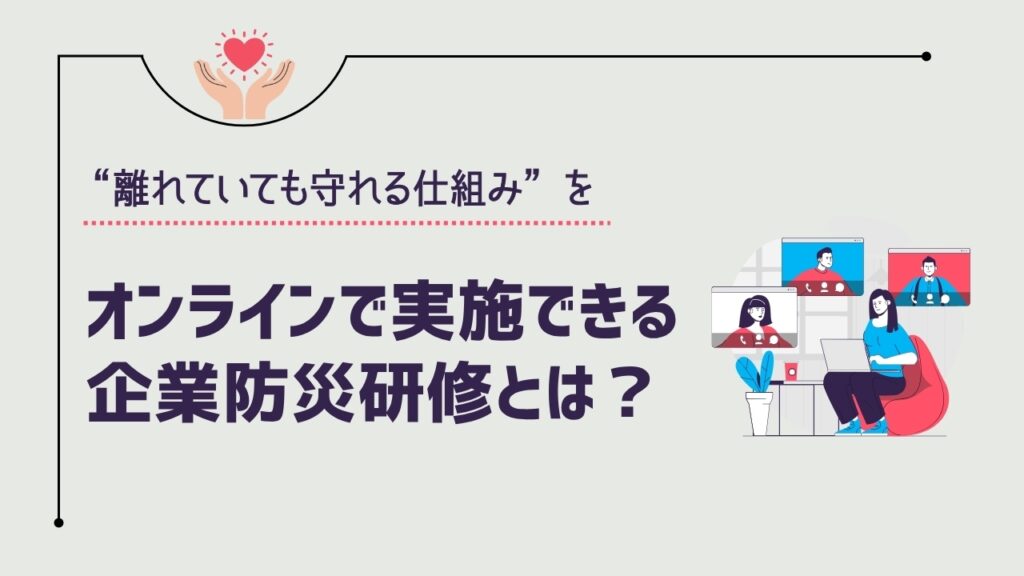
オンラインで実施できる企業防災研修とは?
-
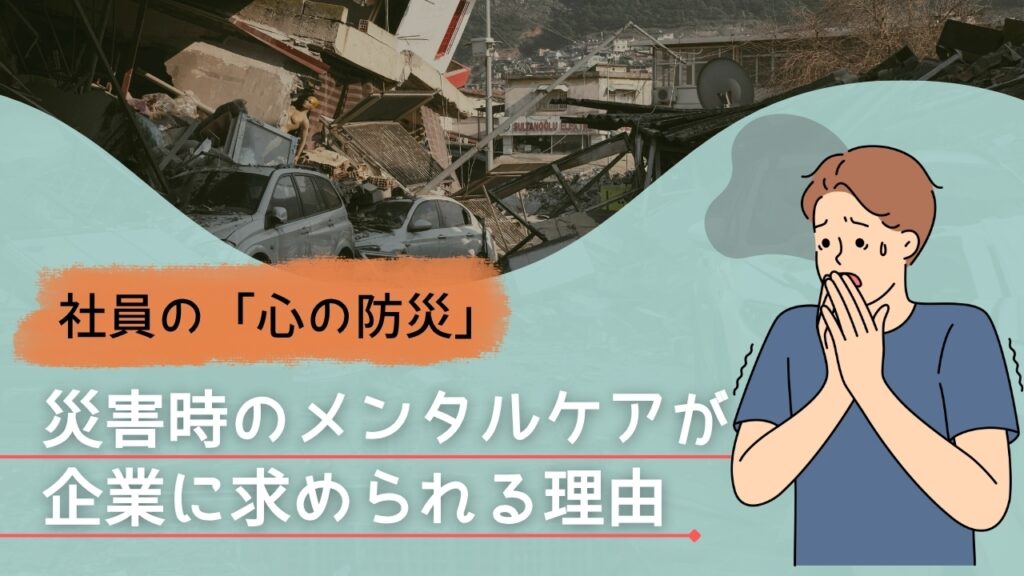
災害時のメンタルケアが企業に求められる理由
-
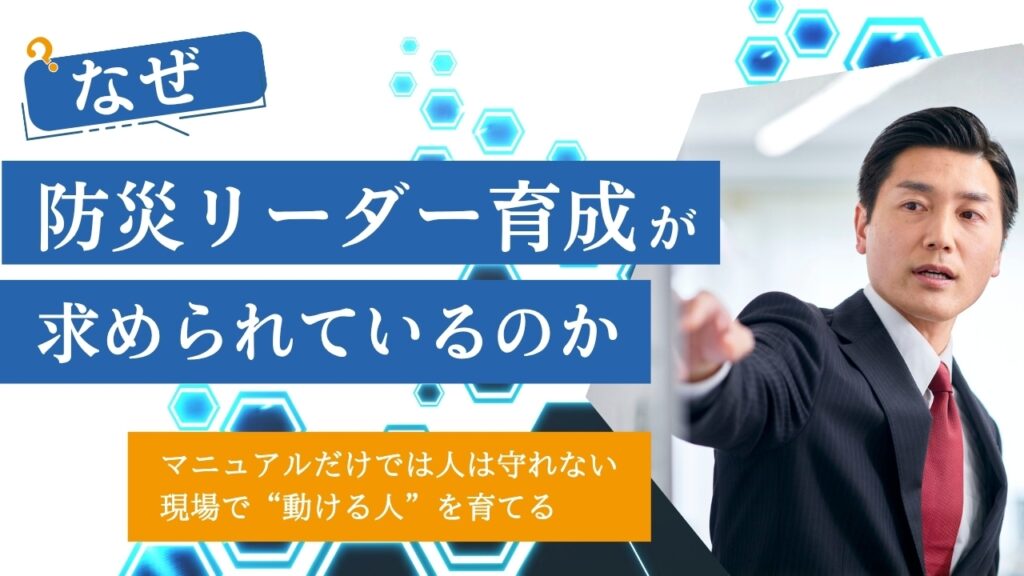
なぜ今、防災リーダー育成が求められているのか
-
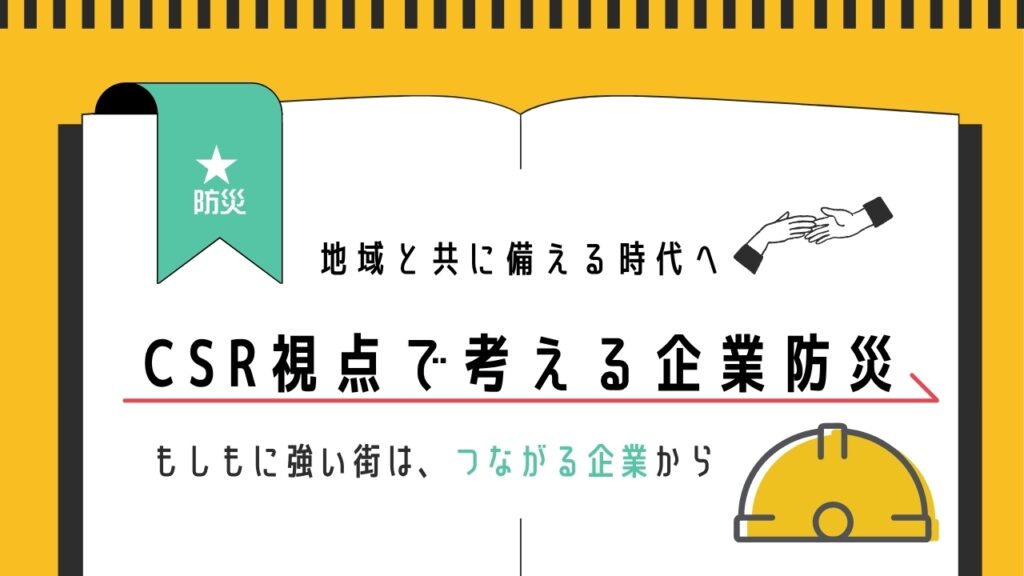
CSR視点で考える企業防災|地域と共に備える時代へ
-
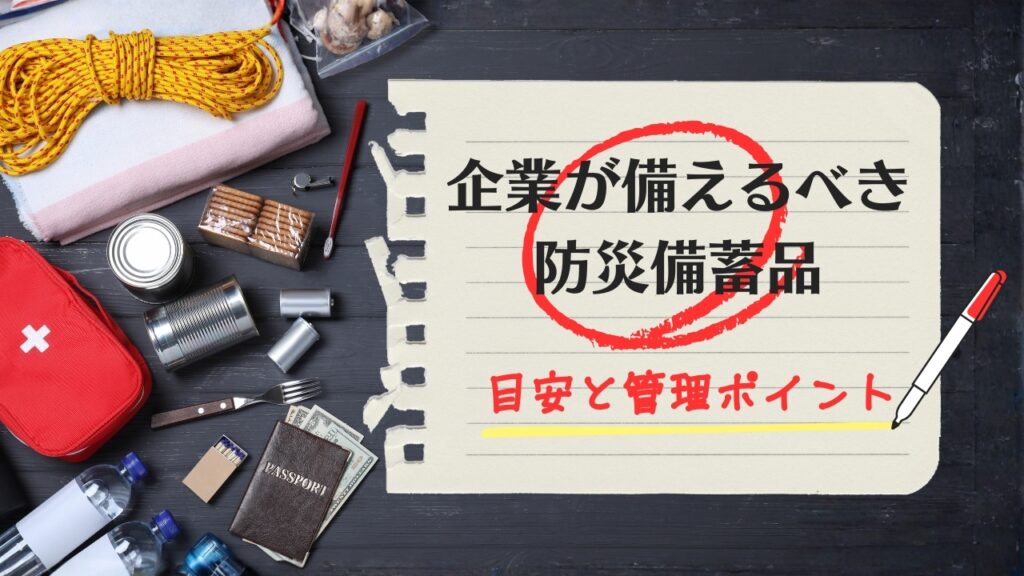
企業が備えるべき防災備蓄品の目安と管理ポイント
-
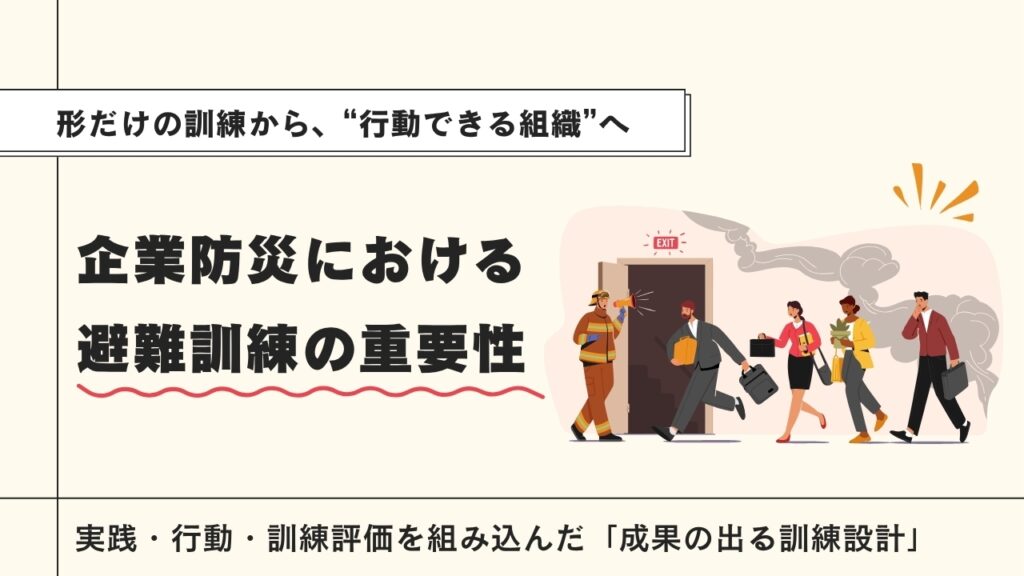
企業防災における避難訓練の重要性|形だけの訓練から、“行動できる組織”へ
-
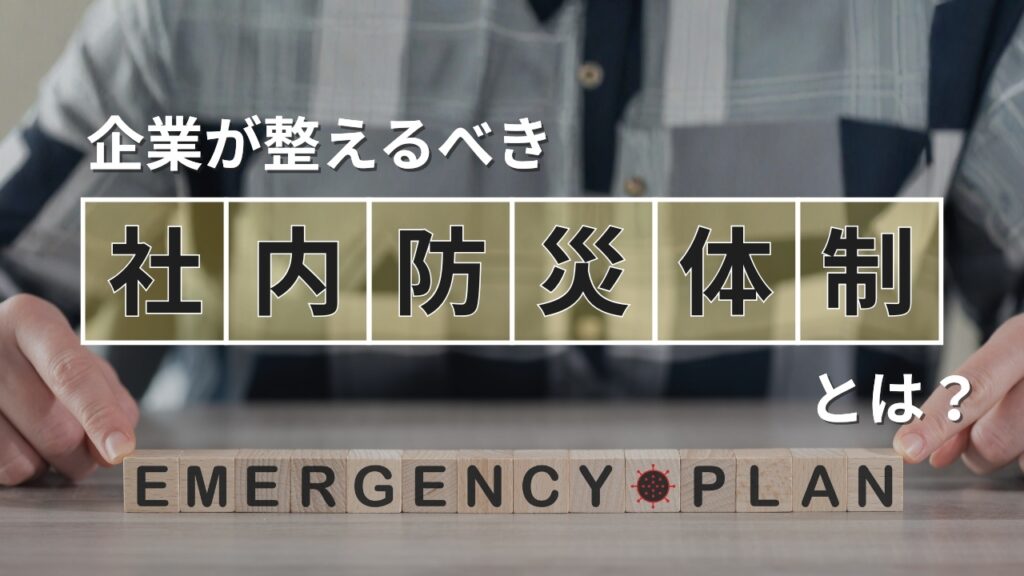
企業が整えるべき「社内防災体制」とは?
-
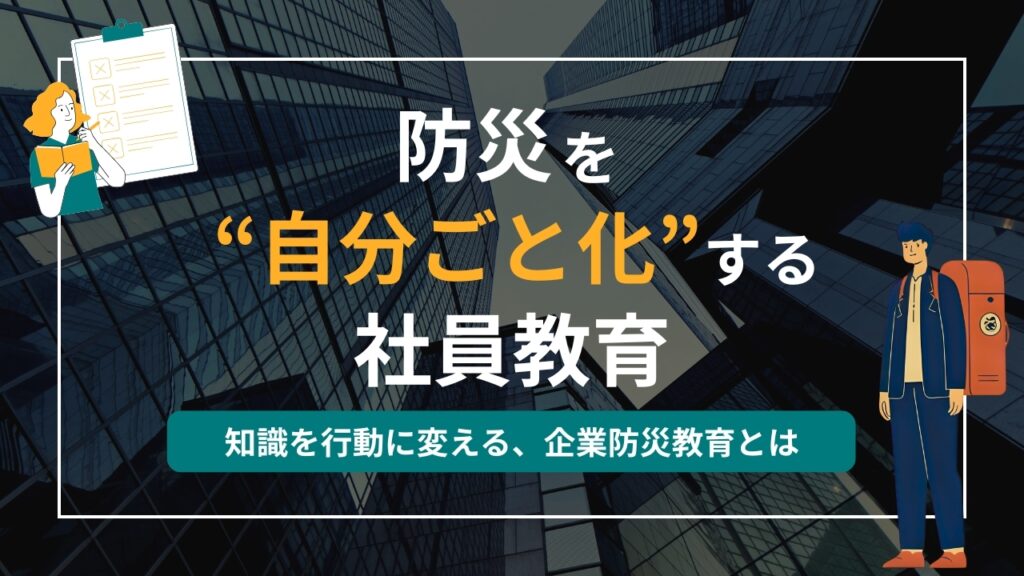
防災を“自分ごと化”する社員教育 |知識を行動に変える、企業防災教育とは
-
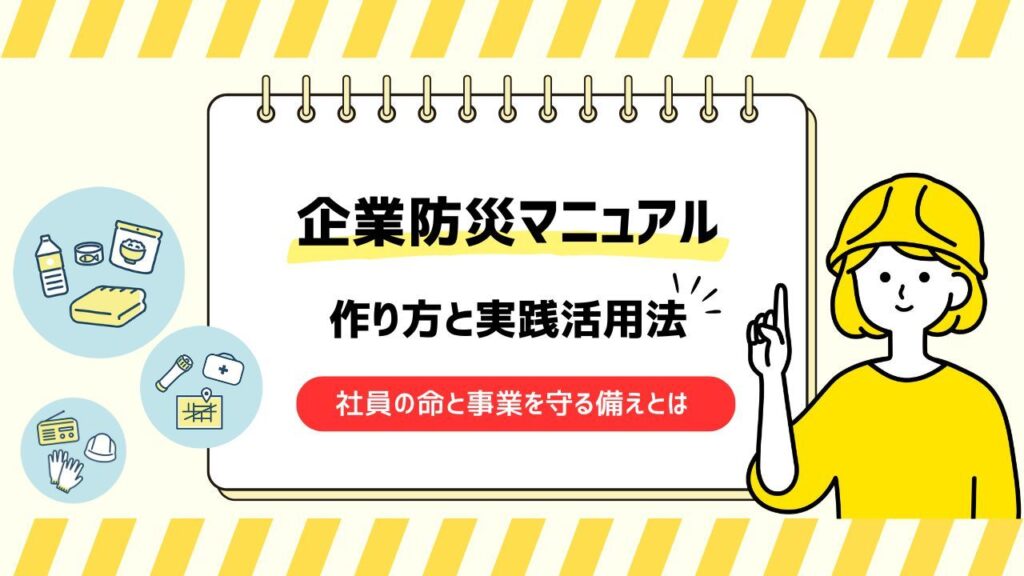
企業防災マニュアルの作り方と実践活用法|社員の命と事業を守る備えとは
-

企業防災とは?企業を守る実践的な防災・BCP対策ガイド
-

【企業防災研修】で社員と会社を守る!防災意識を高めるオーダーメイド研修とは
-
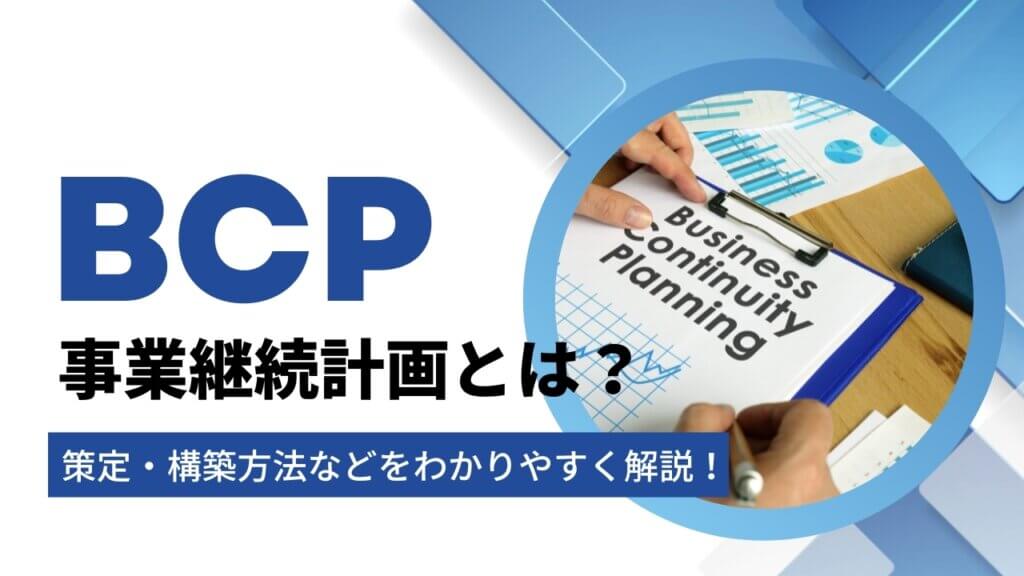
BCPとは?事業継続計画の策定・構築方法などをわかりやすく解説!