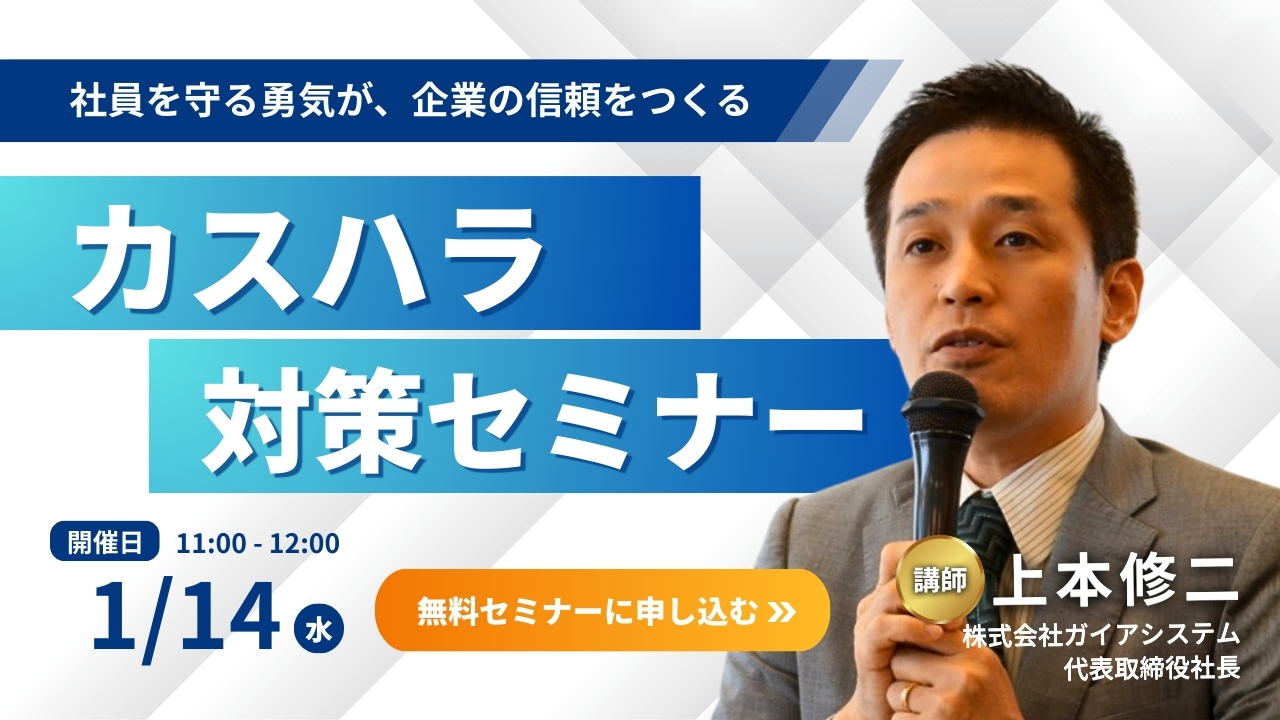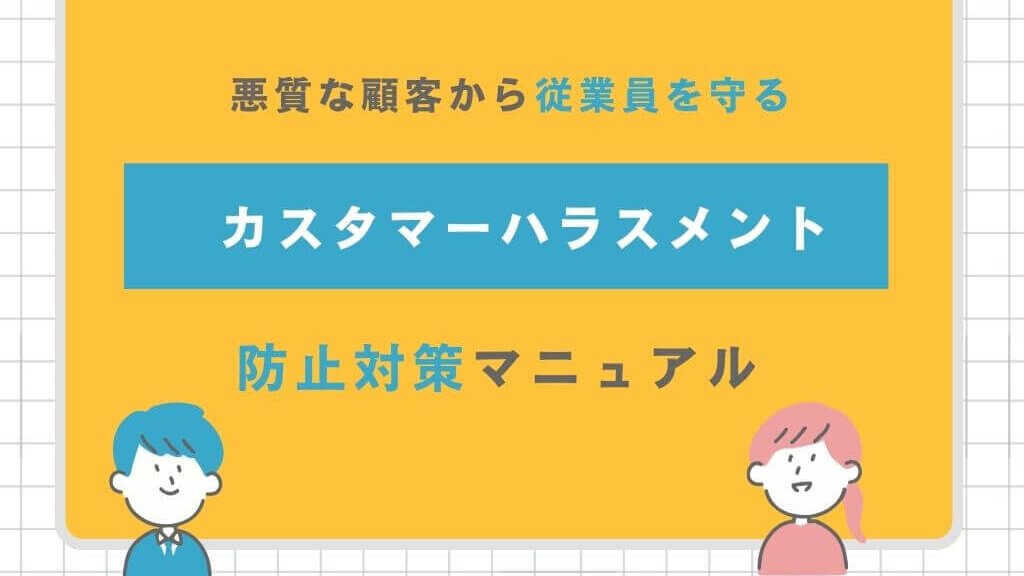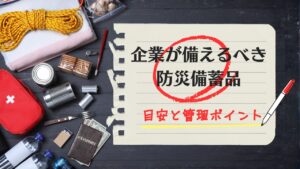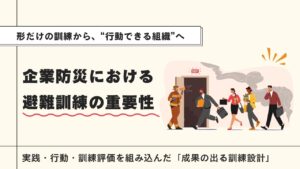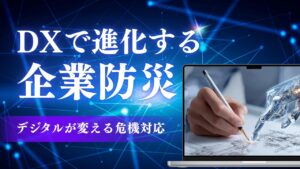企業が備えるべき防災備蓄品の目安と管理ポイント
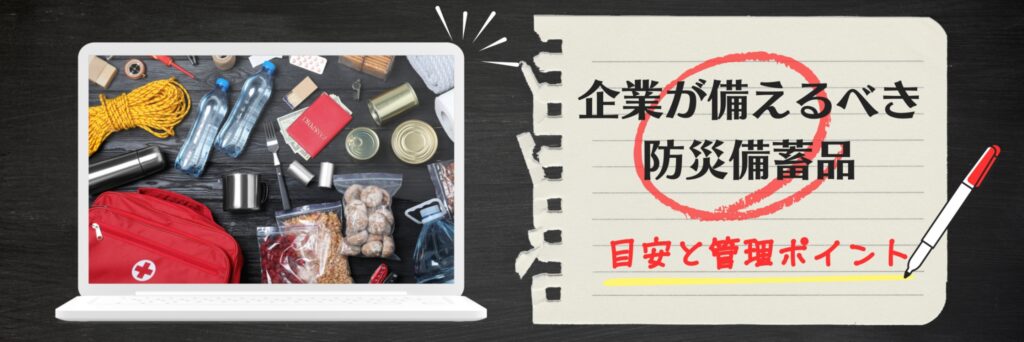
地震・台風・豪雨など、日本では大規模災害が“いつでも起こり得る”環境にあります。
その中で企業に求められるのは、社員の安全を守り、事業を止めないための「備蓄と運用体制」です。
特に発災直後の 72時間(3日間) は、物流が止まり、外部支援が届かない期間。
この時間を乗り切るための備蓄は、企業の“最低限の責務”と言えます。
本記事では、以下をわかりやすく解説します。
- 必要な備蓄品リスト
- 社員数別の必要量
- 実務的な管理方法
- 防災の仕組み化のポイント
まず備えるべき防災備蓄品リスト(企業向けの必須アイテム)
備蓄品は、企業の規模に応じて「何を」「どれだけ」揃えるかが重要です。
まずは“最低限そろえるべき品目”をカテゴリ別に整理します。
飲料・食料(生存に直結)
- 飲料水(500mlまたは2Lペットボトル)
- アルファ米
- レトルト食品・缶詰・栄養補助バー
- 使い捨て食器・割り箸・紙コップ
選び方のポイント
- 5〜7年保存の長期保存タイプを優先
- 水は“1人1日3L”が基本
- アレルギー・宗教食も想定しておく
衛生・医療用品
- 簡易トイレ(1人1日5回×3日分)
- ウェットティッシュ・アルコールスプレー
- マスク
- 救急セット
- 生理用品
ポイント
災害時は「トイレ問題」が最も深刻。
社員数に応じて十分な枚数を確保しておくことが必須
寝具・防寒用品
- アルミブランケット
- 毛布
- 簡易マット
- カイロ
- 防寒シート
ポイント
停電で暖房が使えない状況を想定。
冬場は“想定以上に”防寒が重要です
情報・通信・照明
- 手回しラジオ
- LEDランタン
- 懐中電灯
- モバイルバッテリー
- 発電機
- 充電ケーブル・延長コード
保護具(ヘルメットなど)
- ヘルメット
- 防災頭巾
- 軍手
- 破片対策のゴーグル
その他(業務継続に必要な物)
- 工具セット
- ブルーシート
- ガムテープ
- 名簿・安否確認カード
- Wi-Fiルーター
- 衛星電話(必要に応じて)

安否確認体制(LINEグループや社内アプリなど)との連携も欠かせません。
どのツールを使うか、誰が連絡を発信するかなど、平時から仕組みを整えておくことが、災害時のスムーズな対応につながります。
災害時には、天井材の落下やガラス片の飛散など、オフィスでも頭部や目を守る装備が不可欠です。特にヘルメットは、企業防災における“基本の備え”とされており、社員1人につき1つの常備が推奨されています。
労働安全衛生規則でも、崩落や転倒の危険がある場所では保護帽の着用が義務付けられており、オフィスでも例外ではありません。収納式・折りたたみ型など、省スペースで保管できるヘルメットを選ぶと、日常業務の邪魔にならず運用しやすくなります。
どれから揃える?防災備蓄の優先順位と考え方
災害時の備蓄は「すべてを一度に揃える」必要はありません。
まずは 命を守るために必須のものから順番に整える ことが重要です。
企業では人数が多いため、優先順位を明確にして段階的に揃えていく方が現実的です。
備えの優先順位
- 命を守る備え(水・食料・衛生用品)
- 避難・滞在を支える備え(毛布・簡易トイレ・照明)
- 情報を得る備え(ラジオ・モバイル電源・通信機器)
まずは「①命を守る備え」を優先的に揃え、その後、滞在環境(②)や情報収集(③)を計画的に追加していくと、無駄がなく確実に備蓄体制を整えることができます。
命を守る備え(水・食料・衛生用品)〈最優先〉
災害直後の72時間は、外部支援が届かず、企業は自力で生き延びる時間になります。
まずは“生存に直結するもの”から確保することが最優先です。
特にトイレ問題は深刻で、社員数に応じた枚数がないと衛生環境が急速に悪化するため、食料・水と同じレベルで重要な備蓄品と考える必要があります。
避難・滞在を支える備え(毛布・簡易トイレ・照明)
停電や空調停止が長時間続くと、寒さ・暗さ・疲労が社員の体力や判断力を奪います。
避難所や社内に長時間滞在する可能性がある企業にとって、寒さ対策や照明の確保は、二次被害の防止に直結します。
情報を得る備え(ラジオ・モバイル電源・通信機器)
災害時は正しい情報を得られるかどうかで、初動対応・避難判断・事業継続の成否が大きく変わります。
停電や通信障害が発生する可能性を考慮し、複数の電源確保手段や情報源を持っておくことが不可欠です。

災害は予測できませんが、優先順位を明確にした準備こそ、社員の命と企業を守る最も確実な方法です。
【無料】資料ダウンロード

防災研修 | カリキュラム事例
【資料の内容】
・防災研修が必要な理由
・企業の災害対策の実態
・企業の災害対策に関する実態調査
・防災研修のカリキュラム紹介
・価格表/実績紹介
社員数で違う!従業員規模別・必要量の早見表
企業規模に応じて備蓄量は大きく変わります。以下は「1人3日分」を基準にした目安です。
1人あたり3日分の基本量
| 品目 | 1人1日あたりの目安 | 3日分の合計 |
|---|---|---|
| 飲料水 | 3L(500ml×6本) | 9L |
| 食料(保存食) | 3食分(約1,000kcal/日) | 9食分 |
| 簡易トイレ | 5回分 | 15回分 |
| 毛布・アルミブランケット | 1枚 | 1枚 |
| マスク・除菌用品 | 適量 | 各3枚以上 |
社員数別・必要量
| 社員数 | 水(1人9L) | 食料(1人9食) | 簡易トイレ(1人15枚) |
|---|---|---|---|
| 50人 | 450L(500ml×900本) | 450食 | 750枚 |
| 100人 | 900L(500ml×1,800本) | 900食 | 1,500枚 |
| 200人 | 1,800L(500ml×3,600本) | 1,800食 | 3,000枚 |
大量備蓄が必要な企業ほど、倉庫+フロア分散+個人配備が特に効果的です。
たとえば従業員200名の企業であれば、以下の量が必要数の目安になります。
- 飲料水:約1,800L(500mlペットボトル×3,600本)
- 保存食:約1,800食分
- 簡易トイレ:3,000枚程度
社員の命を守る「3日間の備え」が、企業の信頼を守ることにつながります。今日からできる第一歩として、自社の備蓄リストを見直してみてください。
企業が家庭以上の備蓄を求められる理由とは?
企業にとって防災備蓄は「万一のための保険」ではなく、社員の命を守り、事業を止めないための必須対策です。
大規模災害が起きると、道路や物流網が途絶え、救援物資・燃料が届くまで 平均72時間(3日) を要するといわれています。この“孤立する72時間”を乗り切るには、社内に最低3日分の備蓄が欠かせません。企業が家庭以上の備蓄を求められる理由は、次の3つです。
1|社員が帰宅困難者になる可能性が高い
災害時、交通機関が停止すれば、多くの社員が会社に留まらざるを得なくなります。
「一時滞在者」として数十人〜数百人を受け入れる前提で、食料・水・トイレ・防寒用品を確保しておく必要があります。
2|従業員数が多く、物資不足が起こりやすい
家庭なら数人分で済む備蓄も、企業では 数十倍・数百倍の規模 になります。支援物資が届いたとしても、人数に対して十分でないケースが一般的です。そのため、自社で必要量を揃えることが最も確実な備え になります。
3|顧客対応・インフラ維持など“止められない業務”がある
企業には、災害時にも一定の事業継続が求められる場合があります。
- 顧客対応
- 社会インフラにつながる業務
- 情報管理・システム運用
従業員が安全に働ける環境を整えることが、BCP(事業継続計画)の基盤 です。
企業防災の第一歩は「従業員の命を守る備蓄」から
物資を外部に頼ることができない72時間。
この時間を安全に乗り切れるかどうかは、企業が備蓄を整えているか に左右されます。
「従業員一人ひとりが安心して働ける環境を守る」そのための最も基本的な取り組みが、防災備蓄なのです。
失敗しない備蓄管理|保管場所・点検・ローリングストック術
災害時に備えた物資をいざ使おうとしても、「どこに保管してあるかわからない」「賞味期限が切れていた」では意味がありません。備蓄は“持つ”だけでなく、“管理する仕組み”を整えることが重要です。

ここでは、保管場所の工夫や管理のコツ、ムダなく使い続ける「ローリングストック術」を紹介します。
保管場所
- 倉庫・会議室の一角など、「地震で倒壊しにくい低層階」にまとめて保管
- フロアごとに分散保管
- 水や食料は湿気・高温を避けた場所に置く
- 物品ごとにラベルを貼り、「誰でも取り出せる」状態を維持する
個別保管もおすすめ
オフィスの棚やロッカーに「1人1セット分」を個人配備しておく方法もおすすめです。
個人配備にすることで、災害時に自分の分をすぐに取り出せるだけでなく、備蓄場所が分散されるため、倉庫が使えなくなっても対応しやすくなります。
社員に事前に配布する場合、以下が注意ポイントになります。
- 中身の統一性を保つ:全員分を同じ内容でそろえることで、不足や偏りを防ぐ。
- 定期点検のルール化:年1回の防災訓練などに合わせて中身を確認・更新する。
- 保管環境の確認:ロッカー内の温度・湿度に注意し、食品類は高温多湿を避ける。
小さな工夫ですが、「自分の命を自分で守る」という意識づけにもつながります。
備蓄品の管理方法(年1回以上が理想)
管理の基本は次の4ステップです。
- 賞味期限チェック
- 数量の棚卸
- 使った分の補充(ローリングストック)
- 管理台帳の更新
管理の継続性を高めるためには、総務部など社内で管理責任者を明確にしておくことが重要です。
責任者を決め、毎年同じ月に点検を行うルールを設定することで、備蓄管理が習慣化しやすくなります。
「ローリングストック」でムダなく管理・運用
ローリングストックとは、「普段から食べたり使ったりして、使った分を補充する」備蓄方法のことです。
非常食や飲料水を特別なものとしてしまわず、日常生活の中で循環させることで、無理なく備蓄を維持でき、賞味期限切れや劣化を防ぐことができます。
ローリングストックの手順
- 期限の近い順に並べる
- 毎月の行事や訓練で一部を使用
- 使用後は同じ種類の物を補充
- 年1回、備蓄全体を総点検
“使い続けて入れ替える”ことで、期限切れのリスクがゼロに近づきます。

非常食を定期的に社内イベントや防災訓練で試食すると、味や量の確認にもなり、社員の防災意識も高まります。
備蓄が本当に役立った企業の実例(成功のポイント)
複数の保管場所に分散して、社員全員がすぐ動けた
地震発生時、エレベーターが停止し、一部のフロアでは移動が困難に。しかし、防災備蓄品を各フロアごとに分散して保管していたことで、どの部署の社員もすぐに水・食料・照明を確保できました。「一か所にまとめておくよりも、分散備蓄が安全だ」と、後の社内報にも掲載されたそうです。
期限切れを防ぐ“更新サイクル”が、非常時にも活きた
防災備蓄を年1回入れ替える「更新サイクル」を設けていた企業では、災害時にすべての保存食と水が期限内・使用可能な状態でした。在庫チェックを兼ねて普段の訓練で試食会を行っていたため、社員が味や使い方を知っており、慌てず落ち着いて対応できたといいます。
余剰備蓄を地域へ寄贈し、信頼関係を築いた
賞味期限が近づいた保存食を地域の福祉施設へ寄贈する仕組みを整えていた企業では、実際の災害時にもそのネットワークが活かされ、避難所との連携や物資提供がスムーズに行えました。「日常の防災活動が、地域の信頼につながった」と担当者は話しています。
どの企業の事例にも共通しているのは、「備蓄を形だけで終わらせず、日常的に運用していた」という点です。日頃からの小さな工夫や管理の積み重ねが、いざという時の大きな安心につながります。
防災備蓄に関する疑問まとめ(よくある質問Q&A)
まとめ|備蓄を“整える”から“使える仕組み”へ
防災備蓄は、買いそろえるだけでは十分に機能しません。
本当に企業を守る備えにするためには、
買う → 保管する → 運用する → 仕組み化する
という流れを社内に根づかせることが重要です。
特に企業では、社員数が多く役割も多様なため、「誰もが迷わず使える状態」をつくることが、備蓄の価値を最大限に高めます。
そのために取り組むべきポイントは、たったの3つです。
- 年1回の備蓄点検(賞味期限・数量・状態の確認)
- 防災訓練に備蓄チェックを組み込む
- 安否確認・初動対応などの社内ルールを共有する
こうした継続的な取り組みが、備蓄を“生きた仕組み”に変え、社員一人ひとりが「自分の命を守る意識」を持つきっかけにもなります。
ガイアシステムでは、備蓄の活かし方から初動対応、指揮系統づくりまで、企業の実態に合わせたオーダーメイド型防災研修 を提供しています。
備蓄を整えた今こそ、次のステップとして “防災を企業文化として根づかせる” タイミングです。
社員と企業を守る体制づくりを、ここから一緒に進めてみませんか。
防災研修カリキュラム
有事に備え、社員の命を守るー実践的な防災対策を!
企業向け防災研修
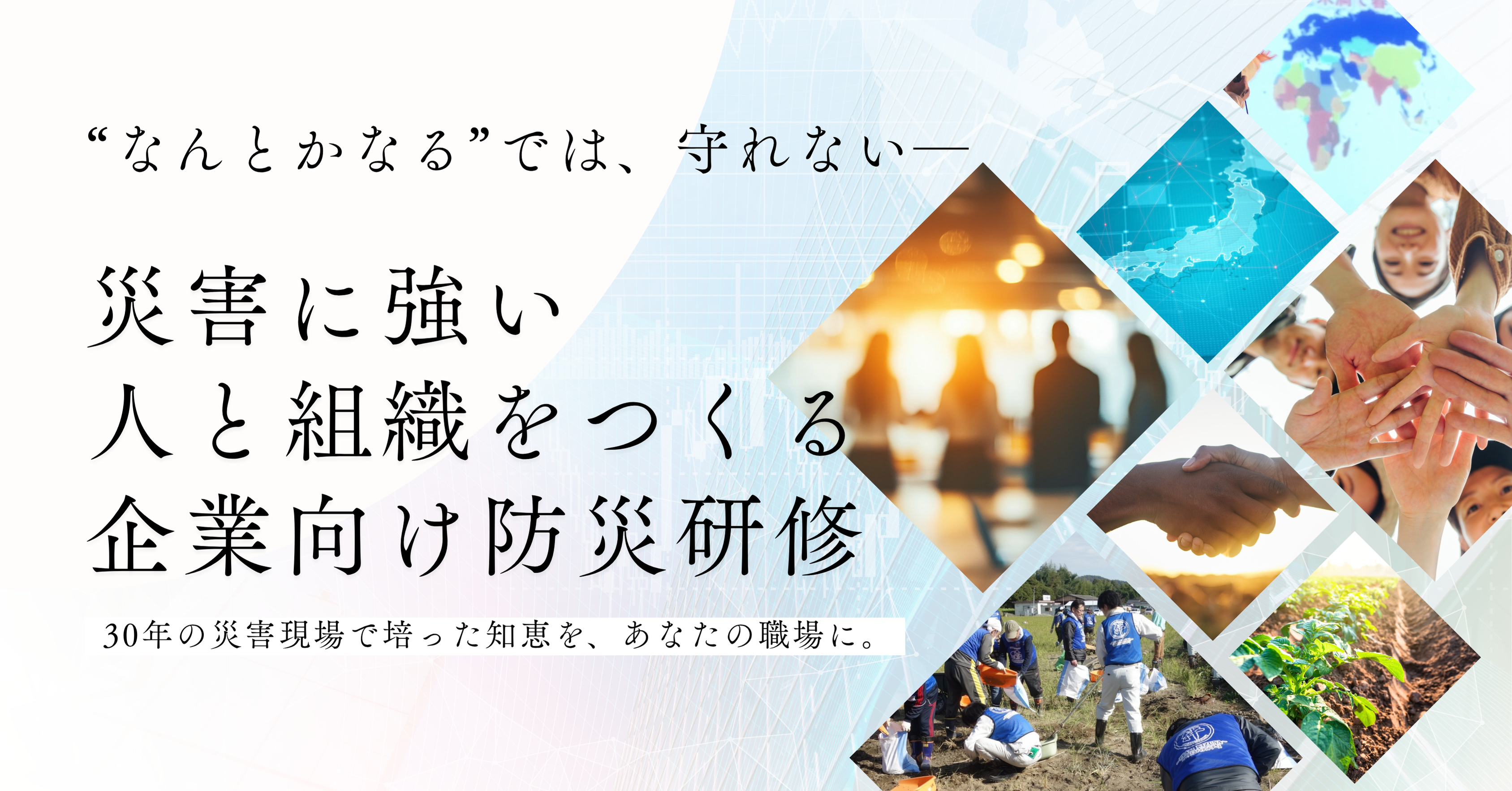
30年以内に80%の確率で発生すると言われる南海トラフ地震。企業には社員の命を守る具体的な「防災力」の強化が求められています。
本研修は、いざという時に“行動できる力”を育てる実践的プログラム。有事に備え、社員の安全を確保するための第一歩を、踏み出しませんか。
企業活動を止めずに従業員や顧客の安全を守る!
BCP(業務継続計画)研修

自然災害が頻発する日本において、企業活動を止めずに従業員や顧客の安全を守るためには、防災への備えが欠かせません。
本研修は、従業員一人ひとりが危機時に適切に対応し、企業全体で迅速かつ効果的に復旧を図る力を養うことを目的に、基礎知識の習得から実践的なシミュレーションを通じて企業全体の防災力を強化します。
リスク意識を高め 危機を未然に防ぐ!
リスクマネジメント研修
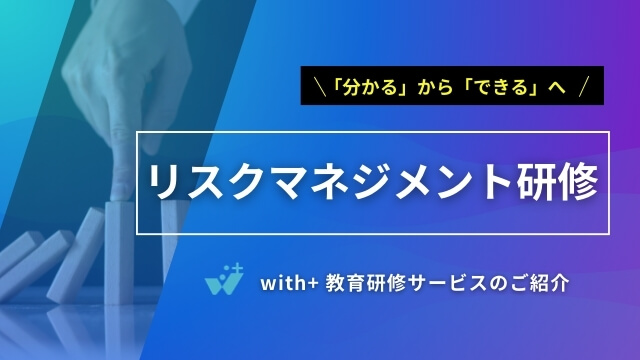
リスクマネジメント研修は、企業が直面する様々なリスクを特定、評価し、適切な対策を立てる能力を養成する教育プログラムです。
リスクの洗い出し、優先順位付け、対応策の策定などを学び、組織全体のリスク管理能力を向上を目指します。
企業防災コラム一覧
-
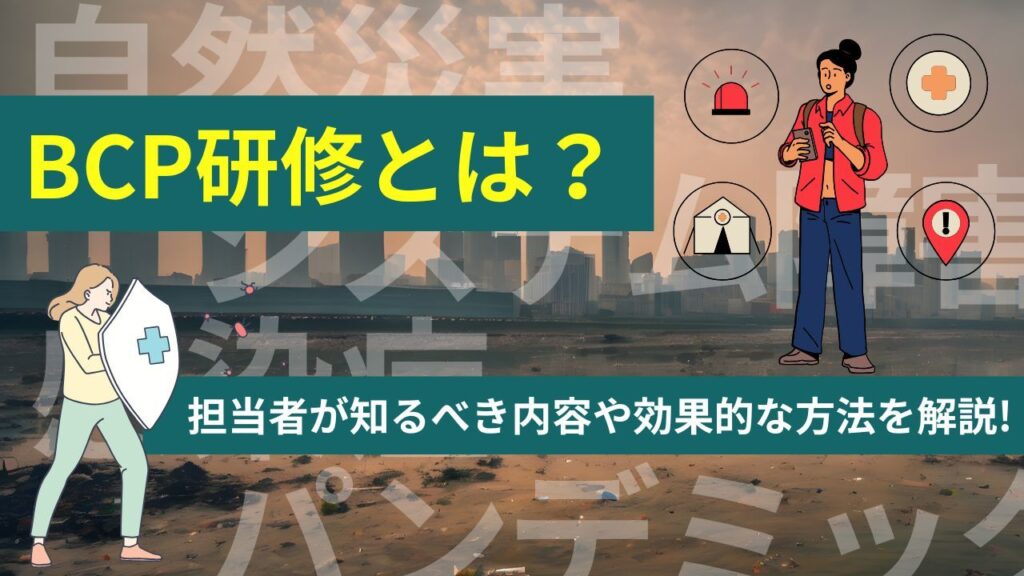
BCP研修とは?担当者が知るべき内容や効果的な方法を解説
-
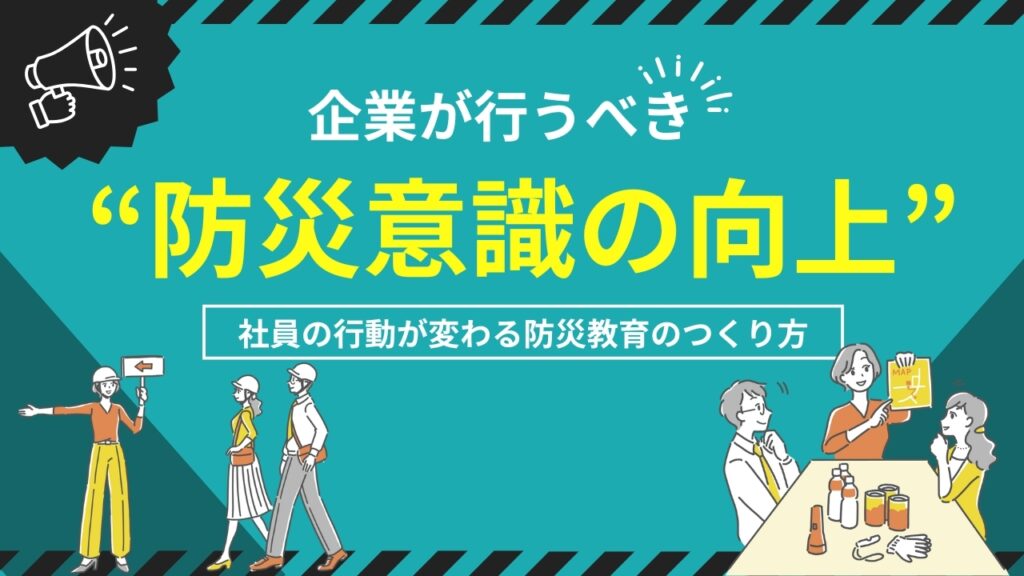
災害時に“行動できる社員を育てる”企業防災とは?防災意識を高める具体策
-
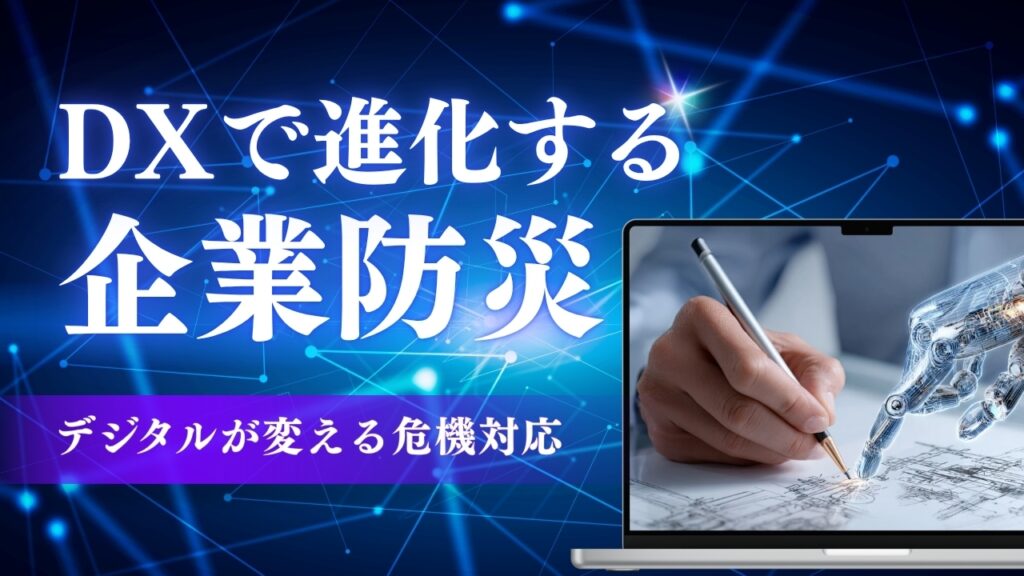
DXで進化する企業防災|デジタルが変える危機対応
-
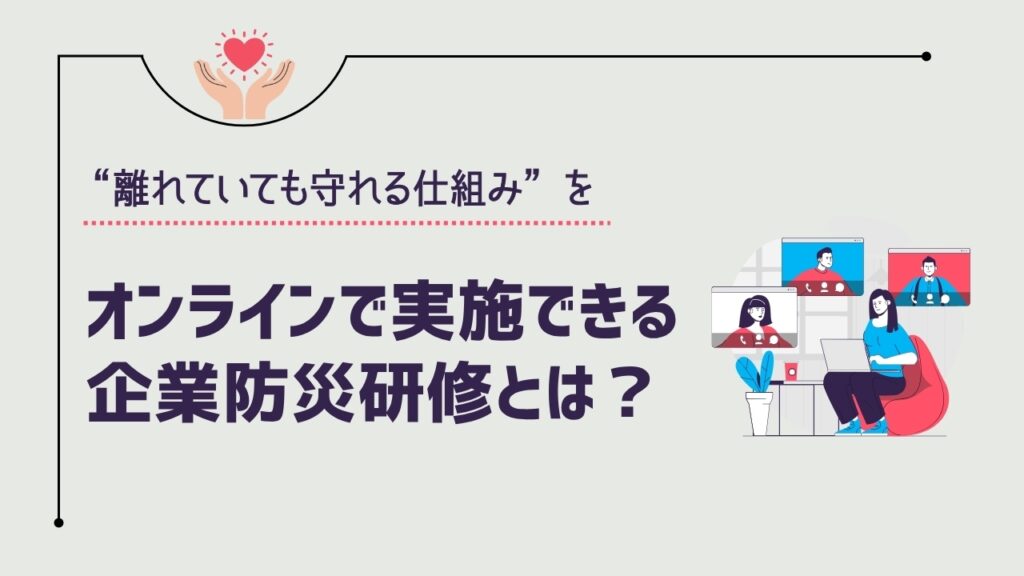
オンラインで実施できる企業防災研修とは?
-
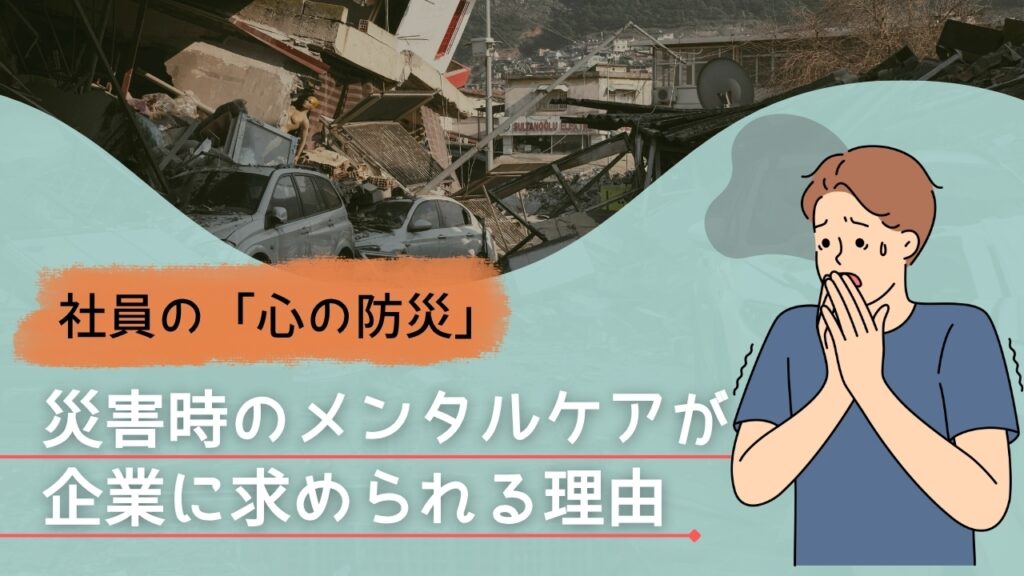
災害時のメンタルケアが企業に求められる理由
-
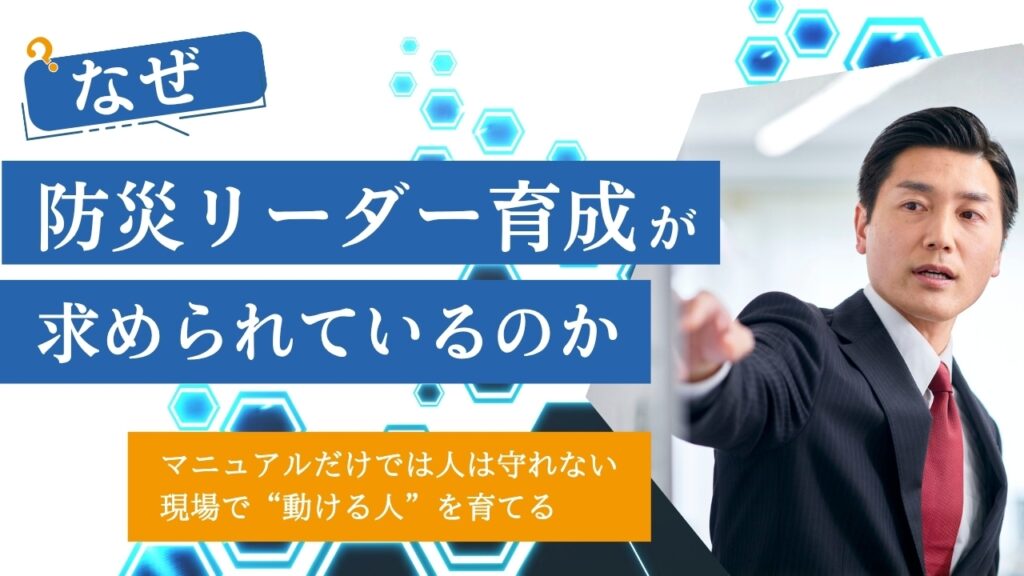
なぜ今、防災リーダー育成が求められているのか
-
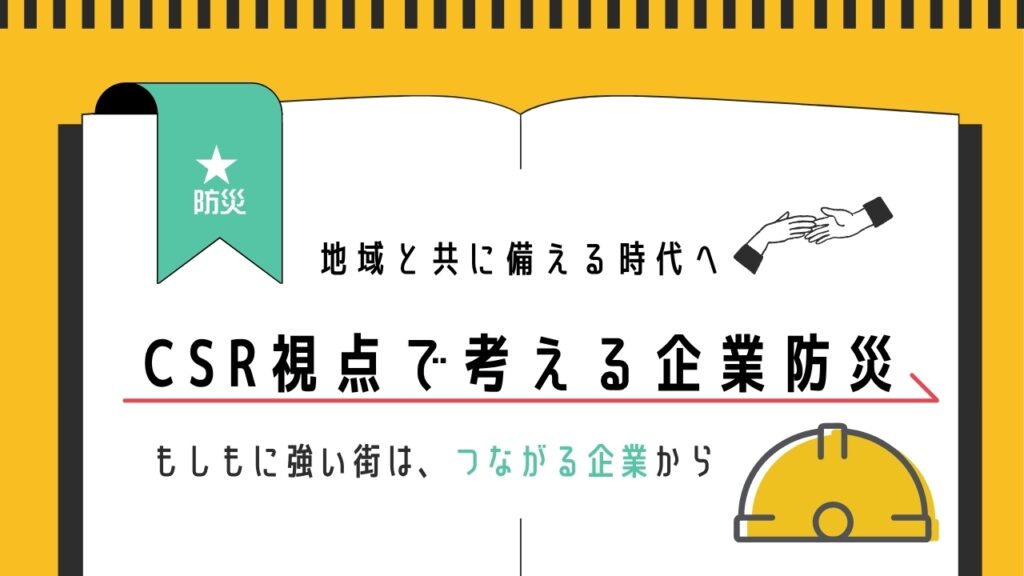
CSR視点で考える企業防災|地域と共に備える時代へ
-
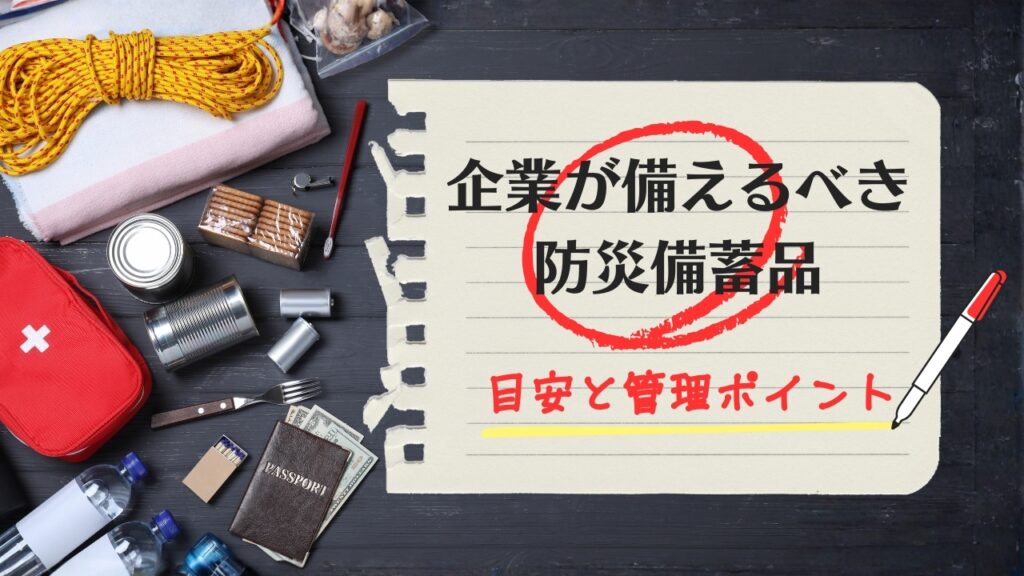
企業が備えるべき防災備蓄品の目安と管理ポイント
-
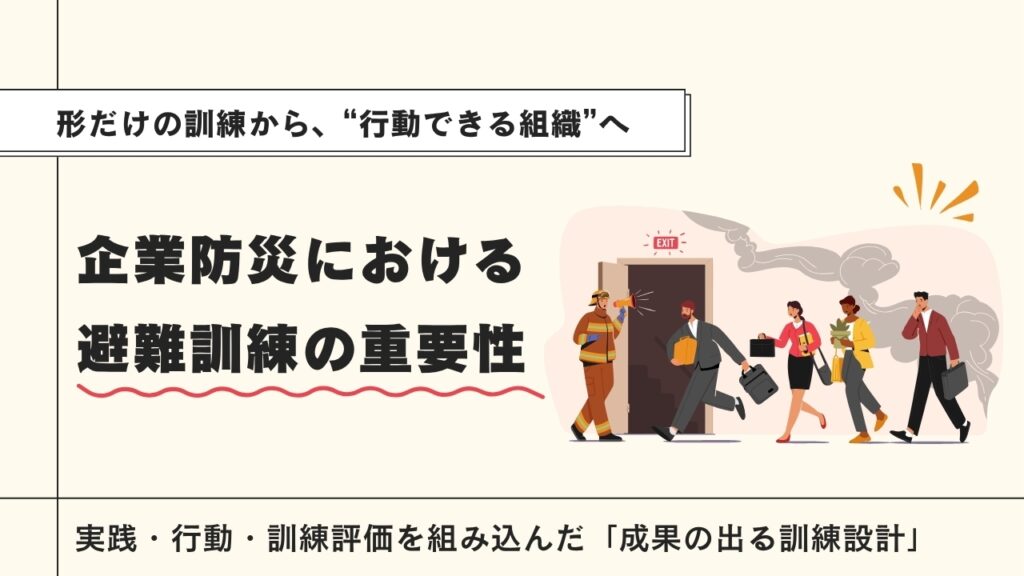
企業防災における避難訓練の重要性|形だけの訓練から、“行動できる組織”へ
-
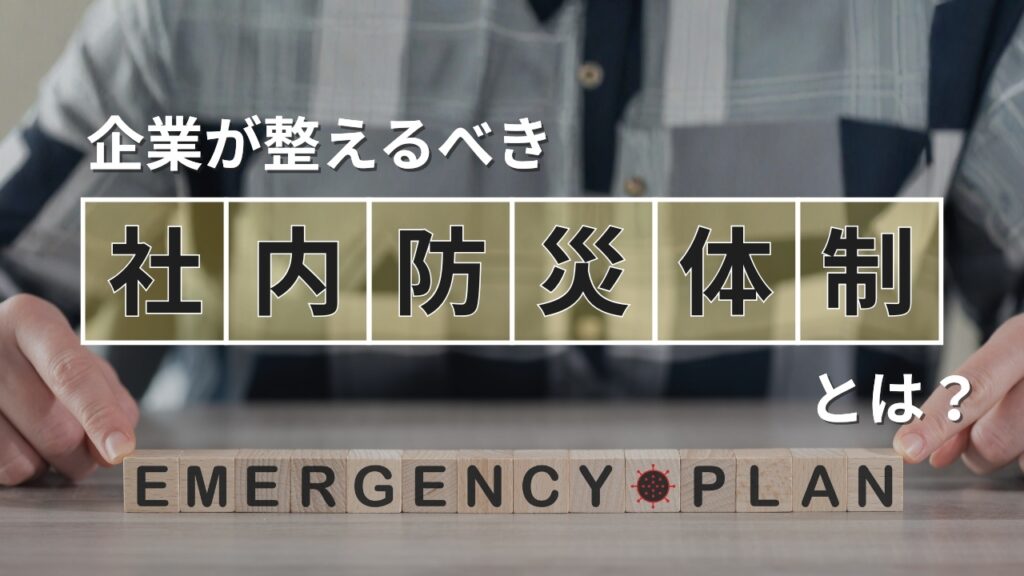
企業が整えるべき「社内防災体制」とは?
-
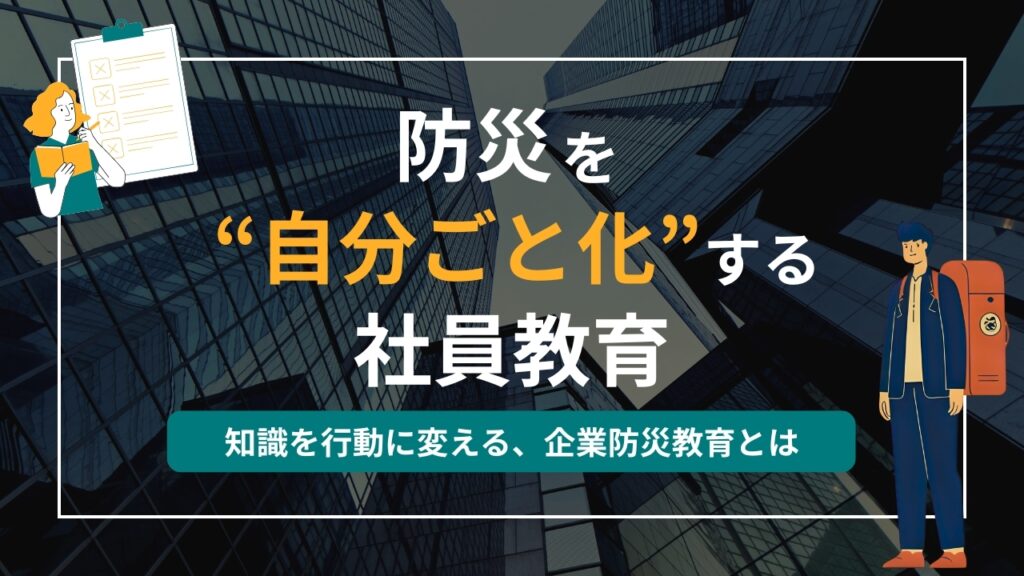
防災を“自分ごと化”する社員教育 |知識を行動に変える、企業防災教育とは
-
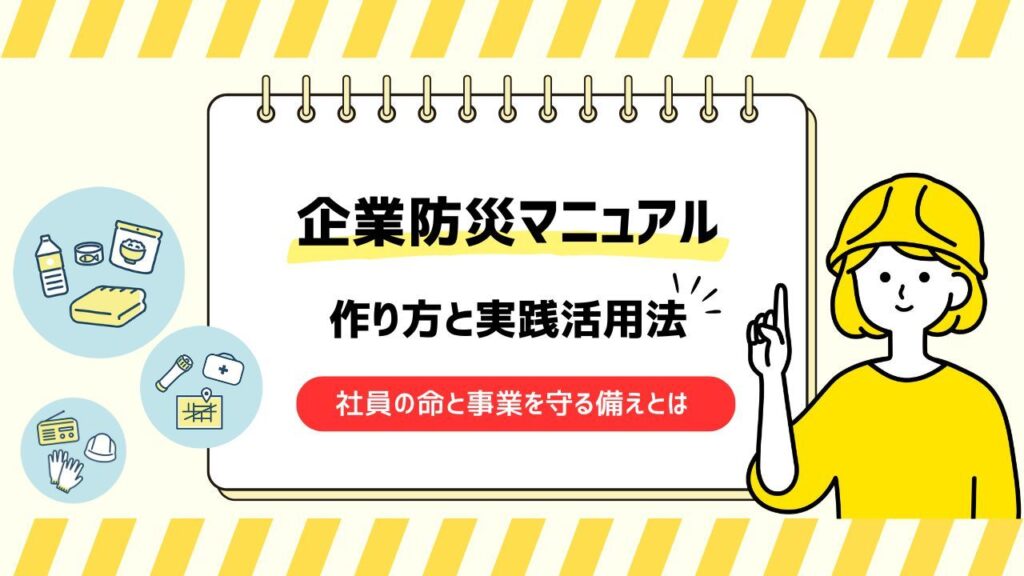
企業防災マニュアルの作り方と実践活用法|社員の命と事業を守る備えとは
-

企業防災とは?企業を守る実践的な防災・BCP対策ガイド
-

【企業防災研修】で社員と会社を守る!防災意識を高めるオーダーメイド研修とは
-
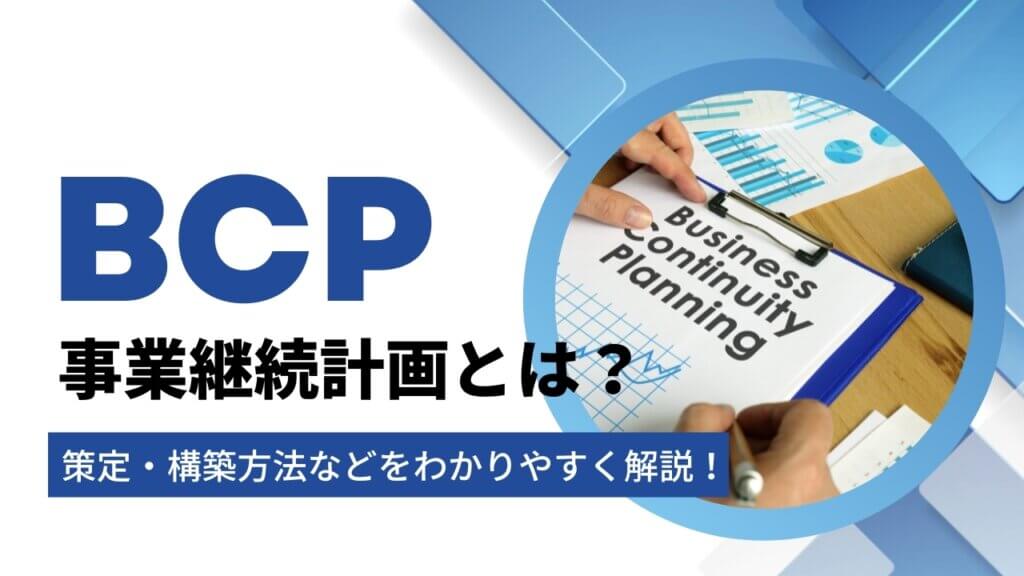
BCPとは?事業継続計画の策定・構築方法などをわかりやすく解説!