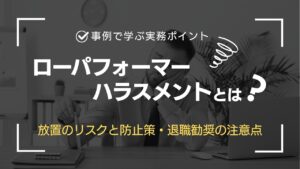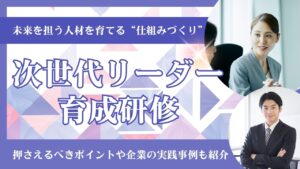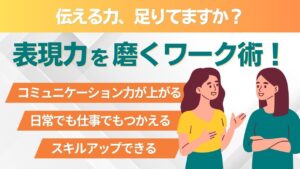ローパフォーマーハラスメントとは?放置のリスクと防止策・退職勧奨の注意点
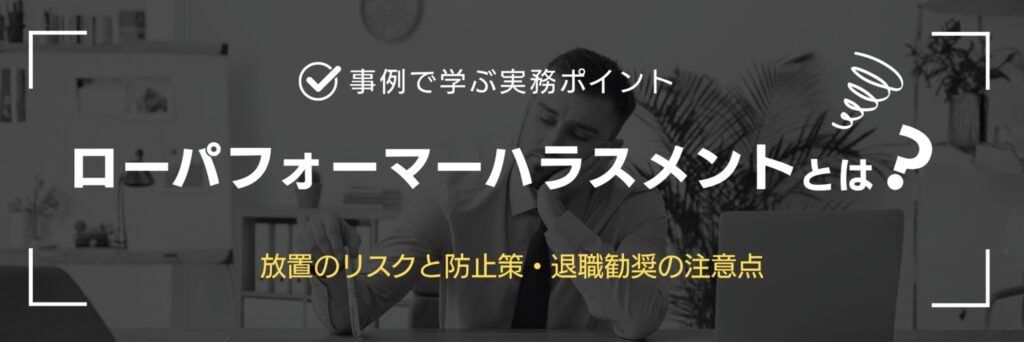
「成果が出ない社員(ローパフォーマー)」への対応は、多くの企業や管理職にとって避けて通れない課題です。指導を重ねても改善が見られない場合、つい感情的な叱責や排除的な対応に発展してしまうこともあります。しかし、指導が行き過ぎれば、単なる指導ではなくハラスメントとみなされる可能性があります。これが「ローパフォーマーハラスメント」です。
対応を放置すれば職場の信頼関係の崩壊や離職、さらには法的トラブルを招くリスクにも直結します。逆に、適切な支援や対応を行えば、社員の成長を促し、組織全体の健全化にもつながります。

本記事では、ローパフォーマーハラスメントの意味や放置するリスク、防止のための具体策、さらに退職勧奨を進める際の注意点までを解説。管理職や人事担当者が現場で迷わないための実務的なヒントをお届けします。
ローパフォーマーとは
「ローパフォーマー」とは、業務の成果が期待される基準に満たない社員を指します。
典型的な特徴として、主体性が低い、同じミスを繰り返す、コミュニケーションが不足しているなどが挙げられます。
こうした状態が生じる背景には、本人だけの問題ではなく、不適切なマネジメント、過剰な業務量、採用や配属のミスマッチ(スキル・適性不足)、さらには本人の性格やスキル不足など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。
企業側の対応や環境が原因でパフォーマンスが下がるケースも少なくないため、単純に「能力が低い」と切り捨てるのではなく、背景を把握することが重要です。
ローパフォーマーハラスメントとは
「ローパフォーマーハラスメント」とは、社員の能力不足や成績不良を理由に、過剰な叱責や孤立、排除などの不当な扱いをする行為を指します。
- 公開の場で繰り返し厳しく叱責する
- 改善の機会を与えず、業務を一切任せない
- 無視したり、チームから意図的に孤立させる
このような対応は、指導の域を超えたハラスメントとみなされる可能性があります。
パワーハラスメントなど、他のハラスメントと同様、社員の尊厳を傷つけ、メンタル不調や職場全体の雰囲気悪化を招くリスクがあります。
ただし、ローパフォーマーハラスメントは「能力不足を理由にした不当な扱い」という点で特徴的です。
ローパフォーマーへの適切な対応を怠ると、
・チーム全体の生産性低下
・優秀な社員の離職
・メンタル不調や訴訟リスクの増加 など、企業にとって重大なダメージにつながります。
適切なフィードバックや改善支援と、不当な扱いの境界を明確にしておくことが重要です。
ローパフォーマーハラスメントの具体的な言動事例
次のような行為・言動は、典型的なローパフォーマーハラスメントです。
叱責・否定
部下を叱責・否定するパターンです。
・会議やチームミーティングなどで「君は何をやってもダメだ」と繰り返し叱責する。
・同じミスをする度に人格を否定するような発言をする。
など、これら以外にも、「使えない」「役立たず」「給料泥棒」「新人以下」など、あらゆる暴言や人格・能力否定が該当します。
排除・孤立型
部下のミス等を過剰に追求し、チームから排除・孤立させてしまうパターンもリスクがあります。
・重要な業務や会議から意図的に外す。
・チーム内で無視したり、必要な情報を伝えない
など、能力不足などを理由にチームから排除したり、意図的に孤立させてしまうことも注意しましょう。
改善を促さず一方的に嫌がらせや叱責する
ミスを隠蔽してしまった部下に対して、過度なプレッシャーや萎縮させるような高圧的な態度で注意することも、ローパフォーマーハラスメントです。
・二度と会社に来るな
・お前のせいでチームの信頼がガタ落ちだ
など、改善を促すことなく一方的に叱責することは避けましょう。
パワハラ・モラハラとローパフォーマーハラスメントとの違い
ローパフォーマーハラスメントと混同されやすいものとして、「パワハラ」や「モラハラ」が上げられます。
ローパフォーマーハラスメントとの違いは、以下の通りです。
| 項目 | パワハラ (パワーハラスメント) | モラハラ (モラルハラスメント) | ローパフォーマー ハラスメント |
|---|---|---|---|
| 主な特徴 | 職務上の優位性を利用し、精神的・身体的苦痛を与える | 長期的に精神的に追い詰める | 成果が出ない社員を狙い、長期的に精神的圧力をかける |
| 加害者の立場 | 上司・先輩など立場が上の人が多い | 上下関係に限らず発生 | 優位性の有無を問わない |
| 根拠・理由 | 立場や権力の差 | 個人的な支配欲・性格的要因 | 業績や能力の不足を理由にする |
| 共通点 | 精神的な苦痛を与える | 精神的に追い詰める | 精神的に追い詰める |
| 違いのポイント | 「立場の差」を利用する | 「長期的・精神的支配」が中心 | 「業績や成果の不振」がターゲットになる理由 |
| 指導との違い | 適切なフィードバックや改善支援があるかどうかで区別される | 改善支援がなければ「ハラスメント」になる | 改善のためのサポートがなく叱責や排除が続くと「ハラスメント」 |
ローパフォーマーハラスメントが問題になる理由
ローパフォーマーハラスメントは、社員個人だけでなく企業全体に深刻な影響を与える可能性があります。
社員への影響
ローパフォーマーハラスメントは、社員の能力や業績に対して叱責や排除が続くため、社員のメンタルが不調になり、休職や離職につながることが考えられます。また、ハラスメントを受けている社員の近くにいる人たちも、モチベーションの低下や職場不信などになる可能性があります。
企業への影響
ローパフォーマーハラスメントによって、チーム全体の士気が下がり、生産性が下がることが考えられます。また、他の社員がハラスメントを受けている様子を見ている社員が離職する中で、優秀な社員(幹部候補など含む)が離職してしまい、社員の定着率が下がる、ハラスメントを受けた社員が訴訟を起こすなど、法的リスクも避けられません。
明確な境界線がない
多くのハラスメントが、「指導とハラスメントの境界線」が不明確であることが課題と言われています。部下やメンバーを育てようとしているのか、「改善」「適切なフィードバック」を行う仕組みがあるのかなど、組織としての評価基準や対応マニュアルが整備されていない状況では、管理職が思いがけずハラスメントしてしまうようなケースもあります。
ローパフォーマーハラスメントの事例とNG対応
ローパフォーマーハラスメントの事例やNG対応には、どのようなものがあるのでしょうか。以下では、ありがちな事例とNG対応を解説します。
多くの企業では、社員それぞれと仕事に対しての評価面談を行います。その際、良いところだけでなく課題を伝えることは当然です。
しかし、その中で「改善のためにどうするか」や「適切なフィードバック」を与えることなく、ひたすら人格を否定するような発言を繰り返すのは、明らかなローパフォーマーハラスメントです。
「あなたは会社のお荷物だ」「給与泥棒だ」など、管理職のストレスや怒りの感情をそのままにぶつけてしまうことは避けるべきです。
部下やメンバーを、明確な理由の説明等をせず重要な業務から外すことも、ローパフォーマーハラスメントの一つです。
「もう明日から業務から外れてもらっていいから」「これだけやってくれてたらいいから」など、理由がわからないままに外されてしまうと、モチベーションや自己肯定感、パフォーマンスの低下を招きます。
休職明け、産休・育休明けの社員に対しての接し方や対応方法によっては、ローパフォーマーハラスメントにつながってしまうこともあるため、注意しましょう。
ローパフォーマーハラスメントは、ただ単純に叱責し、孤立させ、改善の機会を与えないというケースもあります。
「どうせ改善できやしない」「言ったってできないだろう」「これだから、あなたはいつもダメなんだ」など、日常的な叱責を繰り返し、周囲やチームから孤立させてしまうことは大変危険です。
| 適切な指導 | NG対応(ローパフォーマーハラスメント) |
|---|---|
| 業務上の具体的な事実を伝え、 改善方法を一緒に検討・実行する | ただ感情的に叱責し、人格否定を繰り返す。 改善指導等はなし。 |
| 改善計画を一緒に考える(もしくは提示)して、 期限を設けて目標設定を行い、ミーティングなどでフィードバックを行う。 | 改善の機会を与えず、ひたすら叱責を行う。 周囲から孤立させてしまうことも。 |
| 業務に必要な情報(ノウハウなど)を提供し、 業務が円滑に行えるよう支援する。 | 情報提供を遮断し、他の社員とコミュニケーションや連携をさせない。 |
ローパフォーマーハラスメント防止のために企業が取るべき対策
ローパフォーマーハラスメントを防ぐには、”現場任せの対応”ではなく企業全体での仕組みづくりが欠かせません。管理職や社員が「どこまでが指導で、どこからがハラスメントなのか」を共通認識としてモテるようにしておきましょう。
評価基準・ルールの明確化
まず、成果基準や指導プロセスを社内で明文化しておきましょう。
- どの程度の成果を「期待する水準」とするのか
- 改善に向けてどのような支援や面談を行うか
- 指導から配置転換などに至るまでの流れ
など、これらをマニュアルやガイドラインとして文章化しておくと、現場の判断が個人の感覚に左右されにくくなり、管理職も安心して指導を行うことができます。
管理職研修・トレーニング
ハラスメント防止は、ルールを作るだけでなく管理職が「コーチング」や「フィードバック」のスキルを習得することが重要です。
- 叱責ではなく「成長を促す面談」の進めかた
- 事実(行動など)に基づくフィードバックの伝え方
- ハラスメントに該当する言動の境界線
など、これらをケーススタディやロールプレイを通して学ぶ研修は、指導とハラスメントの線引きを体感的に理解する上で、大きな効果があります。
相談窓口・内部通報制度の整備
社員が安心して声を上げられる相談窓口や内部通報制度を設けることも、早期発見・早期対応につながります。匿名で相談できる体制や外部窓口の活用など、「報告したことで不利益を受けない」環境づくりが信頼の土台です。
「適切な指導」の共通認識化
社内研修やマニュアルを通じて、「どこまでが適切な指導か」を全社員に共有することも不可欠です。
具体的な事例をもとに「これは指導、これはハラスメント」という判断を練習することで、現場で迷ったときに正しい対応を選べるようになります。
ローパフォーマー対応のステップ
ローパフォーマーへの対応は、「改善支援を尽くしたうえで、必要に応じて配置転換や退職勧奨に進む」という段階的なプロセスが重要です。いきなり退職を促すのではなく、以下のステップを踏むことで法的リスクを抑えつつ、社員の成長の可能性を最大限に引き出せます。
問題点の分析
まず、パフォーマンス低下の原因を客観的に把握します。
- 上司や同僚からの多面的評価
- 業務データや成果指標の確認
- 職場環境や業務量の検証
本人の努力不足だけでなく、業務過多や役割不一致など、組織側に原因があるケースも少なくありません。
面談・目標設定
次に、本人との面談で現状と課題を共有し、具体的な目標と期限を設定します。
「何を」「いつまでに」「どの水準まで」改善するのかを数値や行動レベルで明示することで、本人も納得感を持って取り組めるようになります。
改善支援
目標に向けて、研修やコーチング、OJT(職場内訓練)など成長の機会を提供します。
改善を求めるだけではなく、上司や同僚が支援する姿勢を示すことで、本人のモチベーションを引き出せます。
環境調整
マネジメント体制や業務量、人間関係など、職場要因の見直しも並行して行います。例えば、業務量を一時的に減らして改善に集中させる、適性に合った業務を再配分するなど、企業側の柔軟な対応が改善の鍵です。
配置転換の検討
一定期間の改善機会を経ても成果が出ない場合は、適性に応じた異動や職務変更を検討します。新しい環境で能力が発揮されるケースもあり、退職以外の選択肢を模索することが本人と企業双方の利益になります。
退職勧奨へ移行
配置転換でも改善が見込めない場合、最終手段として退職勧奨を行います。
- 指導や改善支援の記録(指導書・面談記録など)を残す
- 配置転換など他の選択肢を尽くした証拠を確保する
- 脅迫や過度な圧力を避け、法令に沿った手続きを踏む
これらを徹底することで、訴訟や不当解雇といった法的リスクを最小限に抑えられます。
退職勧奨・解雇時の注意点
ローパフォーマーへの対応を進めても、一定の改善が見られない場合、最終的に退職勧奨や解雇を検討するケースがあります。
しかし、退職勧奨や解雇は「最終手段」であり、法的に厳しく制限されている点を忘れてはいけません。手順を誤れば、不当解雇やハラスメントとして訴えられるリスクが高まり、企業に深刻なダメージをもたらします。以下のポイントを押さえて、慎重かつ透明性の高い対応を徹底することが重要です。
指導・改善の経過を記録として残す
退職勧奨や解雇を行う場合、これまでの改善支援を客観的に示す証拠が不可欠です。
- 面談記録(日時・内容・本人の発言)
- 指導書・改善計画書
- 目標設定や評価結果
これらを時系列で整理し、指導や支援を十分に行ったことを明確にしておくことで、「突然の一方的な解雇」と受け取られるリスクを回避できます。
配置転換や業務調整など、他の選択肢を尽くす
退職勧奨に進む前に、異動や職務変更、業務量の調整などあらゆる改善策を検討した記録が必要です。
- 他部署への配置転換の可否
- 業務内容や担当範囲の見直し
- 研修や再教育の実施状況
「会社としてできる限りの支援を尽くした」という事実は、万一の法的紛争において強力な証拠となります。
解雇は最終手段として慎重に
解雇は労働契約法や判例で厳格に制限されており、客観的合理性と社会的相当性が認められなければ無効となる可能性があります。
- 業務上の能力不足だけでは「普通解雇」の要件を満たさない場合が多い
- 改善のための合理的期間や支援を経ても成果が見られないことを証明する必要がある
- 弁護士や社会保険労務士など専門家の確認を得て進めることが望ましい
解雇通知を行う際は、手続きの適正性や説明責任を徹底し、本人の人格を尊重する対応が求められます。
退職勧奨で避けるべきNG行為
退職勧奨自体は違法ではありませんが、脅迫的な言動や過度な圧力を伴うと不法行為にあたる可能性があります。
例えば以下のような対応は、裁判で違法と判断されるリスクがあります。
- 「辞めなければ人事評価を下げる」「同僚に迷惑だ」といった威圧的発言
- 長時間の面談や繰り返しの呼び出しによる精神的圧迫
- 退職届の強要や、退職以外の選択肢を提示しない
退職勧奨はあくまで「会社として提案する選択肢のひとつ」であり、本人が自由意思で判断できる環境を整えることが不可欠です。
研修導入の必要性とメリット
多くの管理職は「指導とハラスメントの境界」を学ぶ機会が少なく、無自覚にハラスメントを起こしてしまうリスクがあります。
研修を導入することで、以下のような効果が期待できます。
- ハラスメント防止:指導の適正化により法的リスクを低減
- 社員定着率・エンゲージメント向上:安心して働ける職場づくり
- チーム生産性向上:メンバーが安心して能力を発揮できる環境整備
ガイアシステムでは、ハラスメント防止とローパフォーマー対応に特化した研修を提供しています。
実践的なケーススタディやロールプレイを通じて、現場で即活かせるスキルを習得可能です。
オーダーメイド設計やアフターフォローにも対応しており、組織課題に合わせた研修が実施できます。
ローパフォーマーハラスメントQ&A
まとめ
ローパフォーマーへの対応は、単なる人事上の課題にとどまらず、企業文化や法的リスクにも直結する重要なテーマです。適切な対応を怠れば、ハラスメントの発生や離職、職場環境の悪化といった深刻な影響を招きかねません。
一方で、ハラスメントを防ぎながら社員の改善や成長を支援する仕組みを整えることは、健全な職場づくりに直結します。そのためには、管理職が適切な指導スキルを身につけ、評価基準やルールを統一することが第一歩です。さらに、管理職向けの専門研修や制度設計を活用すれば、職場全体で共通理解を深めつつ、社員の成長を促し、企業リスクを最小化する体制を構築できます。
こうした取り組みは、生産性向上や社員エンゲージメントの向上にもつながります。
ガイアシステムでは、ローパフォーマーハラスメントをはじめとした各種ハラスメント研修を実施しています。自社の課題に合わせた実践的なプログラムをご用意していますので、ぜひお気軽にご相談ください。
お客様の課題やカリキュラムに応じてお見積りパターンをご提案しています。
まずは気軽にご相談ください!
お電話でのお問い合わせ 0120-117-450
専任のコンサルタントが丁寧にご相談を受け付けます。
お気軽にご相談ください。