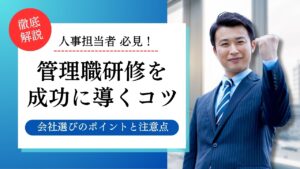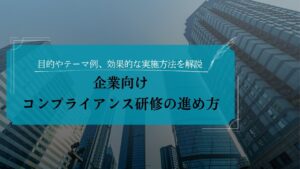管理職研修の必要性とは?”こんな時代”だからこそ取り組むべき理由

「管理職研修って本当に必要?」「社内で管理職研修をやっているけれど、あまり効果が見えない」
研修担当をしていると、こんな疑問を持つことはありませんか?
研修はコストや時間がかかるため、必要性が十分に理解・納得されていないと、なかなか導入に踏み切れないという声もよく聞きます。

今回は、管理職研修の必要性について整理し、研修を導入・実施する意義や、その際に押さえておきたい実践のポイントについてわかりやすく解説します。
管理職研修の必要性が高まる背景
管理職研修の必要性は、年々高まっています。これには、次のような要因が考えられます。
働き方改革と労働環境の変化
近年、テレワークやフレックスタイム制が普及したことで、管理職はメンバーの業務量や進捗を把握し、サポートするスキルが不可欠となりました。管理職研修を受けることで、テレワーク導入後のメンバーの残業時間を減らすことも期待できます。
多様性のマネジメント
組織の多様性が高まるにつれて、それぞれに適したマネジメントが難しくなっていますが、管理職研修に「ダイバーシティ」に関する内容を取り入れることで、チーム内で意見交換が増えた事例もあります。
年齢、性別、価値観が異なる部下やメンバーに対して適切なマネジメントができるようになることで、組織全体の生産性向上も期待できるでしょう。
組織の成長・変革対応
企業全体が成長・変革する時は、現場全体の混乱やメンバーそれぞれのストレス、不満などが強くなりがちです。慣れている仕事内容や方向性、環境が変わるとどうしても現場の空気感も悪くなります。
そこで、新規事業や組織変革など大きな変化がある時ほど、管理職がそれぞれのストレスを解消しつつ導いていく必要があるのです。管理職研修では、そのような時に効果的なスキルや知識も身につけられます。
管理職研修で身につけられるスキル一覧
管理職は、経営層と現場の橋渡しを担う要となる存在です。
その役割は単なるマネジメントにとどまらず、チームを導き成果を高めるために幅広いスキルが欠かせません。ここでは、研修を通じて身につけられる主なスキルと、「なぜ管理職研修が必要なのか」という理由を紹介します。
管理職研修で習得したいスキル一覧
- 基礎実践スキル、コミュニケーションスキル
- ティーチングスキル(指導力)
- コーチングスキル(質問力・傾聴力・面談力)
- セルフマネジメントスキル
- ファシリテーションスキル
- ジョブアサインスキル
- 本質的問題抽出、問題解決スキル
- 目的策定、目標策定、目標管理スキル
- プレゼンテーションスキル
- チームマネジメント、チームビルディング

以下、上記10個のスキルから抜粋してご紹介します
チームマネジメント、チームビルディング
チーム全体のマネジメントでは、進捗状況の可視化やタスクの優先順位づけなどが重要です。しかし、それらは経験則だけでなんとかなるものではありません。売り上げ目標やプロジェクト進行の管理では、効率的な組織運営が成功の鍵となります。
管理職研修は、自分の経験とスキルを結びつける場にもなるのです。
ティーチングスキル(指導力)・メンバー育成・部下育成
部下育成のスキルは、「個々の能力に応じた指導とサポート」が重要です。
近年「いかに自社に定着してもらうか」が重要な課題となっている企業が多いかと思いますが、
社員の定着率を高めるためには、定期的な1on1や、成長に応じた目標設定が効果的です。
自分の経験だけで対応すると、どうしても誰に対しても同じやり方になってしまい、部下やメンバーにとっては「成長が見込めない」と感じてしまいます。結果、離職の原因となることもあります。
経営層と現場の橋渡し
管理職は、経営層からの指示を現場に落とし込むことも重要な役割です。しかし、伝え方や現場の理解度を確認せずに指示を伝えると、現場全体や個々の混乱、さらにミスの増加につながる恐れがあります。
そこで、現場それぞれに合った適切なコミュニケーションスキルが必要なのです。
コンプライアンス遵守
近年、パワハラ防止法の施行などにともない、法令やハラスメント防止などリスクマネジメントの知識が欠かせなくなりました。
管理職として、研修を通じて事例対応力を身につけておくことが必要です。
管理職研修を実施しない場合に起こるリスク
もし、管理職研修を行わなかったとしたら、どのようなリスクが考えられるでしょうか。
ここでは、4つのリスクを紹介します。
メンバーの離職増加
メンバーの離職理由として、「管理職のマネジメントが不適切だったこと」が挙げられる場合があります。過去には、管理職の育成が十分でなかったために離職者が増え、採用コストが数百万円単位で増加したケースもあります。
職場トラブルの増加
職場トラブルが、管理職の目の届かないところで起こりがちです。管理職が気付いて対応するころには、取り返しのつかないことになっていた…ということは珍しくありません。
近年、パワハラやセクハラなどの「ハラスメント」は種類が増え、発生リスクも高まり続けています。最悪の場合、企業の信用低下や損害賠償などのリスクも考えられるため、研修によって未然に防げるようスキルを身につけておく必要があります。
組織全体の停滞
管理職には、現場の改善や組織の改革という役割があります。管理職が日々の業務に追われていたり、改善提案や組織改革提案が滞ってしまうと、作業効率が落ちることにつながります。
その結果、生産性が低下し、組織全体の成長が停滞してしまうのです。
業績への悪影響
マネジメントスキルが低いと、売り上げや利益、プロジェクト進行に悪影響が及びます。例えば、プロジェクトの進行管理や個々のタスク調整へのサポートが不十分になってしまうことで、納期遅延やコスト増加などが起こり、全体の利益率低下にもつながるのです。
管理職研修の効果を高めるためのポイント
ここからは、効果的な管理職研修を行うためのポイントをお伝えします。これらのポイントを押さえることで、管理職研修をより効果的に実施できます。
ポイント① 実践型・ケーススタディを意識する
研修では、ただ知識やスキルの種類を紹介し、それらについて学ぶだけでは効果がありません。
それぞれが現場に持ち帰った時に活用できるようにしておく必要があります。
そこで、現場で起こりやすい課題を題材にしたロールプレイやグループワークを行うことをオススメします。
例えば、メンバーや部下との面談を想定したロールプレイを行うことで、実際の学びが実務に直結し、実際に1on1での課題把握やフィードバックの精度向上が期待できます。
ポイント② 自社課題に即したカスタマイズ
管理職研修は、「自社の課題」をしっかりと把握した上でカスタマイズすることが重要です。どの組織でも役立つ内容の研修もありますが、自社の文化や現場の課題に合わせた内容にカスタマイズすることで、より実践に近づけた状態で学ぶことができます。
例えば、製造業の現場であれば「安全管理」や「チームの作業効率化」をテーマとした研修、IT企業であれば「リモートワークチームの進捗管理」など、自社が課題としていることを解決できるような研修を設計すると良いでしょう。
ポイント③ 継続的なフォローアップ
研修後は、継続的なフォローアップが欠かせません。研修後の1on1やフィードバックによって、学んだことを定着させて行動変容を促したり、管理職が自信を持って日々の業務に臨むこと、メンバーや部下との信頼関係構築の強化も期待できます。
社内研修と外部研修を組み合わせるメリット
管理職研修を効果的に行うためには、外部研修の活用も重要です。
最新の知見を取り入れられる
研修を外部講師に依頼することで、他社の事例や最新法令に基づいた知識を取り入れられるなど、社内だけでは気付かない学びが得られます。
例えば、パワハラ防止法改正に対応するための方法や多様性マネジメントの手法など、外部講師から学ぶことですぐに実践に結びつけられるものがあります。
客観的な視点から自社課題を分析できる
外部講師は基本的に中立的な立場であり、組織課題を客観的に見て整理した上で研修内容を考えます。
そのため、研修を受けた後の改善策の優先順位付けや、管理職それぞれが現場で実践しやすいカリキュラム設計が期待できます。
社内説得の材料として活用できる
外部講師を招くことで、管理職研修の必要性を感じていない上層部や管理職自身に対して、研修を導入する理由や期待される効果を説明しやすくなります。
例えば、外部研修の参加後にレポートなどの資料を作成して経営層に見せることで、「研修の効果と改善ポイント」が明確になり、次の研修の企画や実施がやりやすくなります。
管理職研修の必要性に関するよくある質問(Q&A)
管理職研修は”組織の未来”への投資
管理職研修は、単なる教育ではなく、組織の成長に直結する「投資」です。しっかりとコストをかけて適切なスキルや知識を身につけた管理職は、メンバーや部下の定着率向上や業績アップに大きく貢献します。
とはいえ、研修担当者が自社だけでゼロから研修を設計するのは容易ではありません。そのためには、外部の専門機関をうまく活用することが重要です。
効果的な管理職研修をご検討の際は、ぜひガイアシステムも候補に加えてください。弊社では、企業ごとの課題に合わせたオーダーメイド型の研修をご提供しています。
「自社に本当に必要な研修内容を設計したい」「効果的な運用方法を相談したい」など、管理職研修に関するお悩みにも対応しております。どうぞお気軽にご相談ください。
お客様の課題やカリキュラムに応じてお見積りパターンをご提案しています。
まずは気軽にご相談ください!
お電話でのお問い合わせ 0120-117-450
専任のコンサルタントが丁寧にご相談を受け付けます。
お気軽にご相談ください。