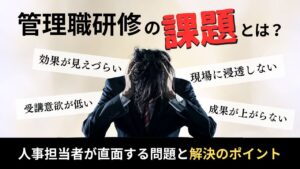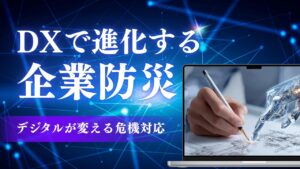管理職研修の課題とは?人事担当者が直面する問題と解決のポイント
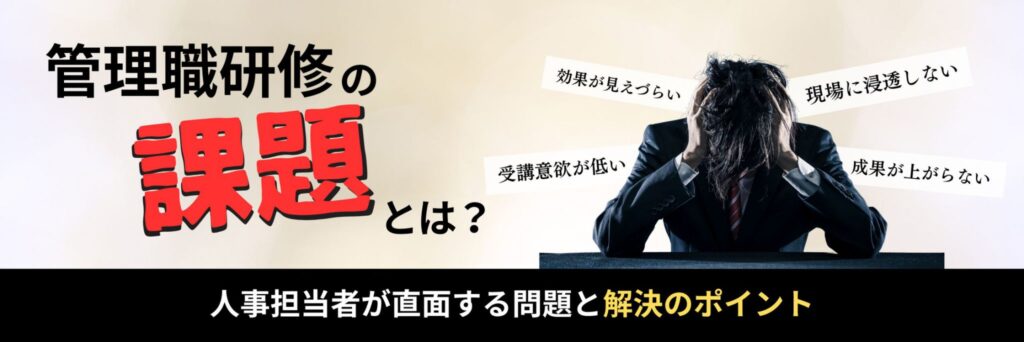
管理職研修は、企業の成長に欠かせない重要な研修として多くの企業で導入されています。ですが、「効果が見えづらい」「現場に浸透しない」など研修そのものには課題が多く、頭を悩ませる人事担当者も少なくありません。
本記事では、管理職研修の目的を振り返りつつ、実践における課題とその解決の方向性を整理してご紹介します。
管理職研修の目的
まずは、管理職研修を受講する管理職の目的を理解しておきましょう。
- 組織全体の生産性向上
正しいマネジメントにより業務の無駄を減らし、部署やチームの連携を円滑にします。
研修でスキルを身につけることで、組織全体の成果を高められます。 - 社員のモチベーション向上
部下の特性や強みを理解し、適切なサポートや評価を行うことで、社員のやる気を引き出します。
働きやすい環境は定着率向上にもつながります。 - 変化対応力の強化
社会情勢や市場環境の変化に柔軟かつ的確に対応できる思考と行動力を養い、
組織の不確実な時代への対応力を高めます。 - 次世代リーダー育成
若手社員に責任ある役割を与え成長を支援することで、
次世代リーダーを育て、組織の持続的な発展を支えます。
管理職が抱える課題
管理職研修を受講する管理職が感じる課題として上位を占めるのは、「部下育成力・コーチング力」「管理職としての役割意識」「リーダーシップ」があげられます。人材や働き方に多様性がある現代では、管理職は考え方やスキルも柔軟に変えていかなければなりません。
以下、管理職か抱える「課題」として多い4つを解説します。
部下とのコミュニケーション
この調査では、上司・部下間のコミュニケーションに「課題がある」と答えた人が約7割に登りました。多くの管理職は、「一般的な指示」や「報連相で留まる会話」が続くことに課題を感じており、部下やメンバーは「相談しづらい」「意見が届かない」「指導の内容がわかりづらい」といった感情を抱いてしまうケースもあるようです。
目標設定や評価
管理職は、チームやメンバーそれぞれの目標設定や評価を行う重要な役割を担っています。
仕事における目標は、「方向性を明確にして行動を促すため」に重要です。ただ「最善を尽くせ」「頑張れ」といった指示では具体性がなく、成果にはつながりません。
成果だけでなく、「プロセス」や「努力」も評価に含める適切な目標設定は非常に難しく、多くの管理職が課題と感じています。
業務バランス
管理職は、自分の業務とメンバーのマネジメント業務を同時にこなす必要があります。そのバランスが崩れると、業務効率の低下やストレス増にもつながります。
管理職になったばかりの場合、時間や人間関係、業務の調整に苦労し、部下やメンバーへの指導や戦略的な判断に十分なリソースを割けないこともあるため、注意が必要です。
リスク管理
管理職は、業務遂行上の法的責任から市場変動、プロジェクト失敗などに対する様々なリスクを俯瞰し、先手を打つことが必要です。リスク管理は、日々の業務で起こりうる不確実・潜在的なリスクを識別、評価して影響を最小限に抑えるものです。
管理職はリスクをできるだけ可視化して、継続的に管理する仕組みの構築が求められます。
管理職の課題別の研修事例(内容・効果・事例)
管理職研修では、受講者である管理職自身が抱える「課題」を解消することを目的としています。
単なる知識のインプットにとどまらず、ケーススタディやロールプレイを通じて「自分の課題を具体的に解決するための実践の場」を持つことで、研修の成果につながります。
ここでは、管理職が抱えやすい課題ごとに、研修の内容・効果・導入事例をまとめます。
※本文中に記載している費用感は、あくまで参考例となります。詳細は企業の規模や研修設計内容によって異なりますのでご確認ください。
1. 新入社員の早期離職への対応
- 課題:部下が定着せず、早期離職が続いてしまう
- 研修内容:メンター研修(部下を支える関わり方・傾聴力・フォロー方法の習得)
- 効果:部下の不安解消、定着率向上、離職コスト削減
- 事例紹介:IT企業(新入社員50名、離職率20% → 5%に改善)
- 導入期間:約3か月(フォロー含む)
- 費用感:30~80万円
2. 部下育成が進まない
- 課題:OJTをしても成果が出ず、部下が育たない
- 研修内容:OJT指導研修(育成計画の立て方・効果的なフィードバック方法を学習)
- 効果:部下の成長スピード加速、管理職の育成スキル強化
- 事例紹介:製造業(指導力不足が課題 → 1年で育成スピード2倍に)
- 導入期間:1日研修+半年フォロー
- 費用感:40~100万円
3. 若手社員のモチベーション低下
- 課題:部下が主体的に動かず、キャリア意識も低い
- 研修内容:キャリアデザイン研修(部下のキャリア支援や動機づけの手法を学ぶ)
- 効果:部下の主体性発揮、チームのエンゲージメント向上
- 事例紹介:商社(入社3~5年目の部下を対象に離職意向が半減)
- 導入期間:1~2日
- 費用感:30~70万円
4. 職場内の人間関係トラブル
- 課題:ハラスメントや人間関係の問題で職場の雰囲気が悪化
- 研修内容:ハラスメント防止研修(ケーススタディやロールプレイで予防意識を高める)
- 効果:トラブル予防、心理的安全性の確保、チームの信頼関係向上
- 事例紹介:医療機関(苦情件数が年間10件 → 1件に減少)
- 導入期間:半日~1日
- 費用感:20~50万円
5. 管理職のマネジメント力不足
- 課題:目標設定や評価、チームビルディングが十分にできない
- 研修内容:管理職研修(マネジメントの基礎~応用を体系的に習得)
- 効果:組織力強化、成果創出、部下満足度の向上
- 事例紹介:サービス業(評価制度の定着に成功、部下満足度UP)
- 導入期間:2日+半年フォロー
- 費用感:80~150万円
6. クレーム対応の弱さ
- 課題:部下や自分自身が顧客クレーム対応で消耗している
- 研修内容:接客・接遇研修(ロールプレイを通じた傾聴力・感情コントロール習得)
- 効果:顧客満足度の向上、クレーム件数削減、再購入率改善
- 事例紹介:ホテル(クレーム件数3割減、口コミ評価が向上)
- 導入期間:1日
- 費用感:20~60万円
7. 危機対応力の不足
- 課題:災害・不祥事など、突発的なリスクに備えられていない
- 研修内容:防災・リスクマネジメント研修(BCP理解、緊急時対応訓練)
- 効果:初動対応力強化、組織としての信頼性向上
- 事例紹介:流通業(災害時の復旧時間を半減)
- 導入期間:1日+年1回訓練
- 費用感:50~120万円
8. 次世代リーダー不足
- 課題:中堅層の育成が進まず、幹部候補が不足している
- 研修内容:次世代リーダー研修(課題解決力・意思決定力・プレゼン力強化)
- 効果:幹部候補の育成、組織の持続的な成長を実現
- 事例紹介:建設業(主任・係長層を対象に昇進候補者数が2倍に増加)
- 導入期間:3か月~半年
- 費用感:100~200万円
管理職研修を実施する際の「課題」
管理職研修の実施にあたっては、「効果測定が難しい」「現場に落とし込みづらい」といった共通の課題があります。
単に知識をインプットするだけでは、研修後の実務に結びつかず「研修の成果が見えにくい」と感じる人事担当者も多いのが現状です。
そのため、研修を設計する際には 「自社の課題に合っているか」「現場で実践できるか」「成果をどう測定するか」 を事前に整理しておくことが重要です。これらの課題をクリアすることで、管理職研修は組織の変革を後押しする実効性のあるものとなります。

ここからは、研修を実施する側が感じる課題を解説します。実施する際の課題を把握しクリアにすることで、より質の高い研修を行うことができます。
効果測定ができない
管理職研修の大きな課題の一つが、効果測定の難しさです。
多くの企業では、研修の効果を調べるためにアンケートや満足度調査を実施しています。しかし、これらの方法では表面的な情報しか得られず、実際の業務や成果への変化までは把握できません。
例えば、「リーダーシップが身についたか」「部下との関係性は改善したか」といった効果は、定性的な要素が多いため費用対効果がわかりづらいと言えます。そのため、経営層からは「費用に見合った結果が出ていないのでは」という疑問を抱かれることは少なくありません。研修を行う際には、目的と評価指標を明確化しておき、行動変容や数値成果と結びつけておく仕組み作りが必要です。
管理職層の受講動機が低い
研修を企画しても、管理職層の受講意欲が低いという問題は根強く存在します。管理職は日々多忙なため、「研修に参加する余裕はない」と考える人が多く、研修自体を「業務が増えた」と感じてしまうことがあります。
また、研修内容が自分の担当業務やチームの課題と繋がらない場合、「実務に役立たない」「現場では使えない」と感じ、積極的な姿勢を保ちにくくなります。こうなると、「仕方なく受けるもの」という認識になってしまい、学んだ内容の吸収や定着が難しくなります。
研修に対する動機づけを高めるためには、現場課題と研修内容をリンクさせ、本人のキャリアや役割成長に直結する意味づけを行うことが不可欠です。
研修内容が抽象的・理論的になりやすい
管理職研修のカリキュラムは、理論やフレームワークの紹介に偏りがちで、抽象的な理想論で終わってしまうことがあります。その結果、「実務でどう活用すればよいか分からない」「現場で役に立たない」と感じる人が多く、学びが実践に結びつかない状況になりがちです。
効果的な研修を行うためには、ケーススタディやロールプレイ、社内の具体的な事例を活用するなど、理論を現場の状況に合わせる工夫が欠かせません。
現場への落とし込みが難しい
多くの場合、研修を受けても「現場でどう活かすのか」が不明確なままで終わってしまうことがあります。これは、研修が画一的で業種や職場の内情を反映させられないためです。
そのため、現場では「研修で学んだことを実践する余裕がない」「現実に即していない」という不満を抱く人が少なくありません。
このギャップを埋めるためには、事前に現場のニーズを把握した上で、学びを実践に落とし込めるようなフォロー体制を含めた自社の業務課題に沿ったカリキュラム設計が重要です。
経営層の期待とのギャップ
この研修は、「経営層」「運営担当者」「受講者」それぞれに期待する成果が大きくズレてしまう可能性があります。
経営層は「組織の変革」や「成果の最大化」など、将来的に自社を牽引するリーダーの育成を期待しています。しかし、実際の研修は「とりあえず基本を押さえる」というレベルのプログラムにとどまることが多く、その結果、「経営層が期待するほどの効果は得られなかった」と評価されてしまうことがあります。
それぞれが期待する成果に乖離が続くと研修自体がただの「イベント」になってしまい、研修そのものにコストをかけることが疑問視されてしまいます。それぞれの意図と課題を擦り合わせた上でギャップを埋めた状態でのカリキュラム設計が成功の鍵となります。
板挟み問題の影響
管理職は、常に「板挟み」の状態です。経営層からは「成果の達成」を、現場からは「部下・メンバーのケア」や「働きやすさ」を求められます。そのため、理想的なリーダーを目指そうとしても、「売り上げ(成果)を上げながらメンバーの成長を支援する」という複数の役割を同時に果たす必要があり、学んだ内容を活かす余裕がなくなってしまうことがあります。
この状況は管理職の疲弊感を強め、ストレスフルな状態を作り上げることになります。そのため、カリキュラム設計では「成果とケアの両立」を前提にしながらも、実践的な対応力をつけられるようにすることが重要です。
管理職研修の課題を解決するためのポイント
管理職研修の課題解決のためには、研修を実施するだけでなく「受講動機」「自社戦略との連携」「実践への落とし込み」「効果測定」という4つのポイントを抑えることが重要です。
受講動機を高める仕掛け
まず、管理職が「研修を受けたい」と思えるようなカリキュラム構成が重要です。
現場の課題や自分のキャリアと研修を結びつけ、「これは自分に必要だ」と納得して受講できる内容にすることで、受講姿勢は大きく変わります。
また、管理職のロールモデルとなる上司の紹介やメッセージなど、外的動機づけを取り入れることも効果的です。
自社戦略と結びつけた設計
研修は、一般論だけでなく自社の戦略や事業課題、今後の展開に沿ったものが良いでしょう。戦略の実現に向けて管理職が担う役割や責任を明確にして、それに直結するスキルや思考を学ぶことで、研修は「会社の未来につながる学び」という位置づけになります。
経営層と運営側の意図を共有して、設計することが不可欠です。
職場実践につながる仕組み
研修後の学びは、現場に持ち帰れる仕組みがなければ一時的なものになってしまいます。
フォローアップ研修や上司との面談、現場での実践課題など学んだことを定着させる体制を整えましょう。そして、学びと実務カリキュラムを丁寧に設計することで、研修を成果に繋げていきましょう。
自社にあう効果測定の改善
研修の効果測定は、自社に合った多面的な方法を検討することが効果的です。
例えば、アンケート中心から脱却し行動変化を上司やメンバーからのフィードバックで確認したり、業務成果やエンゲージメント調査と連動させることがあります。
組織の目的にあった測定指標を設定することが、研修の価値を可視化することにつながります。
ガイアシステムの管理職研修の強み・研修効果を高める仕組み
ここからは、ガイアシステムが提供する管理職研修の強みや効果を高める仕組みをご紹介します。
実践重視のプログラムで行動変容を促進
弊社の管理職研修は、理論のインプットだけでは終わりません。ケーススタディやロールプレイ、グループディスカッションを組み合わせることで実際の現場で活用できるスキルを身につけることができる構成になっています。
知識を「わかった」で終わらせることなく、「できる」「やってみる」へと繋げることで、確実に行動変容を促します。
課題に沿ったオーダーメイドカリキュラム
弊社では、企業ごとに異なる課題に対応できるよう、事前に人事ヒアリングや受講への個別面談、視察を行うことで現場を丁寧に把握します。その上でカリキュラム設計を行うため、「現場の実態に合わない研修」になることはありません。
受講者自身も納得感を持って学べるため、実務に活かしやすく最終的には課題を解決するアクションプランへ結びつきます。
研修後のフォローアップで学びを定着
研修は、「やって終わり」ではなく現場での実践と結びつける仕組みを整えています。
数回に分けて実施するプログラムでは、毎回の宿題や課題解決を通じて学びを定着化させます。そして、単発研修でもオプションとして受講者の個別フォローや人事担当者との連携を行い、学びを組織に根付かせています。
結果として、行動が続き成果につながることを後押ししています。
経営層・上司を巻き込む組織風土の改善サポート
私たちのご提案する研修は、経営層や上司を巻き込む仕組みも特徴の一つです。
経営層インタビューやフィードバックを通じて、研修の学びを組織全体で共有し、変化を後押しします。
また、人事担当者と二人三脚で取り組み、管理職の成長を支える風土づくりをサポートします。
研修後の学びを個人にとどめず、組織文化の変革につなげることで、管理職研修の課題を乗り越えていきます。
管理職研修の課題に関するよくある質問(FAQ)
管理職研修の課題を乗り越えて組織変革へ
管理職研修は、組織の成長に欠かせません。しかし、効果測定の難しさや受講動機の低さなど、多くの課題があります。これらの課題を解決するためには、「設計」「実践」「フォロー」という体制で取り組むことが重要です。
ガイアシステムでは、実践型かつ定着支援型のプログラムを通じて、組織の成果につながる管理職研修を提供しています。自社の課題に合わせた研修をご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。
お客様の課題やカリキュラムに応じてお見積りパターンをご提案しています。
まずは気軽にご相談ください!
お電話でのお問い合わせ 0120-117-450
専任のコンサルタントが丁寧にご相談を受け付けます。
お気軽にご相談ください。