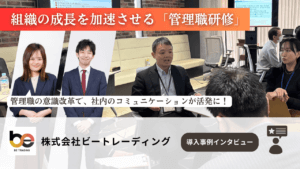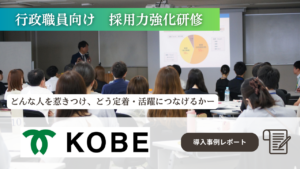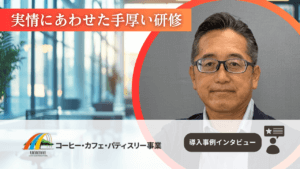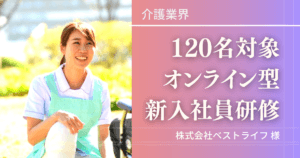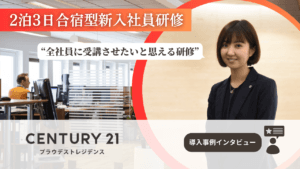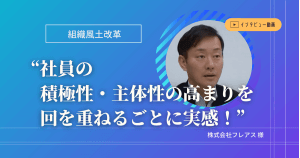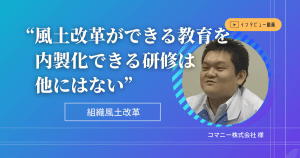学び合い、学び続け、お互いに高め合える組織へ|次世代リーダー育成研修を実施

株式会社花やしき様は、浅草を代表する老舗遊園地として、長年にわたり多くの来園者に「笑顔と感動」を届けてこられました。近年は、社員・アルバイトスタッフを含めた約180名体制となり、組織としての成長とともに「お客様対応の質」と「チームの力」をさらに高める取り組みを進められています。
その一環として、2022年度より、接客研修・次世代リーダー育成研修・評価者研修を継続的に実施。現場の主体性とリーダーシップを育む仕組みづくりに取り組まれています。今回は、こうした研修導入の背景や実施を通して見えてきた組織の変化について、同社の人事ご担当の方にお話を伺いました。
| 企業名 | 株式会社花やしき |
| 業種・業界 | サービス業/娯楽業/エンターテインメント業界/遊園地 |
| 従業員数 | 社員50名 スタッフ130名 |
| 実施内容 | ▶2022年度~2024年度 ・アルバイトスタッフの接客研修 4回 ・一期生 次世代リーダー育成研修 4回 ・二期生 次世代リーダー育成研修 6回 ・評価者研修 5回 |
| 受講者数 | 社員のべ約50名 スタッフのべ約100名 |
| 満足 | やや満足 | 普通 | やや不満 | 不満 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 研修全体の満足度 | 〇 | ||||
| カリキュラム・レクチャー内容 | 〇 | ||||
| 講師力(専門知識・説明のわかりやすさ・受講者対応) | 〇 | ||||
| 研修の内容や成果に対して、価格の適正さ | 〇 | ||||
| 研修前後のサポート体制 | 〇 | ||||
| 研修後の受講者の変化 | 〇 | ||||
| 営業時の研修提案の内容 | 〇 | ||||
| 連絡やフォローの頻度 | 〇 | ||||
| 契約内容や見積もりの分かりやすさ | 〇 |
ガイアシステムを選んだ理由
一番の決め手は「事前のヒアリングの丁寧さ」でした。
他社も検討しましたが、貴社は特に細かくヒアリングを行い、その内容をもとにフルオーダーメイドで研修を提案してくださいました。正直、「こんなに細かく聞くの?」と思うほど徹底的でしたが(笑)、実際の提案を見て納得しました。細やかなヒアリングがあったからこそ、現場に即した研修が実現したのだと感じています。
「株式会社花やしき」の社風について
「人を笑顔にするのが好きな会社」だと思います。
接客業でありエンタメ業界の企業として、「人を喜ばせたい」「楽しんでもらいたい」という想いを持つ人が集まっています。特別な制度や取り組みがあるわけではありませんが、職場環境そのものが社風を育んでいると感じます。
特に、職場が遊園地という特殊な環境であることが大きな特徴です。園内で働く人も、オフィス勤務の人も、すぐ近くに遊園地があり、気軽に立ち寄ることができます。お客様の笑顔や楽しむ姿を見ることで、自分たちの仕事の意義を実感し、それが日々の活力に繋がっていると感じます。


次世代リーダー育成研修の導入目的
1、管理職が「次期管理職を育成する」組織の確立
現在、兼務等で埋めている管理職のポストがあり、更に5年後・10年後を見据えると複数のポストが空く可能性があります。そのため、社内で優秀な人材を育成し、いつでも昇進が可能な体制を整えることが、組織の健全な成長につながると考えています。
そこで、管理職が「次期管理職を育成できる組織づくり」を推進し、その仕組みを確立することを目指しています。
今回の研修では、学び合い・学び続ける文化を醸成し、「部下育成」に重点を置いたプログラムを依頼しました。
また、マネージャー層の下にいる次世代リーダーの成長を支援し、将来的に管理職ポストが空いた際に、社内から昇進できる体制を整えることも重要な目的の一つです。
2、時代の変化に適応した「マネジメントスキル」の習得
管理職の役割は年々複雑化しており、適切な教育支援が必要だと考えています。単なる業務管理だけでなく、マネジメントやプレイヤーとしての役割も求められるため、多角的なスキルの習得が欠かせません。
特に、リーダーシップの在り方も変化しています。従来のトップダウン型だけでなく、状況に応じた柔軟なスタイルが求められる時代です。そのため、座学での知識習得にとどまらず、実践を通じてスキルを身につけることを重視したいと考えています。
3、体系的な教育体制の確立
正直なところ、研修導入前は、現場社員に「部下育成・教育」を任せきりにしている状況でした。
過去にも研修が全くなかったわけではありませんが、単発の研修が中心で、継続的な学びにつながりにくい課題がありました。
単発研修にもメリットはありますが、体系的な教育体制が整っていないことで、育成の質や効果にばらつきが生じていたと感じ、課題意識を持っていました。


研修導入で目指す―「理想の組織」とは
目指すのは、「学び合い、学び続け、お互いに高め合える組織」です。
外部研修も有効ですが、基本的には社内で継続的に学べる環境が理想的だと考えています。
そのうえで、新たな視点が必要なときに外部の力を借りるのが、最も健全な形だと思います。
研修後、学習意欲の高い社員が少しずつ増え、個人的に学ぶ努力をしている姿も見られるようになりました。
ただ、それを「組織全体で共有する仕組み」はまだ十分に整っていません。
例えば、研修受講者が主体となり、社内勉強会や研修を定期開催できるようになれば理想的ですが、昨年は実施回数が限られていました。今年度は少し増えたものの、今後さらに活発化していくことが望ましいと考えています。
現時点での達成度は、理想の50%程度といったところです。
研修前と比較すると、変化はありましたか?
そうですね。
以前は、自発的に学びの場を作る取り組みはほとんどありませんでした。
まだ開催回数は少なく、「学びの文化」をさらに深めていく必要はありますが、「学び合う空気感」が少しずつ醸成され、実際に勉強会が年に数回でも実施されたことは、大きな変化だと感じています。

講師からのコメント
貴社が目指す、学びの文化を定着させることは、社員一人一人の成長を促し、組織全体の活力にもつながります。
社員同士が互いに知識を共有し、学び合う環境が整えば、変化に柔軟に対応できる力が養われます。今後もその文化を育むためのサポートを全力で行いますので、共に前進していきたいです!
研修導入の「効果」と「受講者の変化」
各研修は、非常に満足度の高いものだったと感じています。
一般的な研修は、企業の業態や現場における具体的な課題問わず同じ内容になるパッケージ型が多いですが、
今回はフルオーダーメイドで作成していただきました。
その結果、現場の方々も真剣に取り組むことができ、満足度の高い研修となりました。
満足度につながったポイント
研修の満足度が高かった理由として、以下の点が挙げられます。
- ワーク中心の構成
弊社の意向を汲み、研修内でワークの時間を多く取っていただいたことで、
受講者が主体的に学ぶ機会が増えました。 - 現場に即した内容
単なるインプットではなく、「現場ではこういう課題がある。では、どう対応すればいいか?」と、
実践に直結する具体的な話をしていただいたことが効果的でした。 - 受講者に寄り添う講師のアプローチ
講師の田近先生が、受講者一人ひとりの特徴をしっかり捉え、
受講者の状況に合わせてアプローチを変えていたことも大きな要因です。
個々に寄り添った指導が、より実践的な学びにつながりました。
講師が「受講者に合わせてアプローチを変えた」とは?
例えば、今期の次世代リーダー育成研修の2期生の中には、研修に対して前向きではなく、やる気が感じられない方がいました。
その方に対し、無理に負荷をかけるのではなく、適度なアプローチで徐々に引き出していく形で対応されていました。その結果、研修への姿勢が変わり、やるべきことにしっかり取り組めるようになったと感じています。
また、講師の働きかけは研修時間内にとどまらず、休憩中にも積極的にコミュニケーションを取ってくださっていました。このような丁寧な関わりが、受講者の意識の変化につながったのではないかと思います。
研修後の受講者の変化
研修後、受講者に明らかな変化が見られました。
例えば、アウトプットや周囲とのコミュニケーションが円滑になった社員や、意見やフィードバックの角度や深度が向上した社員がいます。
例えば、もともと物事をしっかり考え、発言も的確だった社員がいましたが、課題に対するアウトプットの質が低く、1行や2行で終わることが多かったです。研修を通じて、課題の意図をしっかり理解し、質の高い回答を出せるようになりました。また、コミュニケーション面でも改善が見られたと感じています。
さらに、研修で得た学びを現場で活かしているという声や、「考え方が以前とは変わった」といった参加者の声もあり、研修が実践に結びついていることが感じられました。


研修を通して、受講者が抱えていた「困りごと」は解消しましたか?
正直なところ…
研修前は、育成に関して「困っている」という認識自体が薄かったと思います。特に、受講者は「自分たちが育成を担う役割がある」とは認識していなかったようです。
研修を通じて、「自分たちが次世代のリーダーを育成するんだ」という意識が芽生えたことは大きな変化です。
この意識の変化が、勉強会などの主体的なアクションにつながっています。
ただし、まだ十分ではないと感じている部分もありますが、受講者自身が動き始めたことは大きな一歩だと思います。

講師からのコメント
研修を通じて、受講者のみなさんが「課題」に対するアプローチを深め、アウトプットの質が向上したことを嬉しく思いっています。
コミュニケーションスキルもより向上され、学びを実践に活かしている姿勢に非常に満足しています。引き続き、成長をサポートできるよう努めていきます。
研修カリキュラムを組む際、要望したこと
次世代リーダー育成研修を2年間にわたり実施する中で、1期と2期では受講者の経験値に違いがあったため、それに応じた内容の調整をお願いしました。
1期の受講者は既にマネジメント経験が豊富で、講義内容を実体験に照らし合わせて実務に活かしやすいと感じていました。
一方、2期の受講者はマネジメント経験が少なく、座学だけでは実践に結びつけるのが難しいと考えたため、グループワークを多く取り入れ、実践的な学びの機会を増やしました。
また、研修の間隔が1ヶ月ほど空くこともあったので、その間に参加者が「スタッフ向けの自主研修」を企画する機会を設け、研修に合わせて「プレゼンテーションスキル」や「トレーナートレーニング」など、現場ですぐに活かせる内容をカリキュラムに追加し、重点的に教えていただきました。
「自主研修後」に、行った取り組み
「自主研修/勉強会」を運営した方に対し、研修後に振り返りの時間を設け、フィードバックを受ける機会を作りました。この時間を通じて、学びを深めることができました。
また、ガイアシステムの研修の場では、研修を実施する際に困ったことなどを講師に相談し、「部下とどのように関わっていくか?」といったテーマで話し合う場を設けました。このようなディスカッションを通じて、実務に即したアドバイスを受けられる機会を提供しました。
今後の課題とご要望について
研修自体にはとても満足しています。
今後のテーマとして「自分たちで学ぶ習慣をつくること」 という点が、今後の課題としてあると感じています。
実際に上長からも、より自己啓発(自己学習)を促進するよう求められています。
そのため、今後は「学びの習慣」を社内の仕組みとしてどう確立するかが重要だと思っています。
研修の最後に、「書籍の紹介」をお願いしたこともありましたが、そういったことに留まらず、「学びを習慣化し、実務に活かせる仕組み」をどう作るかが鍵になると考えています。
研修を通じて「アウトプットの仕方」を学んだので、それをさらに社内の仕組みとして定着させる方法についてアドバイスやサポートをいただけると嬉しいです。
また、次世代リーダーが実施する「学び合う場(勉強会)」は、研修内容や業務課題をディスカッションしながら解決する場として機能していますが、これに加えて「研修以外のインプットを増やす」ことが必要だと感じています。具体的には、「自分たちで知識を取りに行く力」をつけることが次のステップとして必要だと思っています。
管理職研修・カリキュラムのご紹介(一部)
| テーマ | 詳細 | |
|---|---|---|
| 第1回 | マインドセット基本行動 | ・スタートアップ、マインドセット、リーダーとしての心構え ・凡事徹底とは、基本行動の重要性 ・リーダーとしての自己分析、印象マネジメントの重要性 |
| 第2回 | 信頼構築 コミュニケーション 目標策定力と進捗管理 | ・信頼関係を築くコミュニケーションの基礎基本、関係性構築の法則 ・目的と目標の違い、リーダーがつくるべき目標とその作り方 ・会社→部→個人への落とし込み方法、ロジックツリーの使いどころ ・目標設定を通して部下を育成する手法、目標管理2つの手法 |
| 第3回 | 人材育成力面談 部下を育てるジョブアサイン | ・面談は部下育成の要、基本的な面談の目的と実施方法の整理 ・コーチングとティーチングの使い分け ・育成における「指導」と「方向付け」の重要度、改善行動の価値 ・現在のアサイン状況分析、アサイン時に重要な4つの視点 ・部下育成に効果的なアサイン方法 |
| 第4回 | イノベーションと組織実践 トレーナートレーニング | ・改善行動の価値、求められるイノベーション力とは ・成果を出すために必要な課題解決PDCAメソッドと場作り方法 ・組織的実践力3つの手順 ・自発性、自主性を育むファシリテーションスキル |
| 第5回 | セルフマネジメント | ・これまでの実施状況から強化すべきカリキュラムのピックアップ ・部下をマネジメントする前に自身をマネジメントする ・組織におけるメンタルヘルスへの取り組み ・お客様満足度を高めるトレーナートレーニング |
| 第6回 | 総合 プレゼンテーション | ・役員と部下の心を動かすプレゼンスキル ・チームマネジメントの総合政策発表 ・発表に対するフィードバック ・これまでの受け取り直しと今後の現場への落とし込みについて |

講師からのコメント
学びの習慣化や仕組みづくりについて一緒に考え、サポートさせていただけることを楽しみにしています。自己学習の促進は、企業の成長にとって非常に重要な要素ですし、持続的に学び続ける文化を作り上げることは、次世代リーダーの育成にも直結します。
まずは「学び合い」の場をさらに充実させ、受講者自身が自分の成長に責任を持つ意識を高めることが一つの鍵です。また、定期的な振り返りやフィードバックの機会を設けることで、学びが定着しやすくなると考えています。
日常的に「自ら学び・知識を習得する力」を組織全体で広げていけるよう、引き続きサポートさせていただきたいです。
花やしきで働く皆さんは、人を笑顔にしたい、誰かの役に立ちたいという利他の精神が高い方が多くいらっしゃいました。研修時には、気持ちよく元気をもらえる「挨拶」をしていただき、相手が話しやすい空気を作るための「リアクション」も、素晴らしいレベルで行われていました。これはまさに「愛情軸」で、人と関われる気配りや心配りだと感じています。
ビジネススキルも高く、経験値もあるのに謙虚。成長意欲が高く、前向きに挑戦をされている姿勢には、私自身が刺激を受けました。
170年の歴史ある花やしき様。東京の浅草という土地にあるからこそ、たくさんの人が集まり、そして出会った皆さんが「ワクワク」し、かけがえのない思い出となり、笑顔になって帰る―。そんな遊園地を創りたいと奮闘される皆さんのお力になれたらと心より願っております。