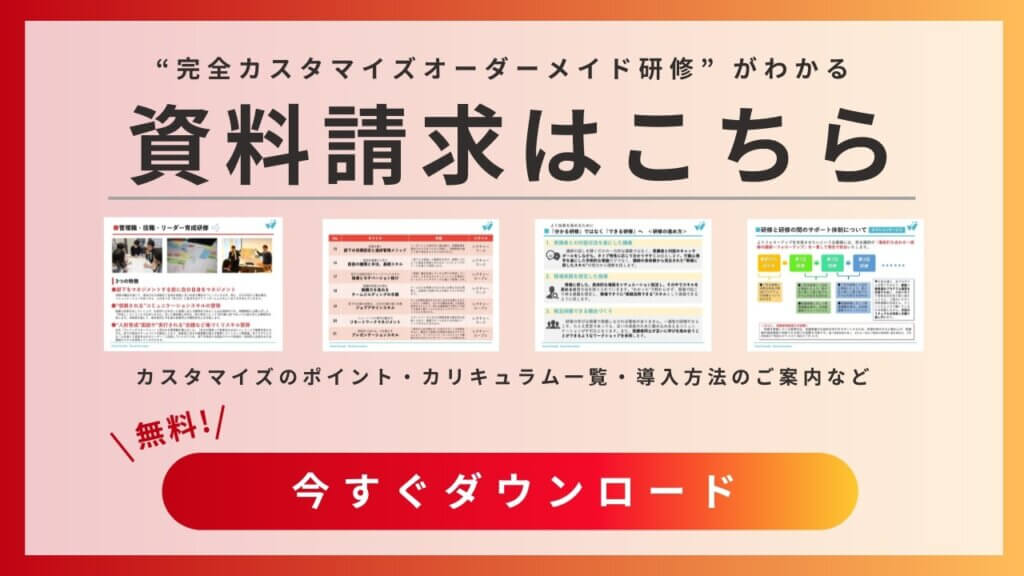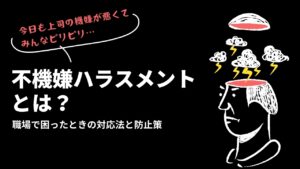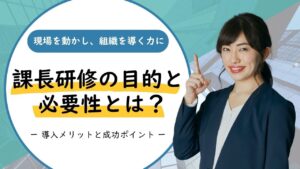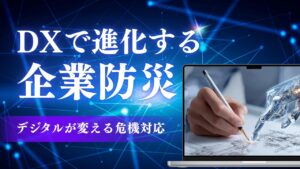不機嫌ハラスメントとは? 職場で困ったときの対応法と防止策
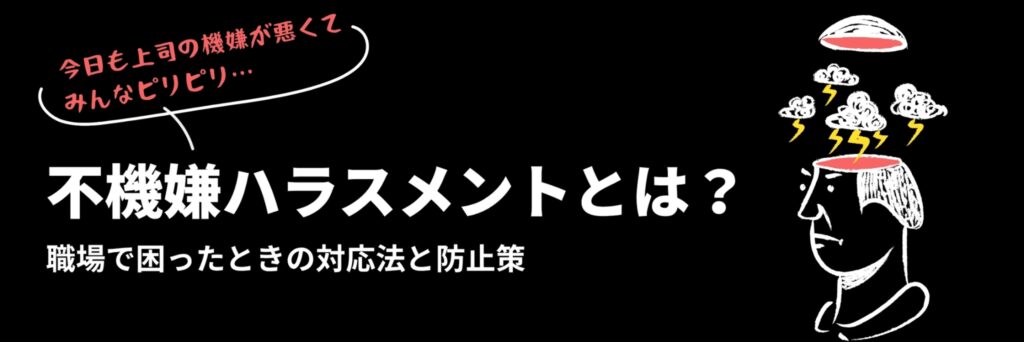
「今日も課長の機嫌が悪くて、みんなピリピリしている」「あの人がいるだけで職場の空気が重くなる」そんな経験はありませんか?「不機嫌ハラスメント」は目に見えにくいながら、心理的圧力や職場環境の悪化を招く深刻な問題です。
本記事では、不機嫌ハラスメントの特徴・兆候・事例・対応策から、組織での防止策までを詳しく解説します。

研修や制度導入による解決策も紹介しています。職場改善を検討している方にも参考にしていただきたい内容です。
不機嫌ハラスメントとは?
不機嫌ハラスメント(通称:フキハラ)とは、個人の機嫌の悪さを職場で露骨に表現し、周囲の人に不快感や恐怖感を与える行為のこと。直接的な暴言や暴力ではないものの、その影響は決して軽視できません。
よくある例:
- 会議中のため息や沈黙
- 気分次第で態度が変わる
- 無視や孤立化を誘う
こうした行動は直接的な言葉や命令ではなく「態度」や「雰囲気」によって心理的負荷をかけるため、被害者や周囲が気づきにくい点が特徴です。
職場の不機嫌ハラスメントは、なぜ問題なのか?
不機嫌ハラスメントは職場全体に深刻な影響を与えます。
- 職場環境の悪化:緊張感や不安が広がり、コミュニケーションが減少
- メンタル不調:ストレスやうつ症状、睡眠障害のリスク増加
- 離職リスク:働き続けられず早期離職に繋がる
不機嫌ハラスメントと他のハラスメントとの違い
- パワハラとの違い
パワハラは「大声で叱る」「無理な命令をする」など、言葉や行動がはっきりしているのが特徴です。
一方、不機嫌ハラスメントはため息・沈黙・冷たい態度など“雰囲気”で圧力をかける点が異なります。 - セクハラとの違い
セクハラは性的な言動が中心ですが、不機嫌ハラスメントは感情の揺れや機嫌の悪さによって周囲に心理的負担を与えます。 - 不機嫌ハラスメント特有の特徴
本人が「嫌がらせをしてやろう」と意図していなくても、不機嫌な態度そのものが周囲を萎縮させてしまうことが多く、気づかれにくいのが大きなポイントです。

この違いを理解しておくと、「これはパワハラなのか?それとも不機嫌ハラスメントなのか?」と迷ったときの判断基準になります。
職場の不機嫌ハラスメント 具体的事例(ケーススタディ)
職場で見えにくい不機嫌ハラスメントは、些細な態度や雰囲気でも、チーム全体に大きな影響を与えます。
以下は典型的なケースです。
- 事例①:会議でのため息と沈黙
-

ある上司は、部下の発言のたびに深いため息をつき、反応を示しませんでした。
直接否定はしていないものの、部下は「自分の意見には価値がないのか」と感じ、発言を控えるように…。
結果として、チームの議論が停滞し、イノベーションの機会を失うことになりました。 - 事例②:無視による孤立
-

あるチームで、新入社員が分からないことを質問しても、先輩社員が返答を避けたり、無視する態度をとったことがありました。
質問できない雰囲気が広がり、新入社員は必要な情報を得られず孤立感を抱いてしまいます。
結果として、半年以内に退職してしまい、チーム全体の業務効率にも影響が出ました。 - 事例③:気分次第で態度を変える上司
-

普段は穏やかですが、気分が悪いと部下を無視したり怒鳴ったりする上司。
部下は「今日は大丈夫だろうか」と常に顔色をうかがい、業務に集中できなくなります。
結果、過剰なストレスで休職者が出るケースもありました。
これらの行為は、法律違反とは限りません。しかし、職場の心理的安全性を損ない、社員の定着や生産性に大きなリスクをもたらす重大な問題です。
不機嫌ハラスメントチェックリスト・見極め基準
兆候やサインを知ることで、早期に対応可能です。
早期発見チェックポイント
不機嫌ハラスメントは、はじめは小さなサインとして現れます。次のような兆候が職場に見られたら注意が必要です。
- 会議で発言者が減っている、議論が停滞している
- 質問や報告がしにくい空気がある
- 一部の社員が孤立している
- 指示が不明確・一貫性がない
- 部下が常に上司や同僚の顔色をうかがっている
- 業務へのモチベーションが下がっている
これらが複数当てはまる場合、職場に「不機嫌ハラスメント」が存在している可能性が高まります。「ただの一時的な不機嫌」と「ハラスメント」の境界は曖昧ですが、判断のポイントは頻度・継続性・影響範囲 にあります。
不機嫌ハラスメント チェックリスト
さらに具体的に職場の状態を確認するために、以下のチェックリストを活用してください。
- 特定の人物が不機嫌な態度を繰り返している
- 周囲が委縮し、声をかけにくい空気になっている
- 会議や日常業務で発言が減っている
- 新入社員や若手が早期退職している
- 不機嫌な人の前では社員が緊張して萎縮する
- 職場全体の雰囲気が常に重い
- メール・チャットで返答をしない、無視する行為がある
3つ以上当てはまる場合は、不機嫌ハラスメントが組織に定着しているサインです。
早期に対応することが、職場環境の悪化を防ぐ第一歩になります。
職場での不機嫌ハラスメントを見極める方法
| 場面 | 具体的な振る舞い(加害側) | 被害者に起きる心理的変化 |
|---|---|---|
| 会議・打ち合わせ | ため息や長い沈黙が多い | 萎縮して発言できなくなる |
| 日常のやり取り | 冷たい態度や無視をする | 自己否定感が強まる |
| 業務指示 | 気分次第で評価や指示が変わる | 集中力低下・体調不良が増える |
不機嫌ハラスメントを受けたときの初期対応
不機嫌ハラスメントは、目に見えにくく「自分が敏感すぎるのでは?」と感じやすい問題です。
しかし、放置すれば職場全体に悪影響が広がり、改善が難しくなります。大切なのは、早めに声をあげ、改善のきっかけをつくることです。ここでは、個人が取れる初期対応を整理します。
感情的に「嫌だった」「怖かった」と伝えると、相手に軽視されてしまうことがあります。
そのため、日付・場面・具体的な行動を客観的に伝えることが重要です。
例:「○月○日の会議中に、発言するたびに深いため息をつかれ、発言を続けられなかった」
このように整理すれば、感情論ではなく事実として共有でき、周囲も対応を検討しやすくなります。
「言った・言わない」のトラブルを避けるため、証拠を残すことが欠かせません。
- 日付・状況・相手の態度をメモする
- メールやチャットの履歴を保存する
- 会議の議事録などに記録を反映させる
後から人事や外部機関に相談するときにも、客観的な材料として役立ちます。
不機嫌ハラスメントは、想像以上に心身へ負担を与えます。早めにサポートを活用しましょう。
- 社内の産業医やカウンセリング窓口
- 外部のEAP(従業員支援プログラム)
- 医療機関での相談
「休むことも対応の一つ」と考えることが大切です。
多くの企業には、ハラスメント相談窓口や人事部があります。
- 匿名で相談できる仕組みがある場合は活用
- 信頼できる上司や人事担当者へ報告
- 外部機関(労働局、労働組合など)へ相談する選択肢もある
「一人で抱え込まない」ことが最も大切です。
相談フローの例
- 事実を記録する
- 社内の相談窓口へ報告する
- 必要に応じて人事・外部機関へ相談する
- 状況に応じて、職場改善策や研修導入を検討してもらう

初期対応のゴールは、「個人が我慢する」ことではなく、「職場全体で改善につなげる」ことです。
不機嫌ハラスメントが及ぼす職場への影響
不機嫌ハラスメントは、単なる「個人の機嫌の問題」にとどまりません。
職場全体に悪影響を及ぼし、業績や人材定着にも深刻なリスクをもたらします。ここでは、その主な影響を整理します。
職場の雰囲気悪化と萎縮
不機嫌な態度が繰り返されると、チーム全体が萎縮し、自由に意見を言えない雰囲気が生まれます。
会議で発言が減り、コミュニケーションが停滞することで、建設的な議論や新しいアイデアが出にくくなります。
生産性・チームワークの低下
社員が常に上司や同僚の機嫌をうかがうようになると、本来の業務に集中できません。
心理的負荷によって判断力や集中力が下がり、協力体制も崩れるため、業務効率や成果に直結して悪影響を与えます。
メンタル・健康面への影響
不機嫌ハラスメントを受けると、ストレスが積み重なり、うつ症状や不安障害、睡眠障害などのメンタル不調を引き起こすリスクがあります。
実際に、医療機関やカウンセリングの利用が増えるケースも少なくありません。
早期離職・退職の増加
不快な雰囲気の中で長く働き続けることは困難です。結果として、優秀な人材が早期離職し、組織の安定性や成長が損なわれるリスクが高まります。
「辞めるのは新人だけ」ではなく、中堅やベテラン社員の流出にもつながる点が見逃せません。

不機嫌ハラスメントは 「見えにくいのに、職場全体をむしばむ深刻な問題」 です。
早期発見と組織的な対策を怠れば、生産性や人材確保に大きなダメージを与える可能性があります。
職場での不機嫌ハラスメント防止策
不機嫌ハラスメントは「個人の気分の問題」ではなく、組織文化や職場環境の課題としてとらえる必要があります。
ここでは、企業が取り組むべき具体的な防止策をご紹介します。
コミュニケーション改善
- 定期的な1on1やチームミーティングを行い、社員の気持ちや状況を吸い上げる
- 感情ではなく 事実に基づいたフィードバック を徹底する
- 心理的安全性を高め、誰もが意見を言いやすい職場環境をつくる

管理職研修での感情マネジメント
- 管理職が「自分の不機嫌が周囲に与える影響」を正しく理解する
- 怒りや苛立ちをコントロールする方法を習得する
- 部下とのコミュニケーションを円滑にするスキルを学ぶ
ハラスメント研修の導入
- 「不機嫌もハラスメントになり得る」という認識を全社員に浸透させる
- ケーススタディを通じて、リアルな状況を疑似体験しながら理解を深める
- 職場全体で「見えにくいハラスメントを防ぐ意識」を育む
職場環境改善の工夫
- ポジティブフィードバックを日常的に取り入れる
- 感謝や声かけを習慣化し、チームの雰囲気を明るく保つ
- メンタルヘルス相談窓口の整備や、仕事量・休憩の調整によるストレス軽減を進める

ガイアシステムでは、 不機嫌ハラスメントを含むハラスメント防止研修 を実施しています。
管理職の感情マネジメントや社員同士の健全なコミュニケーションをテーマにしたカリキュラムをご用意し、実際のケーススタディを交えながら「明日から使えるスキル」として定着させる内容です。
お客様の課題やカリキュラムに応じてお見積りパターンをご提案しています。
まずは気軽にご相談ください!
お電話でのお問い合わせ 0120-117-450
専任のコンサルタントが丁寧にご相談を受け付けます。
お気軽にご相談ください。
企業の対応・体制・リスク
不機嫌ハラスメントは法律で明確に定義されているわけではありませんが、既存の労働関連法令や企業の安全配慮義務の枠組みに含まれる問題です。企業は放置すれば法的・社会的なリスクを負うことになります。
関連法令
- 労働施策総合推進法(パワハラ防止法)
企業には、ハラスメント防止措置を講じる義務があります。 - 労働安全衛生法
従業員の安全と健康を守る「安全配慮義務」が課されています。 - 労働基準法
過重労働や不適切な労働環境を放置すれば、違法状態になる可能性があります。
企業のコンプライアンス体制
法令を守るだけでなく、職場の健全性を高める仕組みづくりが必要です。
- 相談窓口の設置(匿名相談・外部窓口を含む)
- 定期的な研修・アンケートの実施
- 就業規則への明記:「不機嫌による威圧や無視もハラスメントに含む」と規定することで抑止効果を高める
- メンタルサポート体制(産業医、カウンセリングなどの整備)
放置した場合のリスク
不機嫌ハラスメントを軽視・放置すると、次のような深刻なリスクにつながります。
- 労働局からの是正指導・行政リスク
- 裁判・労災認定 など法的リスク
- 離職増加・採用難 による人的コストの増大
- 企業イメージの低下・ブランド毀損

企業に求められるのは「ハラスメントは起きない前提」ではなく、起きうるものとして制度を整え、予防と早期対応を徹底することです。
まとめ:職場の不機嫌ハラスメント対策
不機嫌ハラスメントは「見えにくいが深刻な職場課題」です。個人の忍耐に任せるだけでは、被害の拡大や社員の離職リスクを防ぐことはできません。早期対応と組織的な対策が重要です。
- 不機嫌ハラスメントは態度や雰囲気によって心理的圧力を与える
- 兆候やサインを理解し、早期発見に努める
- 記録を残し、社内相談窓口やメンタルサポートを活用する
- 組織として研修や職場環境改善策を導入する
企業が研修や制度整備に取り組むことで、職場の空気を健全に保ち、社員の定着率や生産性向上にもつながります。不機嫌ハラスメント防止の研修や相談窓口の導入は、専門コンサルティングに相談することも有効です。
「職場での不機嫌ハラスメントを防ぐために、管理職向けの感情マネジメント研修や全社員向けハラスメント研修を検討したい」という企業様は、ぜひ当社にご相談ください。
実践的な研修プログラムで、心理的安全性の高い職場づくりをサポートします。