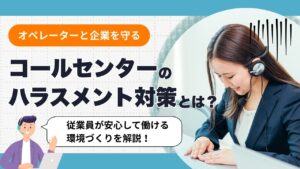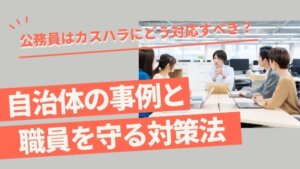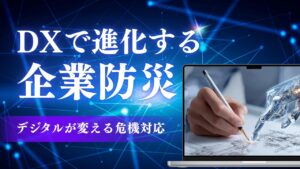コールセンターのハラスメント対策とは?オペレーターと企業を守る方法を解説
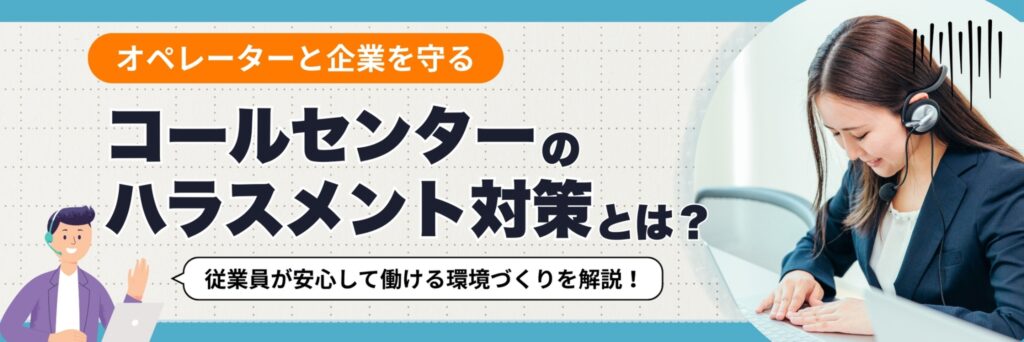
近年、顧客からの過剰な要求や理不尽な言動、いわゆる「カスタマーハラスメント」が社会問題となっています。特に、顧客と直接対話するコールセンターは、カスハラの最前線であり、オペレーターの心身に大きな負担がかかっています。企業にとって、従業員を守り、健全な職場環境を維持することは、もはや避けては通れない重要な経営課題です。

本記事では、コールセンターにおけるハラスメントの実態から、オペレーター個人と企業それぞれが取るべき具体的な対策までを詳しく解説します。
コールセンターを悩ませるカスタマーハラスメントとは

顧客からの厳しいご意見は、サービス改善の貴重なきっかけとなる一方、その一線を越えた言動は従業員を深く傷つけるハラスメントとなります。まず、その定義と具体例を正しく理解することが対策の第一歩です。
カスハラとクレームの違いについてはこちらの記事をご確認ください。
コールセンターへのカスハラが増える背景
なぜ、コールセンターでカスタマーハラスメントは増加傾向にあるのでしょうか。その背景には、現代社会やコールセンター特有の環境が複雑に絡み合っています。
まず、電話越しの非対面コミュニケーションは、顔が見えない安心感から顧客の言動を攻撃的にさせやすい側面があります。また、インターネットやSNSの普及も大きな要因です。消費者の権利意識が過剰になり理不尽な要求に繋がったり、「SNSに悪評を書き込む」といった脅し文句が新たな手口として生まれたりしています。
加えて、経済的な不安など社会全体のストレスが増大し、そのはけ口がオペレーターに向けられるケースも少なくありません。これらの要因が重なり、ハラスメントは従業員の安全を脅かす深刻な課題となっているのです。
コールセンターで発生しやすいハラスメントの具体例
一つは、実店舗の減少で顧客との接点がコールセンターに集中し、問い合わせの母数が増えている点です。顔が見えない非対面でのコミュニケーションは、顧客の言動をエスカレートさせやすい側面があります。
また、インターネットの普及で消費者の権利意識が変化し、「お客様は神様だ」といった考えのもと、理不尽な要求を正当化するケースも増えました。さらにSNSの普及により「悪評を書き込む」といった脅しが新たな手口として生まれるなど、ハラスメントは深刻な課題となっています。
カスタマーハラスメントがもたらす深刻な影響
カスタマーハラスメントを放置することは、オペレーター個人だけでなく、企業全体にも計り知れない損害をもたらします。その影響は、精神的な問題から組織運営のリスクにまで及びます。
オペレーターの心身を蝕む精神的ダメージ
ハラスメントの直接的な標的となるオペレーターは、深刻な精神的ダメージを受けます。
顧客からの暴言や理不尽な要求に日常的に晒されることで、過度なストレス状態に陥り、不眠や食欲不振、抑うつ症状といった心身の不調を引き起こすことがあります。
これにより、仕事へのモチベーションが著しく低下し、最悪の場合、休職や退職に追い込まれてしまうケースも少なくありません。
企業全体に広がる生産性低下と離職の増加
オペレーター個人の問題は、そのまま組織全体の問題へと直結します。
ハラスメント対応に多くの時間が割かれることで、他の顧客への対応が滞り、コールセンター全体の応答率や処理効率が低下します。また、従業員が疲弊し、安心して働けない職場環境では、離職率が高まることは避けられません。
優秀な人材の流出は、サービスの質の低下を招くだけでなく、新たな人材の採用や教育にかかるコストの増大にもつながり、企業の競争力を大きく損なう原因となります。
オペレーターが今すぐできるハラスメントの初期対応
ハラスメントに遭遇した際、オペレーター自身が冷静に対応することも重要です。
もちろん、最終的には組織的な対応が必要ですが、初期対応を知っておくことで、状況の悪化を防ぎ、自身の心を守ることにつながります。
- 冷静さを保ち相手の話を傾聴する
- できないことは毅然と断る勇気を持つ
- 一人で抱え込まず上司に助けを求める
冷静さを保ち相手の話を傾聴する
顧客が興奮している場合でも、まずは冷静に対応し、相手の言い分を遮らずに聴く姿勢が大切です。
感情的に反論するのではなく、まずは相手が何に怒り、何を求めているのかを正確に把握することに努めます。
共感の姿勢を示すことで、相手の興奮が和らぐこともあります。ただし、これは相手の不当な要求を受け入れることとは異なります。
できないことは毅然と断る勇気を持つ
相手の要求が、会社の規則や社会通念を逸脱している場合は、丁重かつ明確に「できかねます」と伝える勇気が必要です。「申し訳ございませんが、そのご要望にはお応えできません」とはっきりと伝えることで、相手に過度な期待を抱かせず、問題の長期化を防ぎます。

曖昧な態度は、さらなる要求を助長させる可能性があるため注意が必要です。
一人で抱え込まず上司に助けを求める
カスタマーハラスメントは、決して一人で対応すべき問題ではありません。
対応が困難だと感じたり、身の危険を感じるような発言を受けたりした場合は、躊躇なく上司やスーパーバイザーに対応を代わってもらうべきです。
エスカレーションはオペレーターの権利であり、自身の安全を確保するための最も重要な行動です。速やかに助けを求める体制が、組織全体で整備されていることが不可欠です。
従業員を守る組織体制の構築

カスハラへの対応は、組織的な取り組みと、明確な基準に基づく体制構築が不可欠です。
特にコールセンターでは、顔が見えない分、より巧妙で悪質なカスハラが発生しやすい環境にあります。
カスハラの対応フロー
カスハラへの対応フローは、「検知」「判断」「対応」「記録」の4段階で構築することが効果的です。
各段階で明確な基準を設けることで、オペレーターの負担を軽減し、適切な対応を可能にします。
検知段階
以下のような判断基準表を活用することで、カスハラの早期発見が可能になります。
| カテゴリー | 具体的な言動例 | 判断基準 |
|---|---|---|
| 威圧的言動 | 大声、怒鳴り声 | 通常の会話音量を著しく超える |
| 人格否定 | 侮辱的発言 | 業務内容と無関係な中傷 |
| 過剰要求 | 執拗な謝罪要求 | 3回以上の謝罪要求 |
判断段階
通話録音システムとAI音声解析を組み合わせた客観的な判定が有効です。
感情的な言葉や特定のキーワードを自動検知し、カスハラのリスク度を数値化することで、適切な対応レベルを選択できます。
対応体制の整備と権限の明確化
お客様対応における体制は、状況の重要度に応じて3段階に分類することが推奨されます。
- レベル1:担当者が通常の範囲で対応可能なケース
- レベル2:管理者の判断が必要なケース
- レベル3:専門部署や外部機関との連携が必要なケース
各レベルにおける判断・対応の権限範囲を明確に定め、現場での適切な判断を可能にする体制を整えることが重要です。特に、対応の中断判断や外部機関への相談基準などについて、具体的なガイドラインを設定する必要があります。
緊急時の対応ガイドラインと通報システム
緊急時の対応には、迅速性と正確性の両立が求められます。そのため、以下のような通報システムの導入が推奨されます。
緊急通報ボタンを通報システムに実装し、オペレーターが一触で上司や関係部署に通報できる仕組みを構築します。この際、通話内容や顧客情報が自動的に共有される仕組みにすることで、支援側の即時対応が可能になります。
また、カスハラ発生時の記録フォーマットを標準化し、以下の項目を必ず記録する体制を整えます。
| 記録項目 | 記録内容 |
|---|---|
| 発生日時 | カスハラ開始時刻と終了時刻 |
| カスハラ種別 | 威圧、暴言、脅迫等の分類 |
| 対応履歴 | 実施した対応策と結果 |
| 影響度 | オペレーターの心理状態評価 |
これらの記録は、法的対応の証拠として活用できるだけでなく、カスハラ予防のための分析データとしても重要な役割を果たします。
【無料】資料ダウンロード
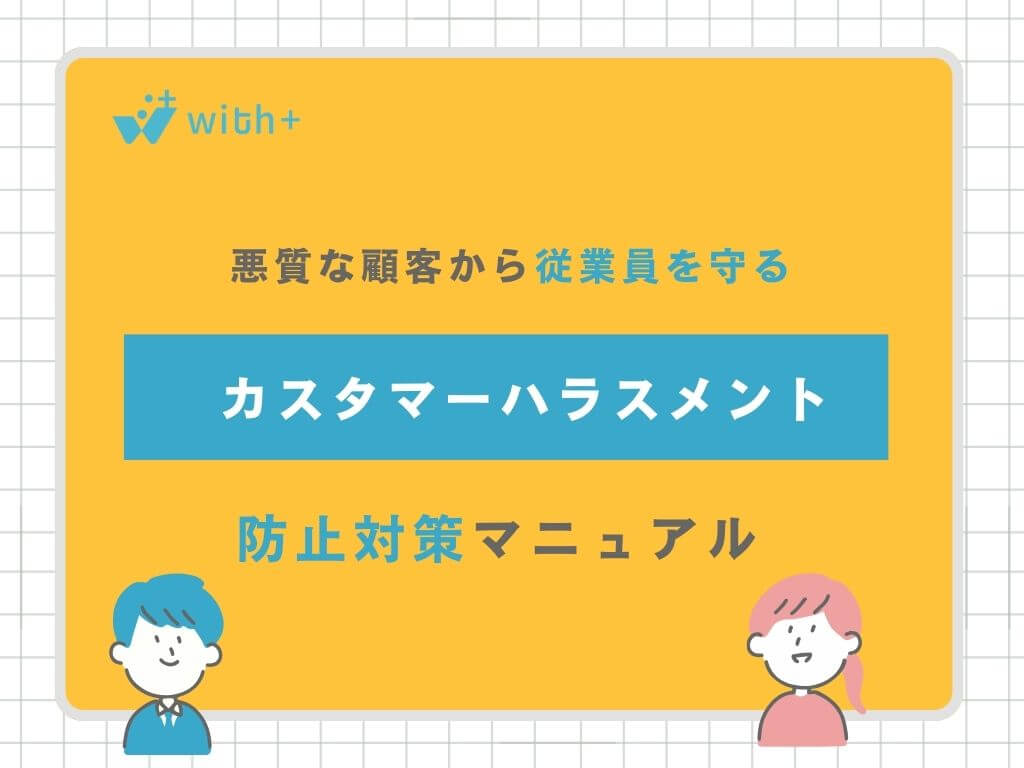
カスハラ防止対策マニュアル
従業員のに大きな負担を与える「カスハラ(カスタマーハラスメント)」本資料では、そもそもどういった行為がカスハラに該当するのか、
企業が取るべきカスタマーハラスメント対応の具体策
オペレーター個人の努力だけでは、カスタマーハラスメント問題の根本的な解決には至りません。
従業員が安心して働ける環境を構築するために、企業は組織として断固たる対策を講じる責任があります。
そこで、企業が講じるべきカスタマーハラスメントへの具体的な対策をご紹介します。
- 対応方針を明確にしたマニュアルを作成する
- ハラスメントを想定した実践的な研修を行う
- 従業員のための相談窓口を設置する
- オペレーターの精神的負担をケアする体制を整える
- 通話録音の実施と事前告知でハラスメントを牽制する
- 職場環境の整備
- リスクアセスメントと定期的な体制見直し
対応方針を明確にしたマニュアルを作成する
企業としてカスタマーハラスメントにどう向き合うか、その基本方針を明確に打ち出すことが第一です。
その上で、具体的な対応手順を定めたマニュアルを作成し、全従業員に周知徹底させます。「どのような行為をハラスメントと定義するか」「どのような場合にエスカレーションするか」「電話を切断できる基準は何か」といった点を具体的に定めることで、オペレーターは自信を持って毅然とした対応を取ることができます。
ハラスメントを想定した実践的な研修を行う
マニュアルを整備するだけでなく、実際のハラスメント場面を想定したロールプレイングなどの実践的な研修を定期的に実施することが極めて有効です。
研修を通じて、暴言への切り返し方や、冷静な対応を保つための心理的なトレーニングを行います。
これにより、オペレーターは不測の事態にも落ち着いて対処できるようになり、組織全体の対応品質の標準化にもつながります。
従業員のための相談窓口を設置する
ハラスメントを受けた従業員が、いつでも安心して相談できる専門の窓口を社内に設置することが重要です。産業カウンセラーや専門知識を持つ担当者を配置し、秘密厳守で相談に応じる体制を整えます。
これにより、従業員は問題を一人で抱え込むことなく、早期に精神的なサポートを受けることができます。相談窓口の存在は、会社が従業員を守るという明確なメッセージにもなります。
オペレーターの精神的負担をケアする体制を整える
ハラスメント対応後のメンタルケアも欠かせません。困難な対応を終えたオペレーターに対して、上司が労いの言葉をかけ、対応内容を肯定的に評価するだけでも、精神的な負担は大きく軽減されます。
また、定期的なストレスチェックの実施や、必要に応じて専門の医療機関と連携するなど、心身の健康を積極的にサポートする仕組みを構築することが求められます。
通話録音の実施と事前告知でハラスメントを牽制する
多くのコールセンターでは既に導入されていますが、通話の冒頭で「この通話は、応対品質の向上のため録音させていただいております」と自動音声でアナウンスすることは、ハラスメントの強力な抑止力となります。
録音されているという事実が、顧客の不適切な言動を未然に防ぐ効果が期待できます。
また、万が一、法的な対応が必要となった際には、録音データが客観的な証拠として極めて重要な役割を果たします。
職場環境の整備
カスハラはオペレーターの心理的負担を著しく増大させる要因となります。そのため、包括的なメンタルヘルスケア体制の構築が不可欠です。
具体的なメンタルヘルスケア施策として、以下の取り組みが推奨されます。
- 定期的なストレスチェックの実施と結果に基づく個別面談
- 産業医との連携による専門的なケア体制の確立
- ピアサポート制度の導入によるチーム内での相互支援
職場環境の整備においては、物理的な環境改善とともに、心理的安全性の確保が重要です。
カスハラを受けた際の休憩スペースの確保や、即座に上司に相談できる体制の構築などが含まれます。
また、定期的なローテーション制度を導入し、特定のオペレーターに負担が集中しないよう配慮することも効果的です。これにより、精神的な疲労の蓄積を防ぎ、長期的な就業継続を支援することができます。
リスクアセスメントと定期的な体制見直し
カスハラ対策の実効性を確保するためには、定期的なリスクアセスメントと体制の見直しが不可欠です。
リスクアセスメントでは、過去のカスハラ事例を分析し、発生パターンや対応上の課題を明確化します。
効果的なリスクアセスメントには、以下の要素が含まれます。
| 評価項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| カスハラ発生状況 | 時間帯、顧客属性、発生要因の分析 |
| 対応体制の適切性 | マニュアルの実効性、支援体制の機能度 |
| 研修効果の測定 | オペレーターのスキル向上度、対応力の評価 |
体制の見直しにおいては、現場のオペレーターからの意見聴取が重要です。実際の対応経験に基づく課題や改善提案を収集し、より実効性の高い対策へとつなげていきます。
定期的な見直しサイクルを確立し、PDCAサイクルに基づいた継続的な改善を行うことで、カスハラ対策の実効性を高めることができます。
悪質なハラスメントへの最終手段

社内での対策を尽くしてもなお、改善が見られない悪質なハラスメント行為に対しては、外部の専門家と連携し、より強固な対応を取る必要があります。
以下は、従業員と企業自身を守るための最終的な防衛策です。
- 弁護士に相談し法的なアドバイスを求める
- 脅迫や強要には警察への通報も検討する
弁護士に相談し法的なアドバイスを求める
度重なる嫌がらせや業務妨害、企業の信用を毀損するような言動に対しては、顧問弁護士などの法律専門家に相談することを検討すべきです。
弁護士に相談することで、企業の対応が法的に適切かどうかを確認できるだけでなく、相手方に対して警告書を送付するなど、具体的な法的措置を取ることが可能になります。専門家の介入は、問題の早期解決につながることが少なくありません。
脅迫や強要には警察への通報も検討する
「殺すぞ」といった生命や身体に対する危害を加える旨の告知や、「土下座しろ」といった義務のないことを強要する行為は、それぞれ脅迫罪や強要罪といった刑法に触れる犯罪行為です。
このような悪質なケースでは、ためらうことなく警察に相談し、通報することも重要な選択肢です。従業員の安全を最優先に考え、法的な保護を求める毅然とした姿勢が、他の悪質なハラスメント行為への牽制にもなります。
【無料】資料ダウンロード
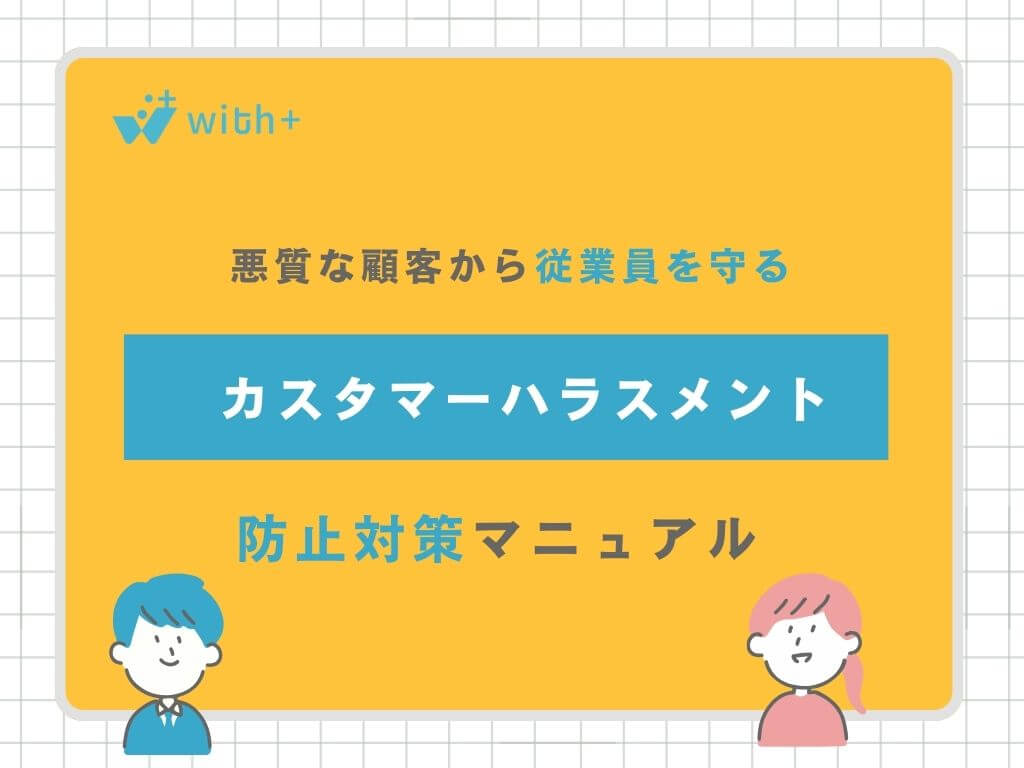
カスハラ防止対策マニュアル
従業員のに大きな負担を与える「カスハラ(カスタマーハラスメント)」本資料では、そもそもどういった行為がカスハラに該当するのか、
まとめ
コールセンターにおけるカスタマーハラスメントは、オペレーターの尊厳を傷つけ、企業の健全な運営を脅かす深刻な問題です。この問題に対処するには、オペレーター個人の努力に頼るのではなく、企業が組織として明確な方針を掲げ、マニュアル整備、研修、相談体制の構築といった具体的な対策を講じることが不可欠です。従業員が安心して働ける環境を作ることが、結果として顧客サービスの質の向上にもつながり、企業の持続的な成長を支える基盤となります。
コールセンターにおけるカスハラ対策の研修なら、ガイアシステムにお任せください。
ガイアシステムでは、現場や業界に応じたさまざまなハラスメント防止研修を実施しています。
貴社の特性や文化に合わせた特別なカリキュラムで、効果の高い研修を実施しております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
ハラスメント研修カリキュラム
従業員をクレーマーから守り、組織の対応力向上を目指す!
カスタマーハラスメント研修|対応力強化
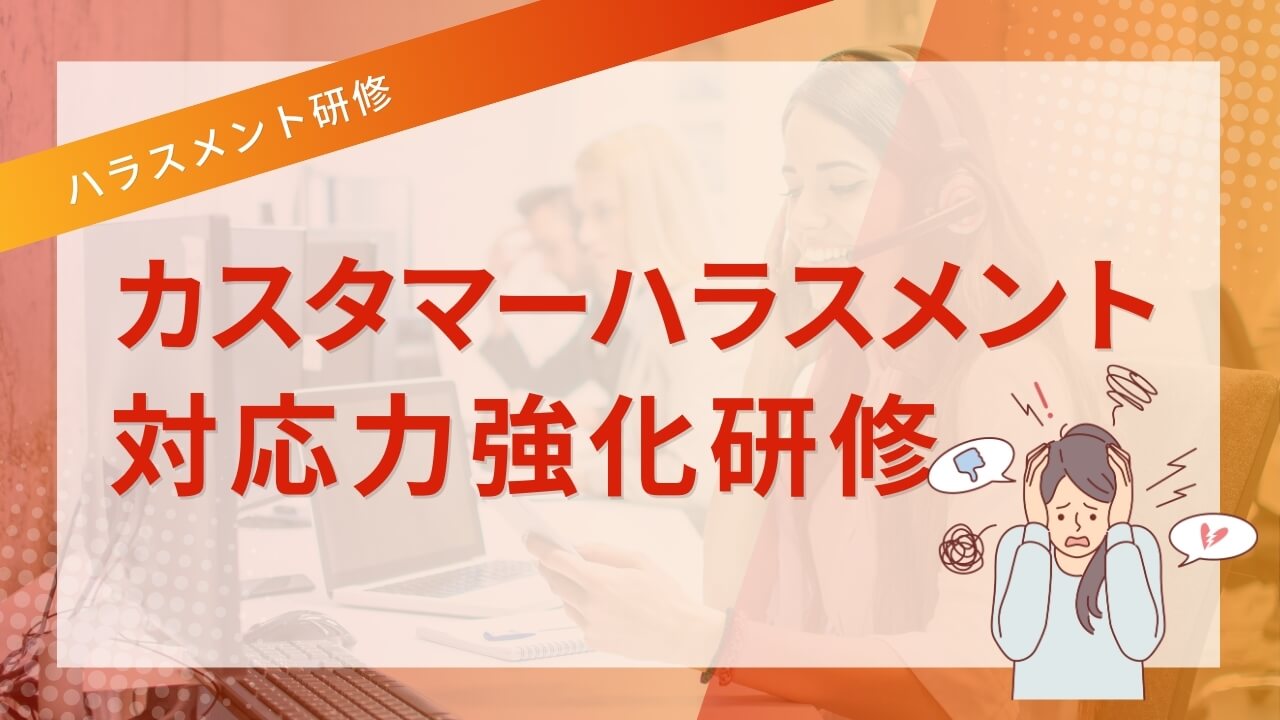
従業員に大きなストレスを与え、離職の原因にもなっているカスタマーハラスメント。個人の能力では解決できないケースも多く、組織が一体となってリスク回避することが必要です。
本研修はカスタマーハラスメントの理解と対応力を強化することを目的に、コミュニケーションスキルを学び、実践的なグループワークを通じて具体的な対策を考えます。
ハラスメントの未然防止、環境改善を目指す!
ハラスメント研修 |パワハラ防止対策
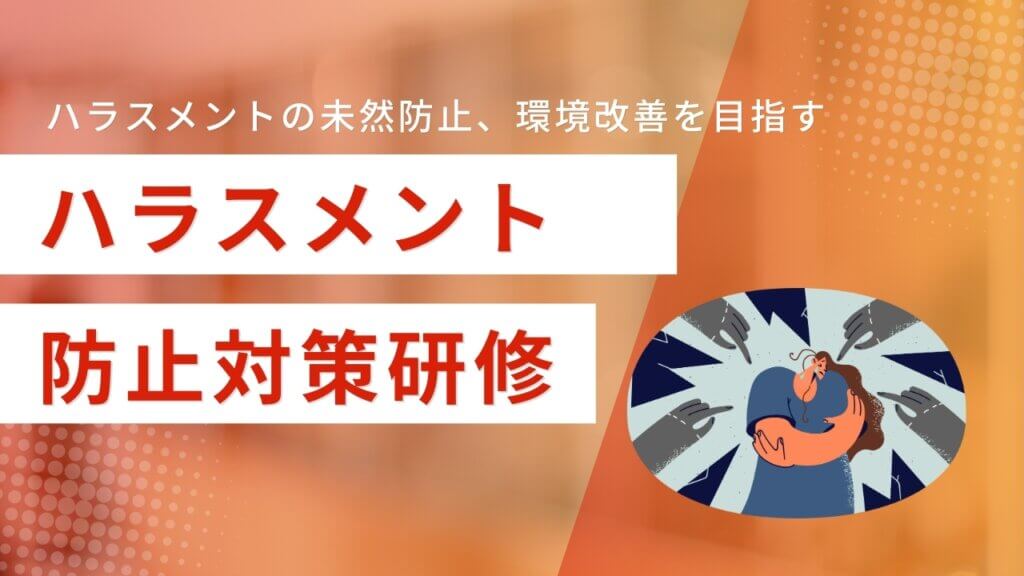
セクハラ、パワハラ、マタハラなど様々なハラスメントの定義や具体例、日常に潜むハラスメントリスクについて学びます。
「グレーゾーンと思われがちな事例紹介」やケーススタディを通じてハラスメントの識別方法を習得し、グループディスカッションで防止策を考案します。また、ハラスメントが起きた際の適切な対応方法や報告手順を身に着けます。
心のメンテナンス手法を習得
メンタルヘルス研修|ストレスと上手に向き合うには
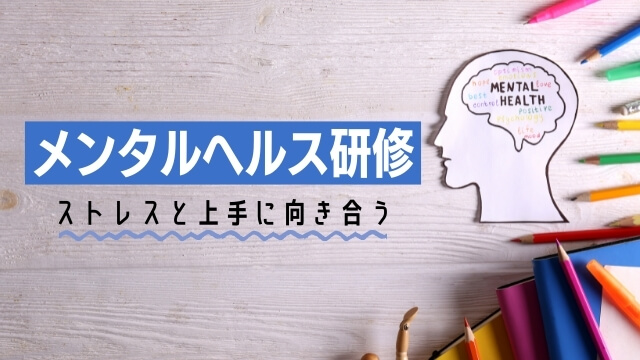
メンタルヘルスに対する知識を身につけ、自分の心の状態を確認し、自らに合ったメンテナンス手法を習得していきます。
・メンタルヘルス研修 全従業員対象 基礎編
・メンタルヘルス研修 役職対象 ラインケア編
・メンタルヘルス研修 全従業員対象 セルフケア編
上記を事例に、内容別・対象別に様々な研修カリキュラムを取り揃えております。
ハラスメントコラム一覧
-
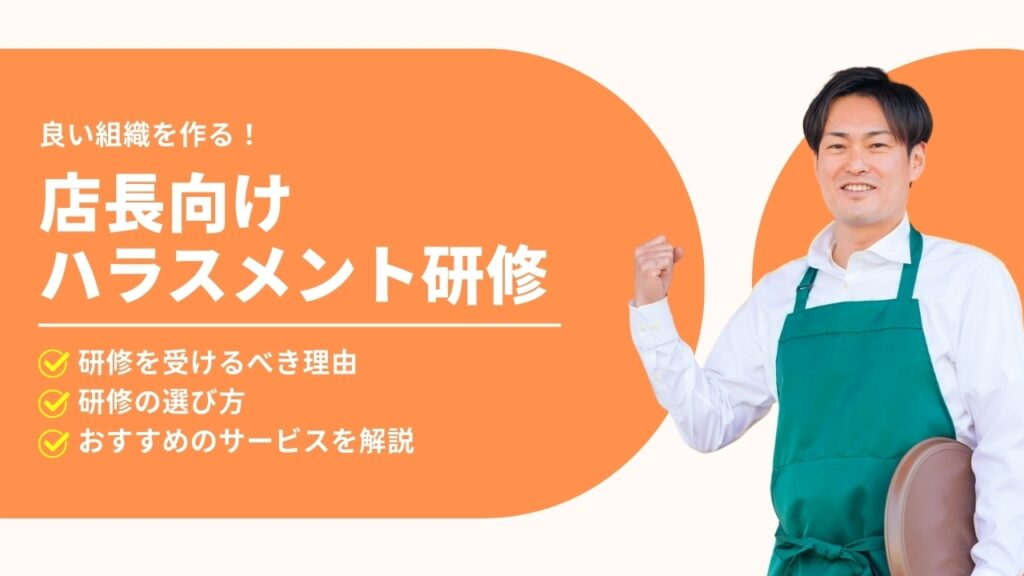
良い組織を作る!店長向けハラスメント研修のポイントを解説
-
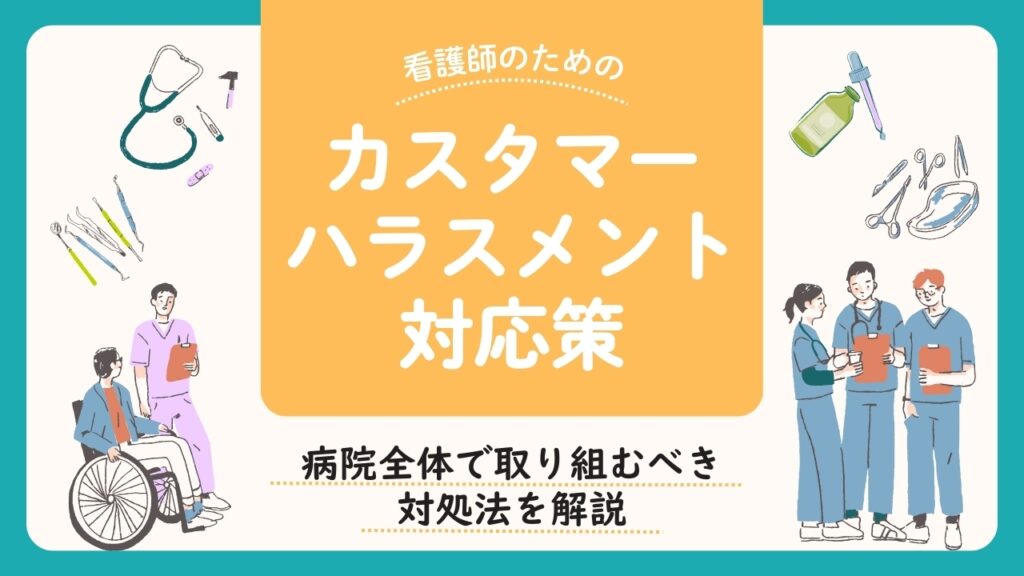
看護師のためのカスタマーハラスメント対応策!対処法を解説
-
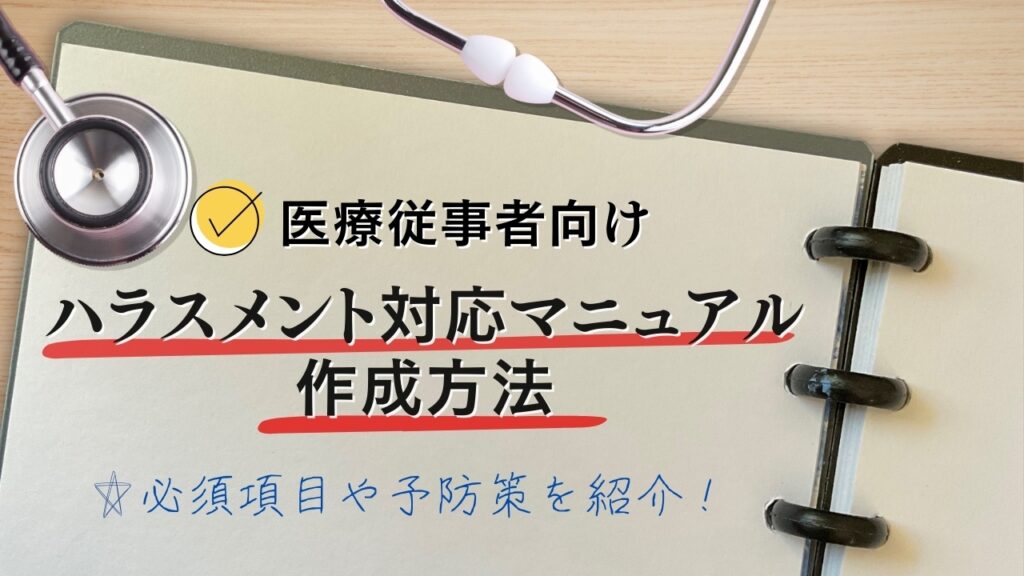
医療従事者向けのハラスメント対応マニュアルの作成方法は?必須項目や予防策を紹介
-

介護施設のクレーム対応研修はなぜ必要?目的やポイントを徹底解説
-
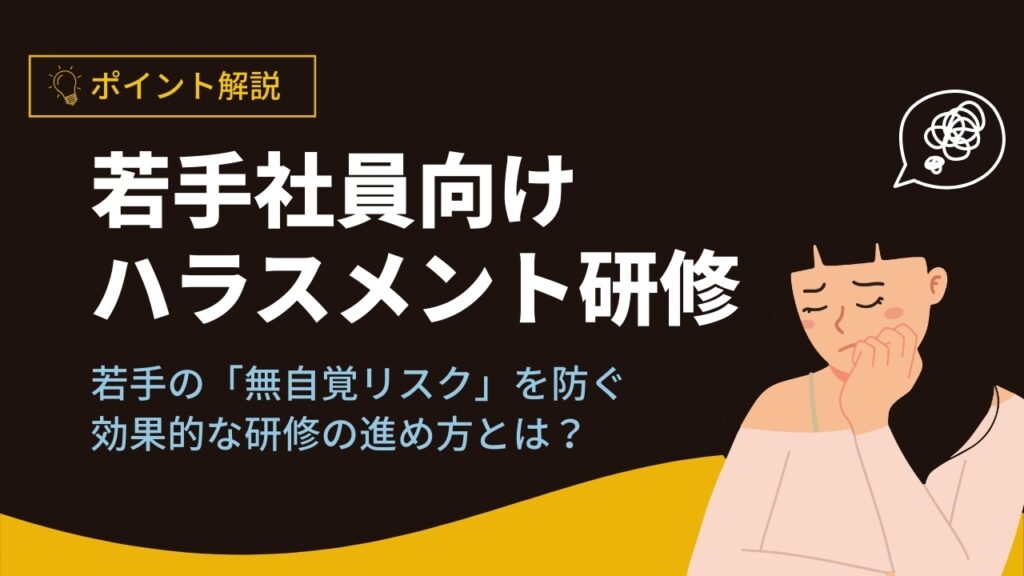
若手社員向けハラスメント研修のポイント解説!効果的な進め方とは
-
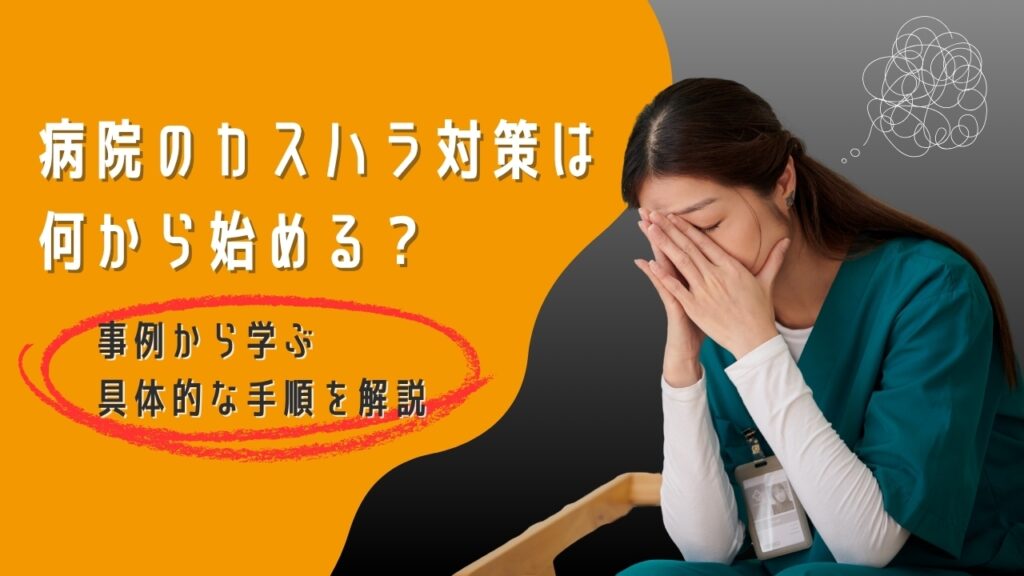
病院のカスハラ対策は何から始める?事例から学ぶ具体的な手順を解説
-
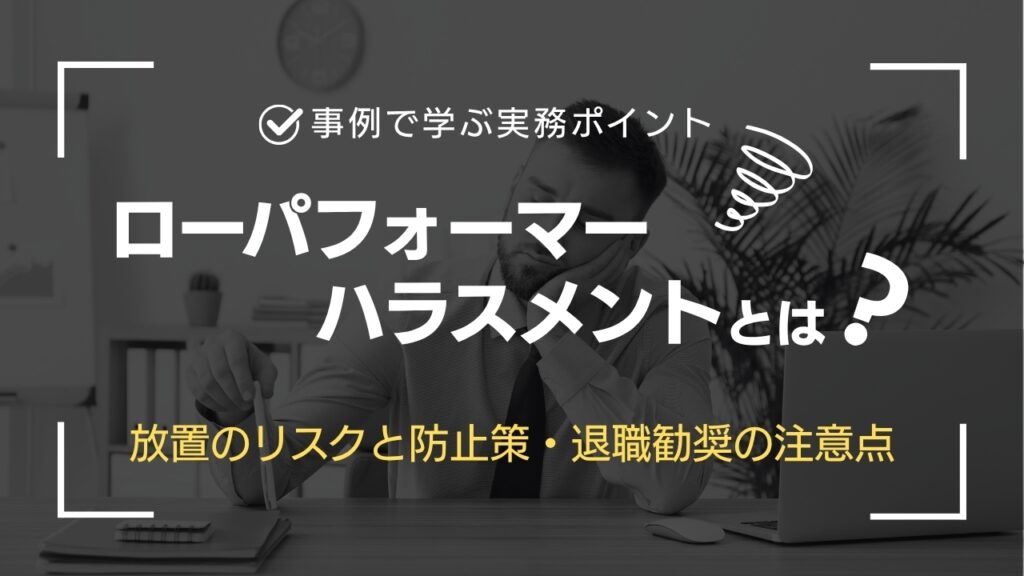
ローパフォーマーハラスメントとは?放置のリスクと防止策・退職勧奨の注意点
-
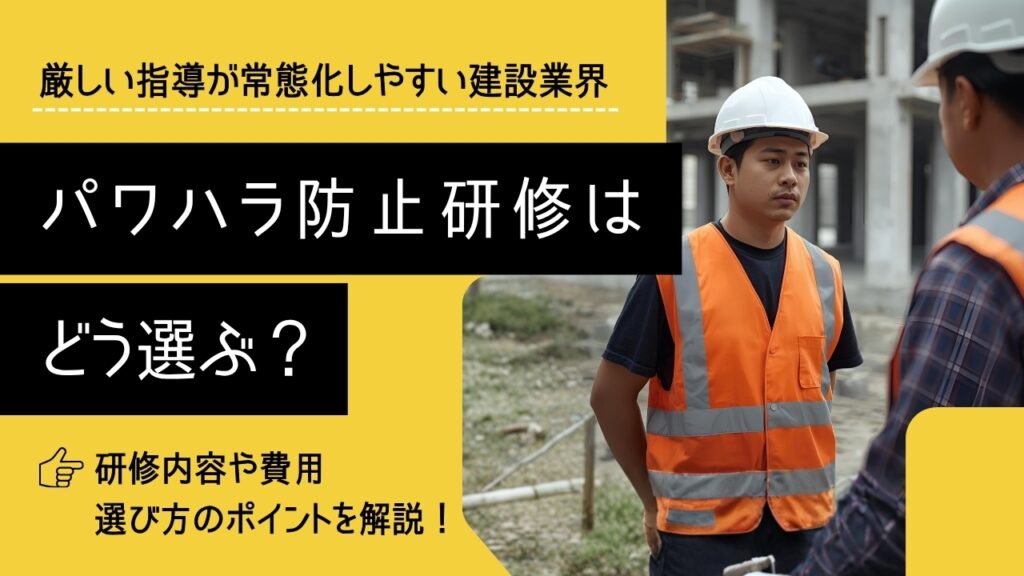
建設業のパワハラ防止研修はどう選ぶ?研修内容や費用、選び方のポイントを解説
-
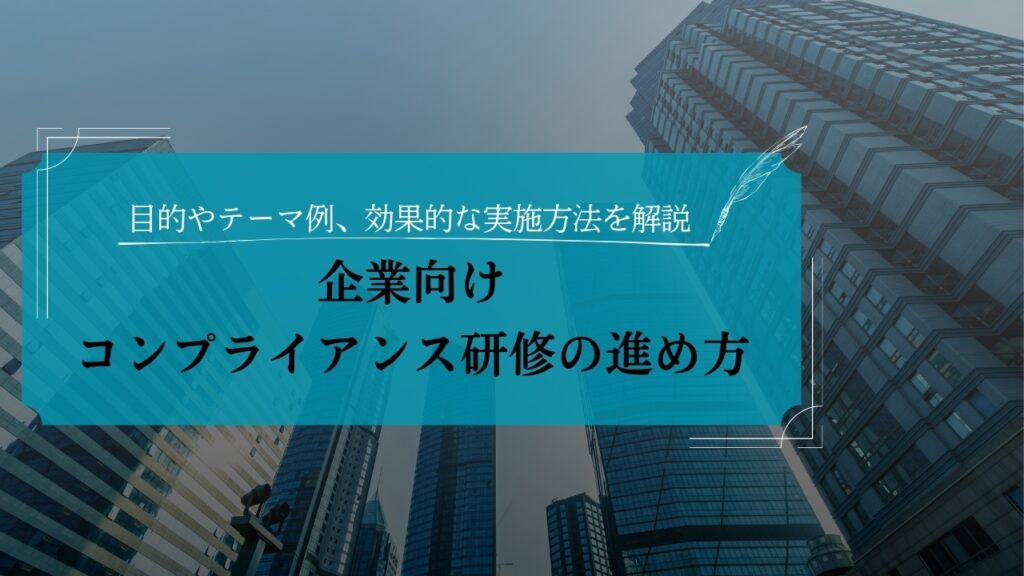
企業向けコンプライアンス研修の進め方!目的やテーマ例、効果的な実施方法を解説
-
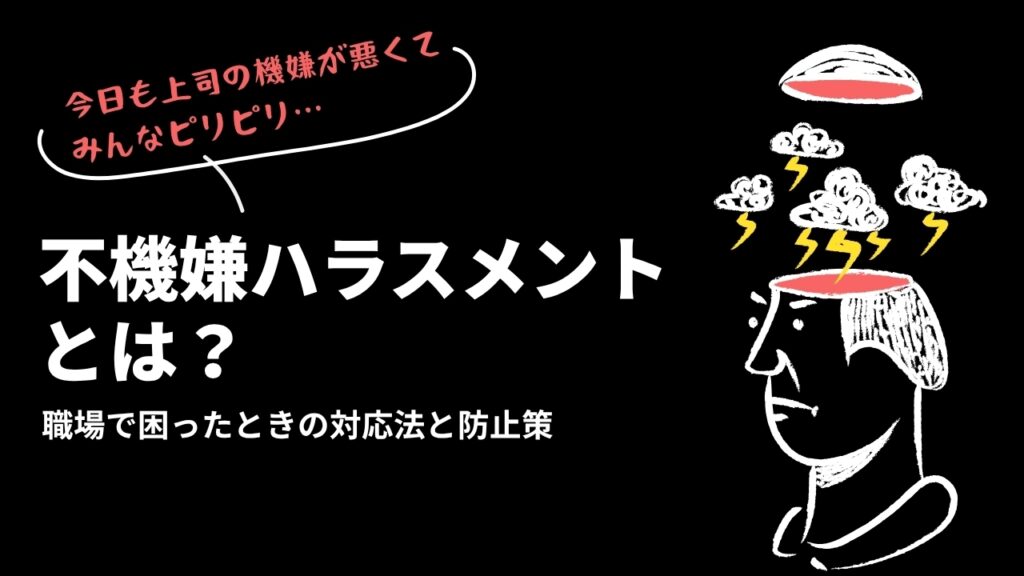
不機嫌ハラスメントとは? 職場で困ったときの対応法と防止策
-

パーソナルハラスメントとは?職場での定義と防止策を解説
-
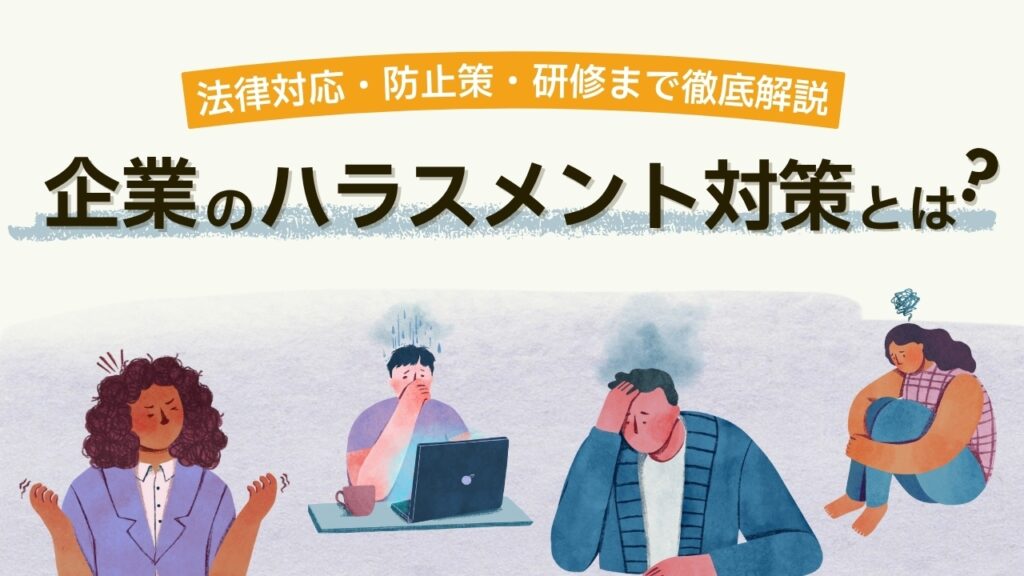
企業のハラスメント対策とは?法律対応・防止策・研修まで徹底解説
-
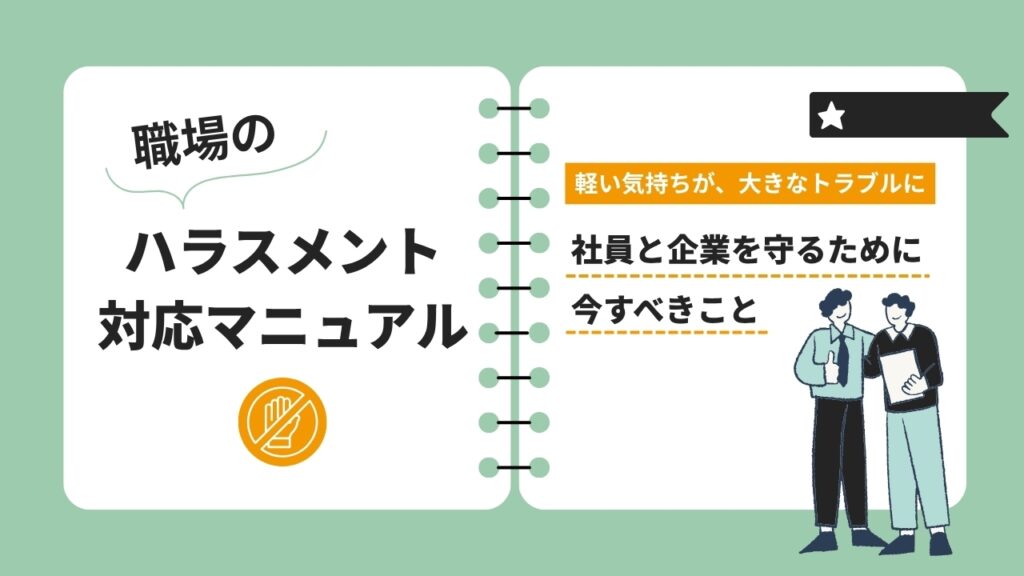
職場のハラスメント対応マニュアル|社員と企業を守るために今すべきこと
-
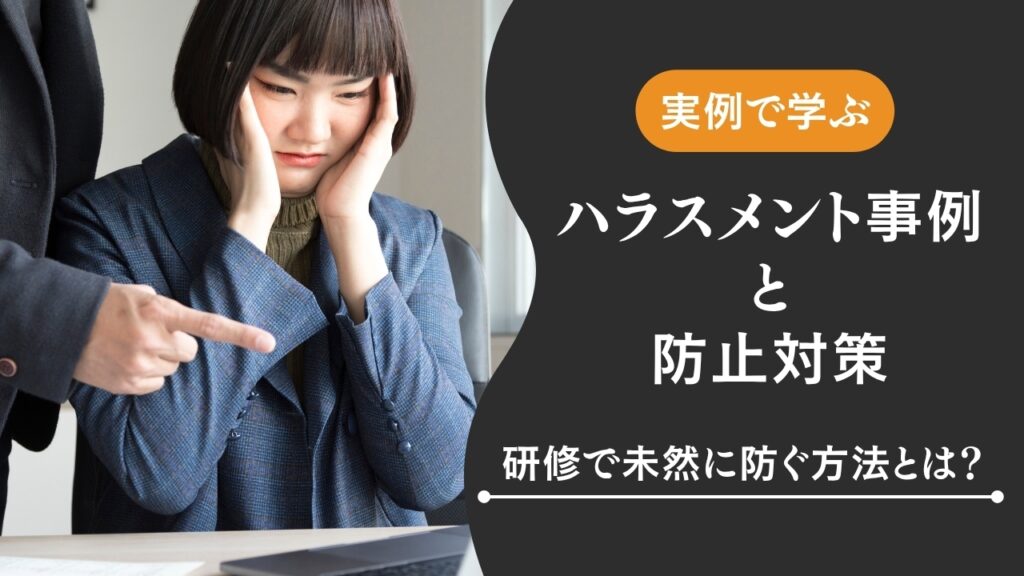
【実例で学ぶ】職場のハラスメント事例と防止対策|研修で未然に防ぐ方法とは?
-
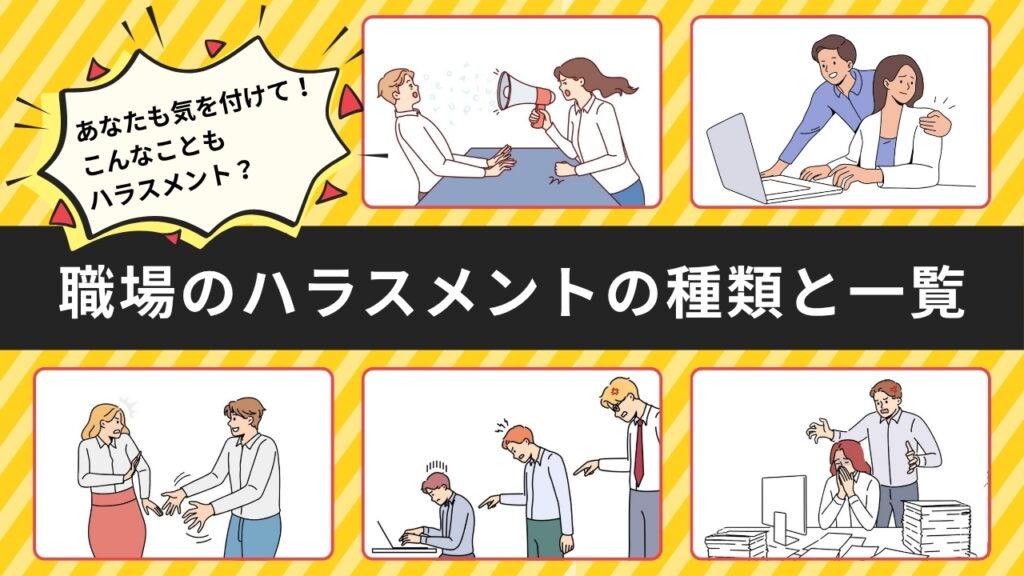
【職場のハラスメントの種類・一覧】あなたも気を付けて!こんなこともハラスメント?
-
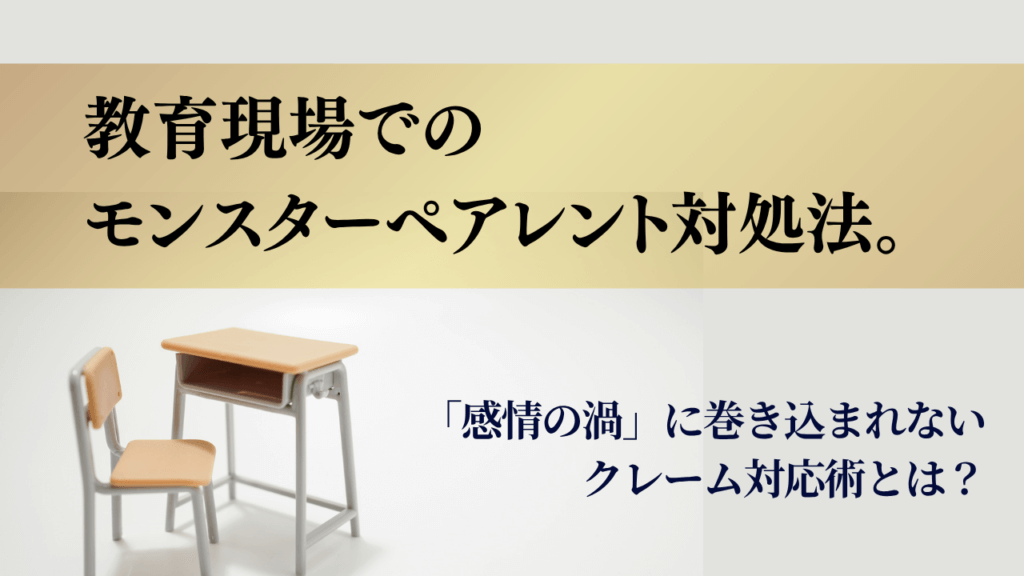
教育現場でのモンスターペアレント対処法。「感情の渦」に巻き込まれないクレーム対応術、効果的な研修法は?
-
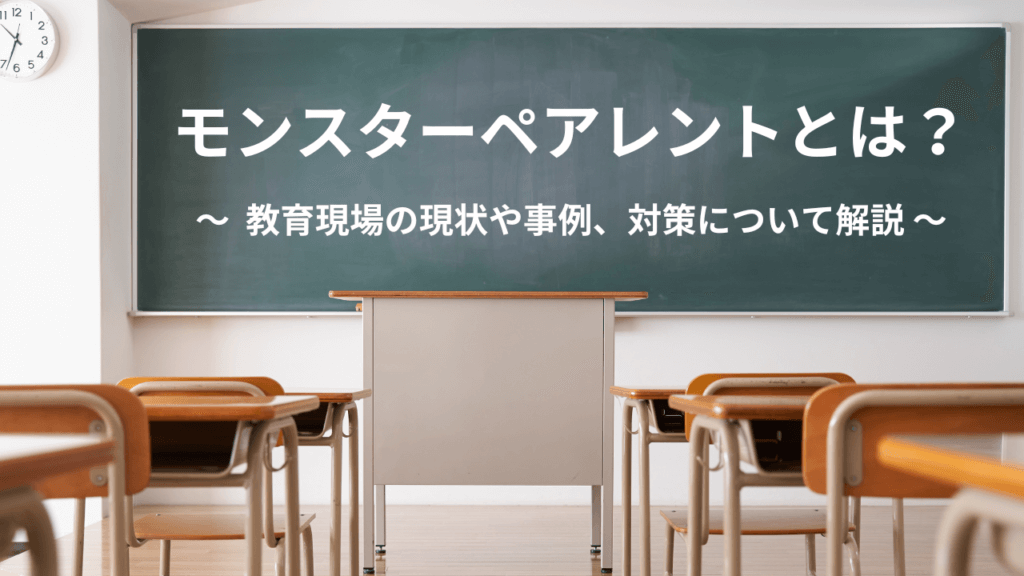
モンスターペアレントとは?教職員を守るためのハラスメント対策について解説
-

カスタマーハラスメント研修とは?研修内容やカスハラを防ぐための取り組み
-
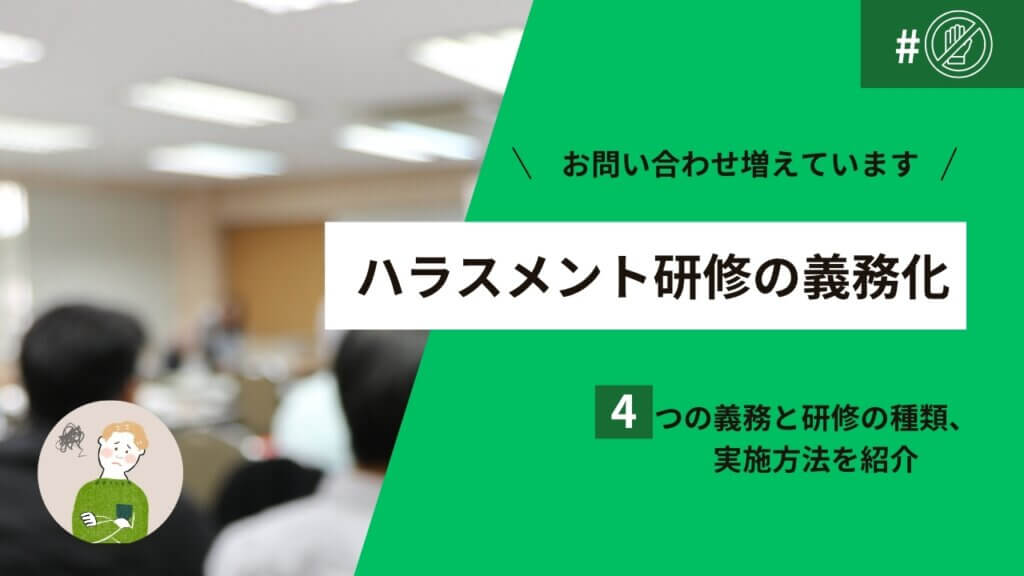
ハラスメント研修の義務化について!4つの義務と研修の種類、実施方法を紹介
-

【2025年最新】パワハラ防止法対応|おすすめハラスメント研修会社を比較!失敗しない選び方とは?
-
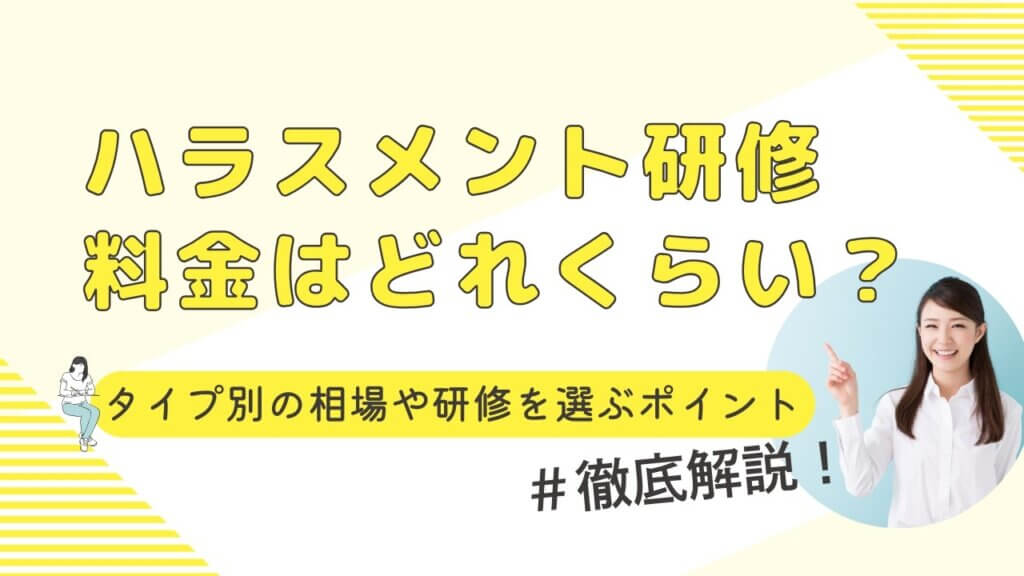
ハラスメント研修の料金はどれくらい?タイプ別の相場や研修を選ぶポイント
-

飲食店のカスハラ対策|事例で学ぶ顧客対応と研修のすすめ
-

病院でのカスハラ事例|医療現場でのリスク対策と研修の必要性
-

介護のカスタマーハラスメント対策とは?介護現場の実態や発生原因も解説!