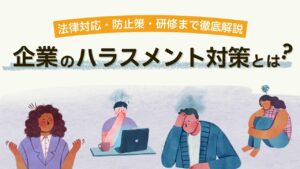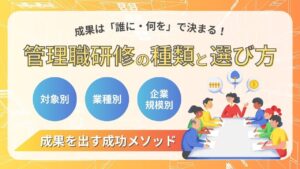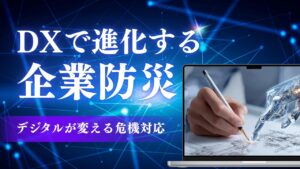企業のハラスメント対策とは?法律対応・防止策・研修まで徹底解説

職場のハラスメントは、社員の心身だけでなく、企業の信頼や生産性にも大きな影響を及ぼします。
本コラムでは、企業のハラスメント対策として今すぐ取り組める方法を、法律対応から防止策、ハラスメント対策研修の活用までわかりやすく解説。

「加害者にも被害者にもならない職場」をつくるためのポイントを押さえ、安全で働きやすい環境づくりの第一歩をサポートします。
なぜ今、企業にハラスメント対策が必要なのか

ハラスメントは「個人間のトラブル」だけでなく、企業全体のリスクとしても重大です。厚生労働省の調査では、ハラスメントに関する労働相談件数は年々増加しています。特にパワハラは、職場の雰囲気や生産性に大きく影響します。
ハラスメントが起きると、社員の離職や生産性低下、企業イメージの毀損など、組織全体に悪影響を及ぼします。
また、2020年のパワハラ防止法施行により、企業には防止の義務が課せられています。早期の制度整備と継続的な対策が欠かせません。
ハラスメントが企業に与える影響
ハラスメントが発生すると、当事者の心身に深刻なダメージを与えるだけでなく、以下のような悪影響が組織全体に広がります。
- 離職率の上昇:働きやすい環境を求めて優秀な人材が辞めてしまう
- 生産性の低下:職場の雰囲気が悪化し、業務効率やモチベーションが下がる
- 企業イメージの毀損:訴訟や報道につながると、採用や取引にも影響する
法律で義務化されている対策
2020年に施行された「パワハラ防止法(労働施策総合推進法)」により、企業にはハラスメント防止の措置を取ることが義務づけられました。
- 防止方針の明確化と周知
- 相談窓口の設置
- 事後の迅速な対応
上記が、法的に求められています。

企業のハラスメント対策は「やるかどうか」ではなく、すでにやらなければならないものになっています。
お客様の課題やカリキュラムに応じてお見積りパターンをご提案しています。
まずは気軽にご相談ください!
お電話でのお問い合わせ 0120-117-450
専任のコンサルタントが丁寧にご相談を受け付けます。
お気軽にご相談ください。
企業が取り組むべきハラスメント対策の全体像
企業がハラスメント対策を行う際には、「制度面」と「運用面」の両方を整えることが不可欠です。
法律で求められている対応だけでなく、社員が安心して働ける環境をつくるためには、以下のような取り組みをバランスよく進める必要があります。
就業規則・社内規程の整備
- 明確なルール作り・ハラスメント行為の定義
「どのような行為がハラスメントにあたるのか」 - 「違反時の処分」を明確にし、全社員に周知すること
- 基準があいまいにならないようにする
相談窓口の設置と機能強化
- 社内外の相談窓口
「誰に相談すればいいかわからない」という状態は最も危険
人事部や外部の専門窓口など、安心して利用できる相談窓口を設置する - 秘密保持と迅速対応を徹底し、社員が安心して相談できる環境を作る
経営層・管理職の意識改革
ハラスメント対策は「トップの姿勢」によって大きく変わります。経営層や管理職が率先して適切な行動を示すことで、「ハラスメントは許されない」というメッセージを職場に浸透させます。
社員への啓発・教育
ルールを整えただけでは、実際の行動は変わりません。
研修やeラーニング、事例紹介などを通じて、社員一人ひとりの理解と行動変容を促すことが欠かせません。

このように、制度の整備と教育・啓発を両輪で進めることで、はじめて実効性のあるハラスメント対策が機能します。
職場で加害者にならないためにできること

ハラスメントは、必ずしも「悪意を持った行為」だけで起こるわけではありません。実際には、無意識の言動や指導の仕方がハラスメントと受け止められ、トラブルに発展するケースが少なくありません。
無意識の言動に注意する
「冗談のつもりだった」「昔はこれが普通だった」といった発言が、相手にとっては大きな苦痛になることがあります。性別や年齢、家庭環境に関する不用意な発言は相手の尊厳を傷つけかねません。
指導とパワハラの線引きを意識する
部下の成長のための指導は必要ですが、感情的な叱責や人格を否定する言葉はパワハラにあたります。
指導は「事実に基づいて具体的に改善点を伝える」ことを意識し、相手を追い詰めないよう配慮することが大切です。
指導とパワハラの線引き
- 事実に基づき具体的な改善点を伝える
- 感情的な叱責や人格否定を避ける
権限や立場を利用しない
上司や先輩といった立場を背景にした要求は、相手にとって断りづらく、ハラスメントになりやすい傾向があります。たとえば「飲み会への強制参加」「プライベートへの過度な干渉」などは注意が必要です。
日頃からセルフチェックを
自分の言動が「もし自分がされたらどう感じるか」を意識することで、加害者リスクを減らすことができます。

つまり、「自分は大丈夫」と思っている人ほど注意が必要です。組織全体で正しい知識を持ち、無意識の言動を見直す習慣をつけることが、防止の第一歩となります。
被害者にならないために知っておきたいこと
ハラスメントの被害にあったとき、多くの人は「我慢すればいい」「自分が悪いのかもしれない」と考えてしまいがちです。しかし、被害を放置することは心身の健康を損なうだけでなく、職場全体の環境悪化にもつながります。被害を受けたときに取るべき行動を知っておくことが、自分を守る第一歩です。早期の気づきと行動が重要です。
まずは「おかしい」と気づくこと
ハラスメントは、相手の意図ではなく自分がどう感じるかが重要です。
「これは不快だ」「耐えられない」と思った時点で、すでに問題がある可能性が高いと認識しましょう。
証拠を残しておく
会話の録音、メールやチャットの履歴、日付と内容をメモしておくなど、客観的な記録を残すことが大切です。
証拠があることで、相談や調査の際に正確な事実関係が伝わりやすくなります。
証拠を残す
- 会話の記録
- メール・チャット履歴
- 日付・内容のメモ
- 客観的証拠は相談や調査に役立つ
信頼できる人や窓口に相談する
一人で抱え込まず、上司や人事部、社内外の相談窓口に相談しましょう。
近年は外部の専門機関や匿名相談窓口を設置する企業も増えており、プライバシーが守られた環境で話すことができます。
自分を責めない
ハラスメントの責任は加害者にあります。
「自分に原因があるのでは」と思い込まず、被害者としての立場を正しく理解することが大切です。

被害にあわないためには 「気づく力」と「声を上げる行動力」 が必要です。組織としても、社員が安心して相談できる環境づくりが求められます。
目撃したときにどう動く?周囲の人ができる対応
ハラスメントは、加害者と被害者だけの問題ではありません。第三者の対応次第で被害の拡大を防ぐことも可能です。傍観してしまうと、無意識に「黙認」してしまうことになり、職場全体のハラスメントリスクを高めてしまいます。
傍観せず、適切に行動する
ハラスメントを見かけたとき、「関わるのは面倒」「自分には関係ない」と思う人もいます。
しかし、早期に気づき、介入することが被害拡大を防ぐ第一歩です。
安全な形で声をかける
被害者に直接声をかける場合は、「自分が見て気づいたこと」「相手の行動で困っていないか」を確認する形で、落ち着いて伝えます。感情的にならず、事実に基づく会話を心がけることがポイントです。
上司や相談窓口へつなぐ
直接対応が難しい場合は、人事部や社内の相談窓口、場合によっては外部の専門窓口に報告することが安全です。
第三者としての行動が、被害者の安心感につながることを理解しましょう。
組織としてのルールを意識する
職場全体でハラスメントの報告や相談の仕組みが明確であれば、第三者も行動しやすくなります。社内規程や相談窓口を確認し、必要な場合は適切に活用しましょう。
ハラスメント防止における研修の役割

ハラスメント対策を組織で効果的に進めるためには、研修が重要な役割を果たします。研修を通じて、社員は自分の行動や言動を振り返り、ハラスメントのリスクに気づくことができます。また、研修は管理職や一般社員など立場ごとに内容を調整することで、より実践的な学びが得られます。

研修は、知識定着と意識改革の両方を促す手段です。
研修で得られる効果
- 意識の向上:無意識の言動や態度がハラスメントにあたる可能性を理解
- 行動の変容:具体的な対応策や安全なコミュニケーションの方法を学ぶ
- 職場文化の改善:全社員が共通認識を持つことで、ハラスメントが起きにくい風土に
管理職向けと一般社員向けの研修内容
- 管理職向け:部下への指導方法、注意が必要な言動の事例、相談対応の方法
- 一般社員向け:ハラスメントの種類、受けた時の対応、周囲ができるサポート方法
ケーススタディやロールプレイの重要性
座学だけでなく、実際のケースを想定した演習を行うことで、日常業務での応用力が身につきます。
社員自身が体験することで、理解が深まり、行動の定着にもつながります。
他施策との連動
研修は、就業規則や相談窓口などの制度と組み合わせることで、組織全体でハラスメント対策が機能するようになります。研修単体ではなく、全体の仕組みの一部として位置づけることが重要です。
組織的に取り組むことが重要
ハラスメント防止は、個人の意識だけでは限界があります。組織として一貫した方針と体制を整え、社員全員が安心して働ける環境をつくることが不可欠です。
経営層・管理職のリーダーシップ
ハラスメント対策はトップの姿勢が大きく影響します。経営層や管理職が率先して適切な行動を示すことで、「ハラスメントは許されない」というメッセージが社内全体に浸透します。
継続的な取り組み
対策は一度実施しただけでは不十分です。定期的な研修や周知活動、相談窓口の運用チェックなどを継続的に行うことで、社内文化として定着させることができます。
制度・仕組みの整備
- 就業規則やハラスメント防止規程の明確化
- 相談窓口や対応フローの整備
- 事後の適切なフォローや処置
これらを組織的に運用することで、個人では対応しきれない問題も、スムーズかつ公正に解決できる体制が整います。
外部専門家の活用
社内だけで対応するのが難しい場合は、外部研修会社や専門家の力を借りることも有効です。
客観的な視点で改善策を提案してもらえるため、社内の対応力を強化できます。
ポイントまとめ
ハラスメント防止は、個人任せにせず、組織として体系的に取り組むことが成功の鍵です。
制度・教育・文化の三つを同時に整えることで、社員が安心して働ける職場が実現します。
ハラスメント対策は企業の義務、組織的な取り組みが鍵
ハラスメントは、個人任せにせず、企業全体で体系的に取り組むことが不可欠です。
制度整備・教育・文化の三つを組み合わせることで、安心して働ける職場環境が実現します。
- 制度や研修などの組織的対策
- 被害者・目撃者への適切な対応
- 無意識の言動に注意すること
企業のハラスメント対策は、ガイアシステムにお任せください
最新法令に基づく制度設計、実践的研修、相談窓口の整備まで、企業規模や業種に応じた総合サポートを提供しています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
ハラスメント研修カリキュラム
従業員をクレーマーから守り、組織の対応力向上を目指す!
カスタマーハラスメント研修|対応力強化
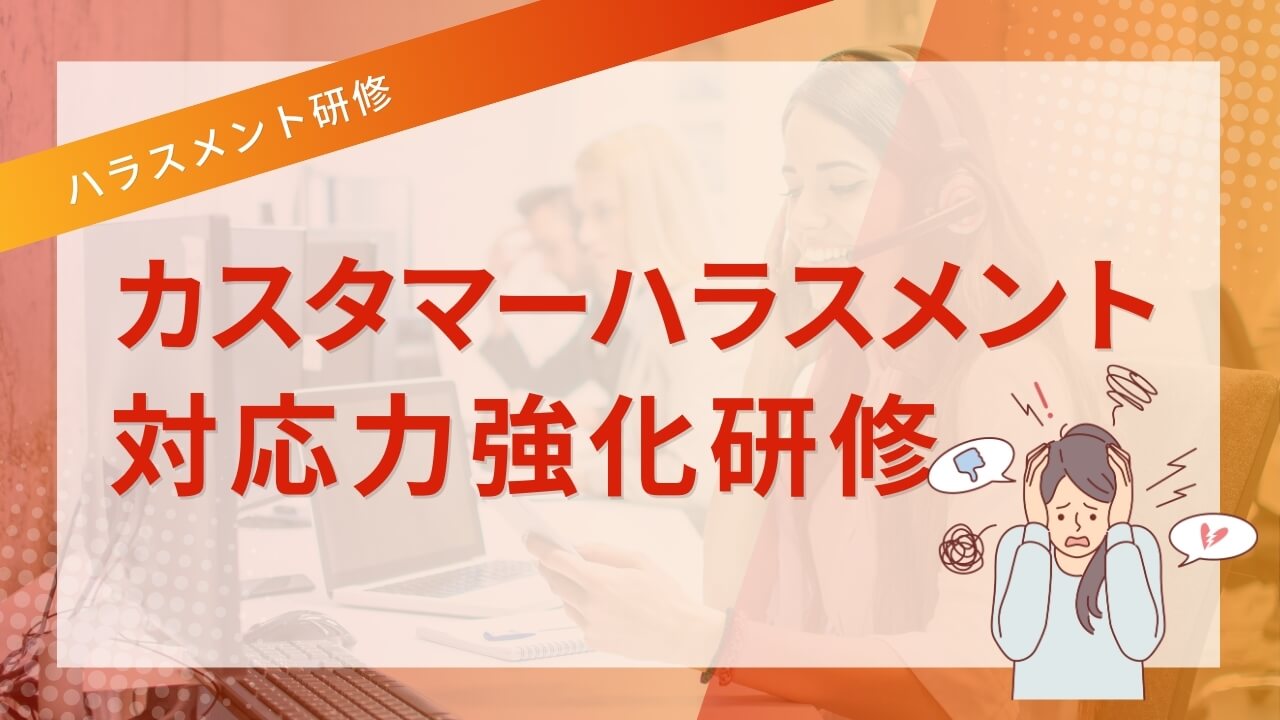
従業員に大きなストレスを与え、離職の原因にもなっているカスタマーハラスメント。個人の能力では解決できないケースも多く、組織が一体となってリスク回避することが必要です。
本研修はカスタマーハラスメントの理解と対応力を強化することを目的に、コミュニケーションスキルを学び、実践的なグループワークを通じて具体的な対策を考えます。
ハラスメントの未然防止、環境改善を目指す!
ハラスメント研修 |パワハラ防止対策
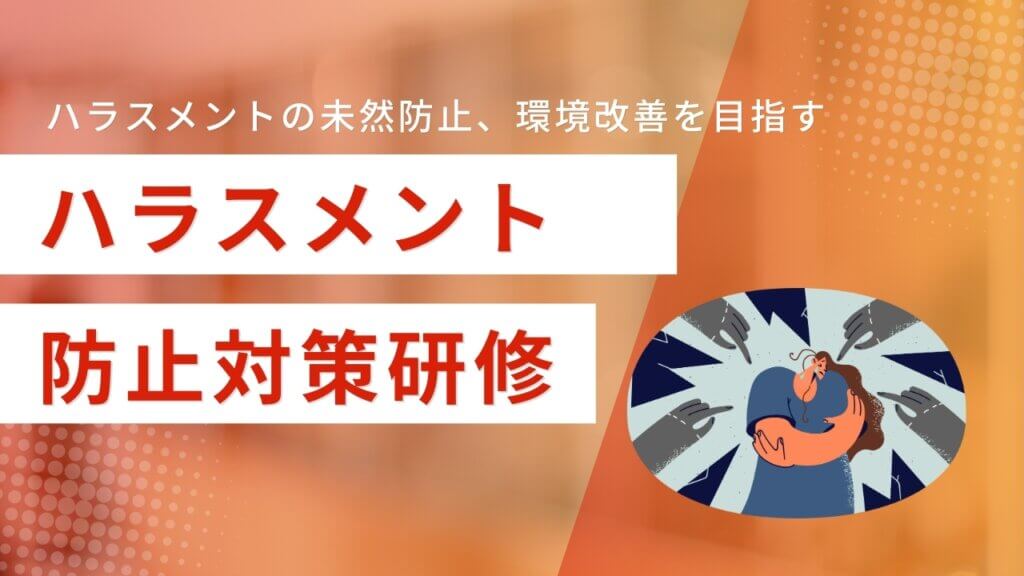
セクハラ、パワハラ、マタハラなど様々なハラスメントの定義や具体例、日常に潜むハラスメントリスクについて学びます。
「グレーゾーンと思われがちな事例紹介」やケーススタディを通じてハラスメントの識別方法を習得し、グループディスカッションで防止策を考案します。また、ハラスメントが起きた際の適切な対応方法や報告手順を身に着けます。
心のメンテナンス手法を習得
メンタルヘルス研修|ストレスと上手に向き合うには
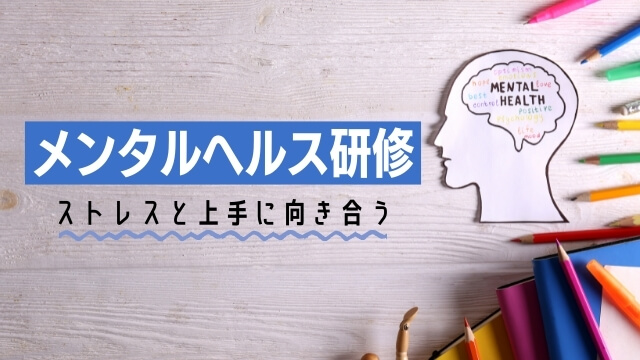
メンタルヘルスに対する知識を身につけ、自分の心の状態を確認し、自らに合ったメンテナンス手法を習得していきます。
・メンタルヘルス研修 全従業員対象 基礎編
・メンタルヘルス研修 役職対象 ラインケア編
・メンタルヘルス研修 全従業員対象 セルフケア編
上記を事例に、内容別・対象別に様々な研修カリキュラムを取り揃えております。
ハラスメントコラム一覧
-
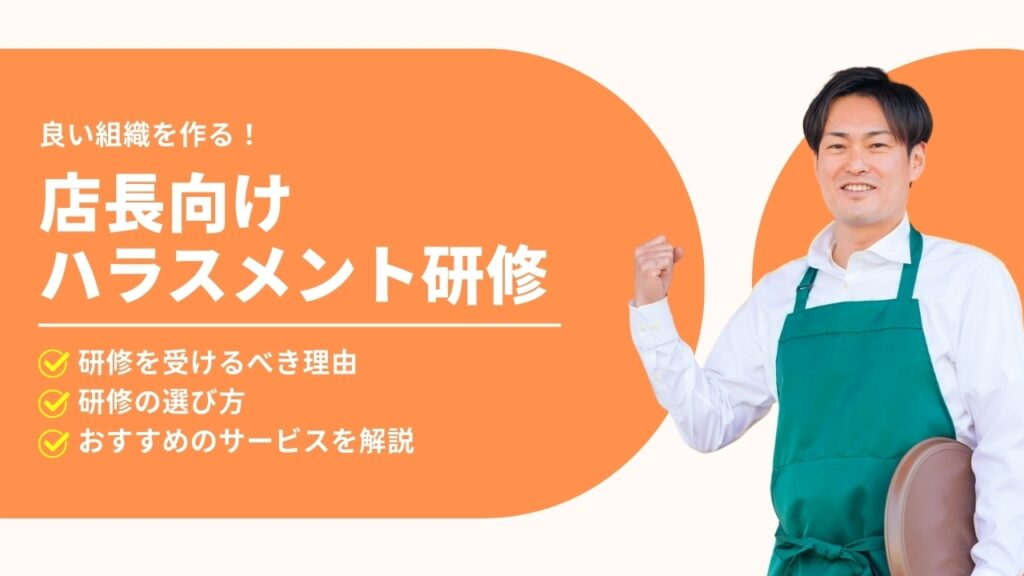
良い組織を作る!店長向けハラスメント研修のポイントを解説
-
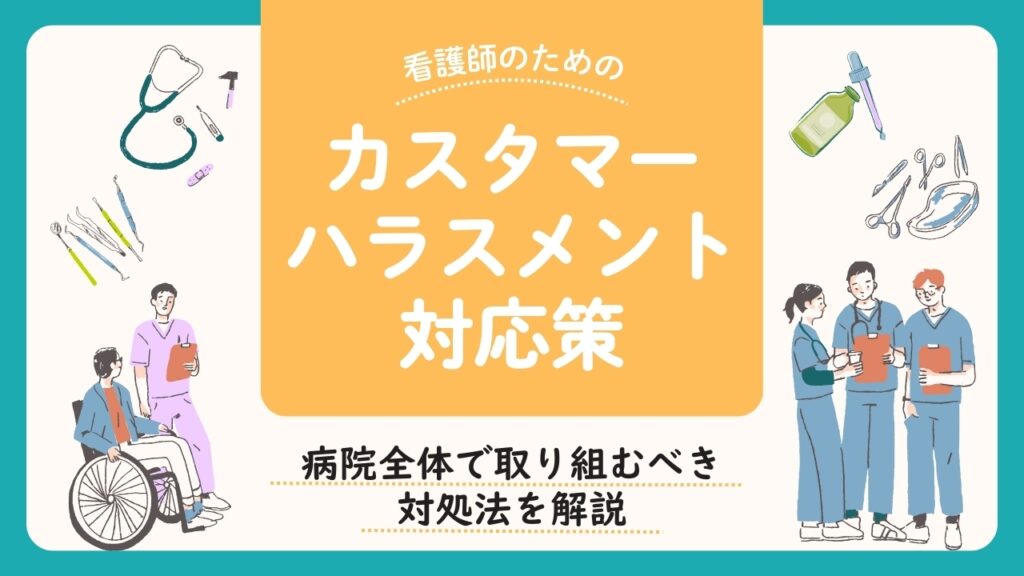
看護師のためのカスタマーハラスメント対応策!対処法を解説
-
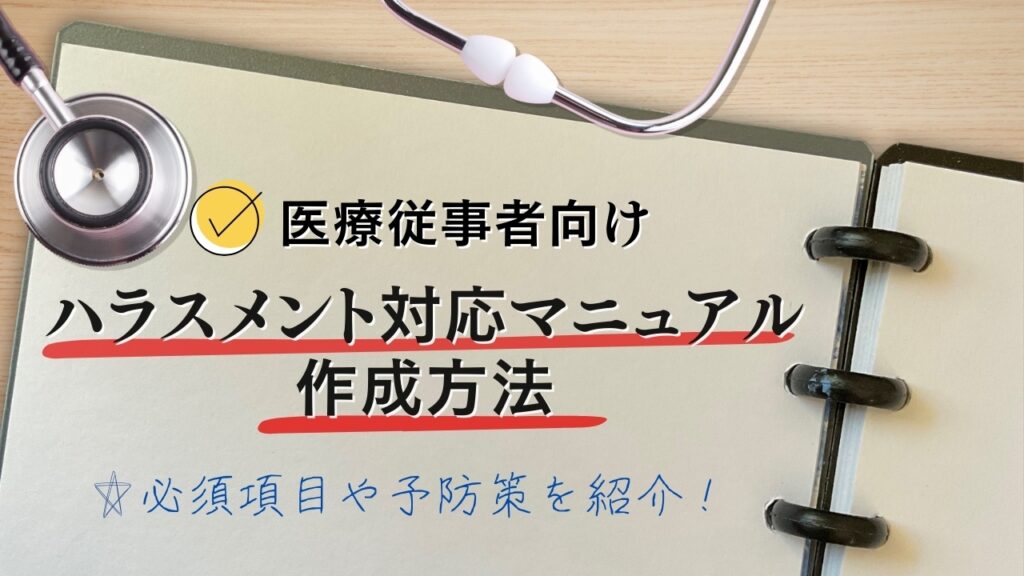
医療従事者向けのハラスメント対応マニュアルの作成方法は?必須項目や予防策を紹介
-

介護施設のクレーム対応研修はなぜ必要?目的やポイントを徹底解説
-
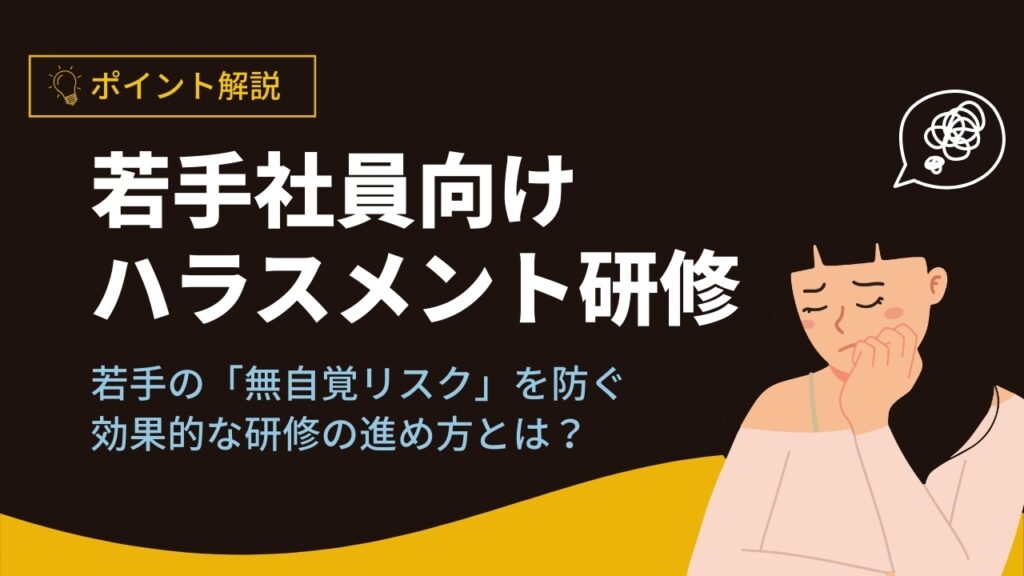
若手社員向けハラスメント研修のポイント解説!効果的な進め方とは
-
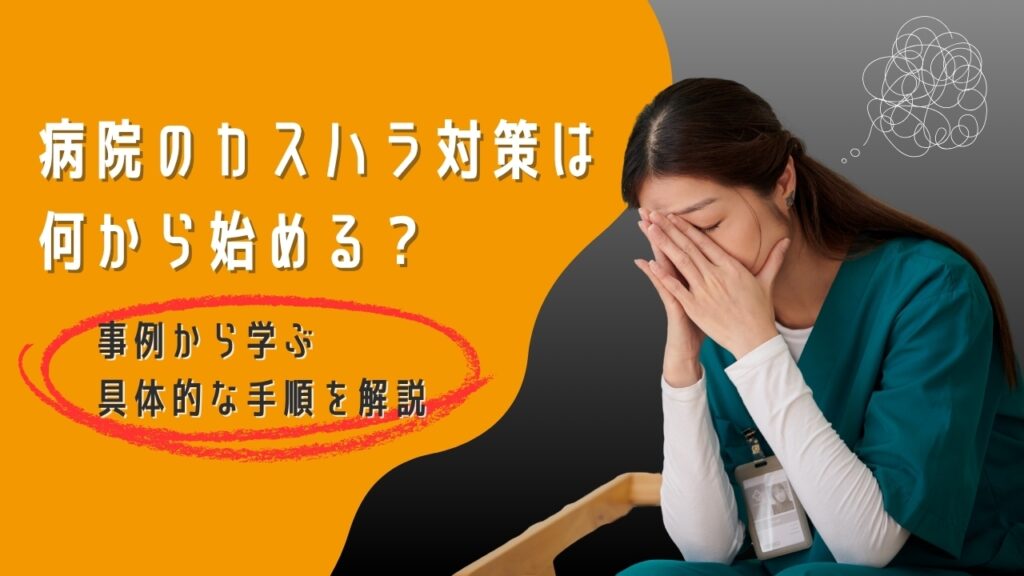
病院のカスハラ対策は何から始める?事例から学ぶ具体的な手順を解説
-
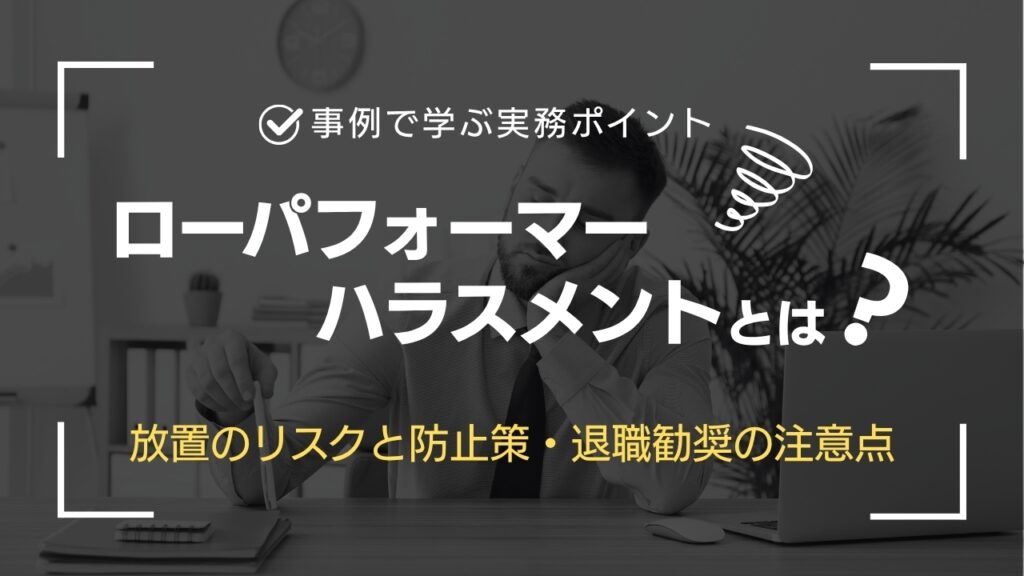
ローパフォーマーハラスメントとは?放置のリスクと防止策・退職勧奨の注意点
-
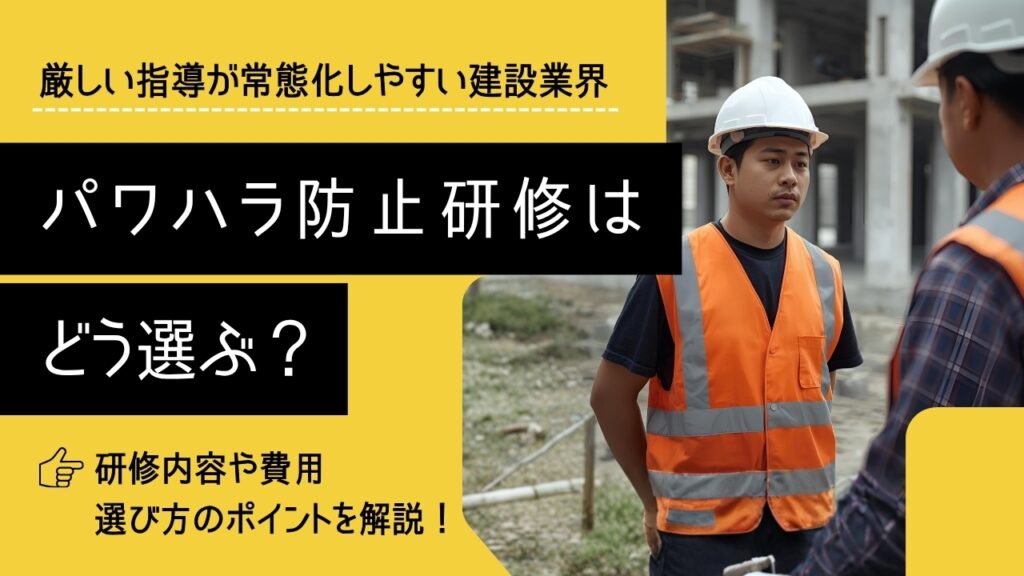
建設業のパワハラ防止研修はどう選ぶ?研修内容や費用、選び方のポイントを解説
-
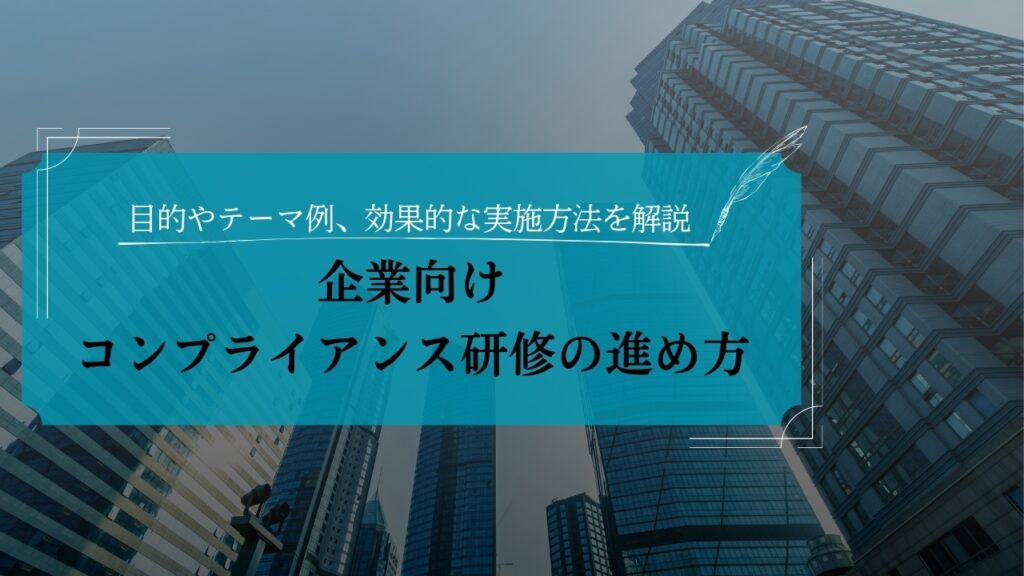
企業向けコンプライアンス研修の進め方!目的やテーマ例、効果的な実施方法を解説
-
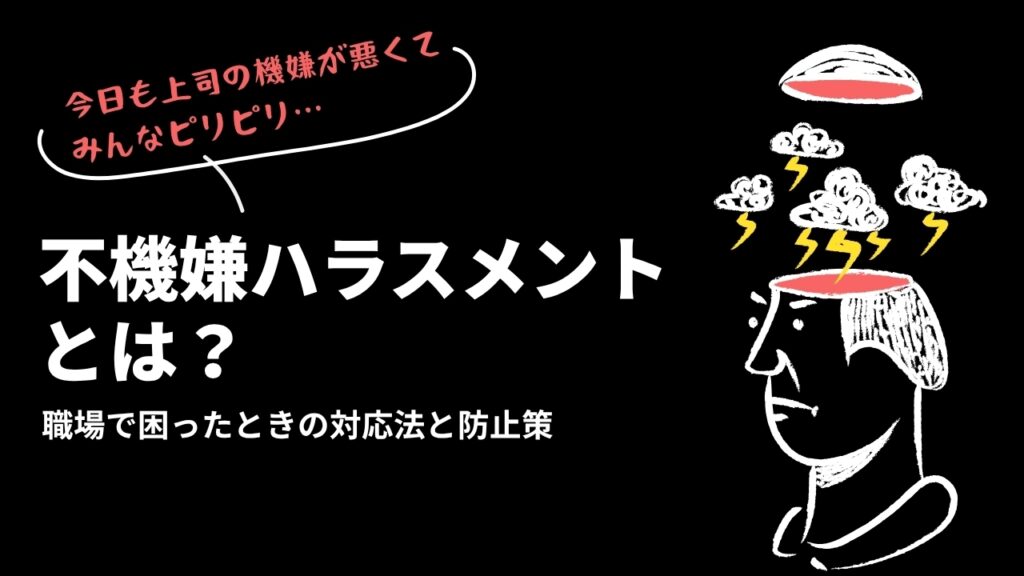
不機嫌ハラスメントとは? 職場で困ったときの対応法と防止策
-

パーソナルハラスメントとは?職場での定義と防止策を解説
-
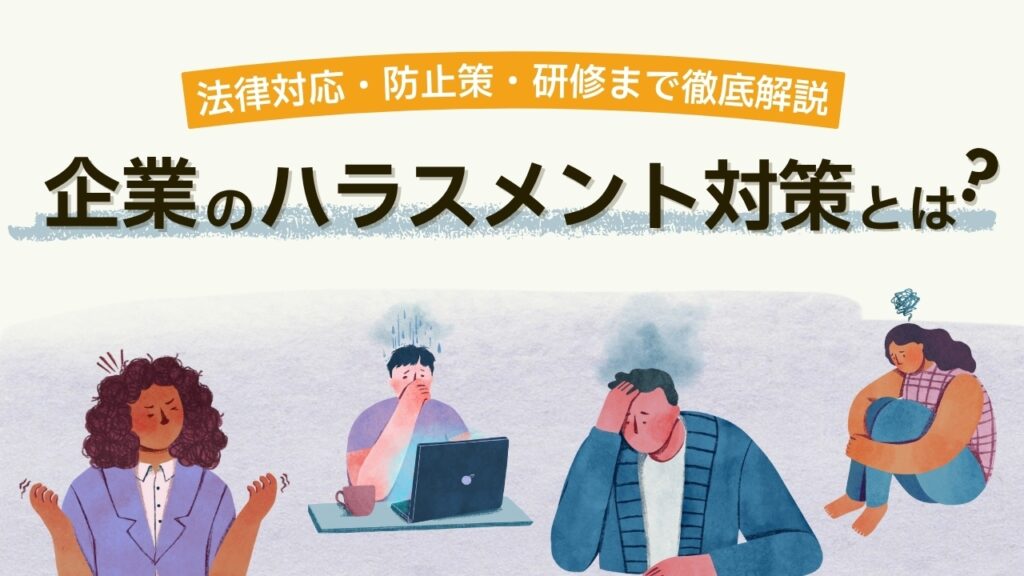
企業のハラスメント対策とは?法律対応・防止策・研修まで徹底解説
-
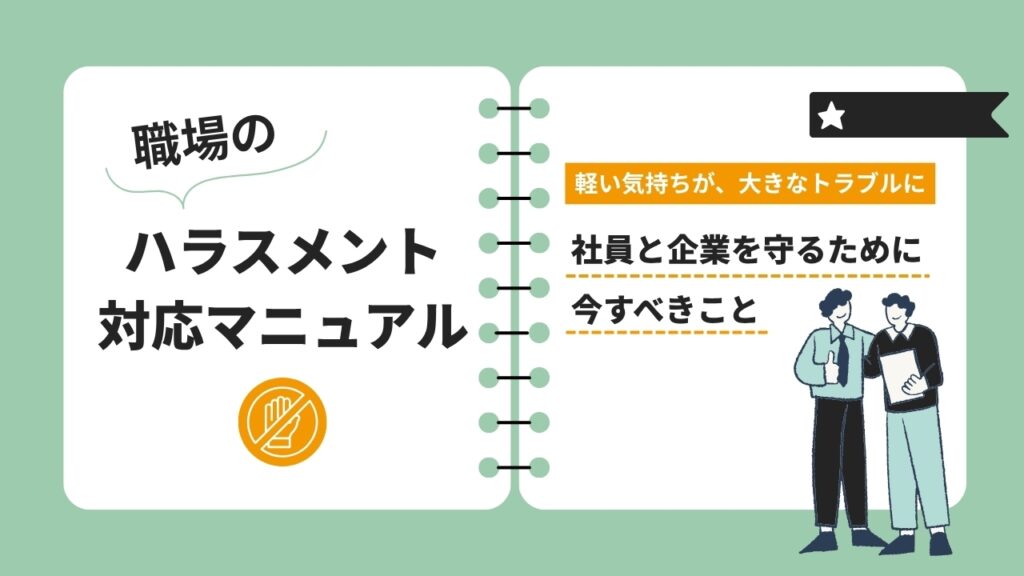
職場のハラスメント対応マニュアル|社員と企業を守るために今すべきこと
-
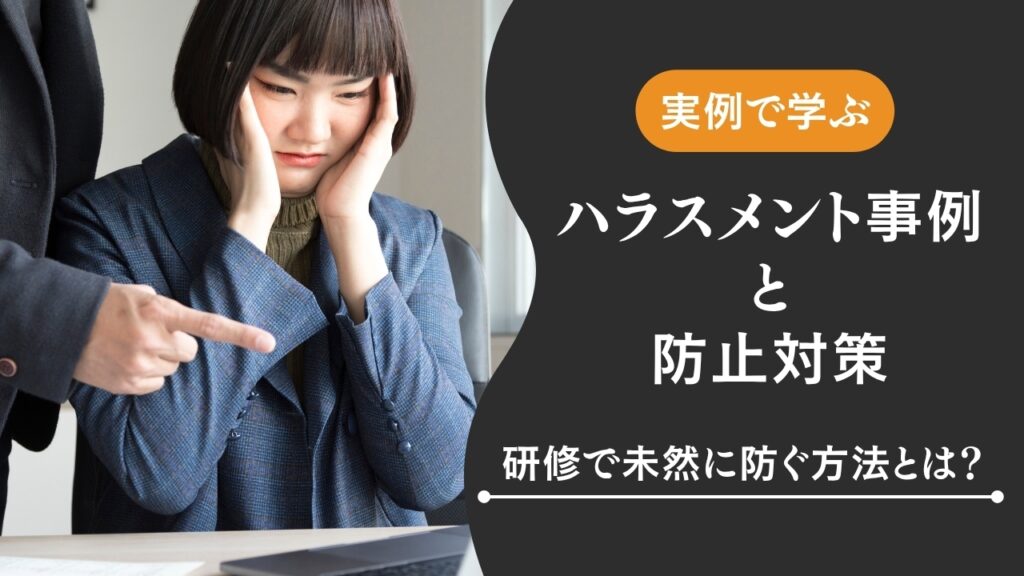
【実例で学ぶ】職場のハラスメント事例と防止対策|研修で未然に防ぐ方法とは?
-
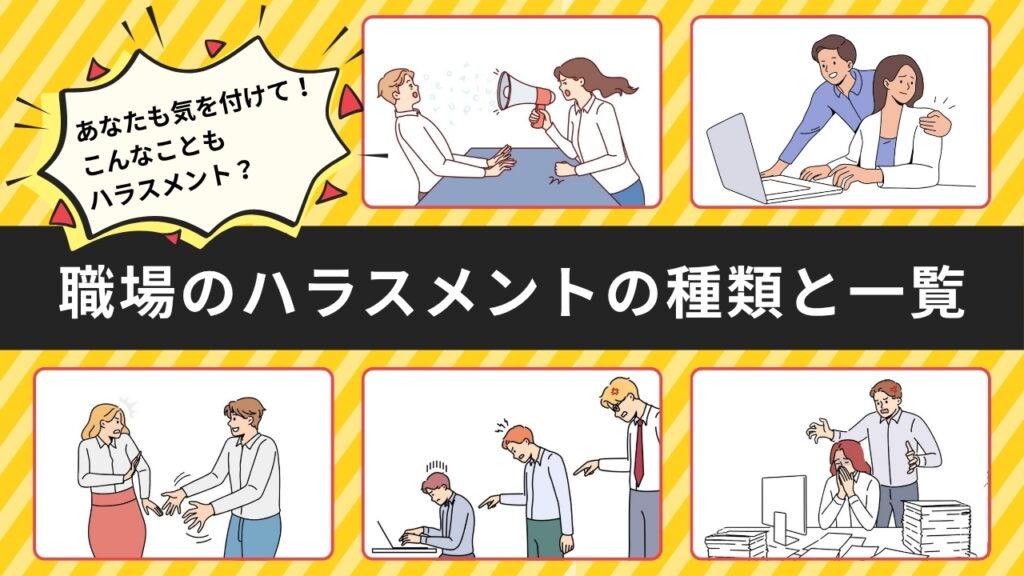
【職場のハラスメントの種類・一覧】あなたも気を付けて!こんなこともハラスメント?
-
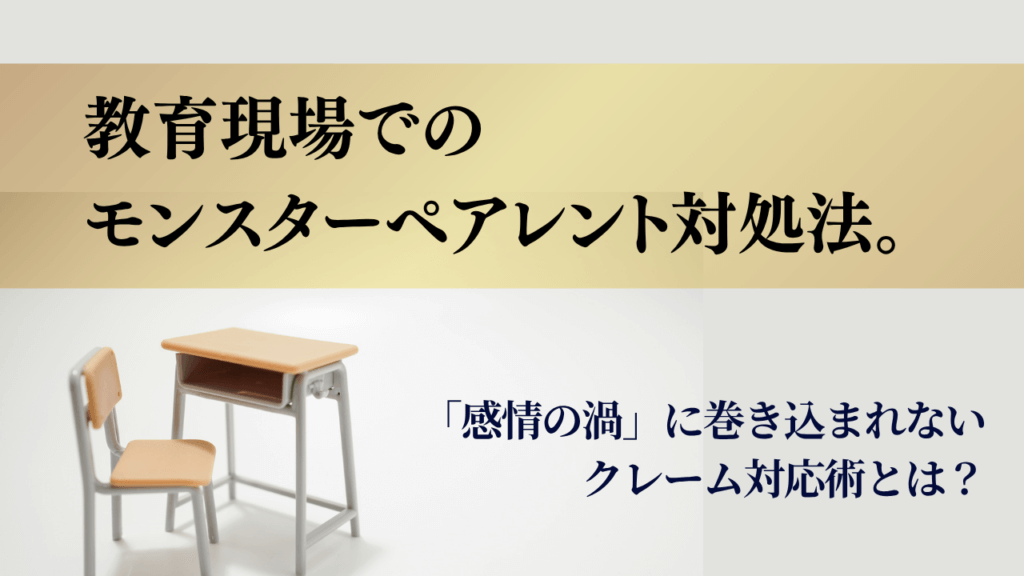
教育現場でのモンスターペアレント対処法。「感情の渦」に巻き込まれないクレーム対応術、効果的な研修法は?
-
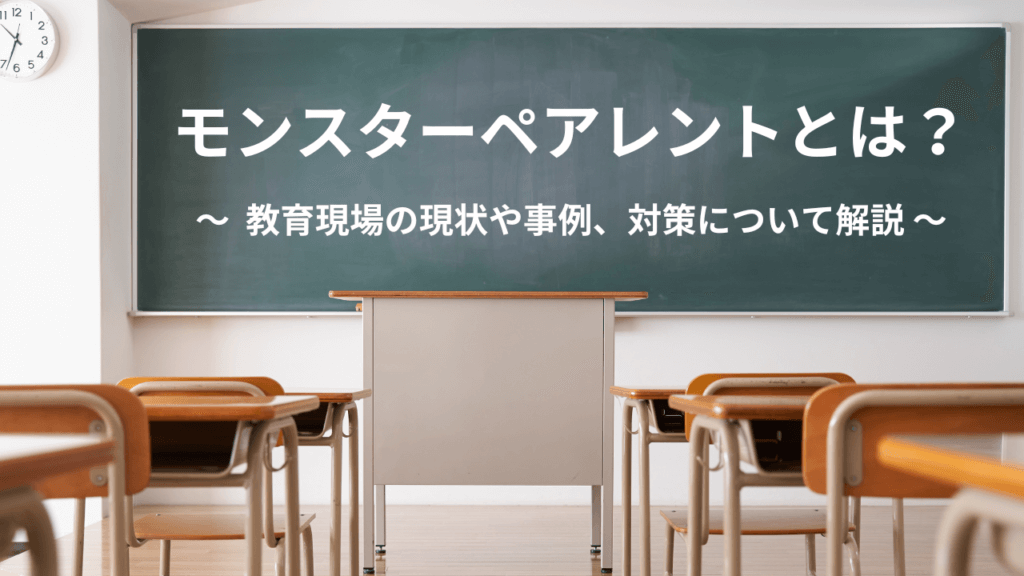
モンスターペアレントとは?教職員を守るためのハラスメント対策について解説
-

カスタマーハラスメント研修とは?研修内容やカスハラを防ぐための取り組み
-
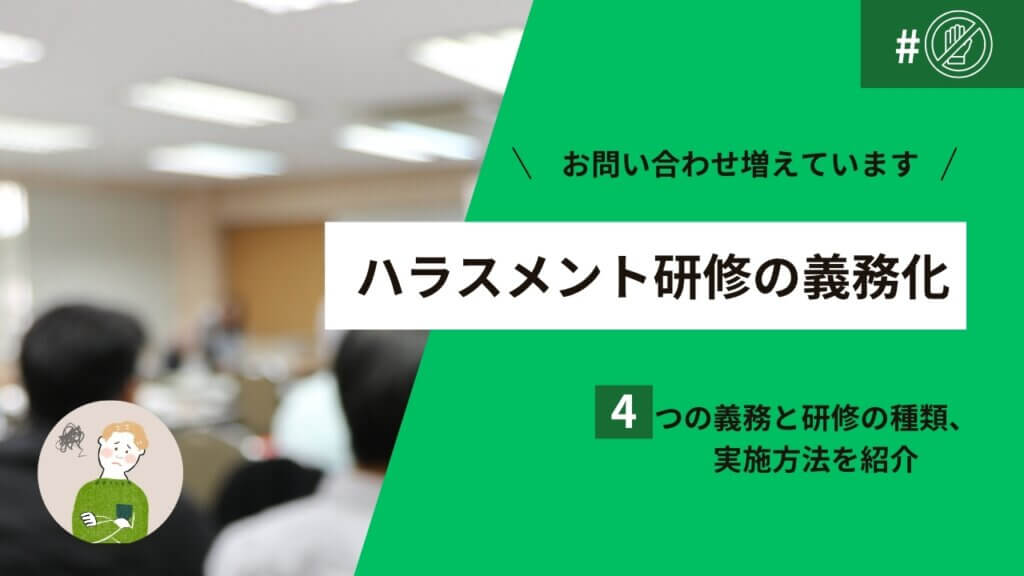
ハラスメント研修の義務化について!4つの義務と研修の種類、実施方法を紹介
-

【2025年最新】パワハラ防止法対応|おすすめハラスメント研修会社を比較!失敗しない選び方とは?
-
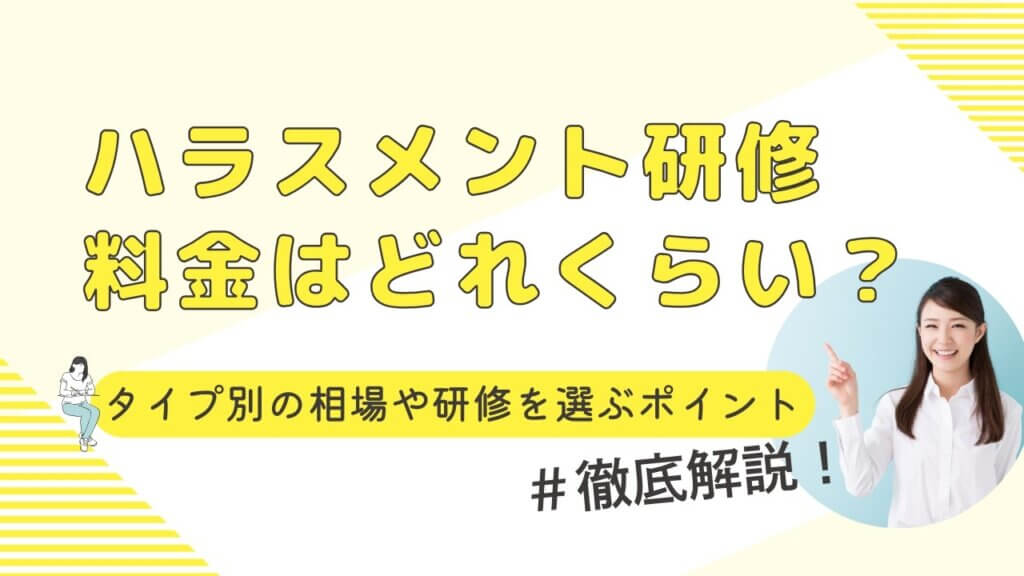
ハラスメント研修の料金はどれくらい?タイプ別の相場や研修を選ぶポイント
-

飲食店のカスハラ対策|事例で学ぶ顧客対応と研修のすすめ
-

病院でのカスハラ事例|医療現場でのリスク対策と研修の必要性
-

介護のカスタマーハラスメント対策とは?介護現場の実態や発生原因も解説!