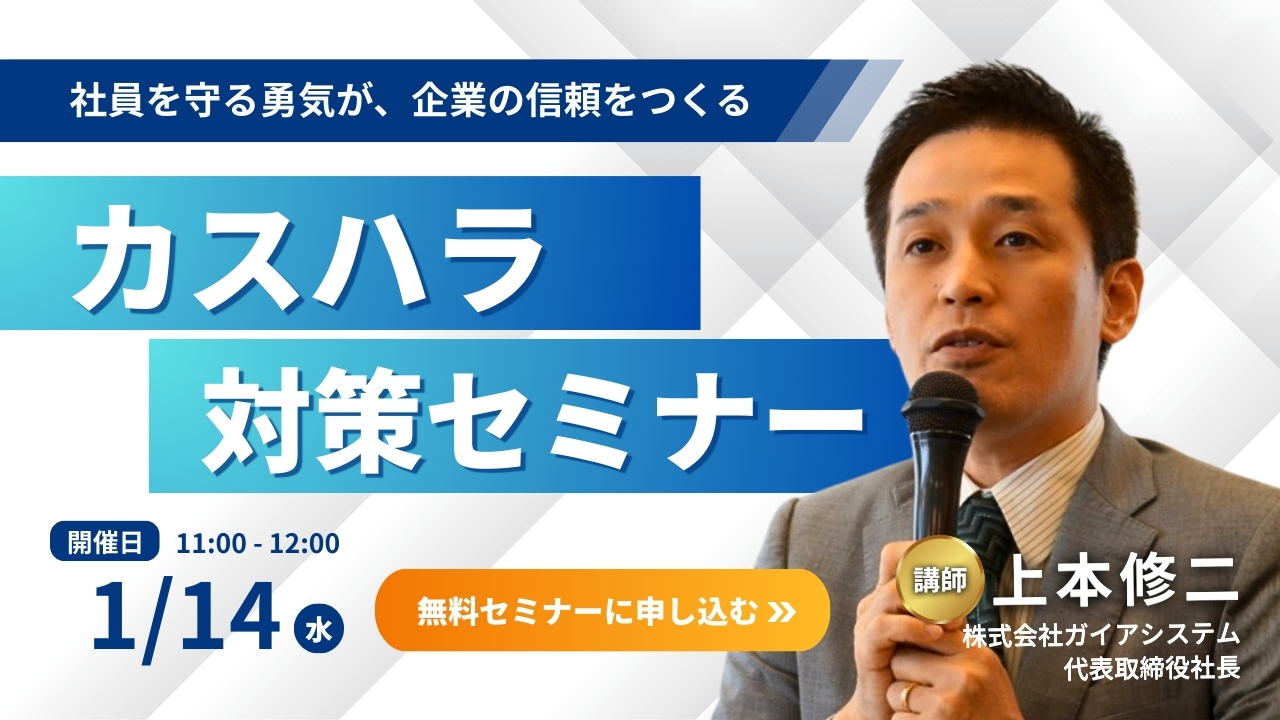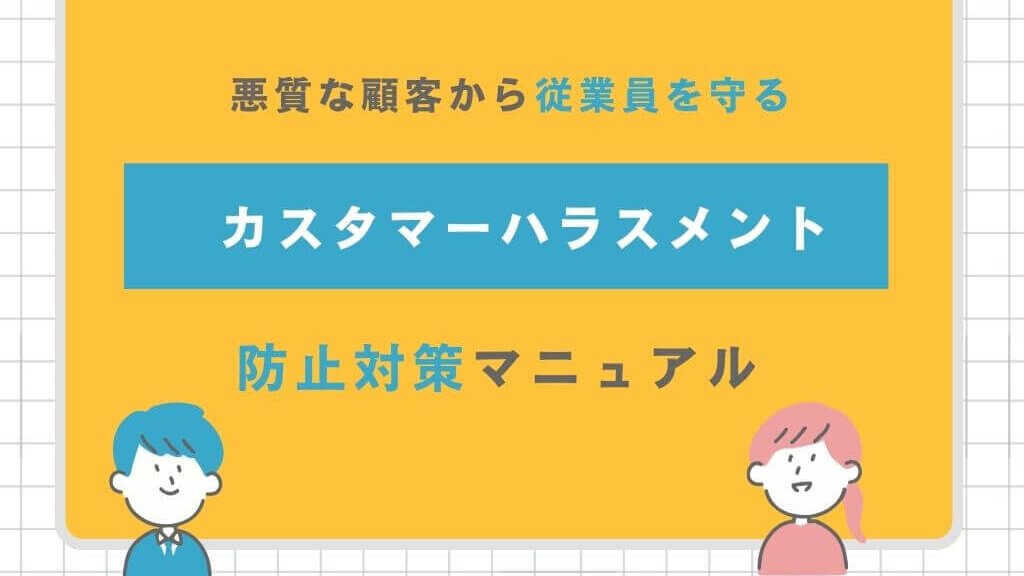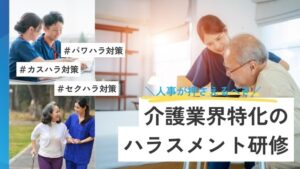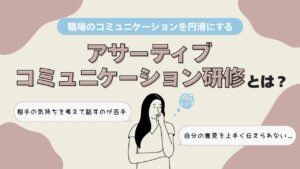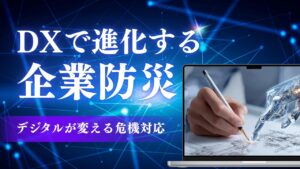介護業界のハラスメント研修とは?|取り組むべき防止対策について詳しく解説!
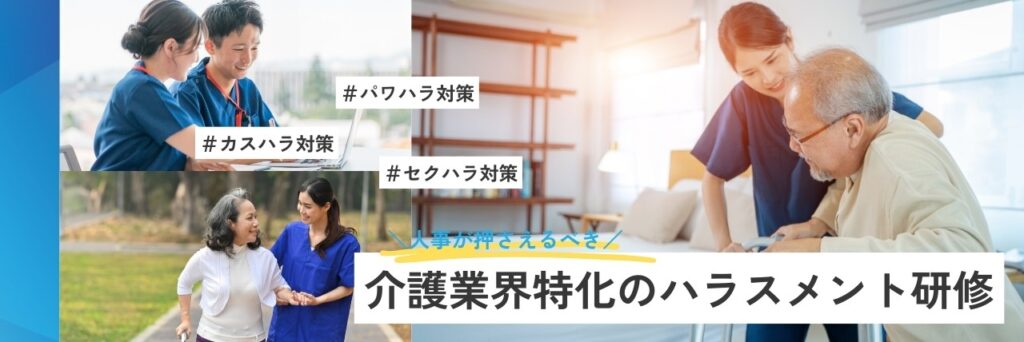
近年、介護の現場では、利用者やその家族から職員への「カスタマーハラスメント(カスハラ)」、職員同士で起こる「パワーハラスメント(パワハラ)」や「セクシャルハラスメント(セクハラ)」が深刻な問題となっています。
本記事では、介護事業者が取り組むべきハラスメント防止対策について解説します。基本方針の策定と周知、カスハラ・パワハラ対応マニュアルの作成、セクハラ・マタハラ防止のための社内ルールと教育、職員のメンタルヘルスケアと相談体制の充実など、組織的な取り組みが求められます。

介護業界に特化したハラスメント研修のプランも紹介しています。介護事業者がハラスメント防止に真摯に取り組むことで、職員が安心して働ける環境が整い、利用者へのより良いサービス提供につながるでしょう。
介護現場でハラスメント研修が必要な3つの理由
介護の現場で、ハラスメント対策がこれまで以上に重要視されています。それは単に職場の雰囲気を良くするためだけではありません。法令の遵守、人材の確保、そしてサービスの質を保つという、施設運営の根幹に関わる重要な課題だからです。ここでは、なぜ今、介護現場でハラスメント研修が急務とされているのか、その3つの具体的な理由を解説します。
【法改正】事業者に求められるハラスメント防止措置の義務化
最も大きな理由の一つが、法改正による事業者の責任強化です。2022年4月から、パワーハラスメント防止措置がすべての中小企業にも義務化されました。これに先立ち、介護報酬改定においてもハラスメント対策の強化が明記され、すべての介護サービス事業者に対して、ハラスメント防止のための必要な措置を講じることが義務付けられています。具体的には、事業主の方針の明確化と周知・啓発、相談体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応などが求められます。これは「知らなかった」では済まされない、法的な責務なのです。研修の実施は、この責務を果たすための極めて有効な手段となります。
職員の離職防止と人材定着への貢献
深刻な人手不足に悩む介護業界にとって、職員の離職は非常に大きな痛手です。そして、その離職の背景には、人間関係のストレスやハラスメントが隠れているケースが少なくありません。利用者やその家族からの過度な要求(カスタマーハラスメント)や、職員間のパワーハラスメントは、職員の心身を疲弊させ、働く意欲を奪います。組織としてハラスメントを許さないという明確な姿勢を示し、具体的な対処法を学ぶ研修を行うことは、職員に安心感を与えます。働きやすい環境が整うことで、結果的に離職率の低下と人材の定着につながり、安定した施設運営が実現できるのです。
介護サービスの質の維持・向上
職員がハラスメントの不安を抱えながら働いている状態で、質の高い介護サービスを提供することは困難です。精神的なストレスは、職員の集中力や判断力を低下させ、利用者への対応の質の低下や、思わぬ事故につながる危険性もはらんでいます。ハラスメント研修を通じて、職員一人ひとりが尊厳を守られ、安心して働ける環境を構築することは、巡り巡って利用者へのサービスの質を高めることになります。職員がいきいきと働ける職場は、利用者にとっても心地よい場所となるのです。
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは?
介護現場で特に深刻化しているハラスメントが、利用者やその家族から受ける「カスタマーハラスメント(カスハラ)」です。厚生労働省は、カスハラを「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」と定義しています。
簡単に言えば、正当なクレームの範囲を逸脱した、以下のような迷惑行為全般を指します。
- 理不尽な要求や、過剰なサービスの強要
- 暴言や脅迫、威圧的な態度
- 身体的な暴力や、性的な言動
介護サービスは人と人との密接な関係性の中で提供されるため、他の業種に比べてカスハラが起こりやすい特性があります。職員が「利用者様・ご家族様だから」と我慢を重ね、心身ともに疲弊してしまうケースが後を絶ちません。職員を守り、質の高いサービスを維持するためにも、組織としてカスハラに立ち向かう姿勢が不可欠です。
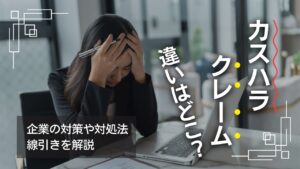
介護現場で起こりやすいハラスメントの種類
介護現場で発生するカスタマーハラスメントは、大きく「身体的暴力」「精神的暴力」「セクシュアルハラスメント」の3つに分類できます。ここでは、それぞれの具体的な行為について解説します。
身体的暴力
身体的暴力は、職員の生命や身体の安全を直接的に脅かす、最も悪質性の高いハラスメントです。いかなる理由があっても決して許される行為ではなく、場合によっては警察への通報も必要となる犯罪行為です。
- 介助中に殴る、蹴る、叩く、つねる
- 物を投げつけられる
- 腕や衣服を強く掴まれて離してもらえない
- 髪を引っ張られる
- 杖や車椅子などで威嚇されたり、実際にぶつけられたりする
精神的暴力
精神的暴力は、目に見える傷は残りませんが、暴言や威圧的な態度などによって職員の心を深く傷つけ、精神的に追い詰める行為です。繰り返し受けることで、職員は自信を失い、休職や離職につながるケースも少なくありません。
- 「馬鹿野郎」「役立たず」「辞めちまえ」といった人格を否定するような暴言を吐く
- 大声で怒鳴りつけたり、威圧的な態度をとったりする
- 「誠意を見せろ」などと言って土下座を強要する
- 介護保険サービスの範囲を超えた、理不尽な要求(個人の買い物、庭の掃除など)を繰り返し行う
- 職員個人の携帯電話番号をしつこく聞いたり、勤務時間外に何度も電話をかけてきたりする
セクシュアルハラスメント
セクシュアルハラスメントは、相手の意に反する性的な言動を指します。介助に伴う身体的な接触が多い介護現場の特性上、問題が表面化しにくい側面もありますが、職員の尊厳を著しく傷つける行為です。性別に関わらず、すべての職員が被害者になる可能性があります。
- 介助の必要がないのに、胸や尻、太ももなどを執拗に触る
- 体をじろじろと舐めるように見る
- 「恋人はいるのか」「スリーサイズは?」など、プライベートな性的事柄についてしつこく質問する
- わいせつな冗談を言ったり、自分の性体験を話したりする

ハラスメントとBPSD(認知症の行動・心理症状)の違い
介護現場では、認知症の利用者に見られるBPSD(認知症の行動・心理症状)とハラスメントを混同してしまうケースがあります。BPSDは、認知症による脳の機能障害に起因する症状であり、利用者本人の意思とは関係なく現れるものです。
一方、ハラスメントは、相手を傷つけたり、尊厳を損ねたりする意図を持った言動を指します。介護職員は、BPSDとハラスメントを適切に見分け、それぞれに合った対応を取ることが重要です。
BPSDへの対応には、認知症ケアの専門的な知識とスキルが必要です。多職種連携によるアセスメントを行い、利用者の個別性に配慮したケアプランを立てることが求められます。場合によっては、環境や職員の対応指針から変えていく必要があります。
お客様の課題やカリキュラムに応じてお見積りパターンをご提案しています。
まずは気軽にご相談ください!
お電話でのお問い合わせ 0120-117-450
専任のコンサルタントが丁寧にご相談を受け付けます。
お気軽にご相談ください。
介護事業者が取り組むべきハラスメント防止対策
介護現場でのハラスメントは、職員のモチベーションや職場の雰囲気に大きな影響を与えるため、事業者による積極的な防止策が不可欠です。ハラスメント防止のためには、職員に対して定期的な研修を実施し、早期の問題発見と対処を促す体制を整えることが重要です。
ハラスメント防止に向けた基本方針の策定と周知徹底
ハラスメント防止の第一歩は、事業者が明確な基本方針を打ち出すことです。ハラスメントを許さない姿勢を示し、利用者・家族や職員に対して周知徹底することが重要です。
具体的には、以下のような内容を盛り込んだ基本方針を策定し、事業所内に掲示するなどして周知を図ります。
- ハラスメントの定義と具体例
- ハラスメントを許容しない方針
- ハラスメント発生時の対応方法
- 相談窓口の設置と連絡先
- ハラスメント防止のための研修の実施
職員のメンタルヘルスケアと相談体制の充実
ハラスメントは、被害者の心身の健康に深刻な影響を与えます。介護事業者は、職員のメンタルヘルスケアと相談体制の充実に努める必要があります。
具体的には、以下のような取り組みが考えられます。
- 社内・社外の相談窓口の設置と周知
- 定期的なストレスチェックの実施
- メンタルヘルス不調者への早期支援体制の整備
- 職場環境の改善に向けた取り組みの推進
- ハラスメント被害者のための休暇制度の整備
職員が安心して相談できる体制を整え、ハラスメントによるメンタルヘルスの不調を早期に発見・対応することが重要です。
【無料】資料ダウンロード
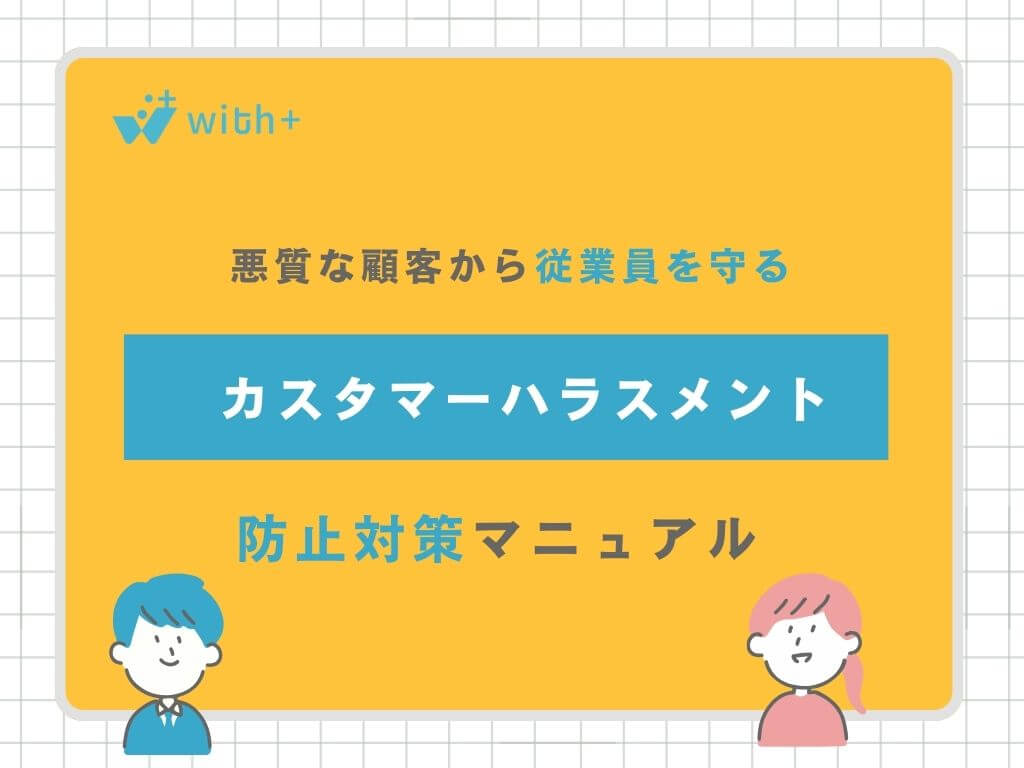
カスハラ防止対策マニュアル
従業員のに大きな負担を与える「カスハラ(カスタマーハラスメント)」本資料では、そもそもどういった行為がカスハラに該当するのか、
ハラスメント研修の企画・実施のポイント
厚生労働省は2021年度の介護報酬改定で、介護事業所に対しハラスメント対策の強化を義務付けました。具体的には、基本方針の周知、マニュアルの作成と研修、相談窓口の設置などが求められています。
ハラスメント研修を企画・実施する際には、管理職と一般職員それぞれに合わせた内容を盛り込むことが重要です。以下では、それぞれの立場に応じた研修のポイントを解説します。
完全オーダーメイドのプログラム設計
お悩み・課題を丁寧にヒアリングし、最適な研修をプランニング!
・講師派遣型、日程・場所・時間・ご予算・オンライン・オフラインなどを、自由に設定できる
・受講者のシフトに合わせ、土日対応もOK。
・受講者の負担を考え、現場のシフトに配慮致します。
管理職向け:ハラスメントの早期発見と適切な対処法
管理職は、部下からのハラスメント相談に適切に対応できるよう、ハラスメントの知識を深める必要があります。研修では、以下のようなトピックを取り上げることが効果的です。
- ハラスメントの定義と具体例
- ハラスメントが与える影響と重大性
- ハラスメントを察知するサイン
- 部下からの相談への対応方法
- ハラスメント発生時の適切な対処手順
また、管理職自身がハラスメントを行わないよう、自己の言動を振り返る機会を設けることも大切です。パワハラにつながりやすい言動や、セクハラと受け取られかねない発言などについて、具体例を交えて解説するとよいでしょう。
一般職員向け:ハラスメントの予防とセルフケア
一般職員向けの研修では、ハラスメントを予防し、万が一被害にあった場合の対処法を身につけることを目的とします。研修内容としては、以下のようなものが考えられます。
- ハラスメントの種類と特徴
- ハラスメントを受けたときの対処法
- ハラスメントを目撃したときの行動
- ストレスマネジメントとセルフケア
- 相談窓口の利用方法
介護現場で起こりやすいカスタマーハラスメントについては、利用者や家族の特性を理解し、適切なコミュニケーションを取ることの重要性を伝えます。一方で、職員の安全と尊厳を脅かす行為は断固として拒否すべきであることも強調します。
研修効果を高めるためのロールプレイングと事例討議
ハラスメント研修では、講義形式だけでなく、ロールプレイングや事例討議を取り入れることで、学びを深めることができます。ロールプレイングでは、ハラスメント場面を疑似体験し、適切な対応を練習します。事例討議では、実際のハラスメント事例をもとに、グループで対応策を検討します。
これらの参加型の手法を活用することで、受講者の主体的な学びを促し、研修内容の定着を図ることができます。また、職場での具体的な行動変容にもつなげやすくなります。
| 研修対象 | 研修内容 | 研修手法 |
|---|---|---|
| 管理職 | ハラスメントの早期発見と適切な対処法 | 講義、事例討議 |
| 一般職員 | ハラスメントの予防とセルフケア | 講義、ロールプレイング |
こうした研修は一回きりで終わらせず、定期的に実施することで、ハラスメントのない健全な職場環境を維持していくことが求められます。
介護現場のハラスメント対策に役立つ情報と支援制度
介護現場でのハラスメント対策には、事業者だけでなく外部の支援制度を活用することも有効です。厚生労働省が提供するハラスメントに関するガイドライン等を取り入れることで、職員がハラスメントに対する理解を深め、予防策を強化できます。
厚生労働省の職場におけるハラスメント防止対策の指針
厚生労働省は、職場におけるハラスメント防止対策の指針を定め、事業者に対して適切な措置を講じることを求めています。この指針は、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止を目的としており、介護事業者もこれに従う必要があります。
指針では、事業者が以下の措置を講じるよう求めています。
- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるハラスメントの事後の迅速かつ適切な対応
- 併せて講ずべき措置(相談者・行為者のプライバシー保護、不利益取扱の禁止など)
介護事業者は、これらの措置を適切に実施し、職場におけるハラスメントを防止するための体制を整備する義務があります。
介護事業者向けハラスメント対策助成金の活用法
介護事業者がハラスメント対策を進める上で、活用できる助成金制度があります。厚生労働省が設けている「職場環境改善計画助成金」は、職場環境の改善を目的とした取り組みに対して、その費用の一部を助成する制度です。
この助成金の対象となる取り組みには、以下のようなものがあります。
- ハラスメント防止対策に関する社内研修の実施
- ハラスメント相談窓口の設置や担当者の配置
- ハラスメント防止に関する社内規程の整備
- 職場環境改善のための従業員アンケートの実施
介護事業者は、これらの取り組みを計画的に実施し、助成金を活用することで、効果的にハラスメント対策を進めることができます。
専門家による介護施設のハラスメント対策コンサルティング
介護施設におけるハラスメント対策を進める上で、専門家によるコンサルティングを活用することも有効です。ハラスメント対策に精通した社会保険労務士や産業カウンセラーなどの専門家は、介護事業者の実情に合わせたアドバイスを提供し、効果的な対策の立案と実行を支援します。
専門家によるコンサルティングでは、以下のような内容が含まれます。
- 職場環境の評価とハラスメントリスクの洗い出し
- ハラスメント防止規程の整備と周知方法のアドバイス
- 管理職向けのハラスメント防止研修の企画と実施
- ハラスメント相談対応スキルの向上に向けた指導
介護事業者は、専門家の知見を活かすことで、自社の状況に即したハラスメント対策を効率的に進めることができるでしょう。
お客様の課題やカリキュラムに応じてお見積りパターンをご提案しています。
まずは気軽にご相談ください!
お電話でのお問い合わせ 0120-117-450
専任のコンサルタントが丁寧にご相談を受け付けます。
お気軽にご相談ください。
まとめ
介護現場では、カスタマーハラスメント、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントが深刻な問題となっており、介護職員の心身の健康や介護サービスの質に大きな影響を及ぼしています。
そのため、ハラスメント防止に向けた基本方針の策定と周知徹底、カスハラ・パワハラ対応マニュアルの作成、セクハラ・マタハラ防止のための社内ルールと教育、職員のメンタルヘルスケアと相談体制の充実など、組織的な取り組みが求められます。
介護業界に特化したハラスメント研修をお探しの際は、ガイアシステムにお任せください。
ガイアシステムのハラスメント研修は、業界に合わせたスキルの習得を目指し、研修価値を最大化するために、完全カスタマイズのカリキュラムを設計します。
貴社だけの特別なカリキュラムで実施する効果の高いハラスメント研修をご提案しています。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
【無料】資料ダウンロード
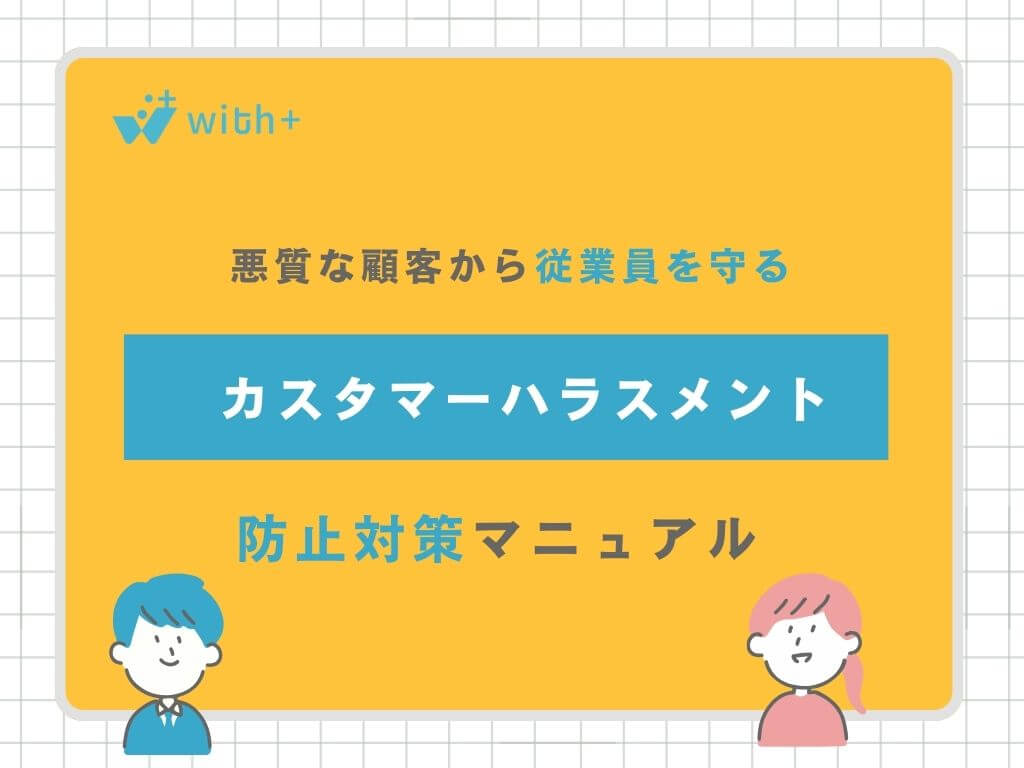
カスハラ防止対策マニュアル
従業員のに大きな負担を与える「カスハラ(カスタマーハラスメント)」本資料では、そもそもどういった行為がカスハラに該当するのか、
ハラスメント研修カリキュラム
従業員をクレーマーから守り、組織の対応力向上を目指す!
カスタマーハラスメント研修|対応力強化
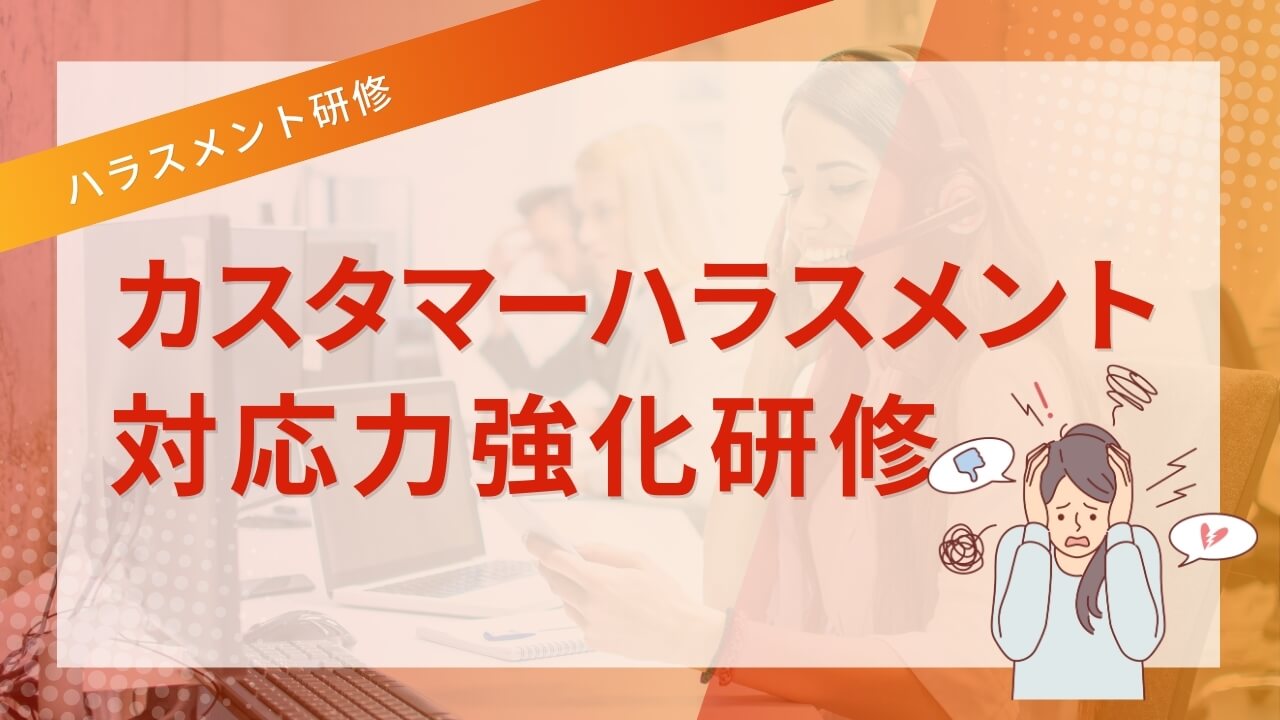
従業員に大きなストレスを与え、離職の原因にもなっているカスタマーハラスメント。個人の能力では解決できないケースも多く、組織が一体となってリスク回避することが必要です。
本研修はカスタマーハラスメントの理解と対応力を強化することを目的に、コミュニケーションスキルを学び、実践的なグループワークを通じて具体的な対策を考えます。
ハラスメントの未然防止、環境改善を目指す!
ハラスメント研修 |パワハラ防止対策
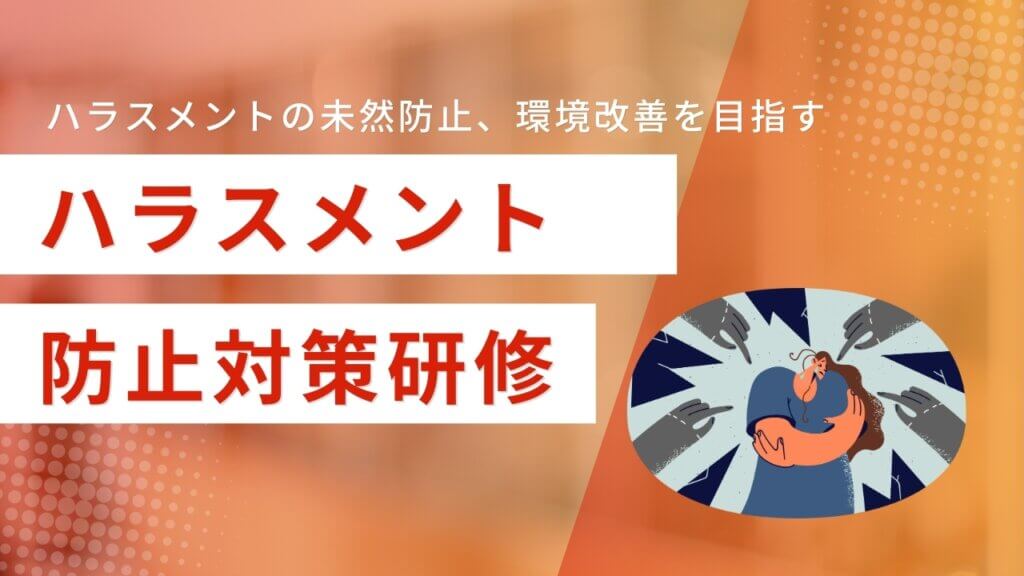
セクハラ、パワハラ、マタハラなど様々なハラスメントの定義や具体例、日常に潜むハラスメントリスクについて学びます。
「グレーゾーンと思われがちな事例紹介」やケーススタディを通じてハラスメントの識別方法を習得し、グループディスカッションで防止策を考案します。また、ハラスメントが起きた際の適切な対応方法や報告手順を身に着けます。
心のメンテナンス手法を習得
メンタルヘルス研修|ストレスと上手に向き合うには
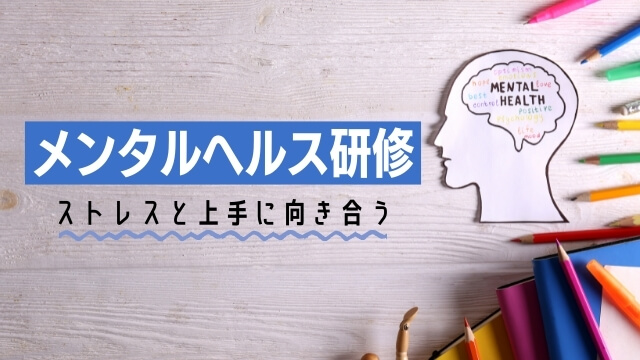
メンタルヘルスに対する知識を身につけ、自分の心の状態を確認し、自らに合ったメンテナンス手法を習得していきます。
・メンタルヘルス研修 全従業員対象 基礎編
・メンタルヘルス研修 役職対象 ラインケア編
・メンタルヘルス研修 全従業員対象 セルフケア編
上記を事例に、内容別・対象別に様々な研修カリキュラムを取り揃えております。
ハラスメントコラム一覧
-
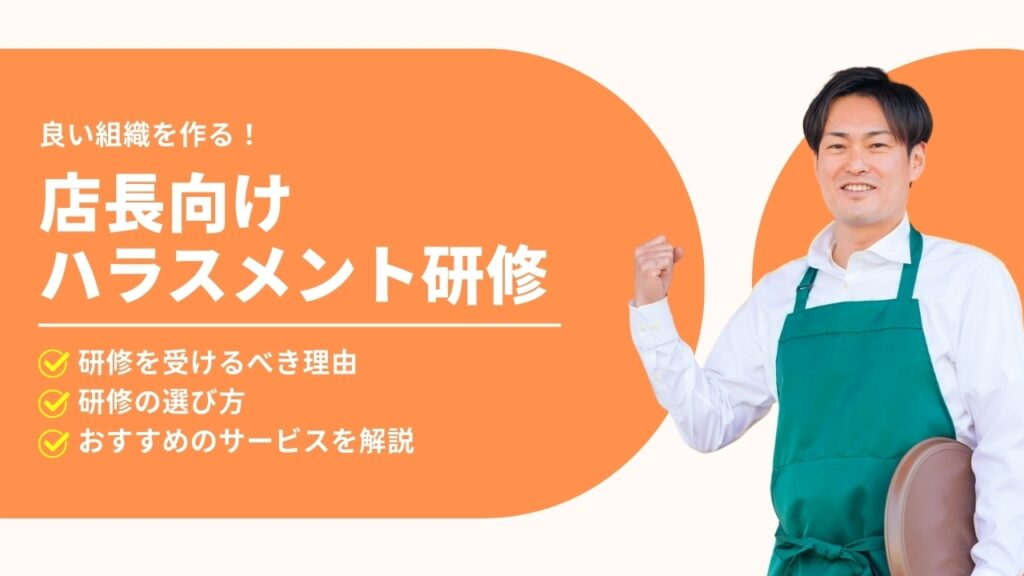
良い組織を作る!店長向けハラスメント研修のポイントを解説
-
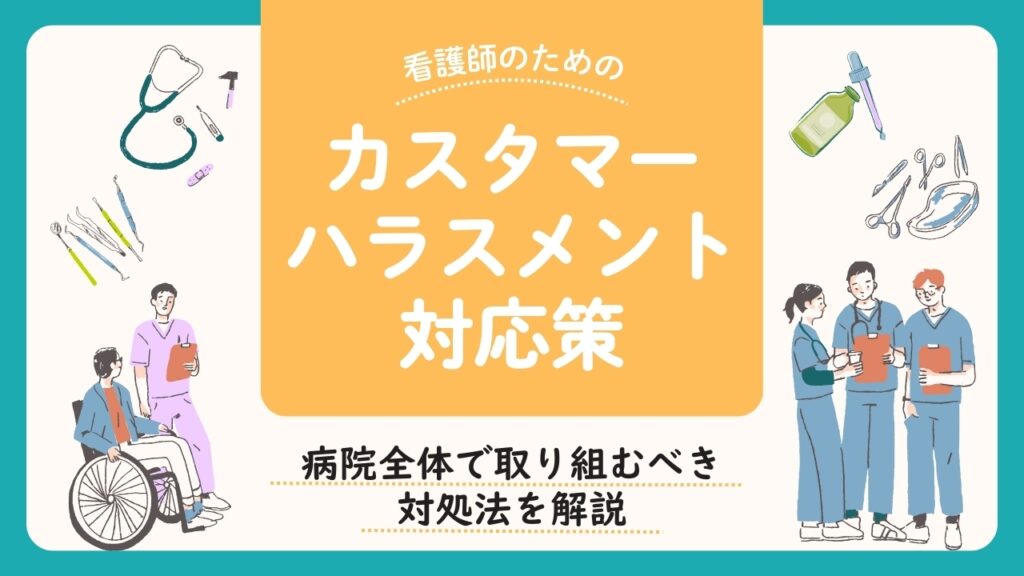
看護師のためのカスタマーハラスメント対応策!対処法を解説
-
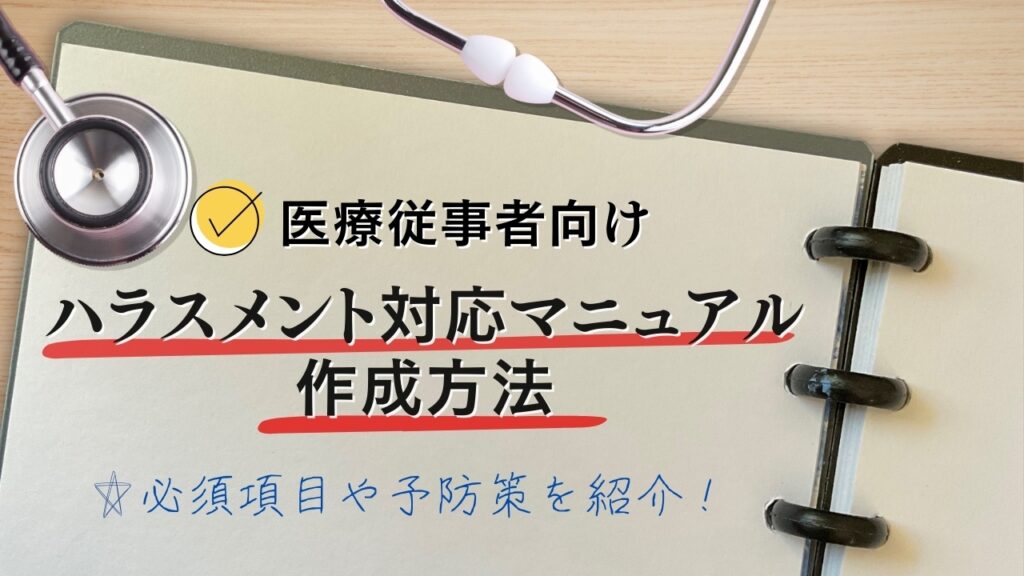
医療従事者向けのハラスメント対応マニュアルの作成方法は?必須項目や予防策を紹介
-

介護施設のクレーム対応研修はなぜ必要?目的やポイントを徹底解説
-
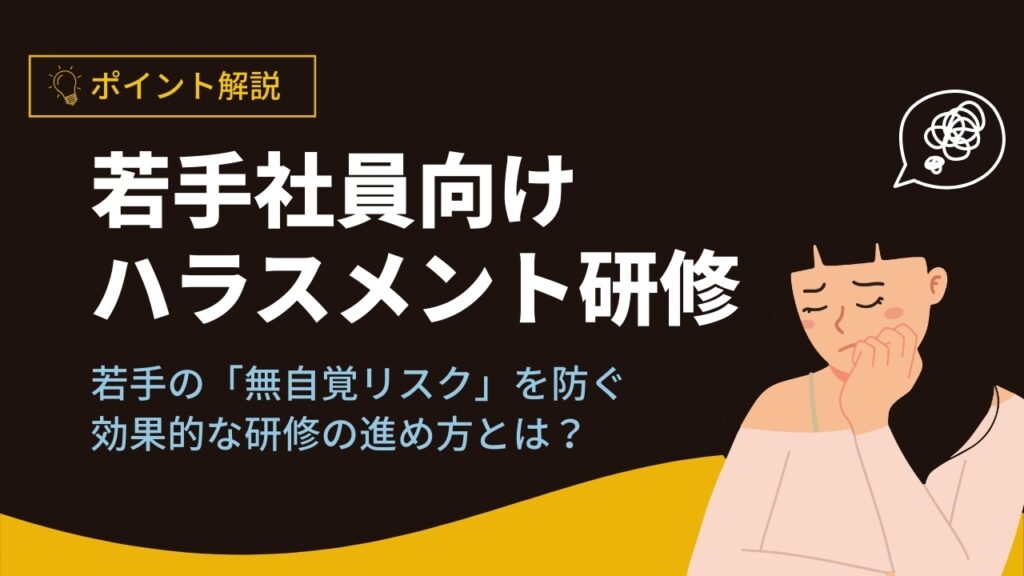
若手社員向けハラスメント研修のポイント解説!効果的な進め方とは
-
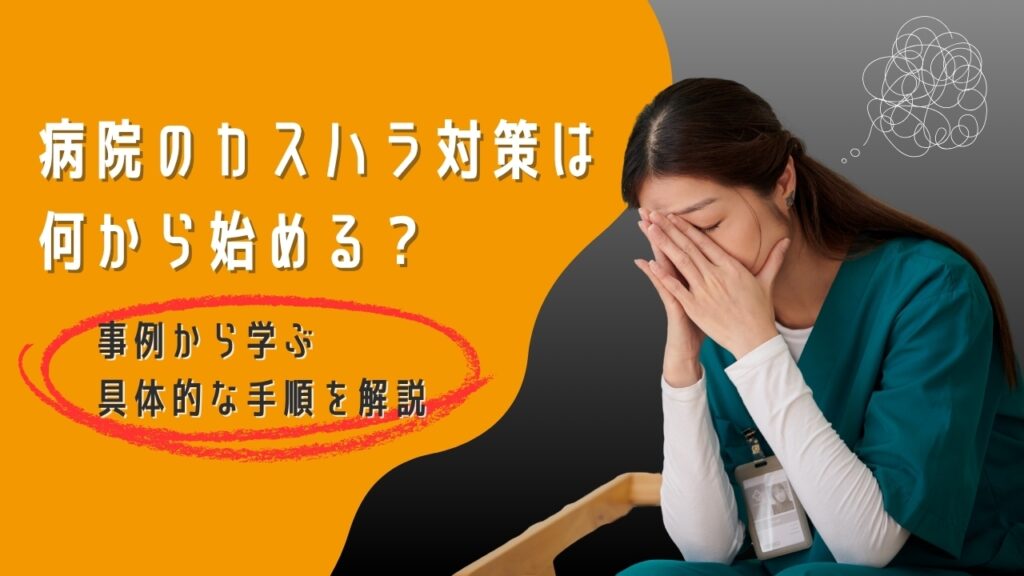
病院のカスハラ対策は何から始める?事例から学ぶ具体的な手順を解説
-
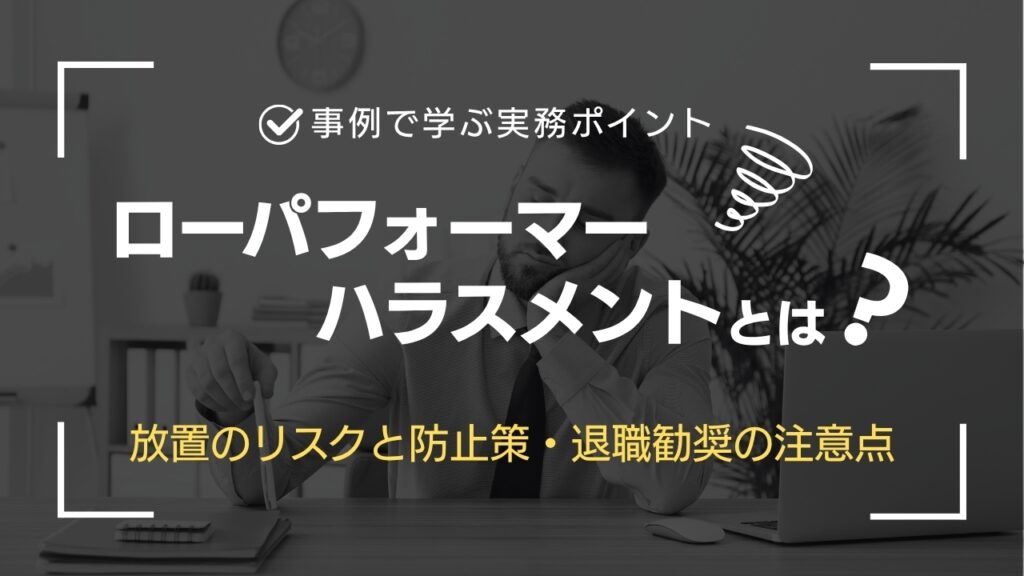
ローパフォーマーハラスメントとは?放置のリスクと防止策・退職勧奨の注意点
-
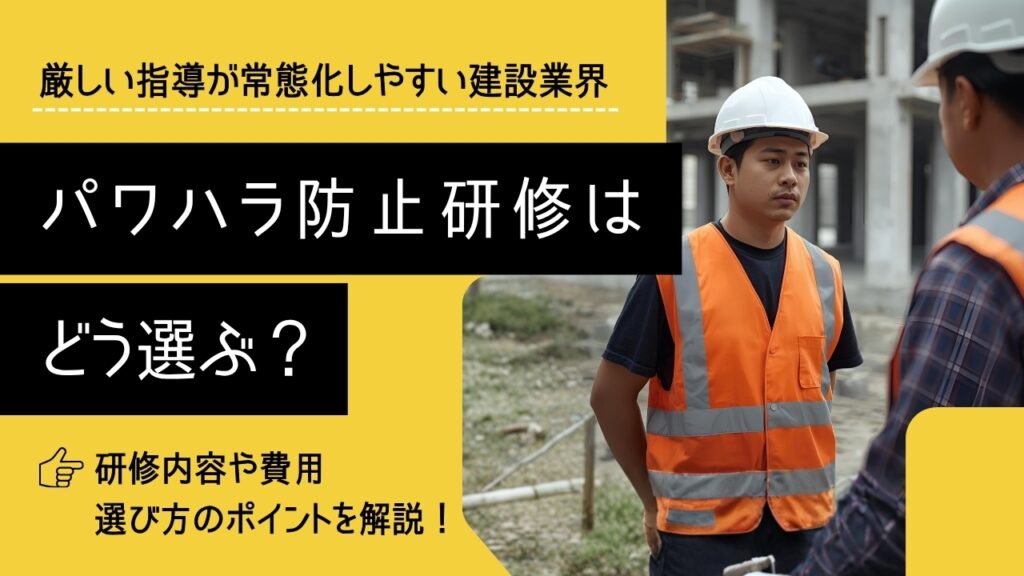
建設業のパワハラ防止研修はどう選ぶ?研修内容や費用、選び方のポイントを解説
-
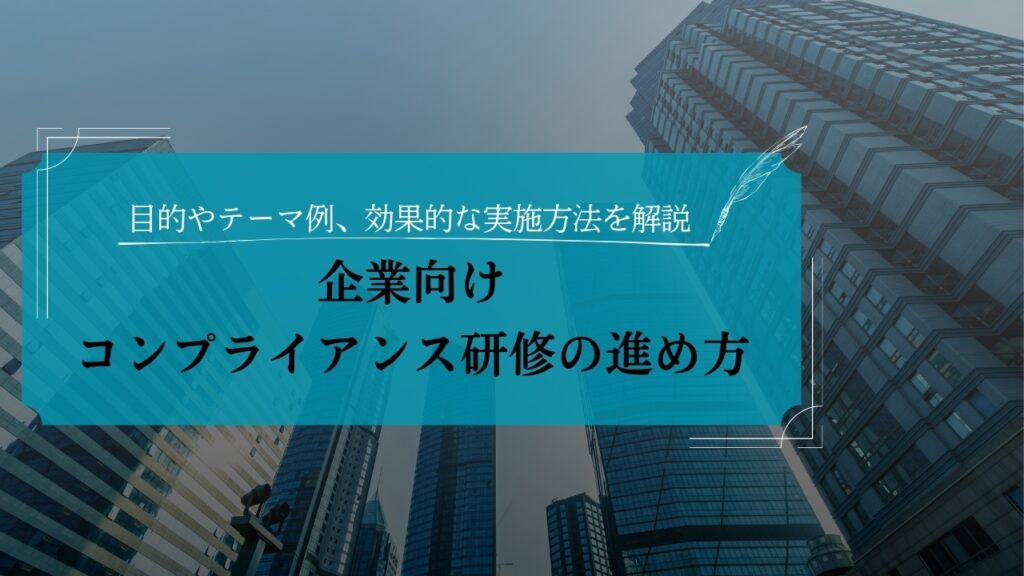
企業向けコンプライアンス研修の進め方!目的やテーマ例、効果的な実施方法を解説
-
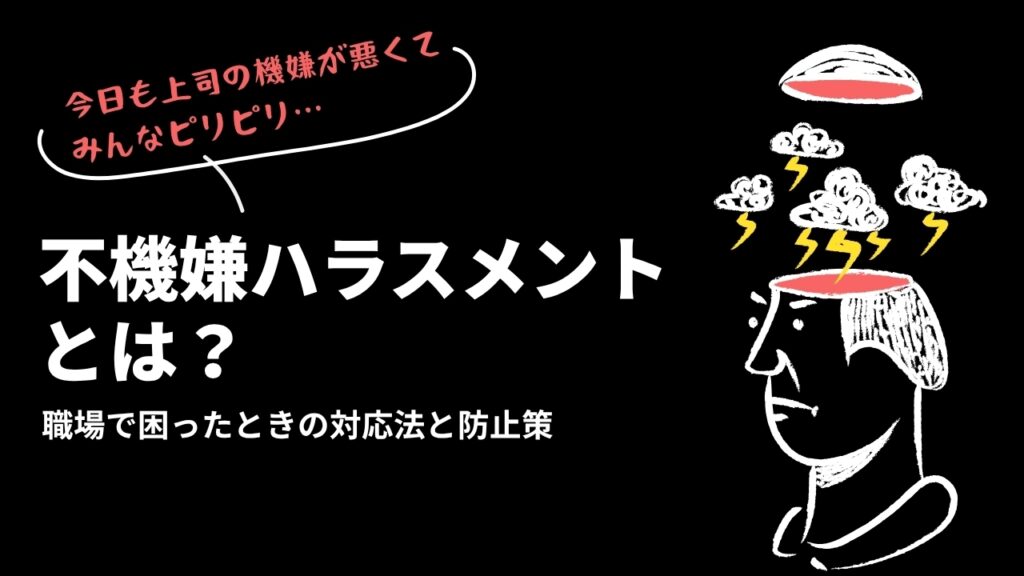
不機嫌ハラスメントとは? 職場で困ったときの対応法と防止策
-

パーソナルハラスメントとは?職場での定義と防止策を解説
-
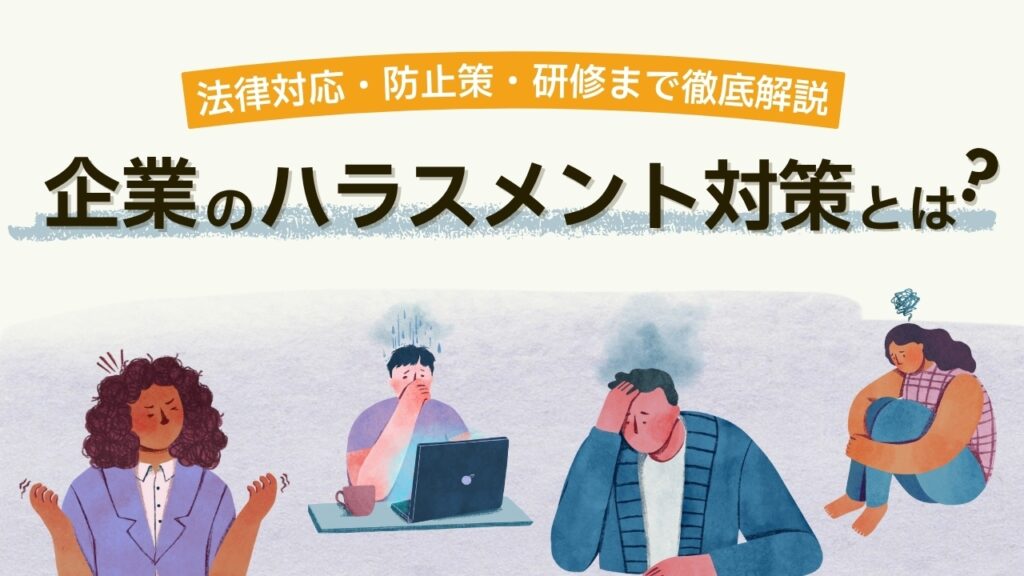
企業のハラスメント対策とは?法律対応・防止策・研修まで徹底解説
-
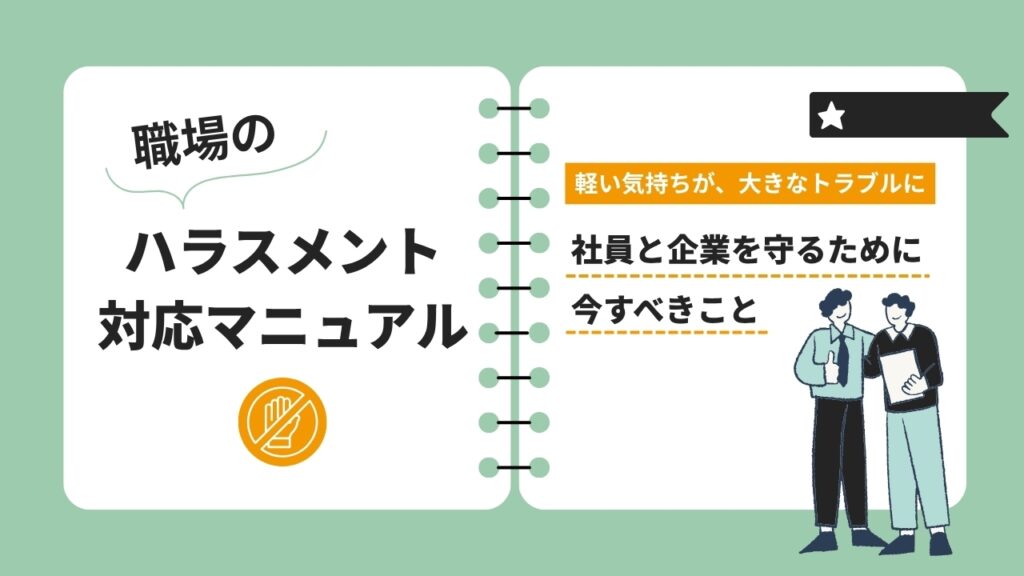
職場のハラスメント対応マニュアル|社員と企業を守るために今すべきこと
-
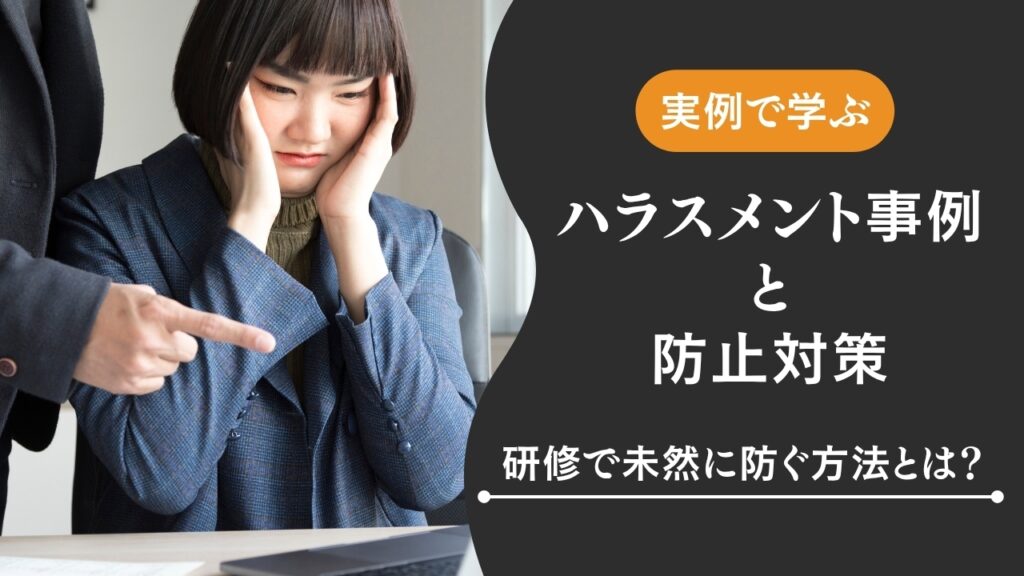
【実例で学ぶ】職場のハラスメント事例と防止対策|研修で未然に防ぐ方法とは?
-
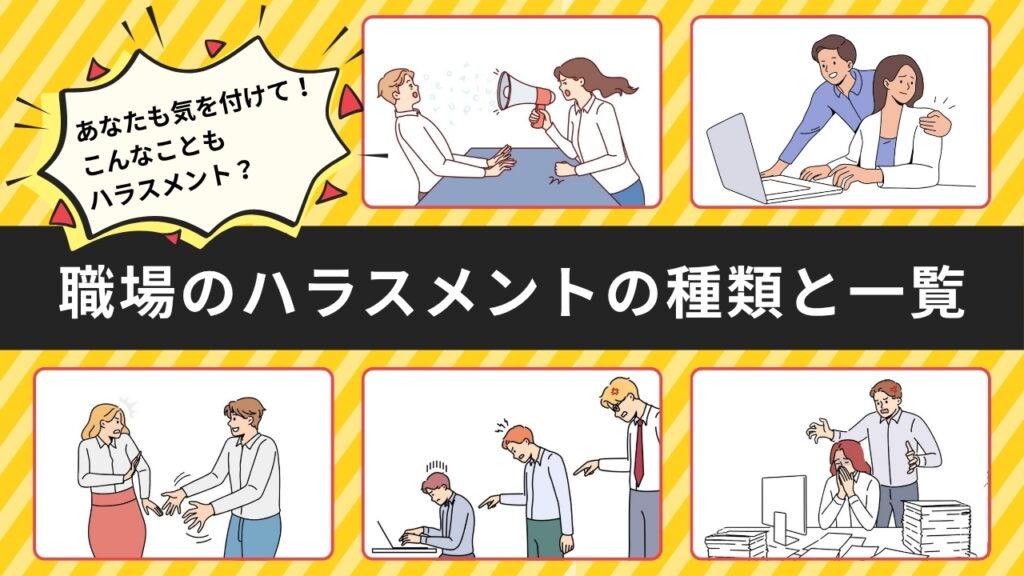
【職場のハラスメントの種類・一覧】あなたも気を付けて!こんなこともハラスメント?
-
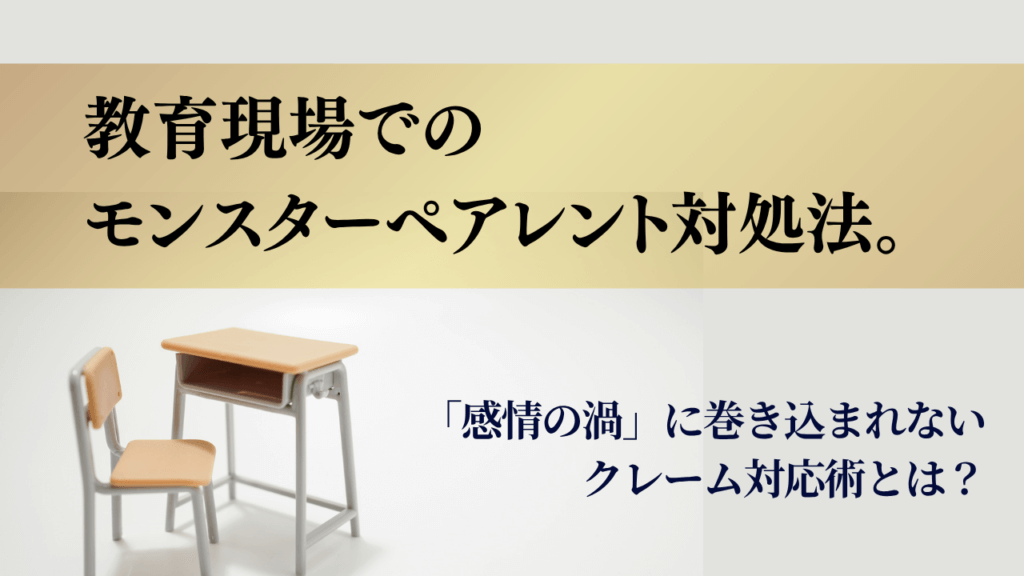
教育現場でのモンスターペアレント対処法。「感情の渦」に巻き込まれないクレーム対応術、効果的な研修法は?
-
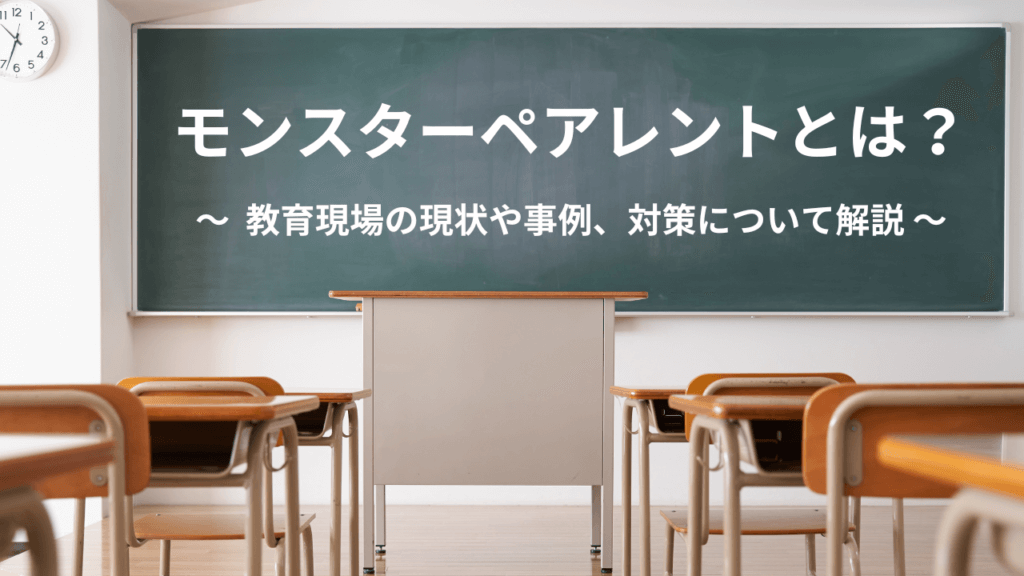
モンスターペアレントとは?教職員を守るためのハラスメント対策について解説
-

カスタマーハラスメント研修とは?研修内容やカスハラを防ぐための取り組み
-
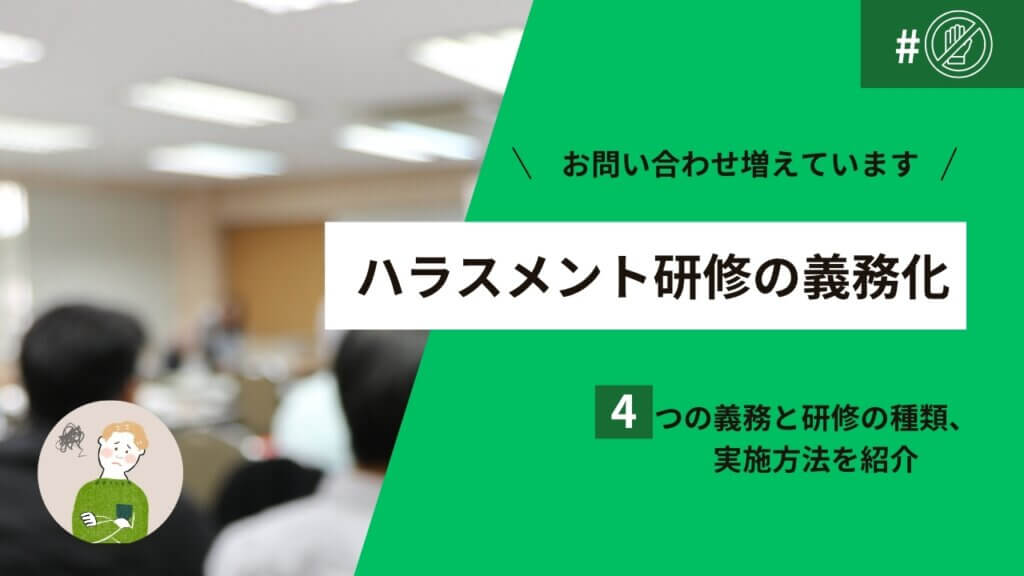
ハラスメント研修の義務化について!4つの義務と研修の種類、実施方法を紹介
-

【2025年最新】パワハラ防止法対応|おすすめハラスメント研修会社を比較!失敗しない選び方とは?
-
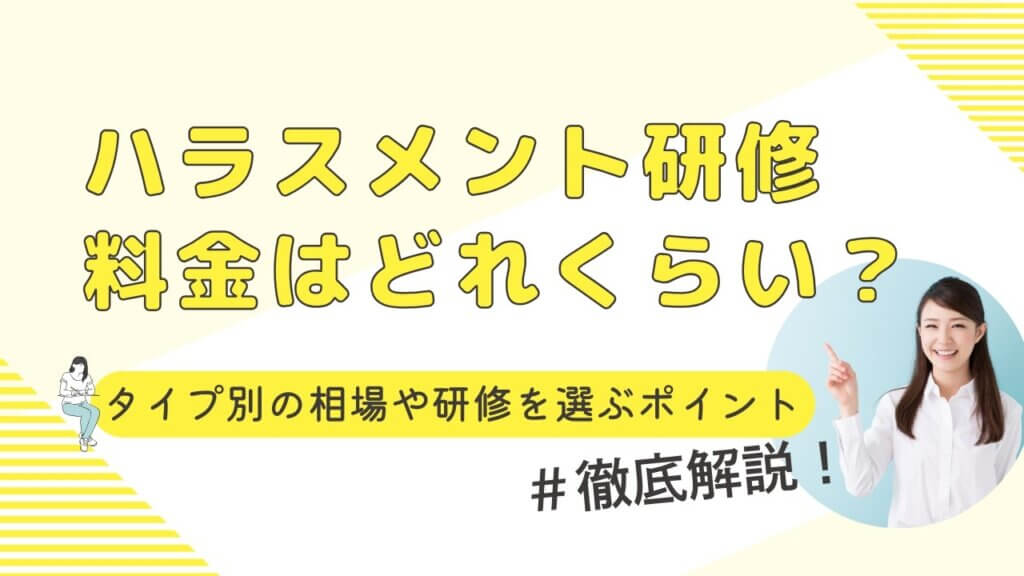
ハラスメント研修の料金はどれくらい?タイプ別の相場や研修を選ぶポイント
-

飲食店のカスハラ対策|事例で学ぶ顧客対応と研修のすすめ
-

病院でのカスハラ事例|医療現場でのリスク対策と研修の必要性
-

介護のカスタマーハラスメント対策とは?介護現場の実態や発生原因も解説!