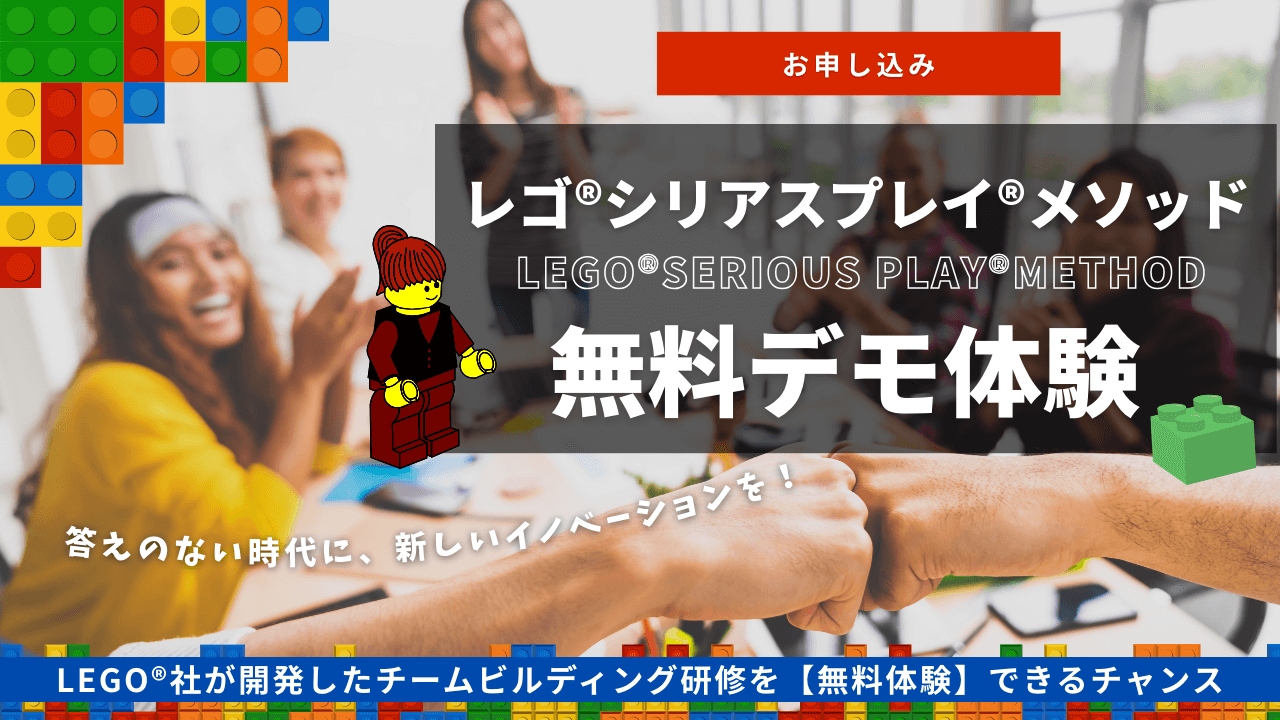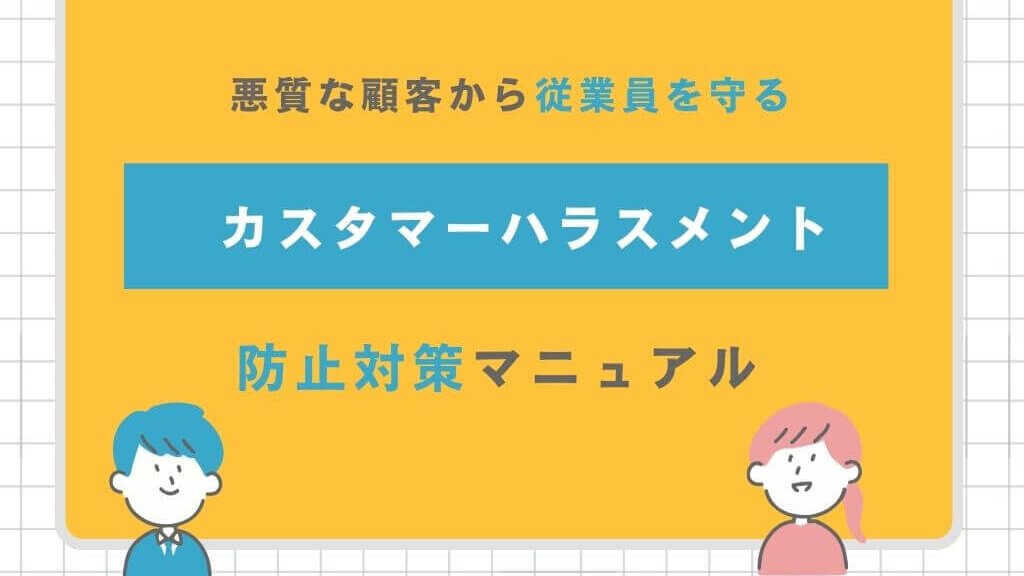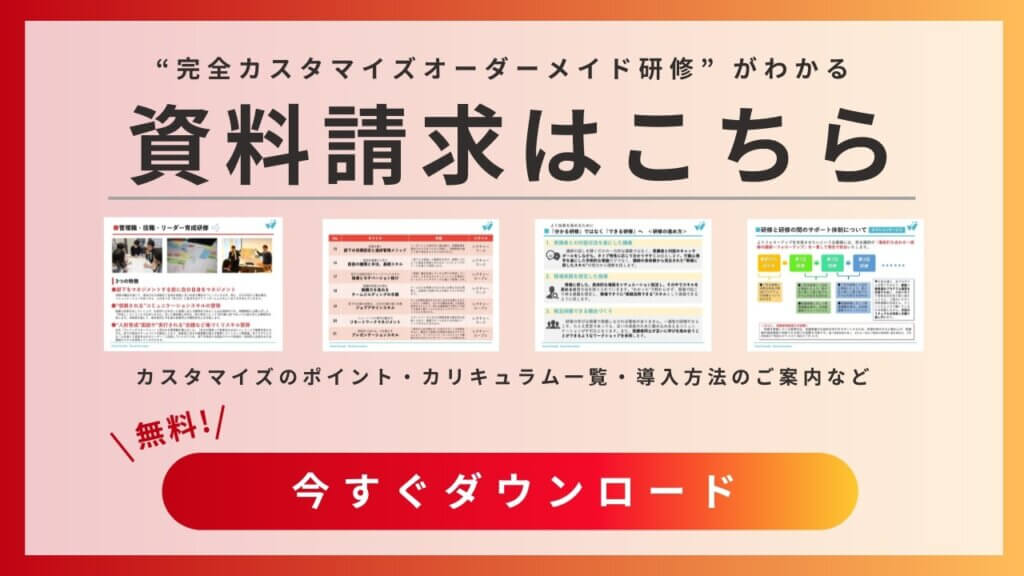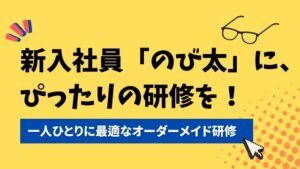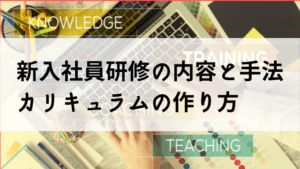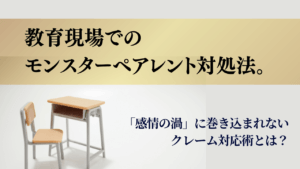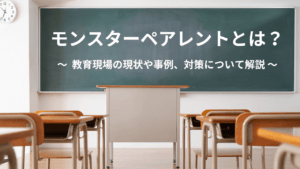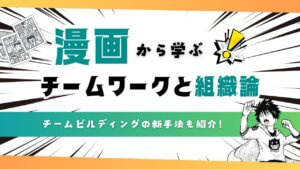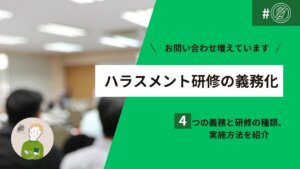【2025年最新】企業研修のトレンド解説!次世代人材を育てる10のキーワードと成功の秘訣
急速に変化するビジネス環境では、従来型の研修だけでは時代の要請に応えられません。最新の知識やスキルを習得し、市場の変化や顧客ニーズに柔軟に対応できる人材の育成が、従業員のモチベーションやチームの結束力向上、イノベーションの促進にもつながり、企業の競争力維持にとって重要です。
そこで今回は、2025年最新の企業研修トレンドを、人事・研修担当者向けに徹底解説します。DX人材育成、リスキリング、DE&I、Z世代向け研修など、今押さえるべき10大テーマを厳選。オンラインと対面を組み合わせたハイブリッド研修やマイクロラーニングといった最新手法、成功事例も紹介します。
なぜ今、企業研修に「トレンド」の視点が不可欠なのか?

VUCA時代を乗り越えるための人材戦略
不確実性が高まるVUCA時代、企業にはこれまで以上に柔軟で迅速な対応力が求められています。従来の一律的な人材育成では、環境変化に追随することは困難です。こうした背景のもと、トレンドを的確に捉えた企業研修が注目を集めています。アジャイル経営やリスキリングを取り入れた育成施策は、個々の適応力を高めると同時に、変化に強い組織づくりを支える基盤となります。
働き方の多様化と人材の流動化への対応
リモートワークの定着や副業解禁といった潮流により、働き方やキャリアの選択肢は大きく広がりました。これに伴い、人材の流動性も増加し、企業には多様な価値観やライフスタイルを受け入れる柔軟な体制が求められています。こうした変化に対応するには、多様性を前提とした研修設計が不可欠です。時代に即した育成投資は、優秀な人材の確保やエンゲージメント向上、さらにはイノベーション創出の土壌づくりにもつながります。
人的資本経営とDX推進の加速
近年、企業価値の源泉として「人的資本」が再評価されています。その中核をなすのが、DX(デジタルトランスフォーメーション)とリスキリングです。デジタル領域の知見を持つ人材の育成は、単なる業務効率化にとどまらず、企業の持続的成長を支える戦略的課題となっています。人的資本の情報開示が義務化される中、IT・DX領域の研修はますます重要性を増しており、企業の競争力強化において欠かせない投資と言えるでしょう。
【2025年版】人事担当者が押さえるべき企業研修10大トレンド

ここからは企業研修を実施検討する上で、押さえておくべきトレンドについて詳しくお伝えします。
①DX人材育成・ITリテラシー向上研修
デジタル変革の波が加速するなか、DX推進の担い手となる人材の育成は、企業の生存戦略そのものとなっています。まずは自社のデジタル成熟度と現場のITリテラシーを可視化し、段階的かつ体系的な研修を設計・実施することで、柔軟かつ機動力ある組織を形成できます。DX人材育成とITリテラシーの底上げが競争力のカギとなるなか、自社のDX進捗や従業員のITスキルを把握し、段階的な研修を設計することで、変化に柔軟に対応できる組織を構築できます
②リスキリング・アップスキリング
急速に変化するビジネス環境において、業務の変容や技術革新に対応するには、社員のスキル再習得・強化が不可欠です。現状のスキルギャップを見極め、実践に直結する継続的な研修を行うことで、即戦力化と持続的成長の両立が可能となります。
③次世代リーダー・管理職育成研修
次世代リーダーの育成が企業の未来を左右します。経営視点を備え、課題解決や意思決定ができる人材を育てるためには、実践的な課題解決やマネジメント力を強化する研修がおすすめ。早期からの意識醸成と戦略的な育成設計に取り組みましょう。
④Z世代・若手社員の定着と即戦力化
新卒や若手社員の中心を占めるZ世代は、「成長実感」や「つながり」を重視する傾向があります。Z世代を戦力化するための新しい育成アプローチとして、デジタルを活用した研修や同期とのつながりを強化することで、早期の定着と戦力化が図れます。
⑤DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)推進
多様性・公平性・包括性を基盤とするDE&Iは、企業の競争力と持続的成長に直結します。経営層から現場まで一貫性のある研修を通じて、心理的安全性の高い職場環境を構築し、個々の力を最大限に引き出す土壌を整えることが肝要です。
⑥ウェルビーイングとメンタルヘルス
従業員の心身の健康は、企業の生産性や組織の一体感に直結します。メンタルヘルスではストレスマネジメントやセルフコントロールなど、日常的な課題に対応する内容を盛り込みましょう。ウェルビーイングの実現が生産性と定着率を左右します。
⑦心理的安全性の醸成
失敗を恐れず挑戦できる風土の有無は、チームのパフォーマンスを大きく左右します。多様な意見を尊重し、発言しやすい文化を醸成するための取り組みは、イノベーションや協働を促します。心理的安全性を高める各種研修(チームビルディング研修、コミュニケーション研修等)が重要です。
⑧ハラスメント・コンプライアンス研修
ハラスメント・コンプライアンス意識の徹底が信頼を生みだします。
法令遵守と健全な職場環境維持のため、ハラスメント防止やコンプライアンス研修は必須です。全社員が正しい知識と倫理観を持つことで、トラブルの未然防止はもちろん、信頼される組織文化の形成にもつながります。
⑨コミュニケーションスキル向上
リモート化や多様化が進む今、組織の一体感や生産性を維持するうえで、対話力や傾聴力といった基本的なコミュニケーションスキルは再注目されています。対人関係の質が、チーム力と離職率を左右するといっても過言ではありません。コミュニケーションスキルを強化できる研修を実施し、組織力の土台を固めましょう。
⑩パーパス経営・企業理念浸透
企業の存在意義や価値観を全社員に共有し、共通の目的意識を持つことは、エンゲージメントの向上や組織の結束力に直結します。理念を“語る”だけでなく、“体験させる”仕掛けづくりが、パーパス経営を真に機能させる鍵です。
研修効果を最大化する手法・学習方法のトレンド
対面とオンラインの長所を活かした「ハイブリッド研修(ブレンディッドラーニング)」
働き方の多様化が進む中で注目されるのが、「ハイブリッド研修(ブレンディッドラーニング)」です。基礎知識の習得にはオンラインの柔軟性を、実践演習や対話には対面の双方向性を活かすことで、研修効果を最大化します。時間・場所にとらわれず自分のペースで学べるオンライン学習と、リアルな場でのフィードバックやチームビルディングの相乗効果により、学習定着と行動変容が促されます。また、遠隔地社員も参加しやすく、全社的な育成の平準化とコスト・時間の最適化にも寄与します。
スキマ時間で効率的に学ぶ「マイクロラーニング」
限られた時間の中で、継続的な学びを実現する手法として注目されているのが「マイクロラーニング」です。数分程度で完結する学習コンテンツを、日常業務のスキマ時間に取り入れることで、学習のハードルを下げ、習慣化を促進。動画・クイズ・チェックリストなど多様な形式で提供されることで、集中力を維持しながら知識の定着を図れます。反復学習にも効果を発揮し、現場での即時活用が可能な実践的スキルの習得が期待されます。
学習意欲を引き出す「ゲーミフィケーション・体験型学習」
受講者の主体性を引き出す手法として、「ゲーミフィケーション」と「体験型学習」への注目が高まっています。ゲーム要素を活用することで、楽しみながら自然と学びに没入できる環境を創出。一方、ロールプレイやケーススタディなどの体験を通じた学習は、応用力や問題解決力の育成に直結します。これらを組み合わせることで、学習意欲とエンゲージメントが向上し、個人の成長だけでなく、チームとしての連携強化や実行力の底上げにもつながります。
一人ひとりに最適化する「パーソナライズドラーニング」
多様な人材が活躍する現代の職場において、有効なアプローチが「パーソナライズドラーニング」です。AIやLMS(学習管理システム)を活用し、個々のスキルレベルや業務内容、関心に応じた学習設計を可能にします。得意・不得意の可視化によって最適な学習ルートを提示し、継続的なフィードバックが学習モチベーションを維持。個別最適化された学習体験は、離脱率の低下と早期戦力化を促し、組織全体の人材育成戦略において欠かせない要素となりつつあります。

トレンドを研修企画に活かすための3つのステップ

Step1. 自社の経営課題と人材課題を明確にする
まず、経営戦略や市場環境、組織の現状を分析し、自社が直面している経営課題や人材課題を洗い出します。たとえば、売上拡大、DX推進、人材流出防止など、経営層や現場の視点を交えて課題を可視化することが重要です。これにより、研修の方向性や優先度が明確になり、トレンドを活かした研修企画の土台が築かれます。
Step2. 研修の目的とゴール(KGI/KPI)を設定する
次に、明確になった課題に対し、研修の目的や達成すべきゴール(KGI)を設定します。KGIは最終目標を数値で定め、KPIはその達成に向けた中間指標として設定します。KPIツリーなどを活用し、目標達成までのプロセスを可視化することで、研修の効果測定や進捗管理が容易になります。
Step3. 費用対効果と対象者に合った手法を選定する
最後に、研修対象者の特性や学習スタイル、業務状況を踏まえ、ハイブリッド研修やマイクロラーニング、体験型学習など、費用対効果の高い手法を選定します。限られたリソースで最大限の成果を上げるために、最新トレンドを取り入れつつ、現場の実情に合った研修設計が求められます。

企業研修で活用できる助成金・補助金制度

企業が従業員の研修や人材育成を行う際に活用できる代表的な助成金・補助金制度について、2025年度の最新情報(2025年7月時点)をもとに解説します。
1. 人材開発支援助成金(厚生労働省)
企業が従業員に対して職業訓練や研修(OJT・OFF-JT)を実施した際、経費や賃金の一部が助成される国の制度です。中小企業・大企業ともに利用可能で、コースごとに助成内容が異なります。
◆主なコースと助成内容(2025年度)
| コース名 | 助成内容 | 助成率・上限額(中小企業) | 備考 |
| 人材育成支援コース | 職務に関連した知識・技能の習得訓練 | 経費:45%賃金:1人1時間800円上限:1,000万円/年 | 10時間以上のOFF-JT等 |
| 事業展開等リスキリング支援コース | 新分野進出やDX推進のための訓練 | 経費:75%賃金:1人1時間1,000円上限:1億円/年 | リスキリングに特化 |
| 教育訓練休暇等付与コース | 有給教育訓練休暇の導入 | 定額36万円 | 休暇制度の導入が条件 |
| 人への投資促進コース | 高度人材育成等 | 上限2,500万円/年 | 先端分野等 |
- 申請は訓練開始の6か月前~1か月前までに計画届を提出し、訓練終了後2か月以内に支給申請を行います。
- 助成対象となる訓練や条件はコースごとに異なりますので、詳細は「人材開発支援助成金」(厚生労働省)(最終アクセス:2025/07/04)を確認してください。
2. キャリアアップ助成金(厚生労働省)
非正規雇用労働者(契約社員・パート・アルバイト等)の正社員化や処遇改善、スキルアップを目的とした研修等に対して助成される制度です。
◆主なコース例
- 正社員化コース
- 賃金規定等改定コース
- 賞与・退職金制度導入コース
3. 自治体のスキルアップ助成金・補助金
◆東京都の例
| 制度名 | 助成内容 | 助成率・上限額 | 対象 |
| 事業内スキルアップ助成金 | 自社で企画した短時間研修 | 受講者数×研修時間数×760円上限150万円/年 | 都内中小企業等 |
| 事業外スキルアップ助成金 | 外部研修・eラーニング等 | 小規模:経費の2/3(上限25,000円/人)中小:経費の1/2(上限25,000円/人)上限150万円/年 | 都内中小企業等 |
| DXリスキリング助成金 | DX関連研修 | 経費の3/4(上限75,000円/人)上限100万円/年 | 都内中小企業等 |
※申請や詳細は各自治体の公式サイトや財団にてご確認ください。
4. 申請の流れと注意点
- 研修計画の立案
- 労働局や自治体への事前相談・計画届提出
- 研修実施(記録・証憑の保管)
- 研修終了後、所定期間内に支給申請
- 書類審査・助成金の受給
注意点
- 助成金は事前申請が必須です。研修実施後の申請は認められません。
- 研修内容や講師、受講者、実施方法などに細かな要件があります。
- 制度改正が頻繁に行われるため、最新情報を必ず確認してください。
人材開発支援助成金を中心に、キャリアアップ助成金や自治体独自のスキルアップ助成金など、企業研修に活用できる制度は多岐にわたります。自社の研修内容や目的に合った制度を選び、計画的に活用することが重要です。
まとめ
今回は、企業研修のトレンドについて解説しました。自社にあったものを考え、準備するのは大変かもしれませんが、「会社の未来」を育てるためには重要なものです。
なかなかリソースが割けないという現実があるかもしれませんが、運営などの任せられるところは委託してはいかがでしょうか。その分、企画に注力することができるためオススメです。
弊社では、準備からアフターフォローまでをコンサルタントが丁寧にサポートします。新入社員研修でお悩みの方は、ぜひご相談ください。