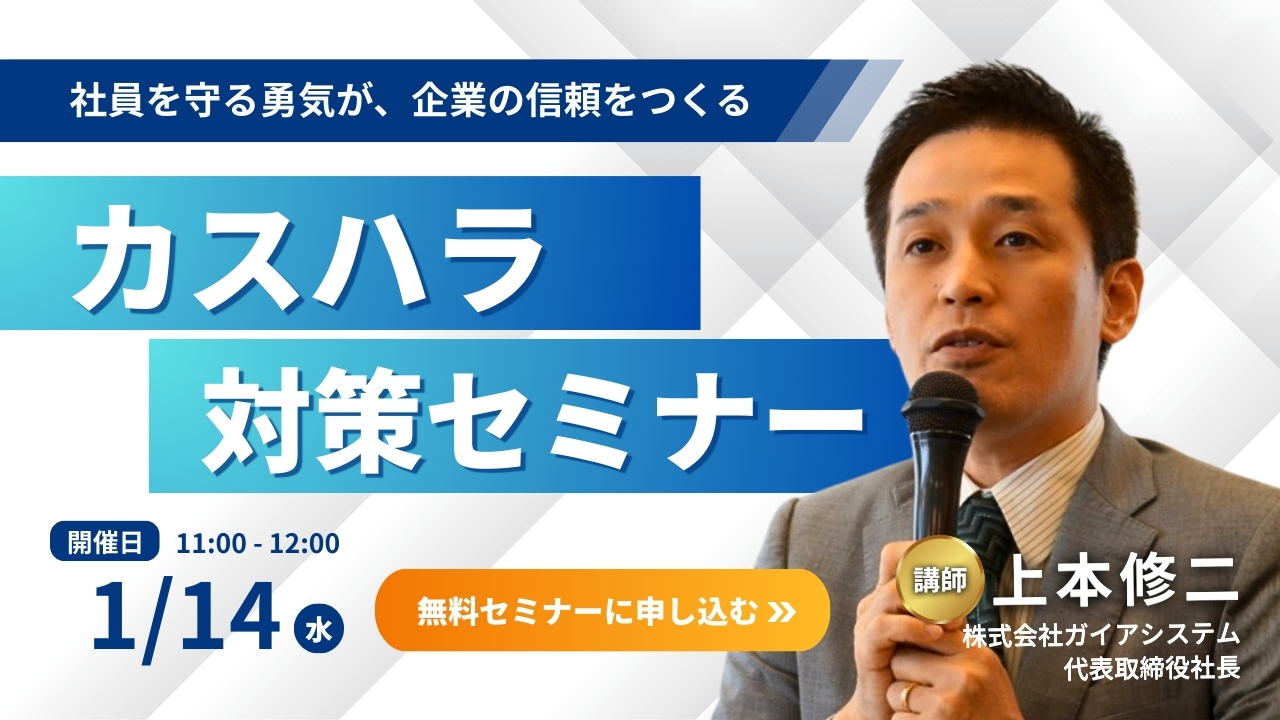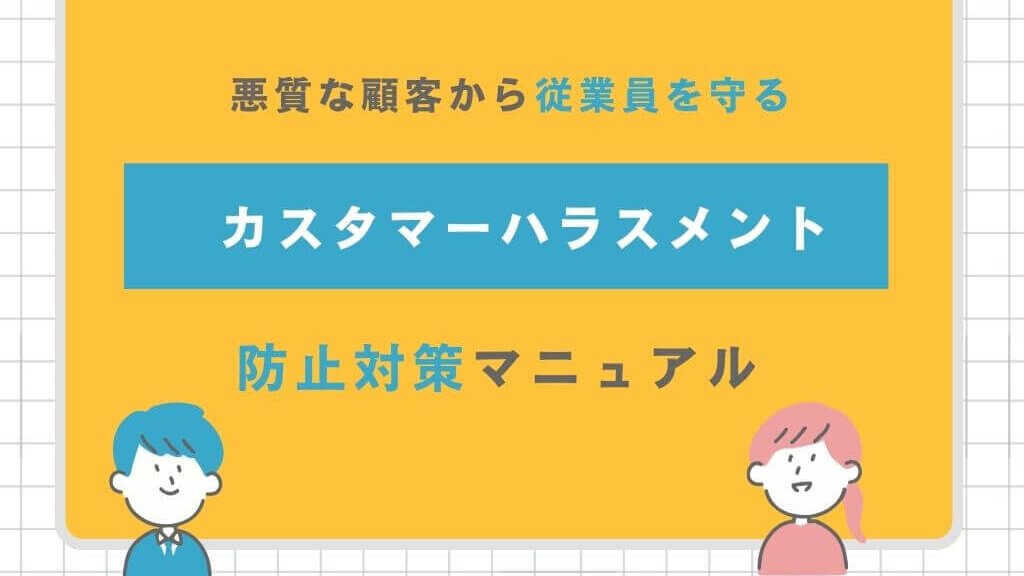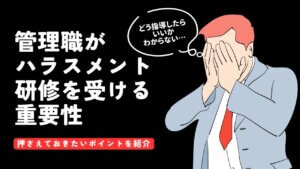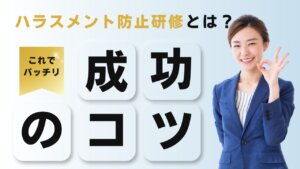管理職がハラスメント研修を受ける重要性は?押さえておきたいポイントを紹介
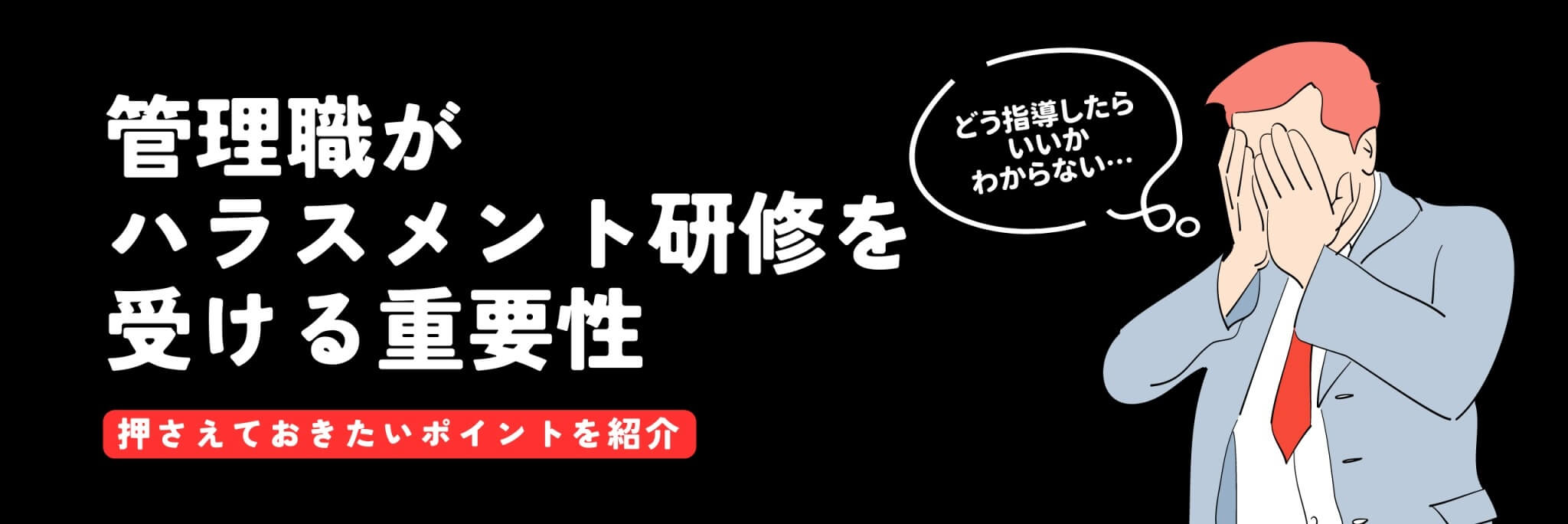
近年、職場におけるハラスメントが問題視されており、その対策としてハラスメント研修を実施する企業が増えています。従業員を指導する立場の管理職になると、「どう指導していいかわからない」「何がハラスメントになるかわからない」など、不安に感じることもあるでしょう。冗談やコミュニケーションのつもりで言った言葉や行動が、ハラスメントに思われてしまう場合もあります。管理職のハラスメントに対する悩みやリスクを解決するうえでも、ハラスメント研修を受ける重要性は高いです。

この記事では、管理職がハラスメント研修を受ける重要性や、押さえておきたいポイントについて詳しく紹介します。
管理職がハラスメント研修を受ける重要性

企業にはハラスメントを予防する法的・社会的責任があり、特に管理職は「未然防止」と「初動対応」の要となる立場です。そのため、一般社員向けではなく、管理職に特化したハラスメント研修の実施が重要とされています。
ここでは、なぜ管理職こそハラスメント研修を受ける必要があるのかを解説します。
ハラスメントの正しい知識を管理職が理解する必要がある
管理職は、部下からの相談を受けたり、日常的に指導・評価を行ったりする立場にあります。そのため、何がハラスメントに該当するのかを正しく理解していない場合、無自覚な加害や不適切な対応につながるリスクがあります。
パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントなどは、「悪意がなくても成立する」ケースが多いのが特徴です。
管理職が基準を正しく理解することで、「知らなかった」では済まされない事態を防ぐことができます。
ハラスメントを生まないコミュニケーションを学ぶ
ハラスメントの多くは、コミュニケーションの齟齬から生じます。研修では、部下の価値観や多様性を尊重し、信頼関係を築くためのコミュニケーションスキルを学びます。
管理職向けのハラスメント研修では、
- 部下の多様な価値観を尊重する姿勢
- 感情的にならずに意見を伝える方法
- 指導とハラスメントの境界線
など、管理職に求められる実践的なコミュニケーションスキルを学びます。
「指導しているつもり」がハラスメントと受け取られないための視点を持つことが、トラブルの予防につながります。
管理職の思い込みを取り除く
管理職はこれまでの経験から、自分なりの指導スタイルや価値観を確立していることが多い立場です。しかし、その成功体験が、現在の職場環境や多様な働き方に合わなくなっているケースもあります。
「自分も厳しく指導されて成長した」「強く言わないと部下は動かない」
こうした思い込みが、結果としてハラスメントに該当する行動につながることも少なくありません。
管理職向けハラスメント研修は、新しい知識を学ぶ場であると同時に、自身の価値観を客観的に見直す機会にもなります。
ハラスメントを許さない組織風土を管理職がつくる
ハラスメント研修を通して管理職が適切に指導できるようになると、ハラスメントを許さない組織風土を作ることができます。ハラスメント対策で大切なことは、従業員一人ひとりが「ハラスメントをさせない・許さない・しない」という認識を持つことです。
管理職が正しい認識を持ち、適切に対応することで、
- 部下が相談しやすい環境が生まれる
- 加害行為に対するブレーキがかかる
- 組織全体の意識が底上げされる
といった効果が期待できます。
ハラスメント研修は、個人の問題を組織の課題として捉えるための重要な施策です。
発生時に「間違えない対応」ができるようになる
どれだけ予防策を講じても、ハラスメントが起きてしまう可能性はゼロではありません。
その際、管理職の初期対応を誤ると、問題が深刻化し、セカンドハラスメントにつながるリスクもあります。もし部下からハラスメントの相談を受けた場合、管理職の初期対応は極めて重要です。
研修では、相談者のプライバシーを守りながら、公平な立場で傾聴するスキルや、事実確認の進め方、然るべき窓口への報告手順などを学び、冷静かつ適切に対応できる能力を養います。
| 相談対応におけるNG行動(×) | 適切な対応(〇) |
|---|---|
| 「あなたにも原因があったのでは?」と相談者を責める | まずは相談者の話に共感し、親身に耳を傾ける |
| 「そのくらい我慢しろ」と問題を軽視する | 事の重大さを受け止め、会社として対応することを約束する |
| 相談内容を安易に第三者に話す | プライバシーの保護を徹底し、許可なく他言しない |
| 自分の判断だけで解決しようとする | 会社のルールに従い、人事部や相談窓口に報告・連携する |
被害者に寄り添った傾聴の姿勢、事実確認の進め方、プライバシーの保護、そして再発防止策の立案まで、一連のプロセスを適切に実行できる能力を身につけます。
実際の相談対応や判断に不安を感じる場合は、管理職の立場や職場環境に合わせてカリキュラムを設計できる外部研修を活用するのも一つの方法です。
ガイアシステムのハラスメント研修では、管理職が「現場で迷わない」ための実践型ハラスメント研修をご提供しています。
企業イメージ・採用リスクを未然に防ぐ
ハラスメント研修を管理職が受けることは、社会的リスクを回避するためにも重要です。ハラスメントは当事者だけの問題ではなく、企業のイメージ悪化により、社会的信用が低下するリスクがあります。
社会的信用が低下してネガティブな噂が出回ると、社員の離職率上昇、採用活動への悪影響、ブランドイメージの毀損といった影響が生じる可能性もあります。
管理職が正しい知識と対応力を身につけることは、企業リスクを最小限に抑えるための重要な投資と言えるでしょう。
ハラスメントを恐れず「適切な指導」を行うために
近年、ハラスメントへの意識が高まる一方で、「指導すること自体を避けてしまう管理職」も増えています。
しかし、指導をしない状態が続けば、部下の成長が止まったり、組織のパフォーマンスが低下したり別の課題が生まれます。ハラスメント研修では、「許されない言動」と「必要な指導」の違いを明確に整理し、管理職が自信を持って指導できる状態を目指します。
ガイアシステムでは、管理職が抱える「指導とハラスメントの境界線が分からない」という悩みに対し、実例を交えたオーダーメイド研修をご提案しています
お客様の課題やカリキュラムに応じてお見積りパターンをご提案しています。
まずは気軽にご相談ください!
お電話でのお問い合わせ 0120-117-450
専任のコンサルタントが丁寧にご相談を受け付けます。
お気軽にご相談ください。
管理職向けハラスメント研修の主な内容
管理職向けハラスメント研修のプログラムは多岐にわたりますが、多くの場合、以下の内容が含まれています。自社に必要な要素は何かを考えながら、研修内容を確認することが大切です。
| 研修カテゴリー | 具体的な学習項目 |
| 基礎知識 | ハラスメントの定義(パワハラ、セクハラ、マタハラ等)、背景、発生要因 |
| 法令・判例 | 労働施策総合推進法(パワハラ防止法)、男女雇用機会均等法等の関連法規 企業の法的責任、近年の判例 |
| 事例研究 | 他社で発生した具体的なハラスメント事例の分析、自社で起こりうるケースの検討 |
| 実践スキル | アンガーマネジメント、アサーティブコミュニケーション、適切な指導・叱責の方法 |
| 対応プロセス | 相談受付(ロールプレイング)、事実確認、対応策の検討、再発防止策の策定 |
ハラスメントの定義と種類
まず基本として、パワーハラスメントの6類型(身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害)をはじめ、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメントなど、各種ハラスメントの定義を明確に学びます。どのような言動が該当するのか、具体的な例を交えながら理解を深めます。
関連法規と企業の責任
パワハラ防止法や男女雇用機会均等法といった、ハラスメントに関連する法律の概要と、それによって企業が負うことになる安全配慮義務について学習します。法律違反があった場合に、企業や管理職がどのような責任を問われるのかを知ることで、コンプライアンス遵守の意識を高めます。
国内外のハラスメント事例研究
実際に起きたハラスメントの事例を学ぶことは、自社でのリスクを具体的にイメージする上で非常に有効です。どのような状況で問題が発生し、どのような結末を迎えたのかを分析することで、自社の職場環境に潜むリスクを洗い出し、予防策を考えるきっかけとします。
アンガーマネジメントと適切な指導方法
管理職自身の感情コントロールも、ハラスメント防止の重要な要素です。アンガーマネジメントの手法を学び、怒りの感情と上手に付き合う方法を身につけます。また、部下の成長を促すための「指導」と、ハラスメントとなる「攻撃」との境界線を明確に理解し、適切な指導スキルを習得します。
相談対応と解決プロセスの実践(ロールプレイング)
知識として理解するだけでなく、実践的なスキルを身につけるために、ロールプレイング形式での演習が行われます。部下からハラスメントの相談を受ける場面を想定し、どのようにヒアリングし、対応すべきかを体験的に学びます。これにより、いざという時に冷静かつ適切に行動できるようになります。
管理職のハラスメント研修の効果を最大化するポイント

ハラスメント研修は、ただ実施するだけでは十分な効果を得られない可能性があります。ここでは、管理職のハラスメント研修を効果的に行うポイントを解説します。「知識の理解」で終わらせず、管理職の“現場行動”まで落とし込むことがゴールです。
部下とのコミュニケーションについても見直す
管理職を対象としたハラスメント研修を実施する際には、部下とのコミュニケーションについても合わせて考えましょう。
ハラスメントが発生する職場環境では、部下とのコミュニケーションが不十分なケースがあります。コミュニケーションが適切に取れていないため、本人に悪意がなくても、嫌がらせと捉えられてしまうケースが想定されます。
ハラスメント研修を実施する際は、部下とのコミュニケーション改善を目指すのもポイントです。そのため、コミュニケーションに特化したハラスメント研修の実施や、別でコミュニケーション研修を実施するのもよいでしょう。
特に管理職は「指導」「フィードバック」「注意」が日常業務に含まれるため、伝え方のすれ違いがトラブル化しやすい立場です。研修で学んだ内容を、1on1・面談・日々の声かけにどう反映するかまで設計しておくと、定着しやすくなります。
コミュニケーション研修についてはこちらもご確認ください!
コンプライアンスに問題がないか確認する
ハラスメント研修を実施する際は、あわせて企業のコンプライアンスに問題がないかも確認しましょう。
コンプライアンスとは、企業に求められる法令遵守や社会的規範の遵守であり、規範に従って公平・公正に業務を行う必要があります。特に最近は企業に高い倫理観が求められるようになっているため、コンプライアンスに力を入れる企業は少なくありません。
そして、コンプライアンスにはハラスメントの対応も挙げられるため、ハラスメント対策とセットで考えるべき事項です。ハラスメントにおいて、どのような言動が行動が不当な扱いに該当するかという観点から、コンプライアンスについて振り返りましょう。
ポイントは「研修で学んだ基準」と「社内ルール(相談窓口・報告フロー・懲戒等)」が矛盾しない状態を作ることです。基準が曖昧なままだと、管理職ごとに判断がブレて現場対応が属人化し、結果的にリスクが高まります。
管理職に当事者という意識を持たせる
ハラスメントは当事者意識がないことによって起こる場合が多いため、ハラスメント研修では管理職に当事者という意識を持たせましょう。
管理職の中には、「ハラスメントは倫理観にかける人間が起こすこと」「自分は他人のことを考えて行動しているから関係ない」と思い込んでいる方もいます。
自分とは関係のない問題という意識でハラスメント研修に参加しても、思うような効果は得られないでしょう。研修の効果を高めるためには、管理職に「誰でもハラスメントの加害者になりえる」という意識を持たせることが大切です。
可能であれば、ハラスメント研修のカリキュラムに自社や身近な事例を入れておくと、当事者意識を持ちやすくなります。
インタラクティブな学習を取り入れる
ハラスメント研修の効果を高めるためには、インタラクティブな要素を取り入れることもポイントの一つです。
インタラクティブには相互・双方向という意味があり、研修では実例を使ったケーススタディやディスカッションなどが挙げられます。一方向の研修だと他人事として捉えてしまい、管理職の意識改革につながらない可能性もあります。
当事者意識を持つという意味でも、インタラクティブな学習ができるハラスメント研修は効果的です。
特に管理職向けは「判断が割れるケース(指導かハラスメントか)」を扱うほど、現場で使える基準が身につきます。
ディスカッション→講師の整理→自社基準への落とし込みの流れを作れると、研修後の実務でも再現しやすくなります。
お客様の課題やカリキュラムに応じてお見積りパターンをご提案しています。
まずは気軽にご相談ください!
お電話でのお問い合わせ 0120-117-450
専任のコンサルタントが丁寧にご相談を受け付けます。
お気軽にご相談ください。
管理職のハラスメント研修で失敗しやすいポイント

時間やコストを割いてハラスメント研修を実施しても、研修内容やその後の対応によっては十分な効果を得られない可能性があります。ここでは、管理職のハラスメント研修で失敗しやすいポイントを紹介します。
研修の内製化は悪循環に陥りやすい
コストを減らしたいという理由で、自社のリソースを使ってハラスメント研修を内製化すると、かえってリスクが高まるケースがあります。
その理由は、研修準備や運営が特定の社員に集中し、業務負荷やストレスが増大しやすいためです。加えて、社内研修では、ハラスメントの当事者や関係者が資料作成・講師を担ってしまい、内容が主観的になるおそれもあります。
その結果、
- 管理職が本音で参加しづらい
- 指摘が曖昧になり、行動変容につながらない
といった悪循環に陥る可能性があります。
研修の客観性と信頼性を担保するためには、第三者視点を持つ外部研修の活用が有効と考えられます。
管理職に適した内容でないと効果を得られない
ハラスメント研修にはさまざまな種類があるため、管理職に適した内容を選ばないと十分な効果を得ることはできません。管理職向けの研修であるにもかかわらず、一般社員や新人向けの内容を流用してしまうと、学ぶべきポイントがずれてしまいます。
- 指導・評価を行う立場としての判断基準
- 部下から相談を受けた際の初期対応
- 組織としてのリスク管理視点
など、管理職には役割に即した内容が求められます。
そのため、ハラスメント研修を実施する際は、階層別・役割別に設計されたプログラムを提供している研修会社を選ぶことが重要です。
また、業種・組織規模・管理職の経験年数に応じてカリキュラムを調整できるオーダーメイド型研修であれば、より高い効果が期待できます。
1度きりの研修では効果が出にくい
ハラスメント研修は、継続的に受講することで真の成果を得られるため、一度きりの研修では効果が出にくい点に注意しましょう。
ハラスメントの問題は日々変化しているため、研修は半年に1回や1年に1回のように定期的に行いアップデートすることが大切です。
研修が終わったあとにはアンケートを実施し、現場で「何が難しかったか」「どこで迷ったか」を把握したうえで次回に反映することも重要です。単発で終わらせず、継続的な取り組みとして設計することが、ハラスメントを許さない組織風土の醸成につながります。
「管理職がハラスメント研修を受ける重要性」に関するよくある質問(Q&A)
まとめ
この記事では、管理職がハラスメント研修を受ける重要性や押さえておきたいポイントを紹介しました。
管理職がハラスメント研修を受けることで、従業員の意識も高まり、ハラスメントを許さない組織風土の醸成につながります。また、ハラスメント対策を適切に行うことで、離職率や企業イメージの低下も防ぎます。
ハラスメント研修の効果を最大化するためには、管理職にあったカリキュラムやカスタマイズされた研修を選ぶのがポイントです。管理職のハラスメント研修なら、ガイアシステムにお任せください。
ガイアシステムでは管理職向けのハラスメント研修を行っており、オーダーメイドでカリキュラムを設計し、効果的な研修をご提案することも可能です。短期間から長期間に及ぶものまで、幅広いカリキュラムに対応しています。
管理職のハラスメント研修を検討しているという担当者様の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
ハラスメント研修カリキュラム
従業員をクレーマーから守り、組織の対応力向上を目指す!
カスタマーハラスメント研修|対応力強化
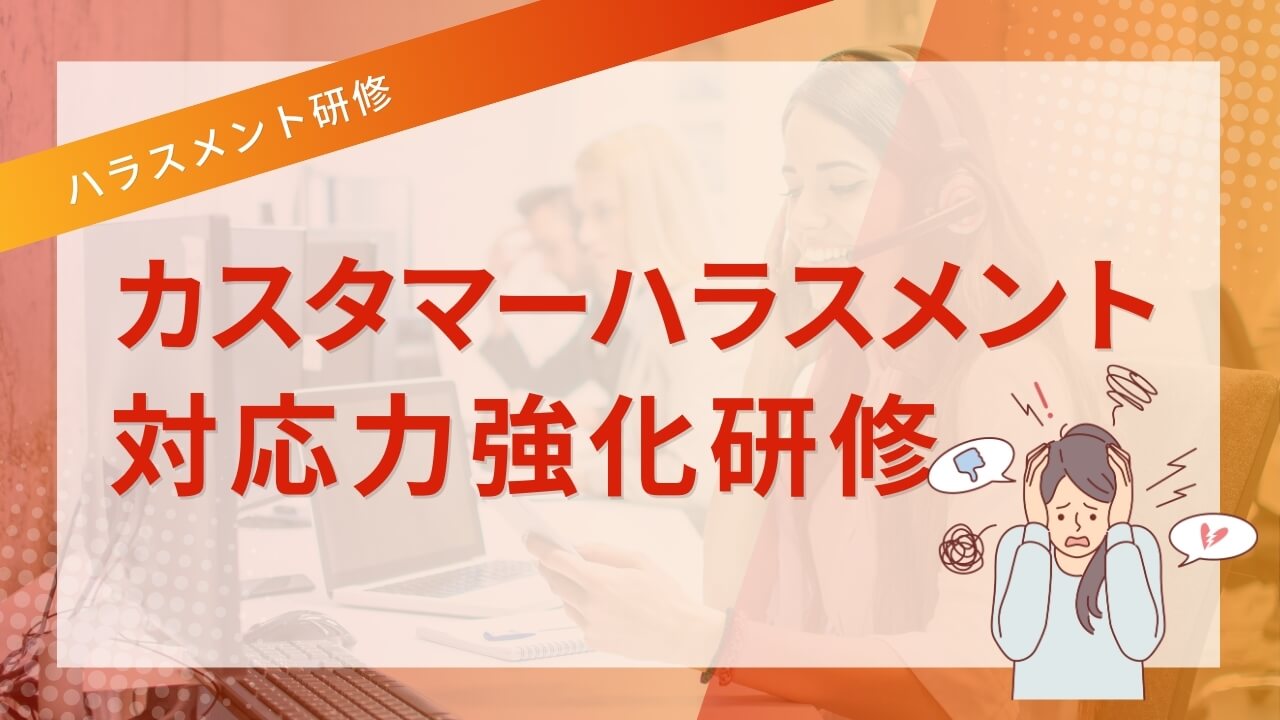
従業員に大きなストレスを与え、離職の原因にもなっているカスタマーハラスメント。個人の能力では解決できないケースも多く、組織が一体となってリスク回避することが必要です。
本研修はカスタマーハラスメントの理解と対応力を強化することを目的に、コミュニケーションスキルを学び、実践的なグループワークを通じて具体的な対策を考えます。
ハラスメントの未然防止、環境改善を目指す!
ハラスメント研修 |パワハラ防止対策
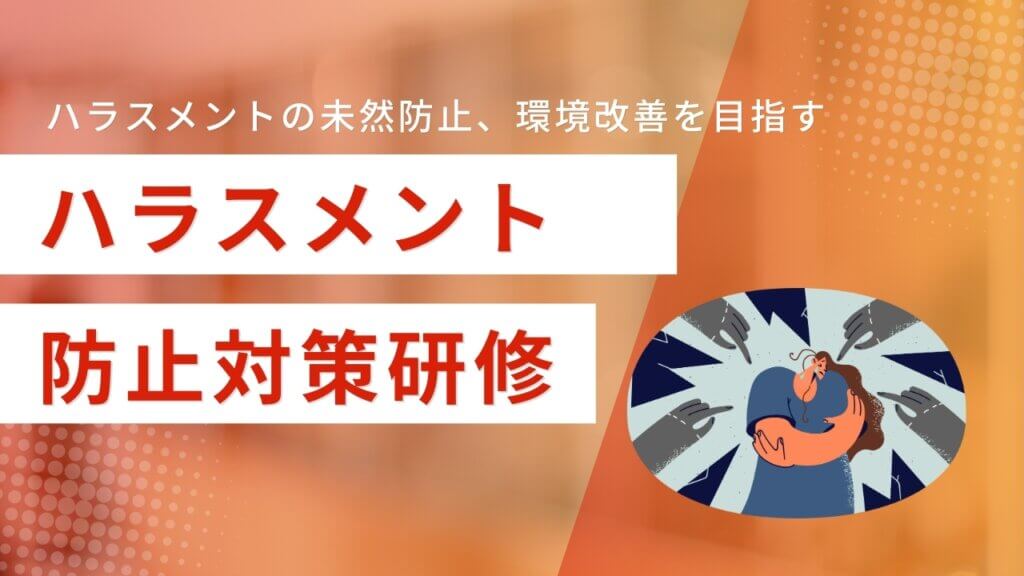
セクハラ、パワハラ、マタハラなど様々なハラスメントの定義や具体例、日常に潜むハラスメントリスクについて学びます。
「グレーゾーンと思われがちな事例紹介」やケーススタディを通じてハラスメントの識別方法を習得し、グループディスカッションで防止策を考案します。また、ハラスメントが起きた際の適切な対応方法や報告手順を身に着けます。
心のメンテナンス手法を習得
メンタルヘルス研修|ストレスと上手に向き合うには
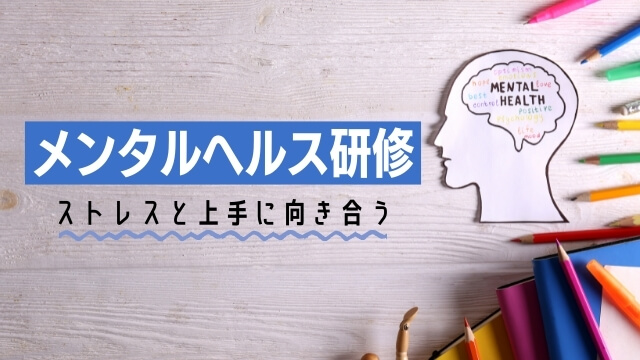
メンタルヘルスに対する知識を身につけ、自分の心の状態を確認し、自らに合ったメンテナンス手法を習得していきます。
・メンタルヘルス研修 全従業員対象 基礎編
・メンタルヘルス研修 役職対象 ラインケア編
・メンタルヘルス研修 全従業員対象 セルフケア編
上記を事例に、内容別・対象別に様々な研修カリキュラムを取り揃えております。
ハラスメントコラム一覧
-
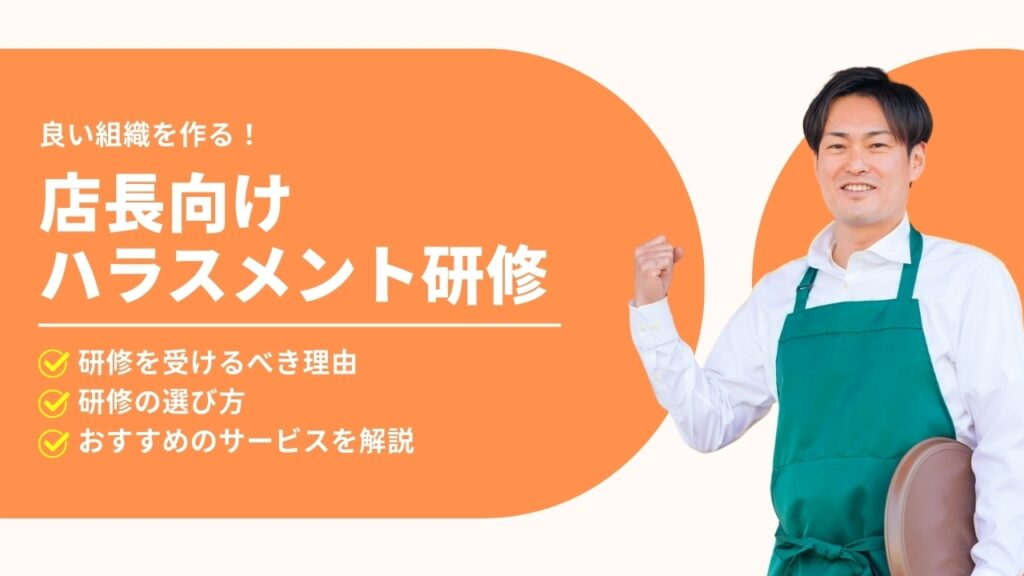
良い組織を作る!店長向けハラスメント研修のポイントを解説
-
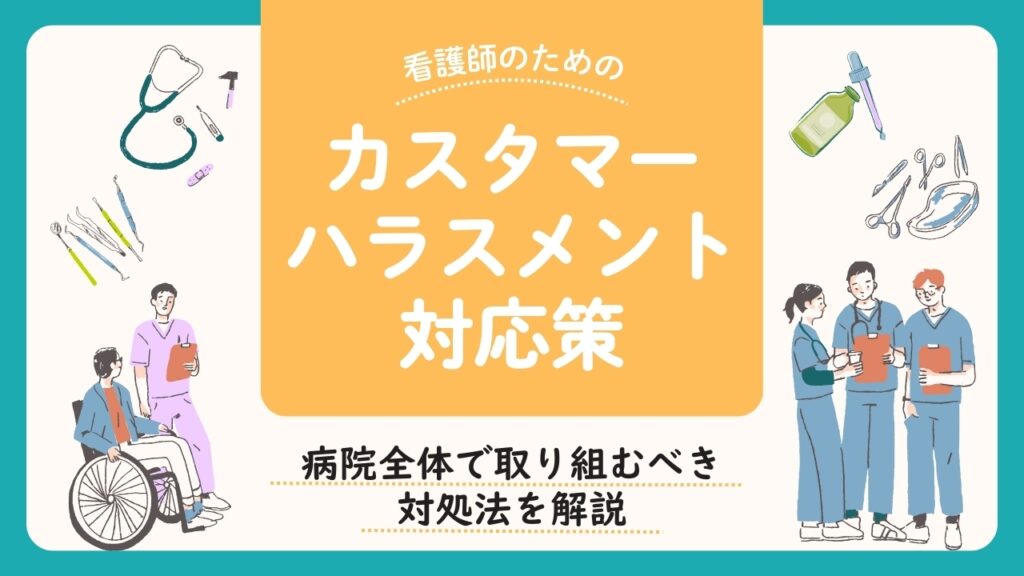
看護師のためのカスタマーハラスメント対応策!対処法を解説
-
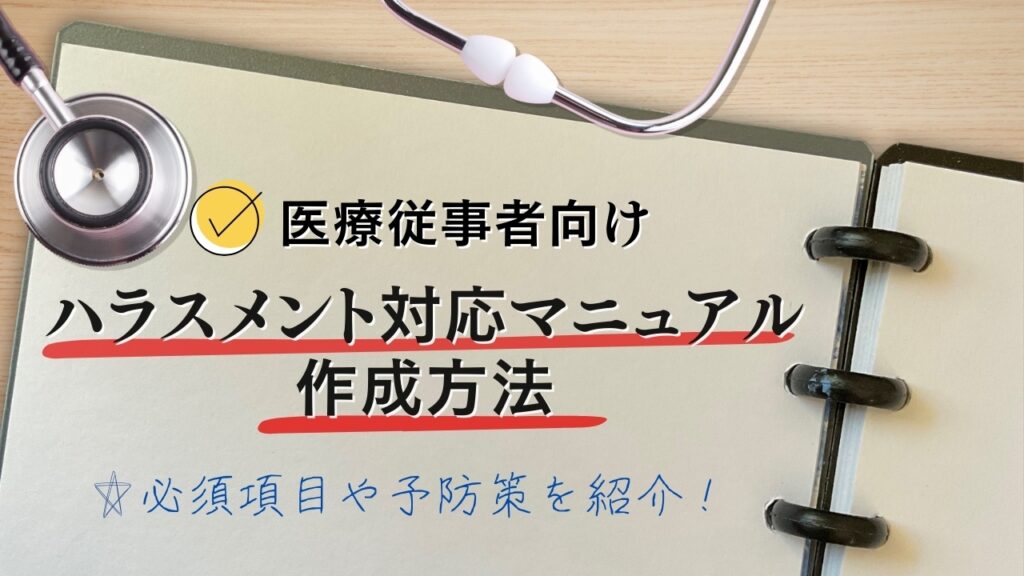
医療従事者向けのハラスメント対応マニュアルの作成方法は?必須項目や予防策を紹介
-

介護施設のクレーム対応研修はなぜ必要?目的やポイントを徹底解説
-
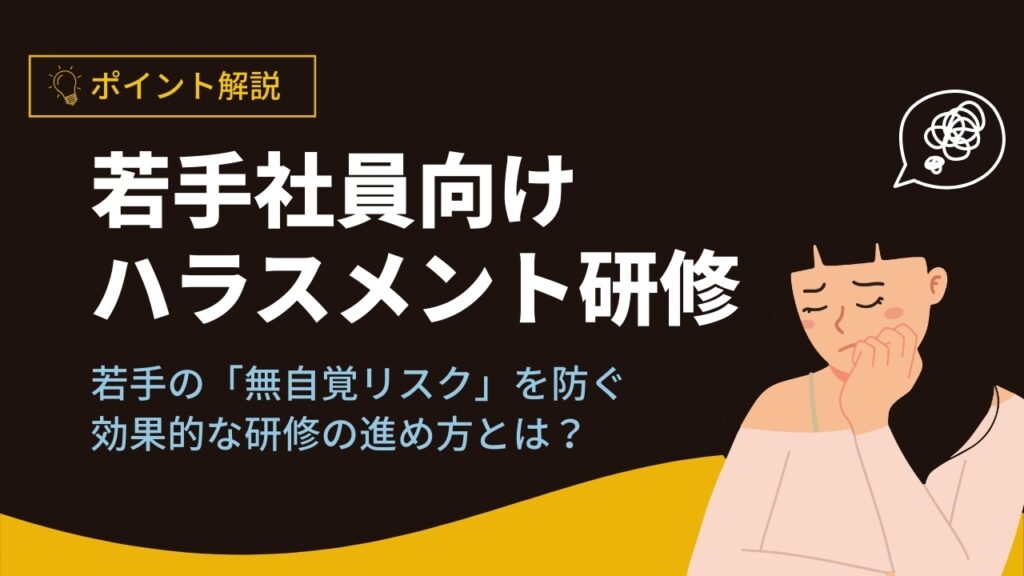
若手社員向けハラスメント研修のポイント解説!効果的な進め方とは
-
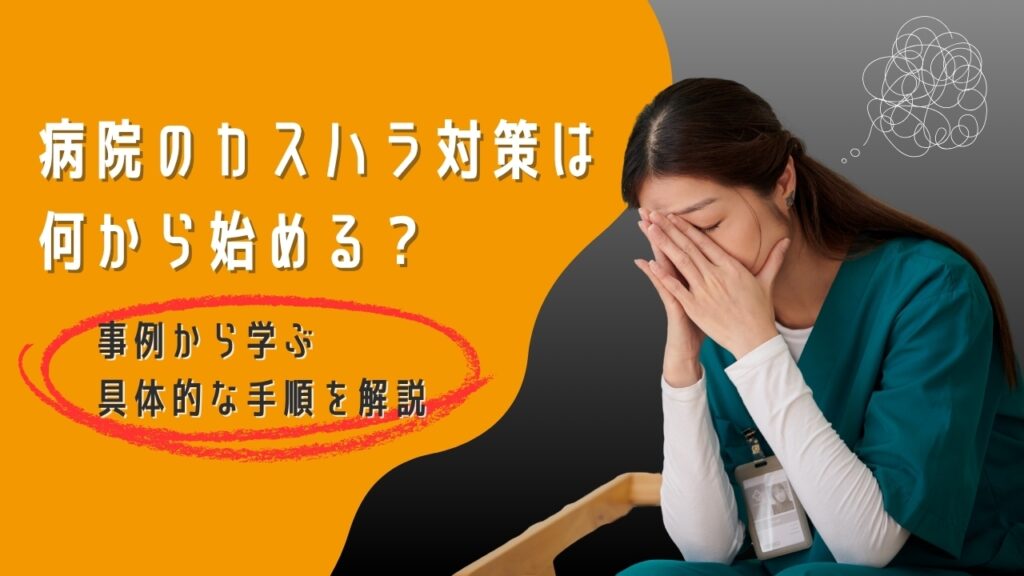
病院のカスハラ対策は何から始める?事例から学ぶ具体的な手順を解説
-
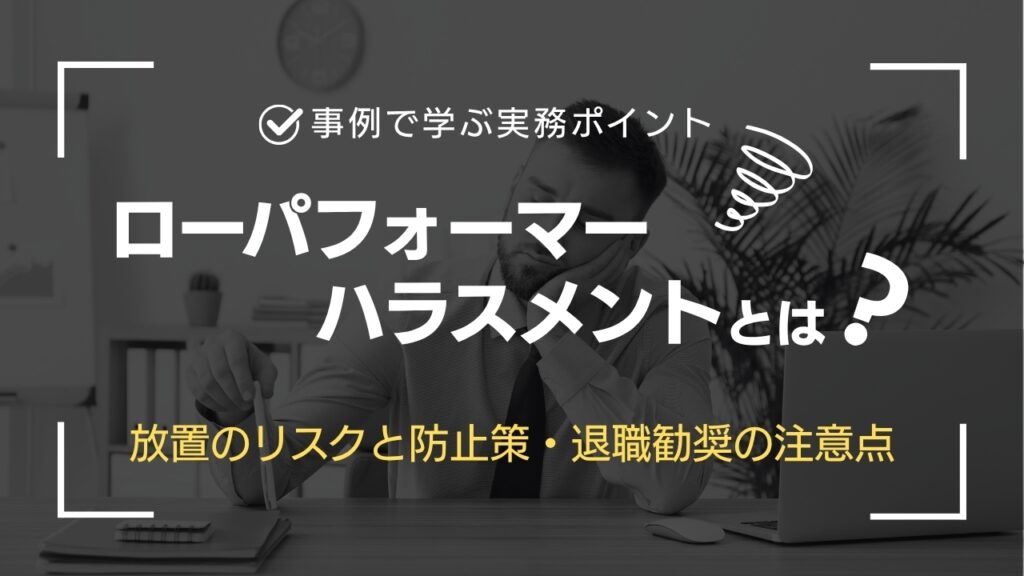
ローパフォーマーハラスメントとは?放置のリスクと防止策・退職勧奨の注意点
-
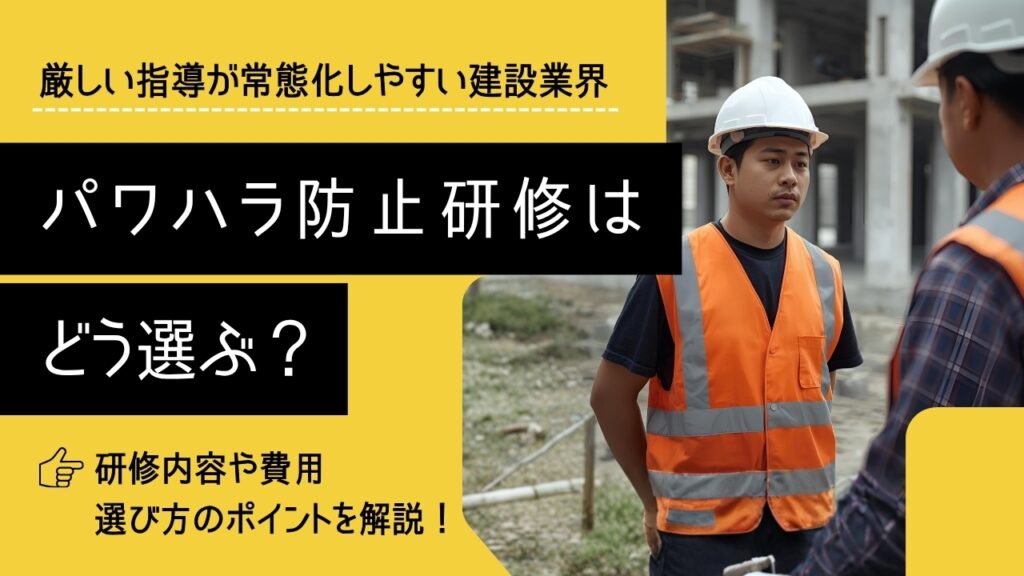
建設業のパワハラ防止研修はどう選ぶ?研修内容や費用、選び方のポイントを解説
-
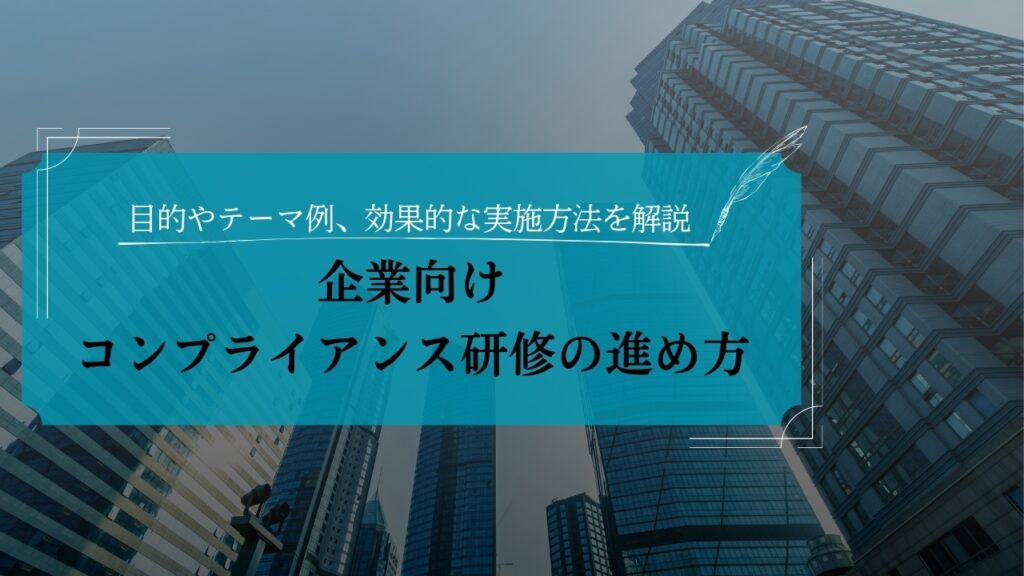
企業向けコンプライアンス研修の進め方!目的やテーマ例、効果的な実施方法を解説
-
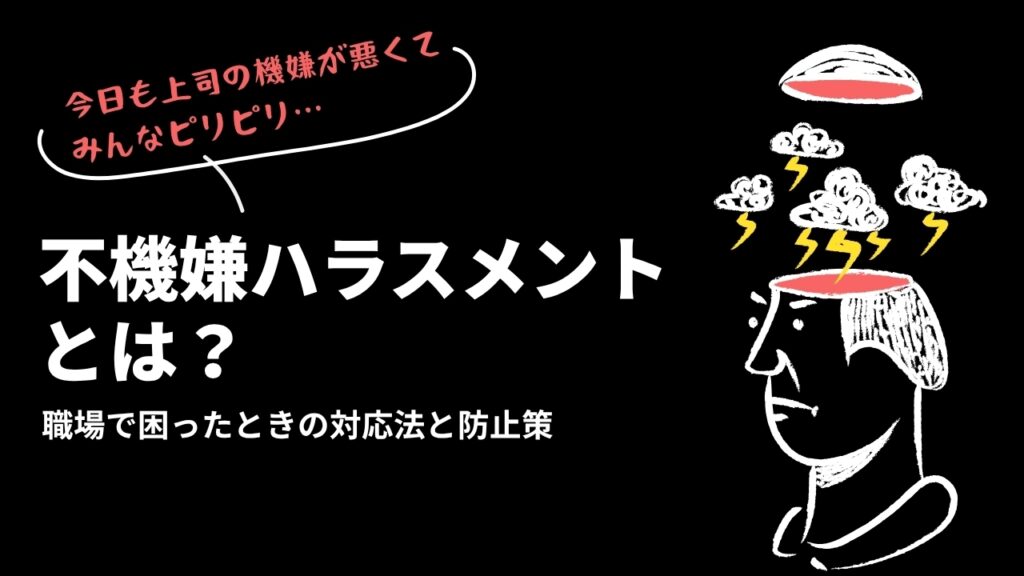
不機嫌ハラスメントとは? 職場で困ったときの対応法と防止策
-

パーソナルハラスメントとは?職場での定義と防止策を解説
-
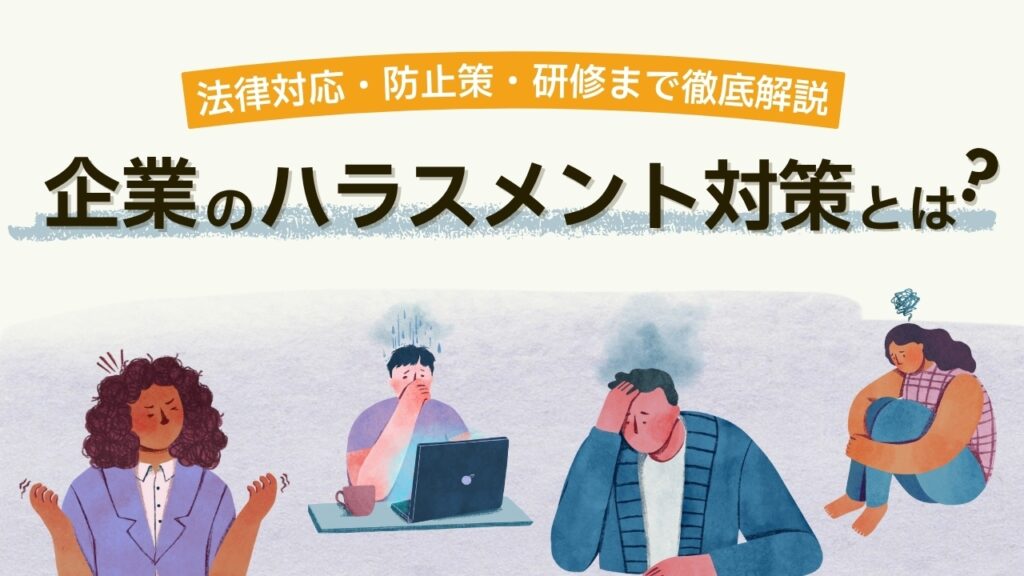
企業のハラスメント対策とは?法律対応・防止策・研修まで徹底解説
-
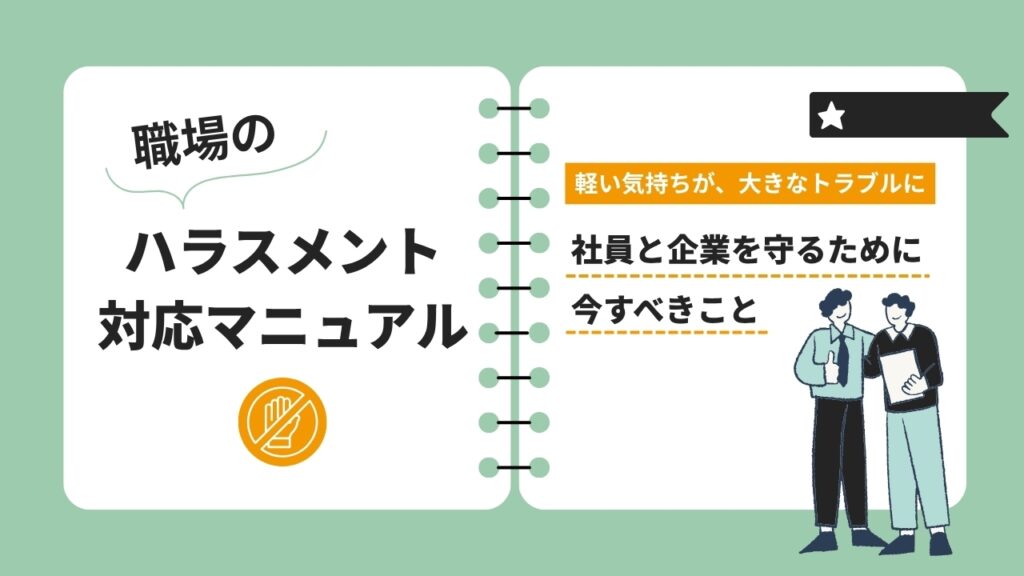
職場のハラスメント対応マニュアル|社員と企業を守るために今すべきこと
-
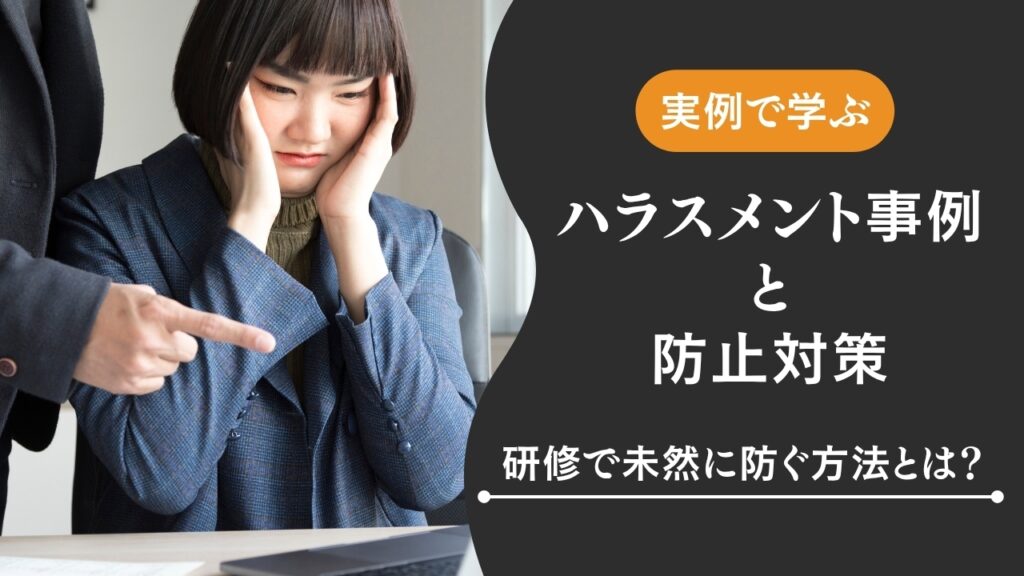
【実例で学ぶ】職場のハラスメント事例と防止対策|研修で未然に防ぐ方法とは?
-
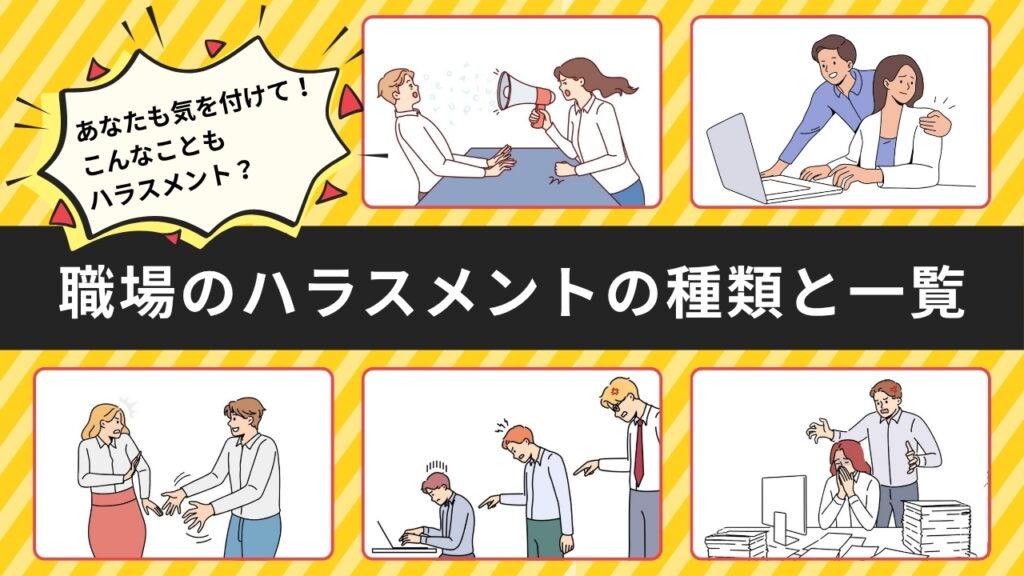
【職場のハラスメントの種類・一覧】あなたも気を付けて!こんなこともハラスメント?
-
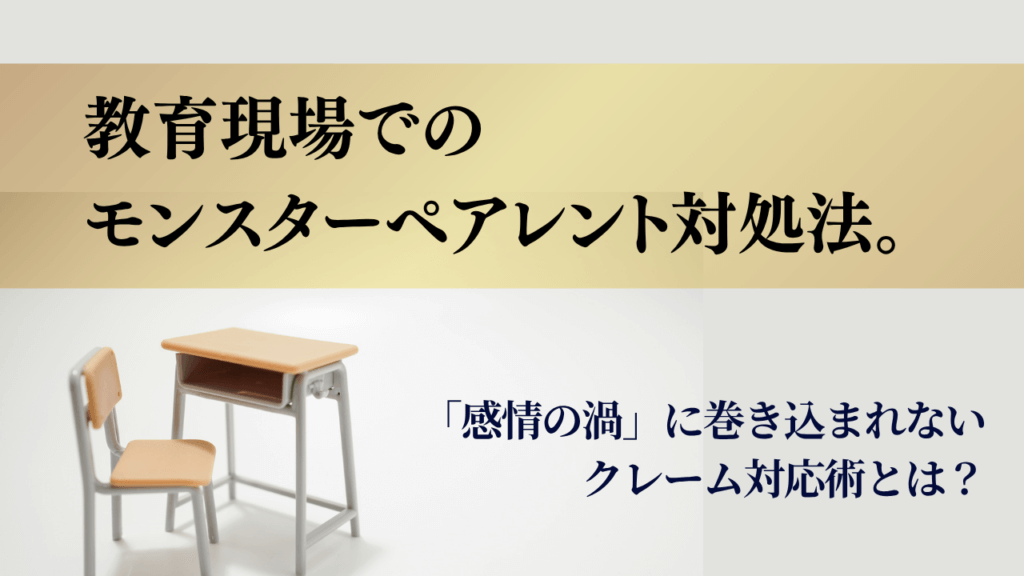
教育現場でのモンスターペアレント対処法。「感情の渦」に巻き込まれないクレーム対応術、効果的な研修法は?
-
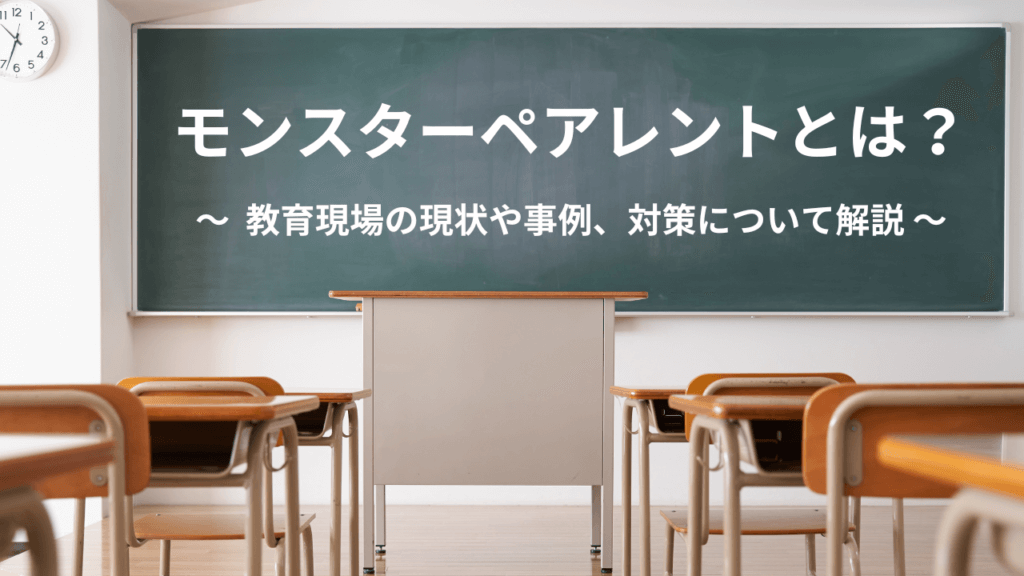
モンスターペアレントとは?教職員を守るためのハラスメント対策について解説
-

カスタマーハラスメント研修とは?研修内容やカスハラを防ぐための取り組み
-
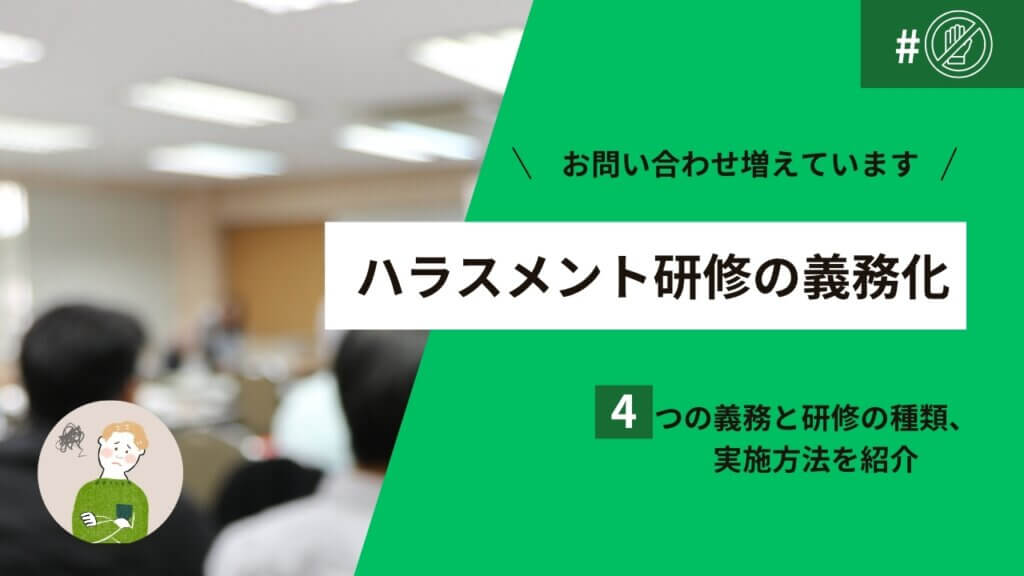
ハラスメント研修の義務化について!4つの義務と研修の種類、実施方法を紹介
-

【2025年最新】パワハラ防止法対応|おすすめハラスメント研修会社を比較!失敗しない選び方とは?
-
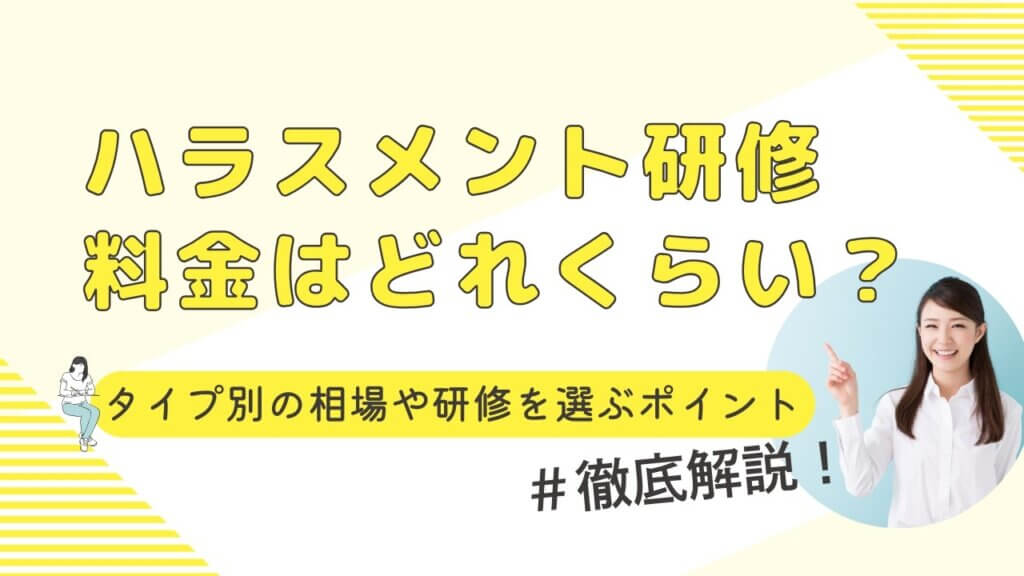
ハラスメント研修の料金はどれくらい?タイプ別の相場や研修を選ぶポイント
-

飲食店のカスハラ対策|事例で学ぶ顧客対応と研修のすすめ
-

病院でのカスハラ事例|医療現場でのリスク対策と研修の必要性
-

介護のカスタマーハラスメント対策とは?介護現場の実態や発生原因も解説!