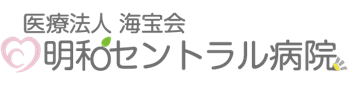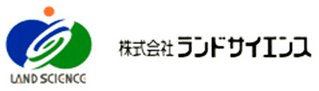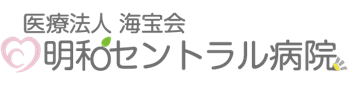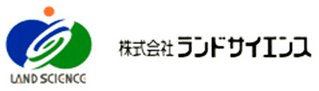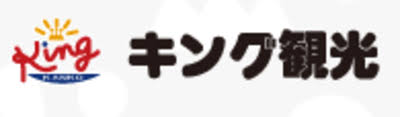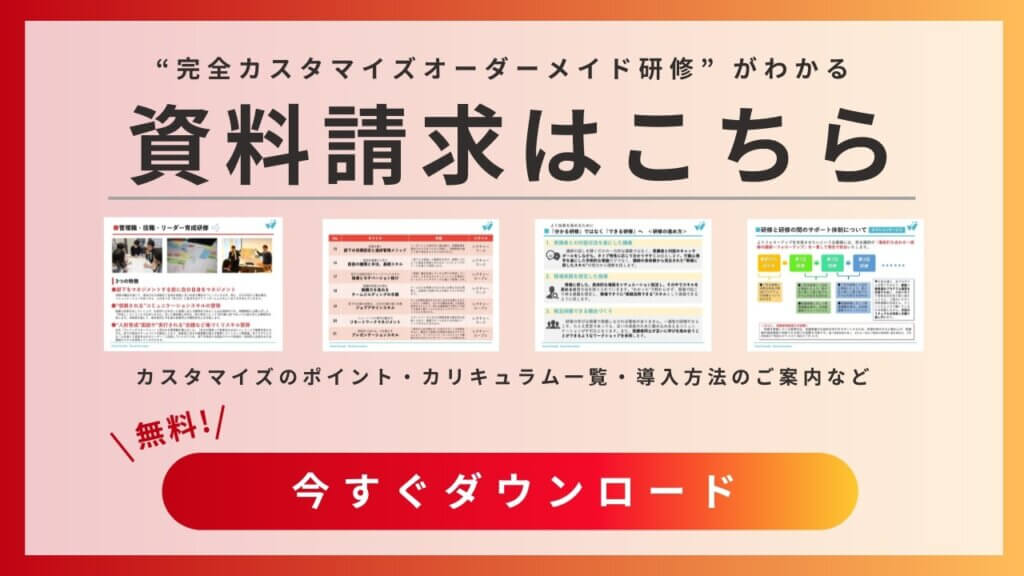動機付け衛生理論
動機付け衛生理論とは、臨床心理学者フレデリック・ハーズバーグによって提唱された「仕事とモチベーションに関する理論」で、仕事の満足要因と不満要因は別々に存在すると説明するものです。
つまり、不満を取り除くだけでは必ずしも意欲が高まらず、満足を生み出す要因を強化することが必要だとしています。
動機付け衛生理論とは?
動機付け衛生理論とは、フレデリック・ハーズバーグによって提唱された「仕事へのモチベーション」を説明する理論で、仕事の満足を生み出す要因(動機づけ要因)と、不満を防ぐ要因(衛生要因)を区別して考えます。
単に不満を取り除くだけでは意欲は高まらず、達成感や承認といった動機づけ要因を意識的に提供することが大切です。
研修の場では、この理論をもとに「どのように部下の意欲を引き出すか」、「チームの雰囲気をどう整えるか」を具体的に学ぶことで、日常のマネジメントや人材育成に活かすことができます。
動機付け衛生理論の基本的な考え方
ハーズバーグは、人が仕事に向かう際の要因を「衛生要因」と「動機づけ要因」に分けました。
衛生要因(不満を防ぐ要因)
- 会社の方針や管理体制
- 労働条件や給与
- 作業環境や人間関係
これらは整っていないと不満につながりますが、整えたからといって大きなやりがいを生むわけではありません。
動機づけ要因(満足を高める要因)
- 達成感
- 承認や評価
- 成長の機会や責任の拡大
これらが満たされることで、仕事へのモチベーションや主体性が高まります。
衛生要因と動機づけ要因の違いを理解する
ここで重要なのは、衛生要因と動機づけ要因は独立しており、因果関係でつながっていないという点です。
例えば、給与を上げたり職場環境を改善しても、一時的に不満は解消されても長期的なモチベーション向上には直結しません。逆に、承認や成長の機会が与えられることで初めて「働く意欲」が高まります。
研修での活用例
研修の場では、この理論を「部下のモチベーションをどう高めるか」というテーマで活用します。
- 管理職研修
部下が不満を感じにくい環境を整えつつ、承認や挑戦機会を与えるマネジメントを学びます。 - OJTトレーナー研修
新入社員に対して「環境の整備」と「やりがいの提供」をバランスよく行う方法を体験的に学びます。 - リーダー育成研修
自分自身の動機づけ要因を知り、部下にも適切に働きかけるスキルを習得します。
このように、理論を理解するだけでなく、実際の行動にどう落とし込むかを研修で学ぶことができます。
よくある質問(Q&A)
まとめ
動機付け衛生理論とは、仕事における不満要因と満足要因を切り分けて考える理論です。
不満を解消するだけでは意欲は高まらず、承認や達成感といった「動機づけ要因」を与えることが本当のモチベーション向上につながります。
ガイアシステムでは、この理論を実践的に学び、現場で活かすことができる オーダーメイド研修 をご用意しています。お気軽にお問い合わせください。
2,000社以上の、さまざまな業界の企業に研修導入をいただいています。